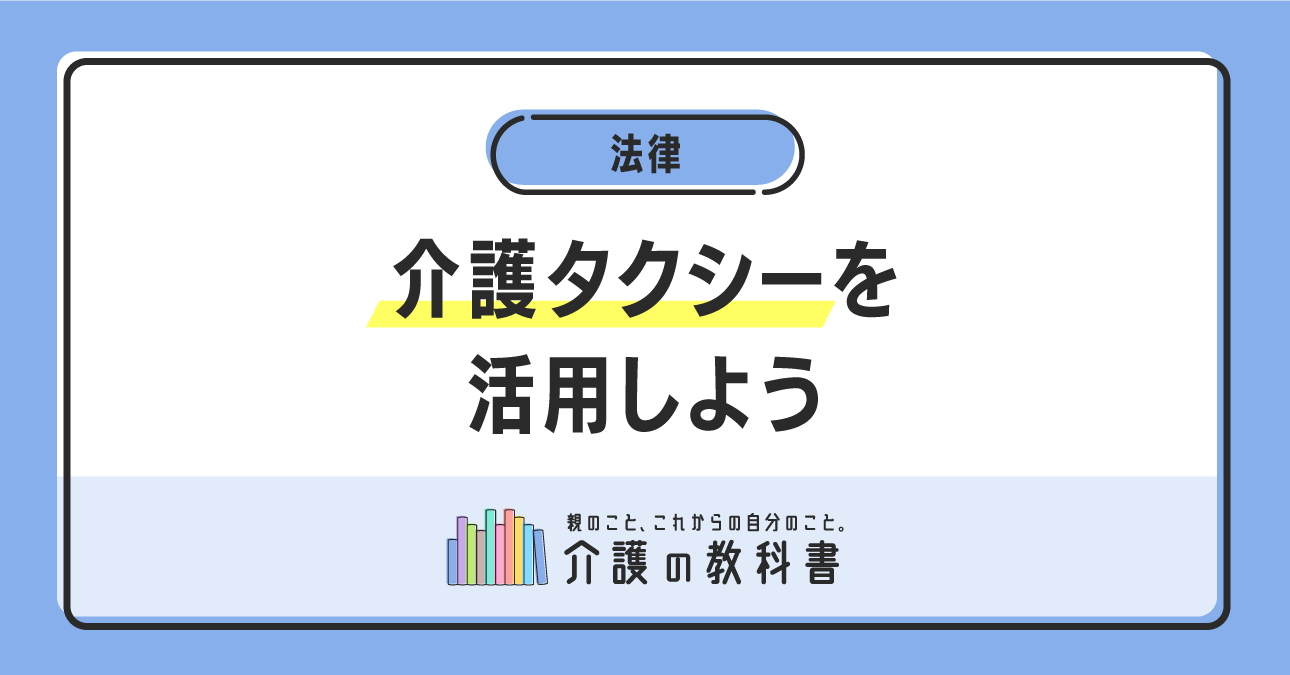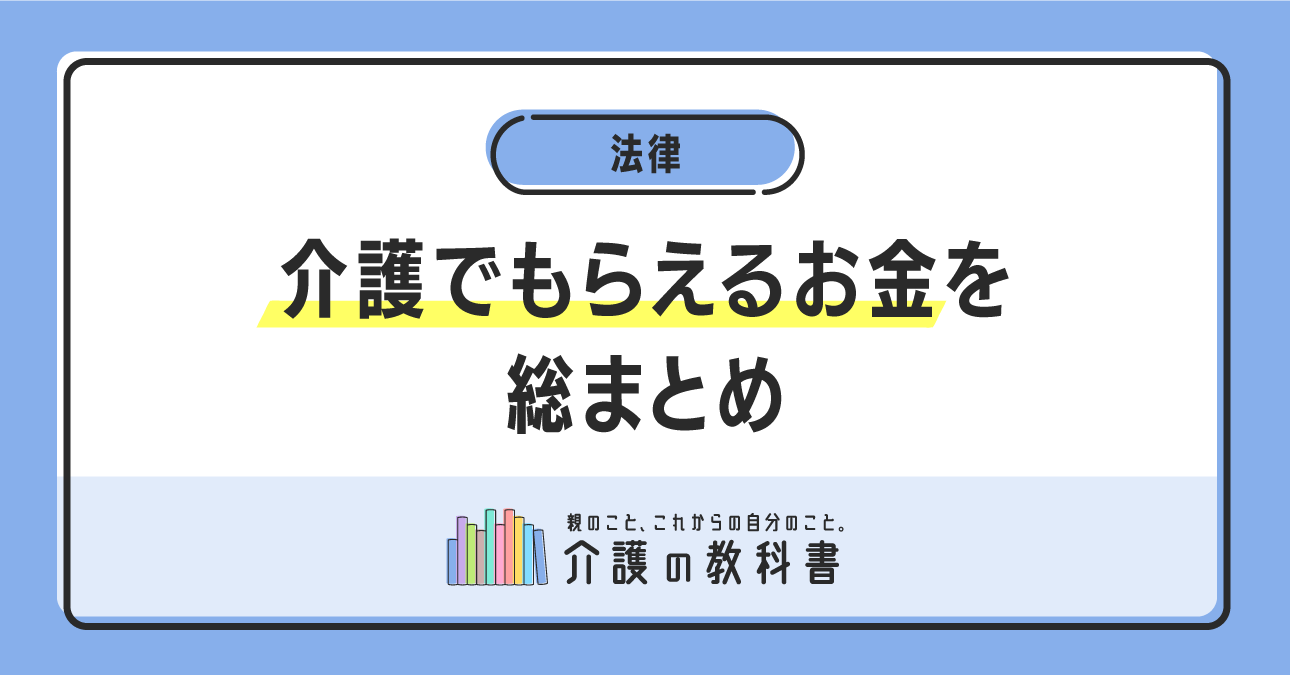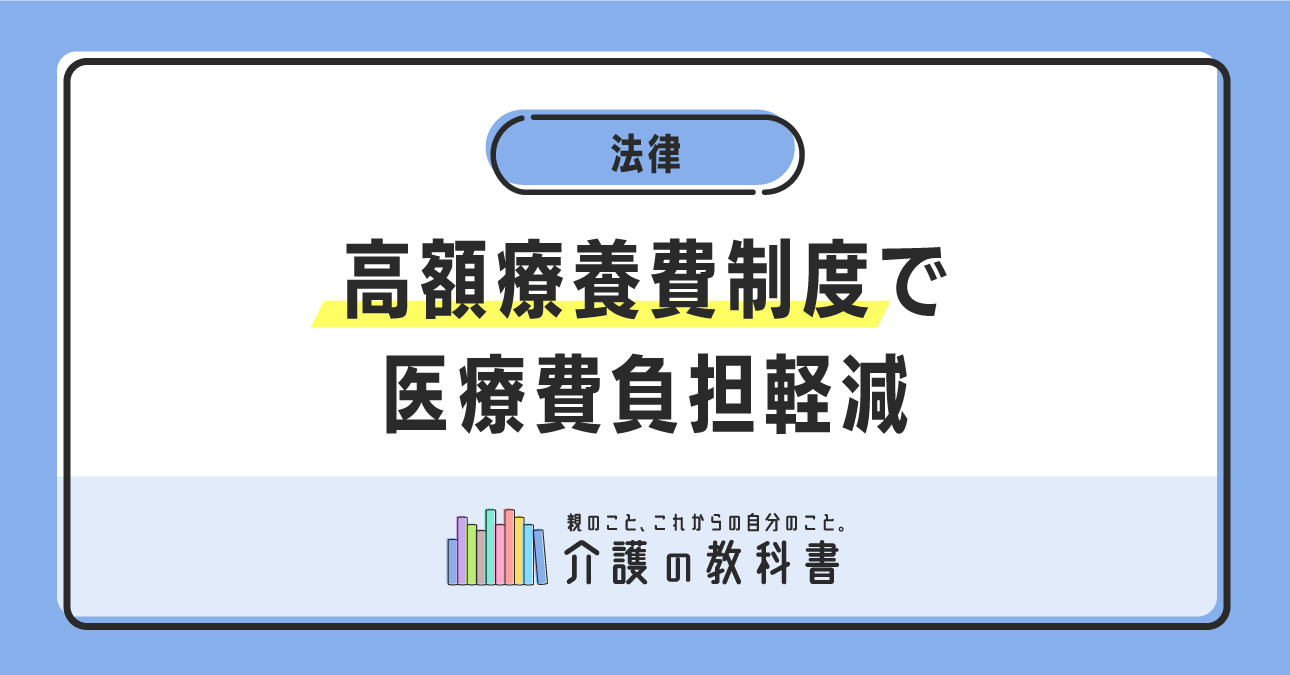こんにちは。甲斐・広瀬法律事務所の弁護士で、「介護事故の法律相談室」を運営している甲斐みなみと申します。
前回は「介護事故は弁護士に相談?納得がいかないときは法律相談を 過失があれば賠償は当然の権利」というテーマで、介護事故にあった場合の対応の入口についてご説明させていただきました。
今回は、介護事故にあった場合に被害者・利用者側が弁護士に相談した後どのように手続きが進むのかについて、さらに掘り下げてご説明していきたいと思います。
初回法律相談の流れ
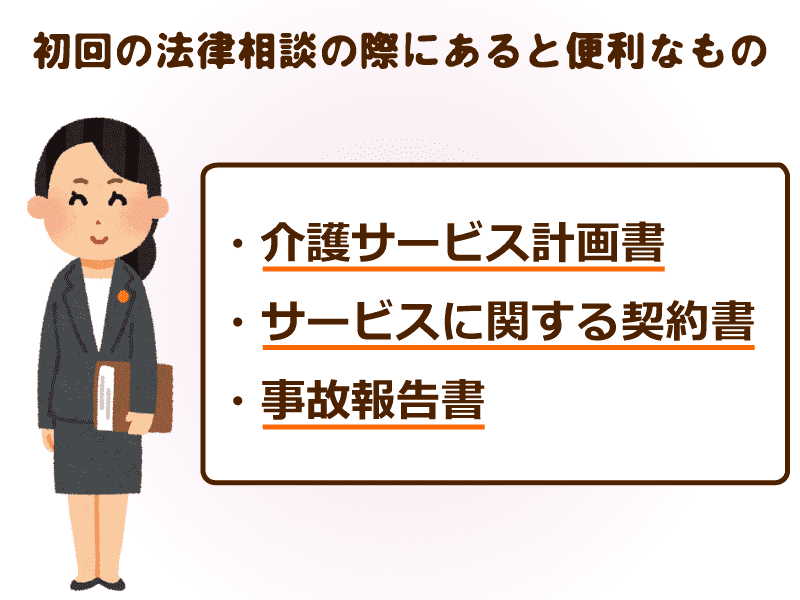
弁護士への依頼は介護事故に限らず、法律相談を通じて弁護士が事案を把握するところからスタートします。私の場合、初回の法律相談の予約の時点で、お手元に介護サービス計画書や事業所との介護サービスに関する契約書・重要事項説明書があるようであれば、ご持参いただくようお願いしています。
これらの資料は、基本的にはご家族のお手元にある資料となります。また、上記のほかに、事故の経過を報告した書面(事故報告書)等の資料があれば、それもご持参いただくようにお願いしています。
第2回でご説明させていただいたように、介護事故について事業所に賠償義務が発生するには、予見できる結果の発生を回避する義務があったのに、それを怠ったという過失が認められることが必要です。
過失の判断をするためには、事故にあった方が、事故前にどのような心身の状態であり、どのような介護を要する状態であった中で、どのような事実経過で事故が発生したのかを把握する必要があります。交通事故であれば、事故の発生状況(事故の場所や速度等)をお聞きすれば、過失の有無や過失割合の判断は可能ですが、介護事故の場合は事故発生状況だけでは過失の判断ができないのです。
そこで、事故の発生状況に関する事実をお聞きすることはもちろんですが、事故前の心身の状態等を含め、以下のような事実経過を確認させていただきます。
- 3年前、脳梗塞によって一人で歩行することはできず、歩行時に介助者が手で引く必要があったのに、事故のときは手引きがなかったため転倒
- 3年前の脳梗塞で嚥下(えんげ)機能の低下があり、厳重な見守りが必要であったのに、事故のときは見守りがされておらず誤嚥によって窒息
このほか、どのような介護サービスをこれまでに受けてきたかなども含め、事故前からの状況を把握してから見通しをつけることになります。ご家族からの聴取で概ね経緯を把握することができた後は、客観的な資料による事実経過や責任追及の可否の調査の段階に進むことになります。
事実経過等の調査
一般の民事事件では法律相談の後、すぐに裁判や示談交渉に入ることが可能である場合が多いです。例えば、人に貸したお金を返して欲しいという事案であれば借用書などの書類はご本人が持っておられるでしょうし、会社間の取引に関するトラブルであれば、契約書や交渉経過を示す資料が会社にあるはずです。ですから、事実経過をその場ですぐに確認することが可能となります。
ところが、介護事故の場合はご家族の見ていないところで日々の介護が行われ、事故が発生します。ですから、法律相談時のご本人・ご家族からの聴取だけでは、事実を正確に把握することは困難です。事故前の心身の状態や介護状況にしても、施設に入所されていたりすると、入所後の心身の状態や介護状況は正確に把握できていないこともあります。
あるいは、事故発生時に、事業所が何時に救急車を呼んで、救急隊到着時に事故にあった方がどのような状態だったか、などということは、通常ご家族にはわかりません。そこで、第7回の「必要に応じてできる情報収集例」でご説明したような書類を、必要に応じて取り寄せしていただき、それらの記録を精査するという調査の段階が必要となります。
介護記録の入手方法はさまざま

ここで、どの事案でも必要となるのが、介護記録です。第7回でご説明したように、介護事業所が日々の介護サービス実施状況や、利用者の心身の状況について記録をしている記録のことをさします。
介護記録と一口に言っても、「フェースシート」や「アセスメントシート」、「ケアプラン」、「介護経過表」など、複数の文書から成り立っていることが多く、その名称は事業所によってさまざまです。
介護記録は、ご本人または遺族が事業所に開示請求をすれば、厚生労働省のガイドライン等にしたがい、本来開示されるべきものです。しかしながら、事案によっては、介護記録を直接事業所に開示請求すれば、事故の経緯等を隠蔽するために、事業所が改ざんしたり一部を破棄したりする可能性があります。
そのような場合には、ご本人やご家族からの開示請求をするのではなく、裁判所に証拠保全の申し立てをします。証拠保全は、介護事故の事案だけでなく、医療事故の事案においても行うことがありますし(診療録等の証拠保全)、労働事件でも行うことがあります(例えば残業代請求や過労死について安全配慮義務違反の責任を問う場合にタイムカード等を証拠保全する場合など)。
証拠保全とは

証拠保全とは、民事訴訟法234条の規定により認められている手続きです。民事訴訟法では、「裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。」と定めています。
「この章の規定」というのは、民事訴訟法「第4章 証拠」の規定のことであり、「証人尋問」や「当事者尋問」、「鑑定」、「書証」、「検証」があります。例えば、重要な証人が生命にかかわる重病にかかっており、今すぐに証人尋問をしておかなければいけない場合も証拠保全です。
ただ、一般的によく用いられる証拠保全の手続きは、将来訴訟になったときに、相手方から書証を出してもらおうとすると、それが改ざん・破棄等されるおそれがあるので、現状での資料の状態を確認して記録に残しておくという意味での検証手続きです。
証拠保全では裁判官が突然相手方事業所へ行き、
証拠の現物を確認する
証拠保全の申立をすると、通常は担当裁判官との面談を行います。ここで、裁判官から「あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情がある」といえるか(保全の必要性の有無)についての指摘がされたり、保全の必要性があるとした場合に、いつ現地へ行って検証手続を行うか、記録の残し方はどうするかなどの実務的な打ち合わせを行います。そして、裁判官の面談を経て証拠保全を行うことが認められると、証拠保全決定が出されます。
通常の訴訟手続であれば、原告側が提出した訴状は、まず被告側に送達(届けること)され、審理が開始されるのは約1ヵ月後 というように、準備の時間が与えられます。
しかし、改ざん・破棄等をされてしまうおそれがあるから証拠保全の申立をしているのに、証拠保全の申立書や証拠保全決定をあらかじめ相手方に送ってしまったのでは、意味がありません。
そこで、証拠保全では、検証をする当日の検証開始時刻1時間前など、検証を行う直前に、裁判所の執行官が証拠保全の決定を送達(届ける)します。直前にならないと知らせないというのが証拠保全の一つの特徴です。
もっとも、検証対象となる資料を、裁判官が見られるように整理する程度の時間は必要ですので、約1時間前に知らせるのが一般的です。そして、検証開始時刻に、裁判官、裁判所書記官、申立代理人の弁護士(及び申立代理人の補助をする事務員)が現地へ行って、検証対象となる書類等のチェックをし、その状況を裁判所の調書に記録します。
ドラマ「白い巨塔」でも、証拠保全のシーンがあったと思いますが、概ねそのような雰囲気の手続きです。ニュースでよく見る検察庁の特捜部の捜査のようにたくさんの人間が段ボールを抱えて入っていくというようなものではなく、代理人弁護士を含めて5人程度で行くことが多いです。
とはいえ、当日の開始時刻直前に突然訪問して、資料をチェックするという点では、事業所側にはかなりインパクトのある手続きでしょう。資料のチェックといっても、現状を確認する手続ですので、その中身についてその場でどうこうするわけではなく、修正の痕跡がないかなどを目で見てチェックするということになります。過去に、柔道整復過誤の事案で、現物を確認したところ、改ざんされていることが確認できた事案もありました。
証拠保全の効果

証拠保全をすると、相手方が訴訟等を起こされた後に改ざん等を防げるという効果があるほか、以下のような効果もあります。
まず、直接相手方の事業所の中に入って資料の現物をみることができますから、開示請求をする場合よりも資料について裁判官を通じて確認してもらえますので、開示漏れがなくなります。
スタッフ同士の情報共有のために、申し送りをするノートが存在したり、リスクマネジメント会議の議事録が別のファイルに綴じられていて、その中で当該利用者等の状況が議論されていたり、パソコンの中にデータが保存されている場合もあります。その場合も、過去の経験などに基づきながら、「こういう場所にこんな資料がありませんか」ということを裁判官と通じて確認してもらうことで、網羅的に資料を収集することができるのです。
また、「その事案に関する資料は基本的に検証をしたもので全てだ」ということを確認できる効果もあります。例えば、医療事故の事案ですが裁判が始まってから、病院側にとって有利な記載がされている手術記録を提出してきたことがありました。
しかし、その事案では提訴前に証拠保全をしており、病院で診療録を確認したときには、そのような手術記録は存在していませんでした。「証拠保全の時に提示していなかったのに、裁判が始まってからこんなものがありました」といって提出してくるのは、後からつくったのではないかとも考えられますので、証拠保全をしておいて良かったと思える事案でした。
証拠保全の必要性が認められるには
証拠保全の申立が認められるためには、具体的に、保全の必要性というものが認められる必要があります。民事訴訟法234条に定められている「あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情がある」というものがあるのです。
かつては、医療事故の案件でも保全の必要性をさほどチェックしていなかったように思いますが、近時は、保全の必要性についての審査が厳しくなっているように感じます。
そのため、証拠保全の申立書やその申立書に添付するご本人、またはご家族の陳述書では、事業所側が証拠を隠蔽しそうな言動をとっていたことを、具体的に記載しなければなりません。「何となく改ざんされそうな気がする」という程度では、裁判所は証拠保全を認めてくれず、申立が却下されることもあります。
ですから、証拠保全を選択する事案というのは、事故の経緯を具体的に教えて欲しいと求めたけれども拒否されたとか、介護記録の開示を求めたところ一部開示されたものの明らかに存在するはずの資料が抜けているという場合のように、改ざんのおそれ等が認められる事案となります。
最近では、診療録や介護記録を任意で開示請求することが実務的にも定着してきていることもあり、医療事故でも介護事故でも、任意の開示請求をまずは行うことも多いです。ご相談者にとっては、証拠保全をする場合は弁護士費用が余計にかかるというのも、一つの考慮要素となります。
任意の開示請求をするときには ほしい資料を具体的に挙げることが大事

証拠保全の場合、相手方に提示を求める資料に漏れがないよう、検証をする対象資料の目録において、対象資料の名称をざっと挙げます。そして、検証日当日も現地において、こういうものがないか、ああいうものがないかということを確認します。
仮に証拠保全が認められない事案や、任意の開示請求を選択する場合でも、事業所側に開示請求をするときには、単に「介護記録を開示してください」と言うだけではなく、事案に応じて提出してもらいたい資料を、具体的に挙げることが重要です。
文書の名称自体は、事業所ごとに違う可能性がありますので、「アセスメントシートにアセスメントの内容を記載したものを出してください」とか、「サービス担当者会議議事録など介護サービスを行う担当者同士での申し送りや介護内容についての議論の状況がわかるものを出してください」というように、伝えればよいと思います。
また、誤嚥の事案で提供された食事の内容が何かが問題となる事案では、献立表を出してもらうなど、事案によって必要な資料が変わってくることもあります。 食事のケースでは、介護記録には「主8、副10」というように、主食・副菜をどの程度食べたかしか記載がないのが一般的ですので、献立表がなければ、何が提供されたのかはわかりません。資料によっては、他の利用者のことも記載されているので開示できないと言われることがあります。
しかし、その場合は、他の利用者に関する記載はマスキングをしてかまわないので、開示してくださいと求めるべきです。
その他の資料を入手する方法
第1回の「必要に応じてできる情報収集例」で記載した他の資料については、以下のような場合に入手することがあります。
以下では、第1回でご紹介した内容に加え、どのような事案で下記のような資料が必要となり、どのようなことが記載されているかということを少し詳しく記載します。
市町村への事故報告書
介護事業所は、事業所内部での事故報告書を作成している場合もありますが、別途、市町村に対し、介護事故についての事故報告書を提出しているはずです。事故の事実経過について具体的な説明がなされない場合には、市町村に提出している事故報告書を市町村から開示してもらうことで、事故の事実経過等を知ることができます。
事故報告書には、事業主側が事故の原因を何と考えているか、また、再発防止のためにどうすればよいかが記載されていることが多いです。この記載が、過失の有無の判断の参考になる場合もありますし、事業主側が責任についてどのように考えているかも伺えます。さらに、事故報告書には、ご本人またはご家族との話し合いの状況や、損害賠償請求の状況についての記載もあることが多いため、この点についての事業主側の認識も知ることができます。
救急活動記録票
119番通報がされた時刻や救急隊が現場に到着した時刻、病院に搬送された時刻、最初の119番通報の内容等を知るために、救急搬送記録が重要となることがあります、救急活動記録票は、利用者ご本人または遺族が条例に基づき消防局等に開示請求することができます。
誤嚥による窒息の事案や、入浴中に溺れた等の事案は、一刻一秒を争う事案です。事業主側から、119番通報をした時刻や救急隊が到着した時刻について、説明がある場合がありますが、事業所職員も、正確な時刻を把握しているとは限りません。
事業主側が何時何分に119番通報をし、何時何分に救急隊が到着したのか、その時のご本人の状態はどうだったのか、何時何分に病院に搬送されたのか、ということを、正確に把握するためには、救急活動記録票を確認する必要があります。
救急活動記録票には、ご本人が既に心肺停止状態になっていたのに施設の職員がこれに気づいていなかったというような記載がなされていた経験もあり事実の確認や過失の判断にとって重要になる場合も多いです。
介護保険認定調査票
事故前のご本人の心身の状態を客観的に知るために、市町村から開示してもらえる、要介護認定調査時の介護保険認定調査票が参考になる場合があります。
特に、認定調査票特記事項欄には、ご本人の転倒のおそれや、嚥下・咀嚼能力、認知症の程度等が詳細に記載されています。単にチェック表で「できる」、「できない」とチェックされているだけではなく、「家では詰まらせないように少し小さく切って、ご家族が見守りしている」というような具体的な記載があります。前述のとおり、事故前のご本人の心身の状態は、事業主側に、事故が起こることを予見できたかという過失の判断が重要となります。
診療録
事故後、後遺障害が残った事案や、事故と死亡との因果関係が争点になりそうな事案では、介護事故発生後に搬送された医療機関における診療録が必要不可欠となります。診療録は、介護記録と同様、開示請求をすれば開示されます。
資料を取り揃えた後に弁護士は何をするか

以上のような資料を取りそろえた後、弁護士は、事故前から事故後までの事実経過を整理し、過失が認められるか、因果関係はどうかなどを、法的な観点から検討することになります。因果関係が争点になりそうな事案では、事故後に入院等していた医療機関の医師に面談をするなどして、意見を聞く場合もあります。
また、必要に応じて、過失や因果関係、損害額について過去の同種事案の判例とも比較して検討することもあります。以上のような調査を経て、賠償請求ができそうかどうかの見通しをつけ、調査だけで終了するのか、それとも示談交渉や裁判に進むのかを判断していきます。
今回は、介護事故で弁護士に相談してから、証拠保全・調査までの過程を掘り下げてご紹介しました。次回以降では、示談交渉や訴訟についてご説明していきたいと思います。