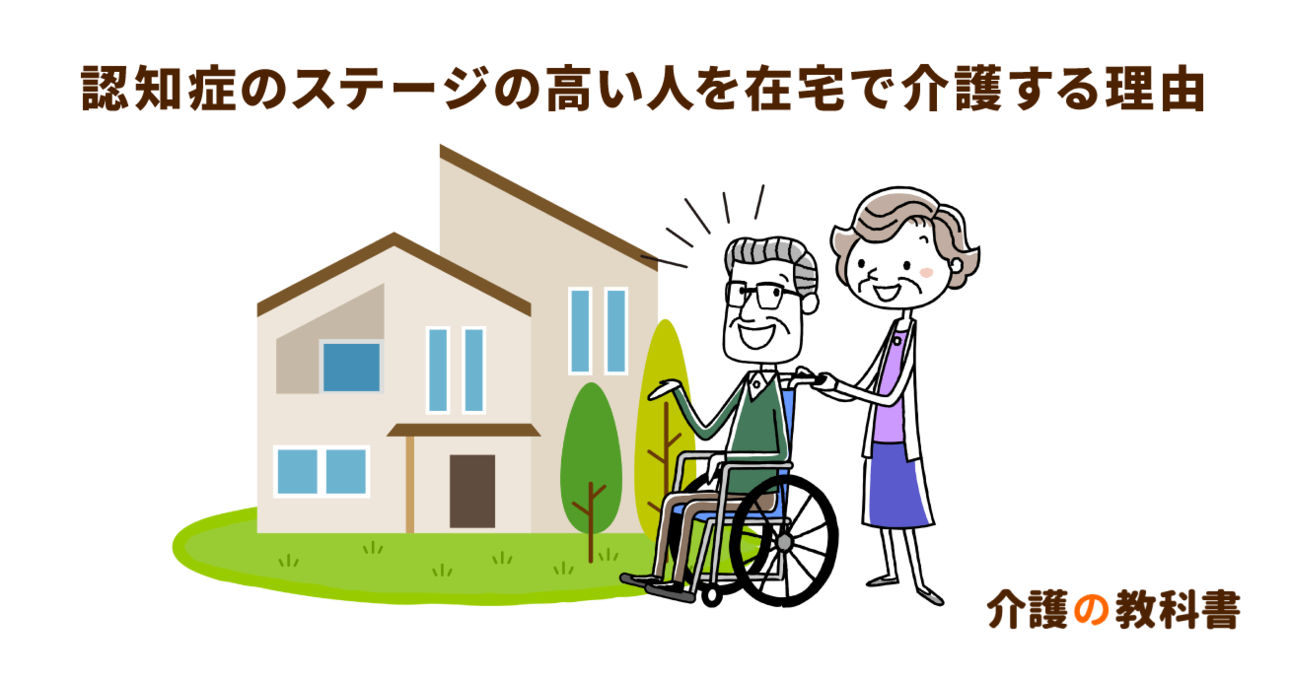こんにちは。フリーライターで、要介護4の祖母を在宅介護して6年目の奥村シンゴです。
今回は、 認知症の祖母を6年間介護してきた者として、認知症発症者本人とその家族が直面するであろう「認知症になった家族をどう受け入れ、周囲に理解してもらうのか」という問題について考えていきます。そして、私自身の経験や認知症の家族を持った著名人の体験談などを交えて語っていきたい思います。
認知症発症者本人への告知は8.2%

今年の4月27日に、女優の朝丘雪路さんが82歳で亡くなりました。その後8月4日、俳優で夫の津川雅彦さんも後を追うかのようにその人生に幕を下ろしました。
朝丘さんはアルツハイマー型認知症を患っていたようで、津川さんは5月20日の記者会見の場で、朝岡さんがアルツハイマー型認知症を5年間、患っていたことを初めて公の場で明かしました。
津川雅彦さんは沈痛な面持ちで「僕のこともね、段々…。それ以上の深い話は勘弁してください。診断書を書いてもらったときにアルツハイマー型認知症と書かれて、それ以外ありませんでした」と、言葉少なく語りました。
認知症の祖母を持つ私としては、すごく考えさせられるきっかけでもあり、もっと多くの人が「認知症」について深く考えるべき機会だと感じました。
2015年のアメリカのアルツハイマー病協会の報告では、発症者本人やその家族に対し、アルツハイマー病を告知するのは45%と低めです。
また、認知症介護研究・研修センターの報告では、日本の医師の 80.2%が「認知症の告知は必要」、74.4%が「患者には病名を知る権利がある」と答えました。
しかし、現実は「場合によって公表している」が56.9%と最も多く、「まったく告知していない」が9.7%、「すべての患者に公表している」のは 8.2%にとどまっています。
これらの調査結果をみると、医者は伝えたいと思っていても、認知症発症者本人や家族に配慮し、知る権利やインフォームドコンセントの考え方が普及してきたといっても、なかなか公表するには至っていないのが現実と言えます。
公表することで周囲の理解を得る

認知症の公表といっても「家族から認知症発症者本人へ公表する場合」と、「家族から職場・友人などの第三者へ公表する場合」の2つがあります。
私の友人は広告業界に勤務し30年間、安定した収入と職業がありながら突然、マンションからシェアハウスへ引っ越してしまいました。
友人は奥さんとは離婚、子ども2人は成人してから一人暮らしで「子供も大きくなって一人で寂しいし、いろいろな人と交流もちたいし」と笑顔で話していたので、それほど気にしていませんでした。
そして、新居での生活が始まり、半年位経過した頃に連絡があり、「実は母親が認知症の進行で、施設に入所したんだよ。だからお金もかかって引っ越したんだ。母親本人にも病状や事情を伝えたら、“わかってたわよ、なにを今さらいうの”と笑われたよ」話してくれました。
私や周囲の友人などに打ち明けるまで、1年かかったそうです。最近は吹っ切れた様子で認知症に関する食事や施設・介護保険の事を積極的に聞いたり、認知症カフェにも通うようになり、情報収集を積極的に行うようになったようです。
芸能人では、俳優の砂川啓介さんが妻の大山のぶ代さんの認知症を公表しました。
二人の体験を綴った本「娘になった妻、のぶ代へ大山のぶ代認知症介護日記」はベストセラーにもなりました。
砂川さんは「入浴もしたがらず、彼女は「入った」というけれど入っていない。歩かなくなり、寝ていることが多く、また脳梗塞かと心配になって調べてもらうと、診断はアルツハイマー型認知症で、もう治らないと僕は考えていました。」と当初の戸惑いを語っています。
そして、「彼女が築き上げた「ドラえもん」のイメージにかかわると思い黙っていました。そうすると、親しい友人たちが病気を察して、あまり連絡してこなくなった。友達をなくすかもしれない。きちんと説明した方がいい。認知症には大勢がなっている。特別なことではないのだからと公表を決意しました。」と家族の認知症を公表するに至った経緯をメディアの前で明かしました。
働き盛りで在宅介護、周囲に公表するか悩んだ3年間
また、私自身も86歳の認知症の祖母を在宅介護して6年目になります。
私の祖母が認知症だとわかり、「ばあちゃん、認知症っていうて頭がボケて、段々いろんなことができんようになんねん。せやけど別に命に関わる病気やないし、一緒におるから大丈夫やで」とすぐに本人に話しました。

すると、祖母は「私、死ぬんなら川へ捨ててね…」と最初は少し弱気でしたが、1ヵ月位すると「なにくそっていう気持ちで負けへんで、頑張るで」と前向きに認知症に向き合うようになりました。
ただ、私の周囲の友人などには、祖母が認知症になってから3年くらいは黙っていました。
「周囲に気を遣わせるのではないか」「施設に入所すればいいといわれたら」「兄弟やほかの家族は何してるの、詮索されるのではないか」と、世間で言えば働き盛りの30代前半で在宅介護をスタートさせた私は、周囲に理解してもらうのは難しいと考えていました。
しかし、祖母の要介護度が2から4に上がったことや、母親が大腸ガンになったりして、なかなか飲み会など誘われても行けなかったり、自分の介護体験談を書きたいという思いも出てきたりしたので、公表することにしました。
そうすると、幼なじみが堰を切ったように「俺さ実は、母親が祖母を介護してて、揉めることが多くてさ、週末になったら実家に帰って悩みや愚痴を聞いてるんだ。それぐらいならできるかなと思って。」と悩みを打ち明けてくれました。
それ以来、幼なじみとは2ヵ月に1回程度飲みながら、愚痴をこぼしたり、悩みを聞いたり、聞いてもらったりして発散しています。
在宅介護をしながら所得を得る新しい時代が
2025年には認知症が700万人を超えるといわれ、今後は「認知症のおばあちゃんの在宅介護をしたい」「介護の体験談を書いて記事を書いたりして仕事をしたい」と素直に言える社会作りが不可欠だと思います。
政府は「介護離職ゼロ」を掲げていますが、介護離職後、就職活動しても再就職できない人が6割に上り、介護施設の整備で対応を図るとしていますが、2025年には33万人超の人材不足になるという厚生労働省が見通しを立てており、在宅介護者も急増するものと予想されます。
例えば、日立製作所が社員の過半数の10万人、MIKIや昭和シェル石油が全社員を対象にしたようなテレワークや在宅勤務が徐々に増えていくと思われます。
介護をしながらでも、育児や仕事ができるように、テレワークを導入し、職場と同じ環境で仕事ができたり、WEBメディアや出版物に自宅で介護の体験談を書いたり、誰でも無料で本を出版できるKindleを利用したり、Youtuberが誕生したりと少しずつ多様な働き方が可能になりつつあります。今後はAIやVRなどのテクノロジーと融合しながら、さらに普及するものと思われます。在宅介護をしながら、世間並みかそれ以上の所得を得られる未来は、そう遠くはないかもしれません。