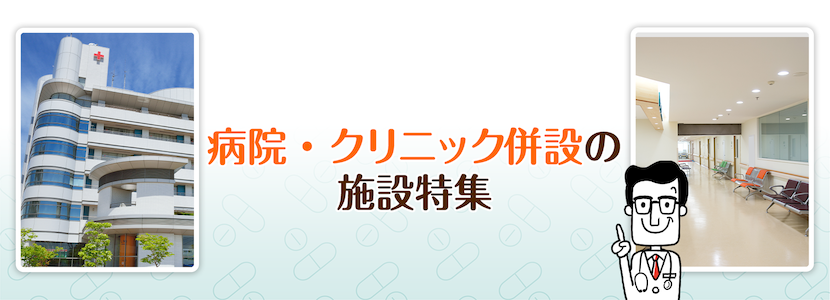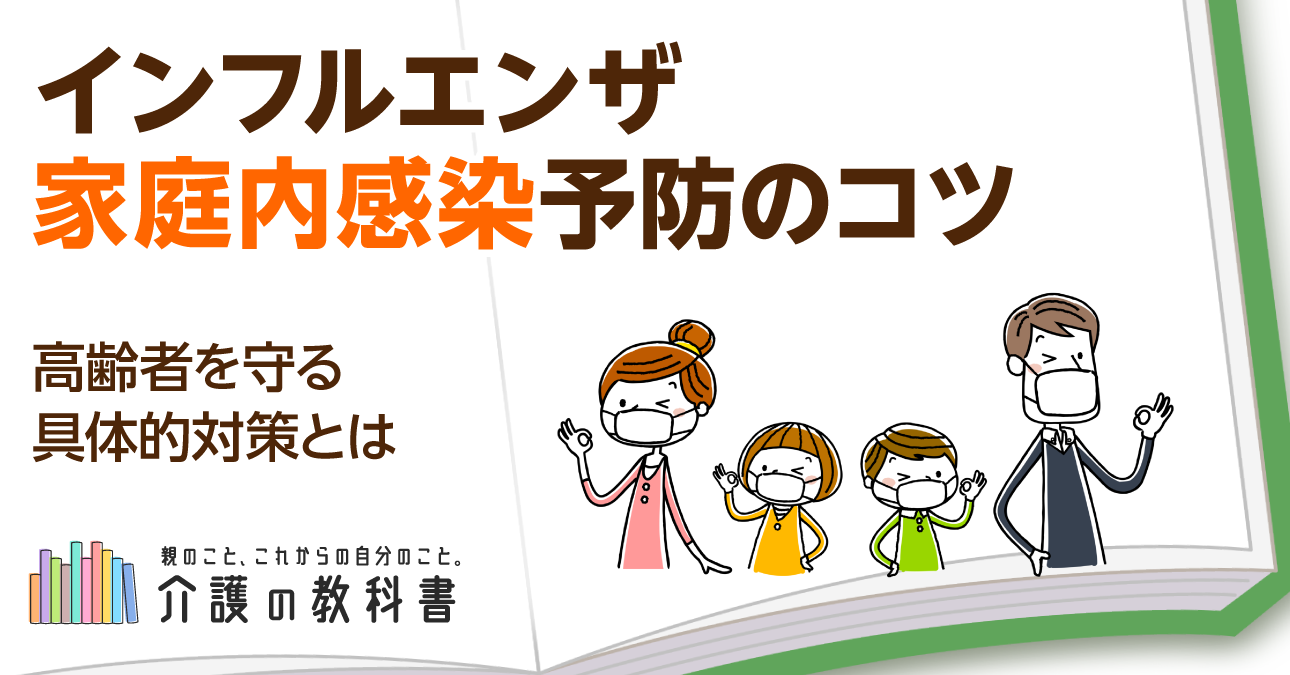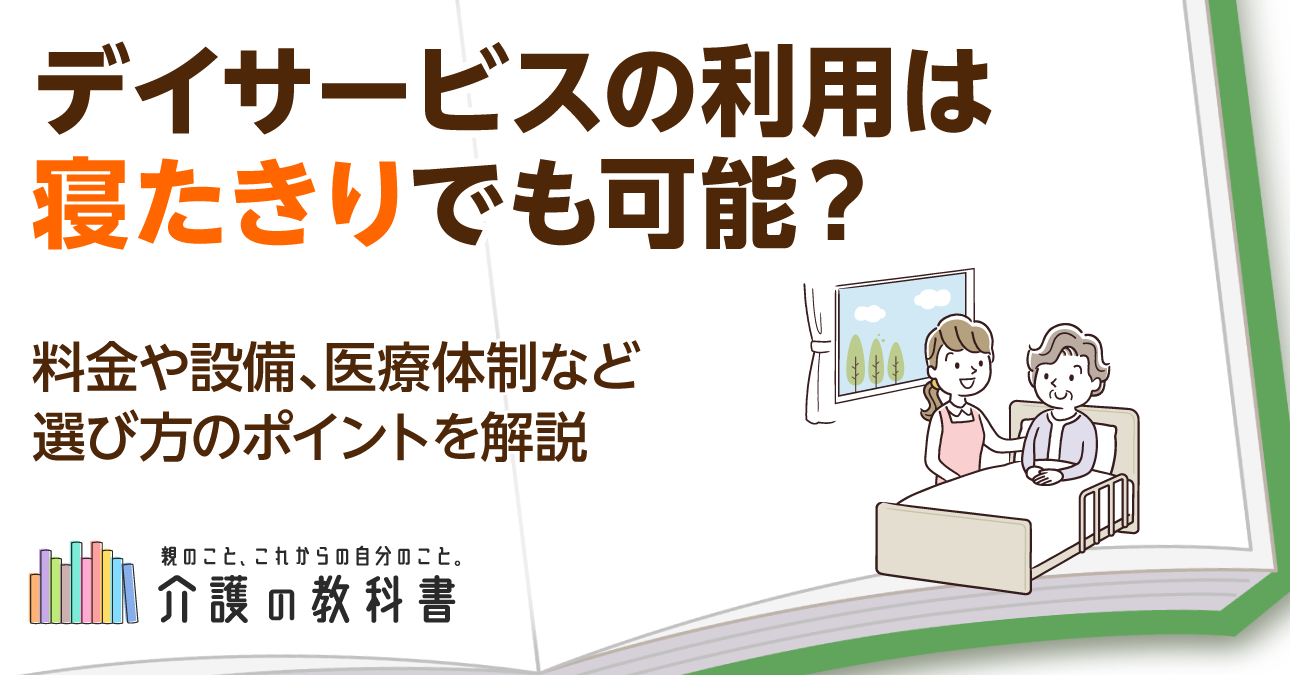ナーシングホームとは?特徴や受けられるケアなどを解説
ナーシングホームという言葉を耳にしても、具体的にどのような施設なのかイメージしにくい方は多いかもしれません。ここでは、ナーシングホームの基本的な特徴や受けられるケア、費用について詳しく見ていきましょう。
ナーシングホームの特徴
ナーシングホームは、医療ケアと日常生活の介護を総合的に提供する介護施設です。もともとは1960年代にアメリカや北欧諸国で誕生した欧米の呼び方で、日本ではまだ法律上の明確な定義はなく、実際には有料老人ホーム(介護付き/住宅型)として運営されていることが多いです。
しかし、24時間365日看護師が常駐し、医療依存度の高い方でも安心して生活できる体制を整えている施設が多い点が大きな特徴です。ただし、看護師の常駐可否や時間帯は施設により異なるため、入居前に実際の体制を必ず確認しましょう。
日本では、主に有料老人ホーム(介護付き・住宅型等)のうち医療連携を強めた施設がこの名称を使用しています。一般的な介護施設では対応が難しい医療的ケアが必要な方、重い病気を抱える方などが主な入居対象です。
ナーシングホームが日本で必要とされるようになった背景には、急速に進む高齢化があります。高齢者の増加に伴い医療ニーズも高まる一方で、病院のベッド数には限りがあり、医療現場の人手不足も深刻化しています。
また、核家族化や共働き世帯の増加により、自宅での介護や看取りには大きな負担がかかるようになりました。
こうした社会的背景から、病院と自宅の中間に位置する施設として、医療と介護を一体的に提供できるナーシングホームへの注目が高まっているのです。
どんな人に向いている?受けられる医療的ケアの範囲
ナーシングホームは、医療依存度が高く、一般的な介護施設では対応が難しい方に適した施設です。具体的には、以下のような方が入居対象となります。
- 病気やケガで退院した後、自宅での生活が困難な方
- 入院治療を終えても、日常的に医療的な管理が必要な場合、自宅では家族の負担が大きくなりがちです。 ナーシングホームでは、看護師が常駐しているため、退院後も継続的な医療ケアを受けながら生活できます。
- 脳血管疾患の後遺症など重度の障がいがある方
- 脳梗塞や脳出血の後遺症により、身体機能に障がいが残った場合、日常生活全般に介助が必要となります。 リハビリテーションと医療的ケアを組み合わせたサポートを受けられる環境は、回復や生活の質の維持に役立つでしょう。
- 医療依存度が高い方
- 人工呼吸器や胃ろう、中心静脈栄養などの医療処置は専門的な知識と技術が必要で、一般的な介護施設では対応できないケースも少なくありません。 ナーシングホームでは、看護師が24時間体制で見守ることが多いため、高度な医療的ケアが必要な方でも安心して過ごせます。
- 終末期を住み慣れた環境で穏やかに過ごしたい方
- がんなどの病気で終末期を迎えた際、病院ではなく、落ち着いた環境で最期の時間を過ごしたいと考える方は多いでしょう。 ナーシングホームでは看取りまで対応できる施設も多く存在しており、緩和ケアを受けながら、その人らしい最期を迎えることが可能です。
受けられる医療的ケアの範囲は施設によって異なりますが、多くのナーシングホームでは、さまざまな医療ニーズに対応しています。提携医療機関の医師による訪問診療や往診も定期的に受けられるため、急な体調変化にも迅速に対応できる体制が整っているのです。
ナーシングホーム入居にかかる費用はどのくらい?
ナーシングホームへの入居を検討する際、多くの方が気になるのが費用面でしょう。医療体制が充実している分、一般的な介護施設よりも費用が高くなる傾向にありますが、施設によって料金設定には大きな幅があります。
入居一時金
0円から数千万円まで施設によって大きく異なります。都市部の高級施設の中には1,000万円を超えるものもありますが、一方で、入居一時金が不要な施設も増えています。退去時には未払い賃料や原状回復費用を差し引いて返還される仕組みが一般的です。
月額費用
10万円から45万円程度と幅広く、平均すると10万円から15万円程度が相場です。家賃相当額、食費、管理費、水道光熱費などが含まれます。
月額費用の一般的な内訳は以下の通りです。
- 家賃:3万円から15万円程度(施設の立地や居室の広さによって変動)
- 管理費:1万円から3万円程度(共用部分の維持管理や事務管理費)
- 食費:4万円から6万円程度(1日3食分)
- 介護サービス費:1万円から3万円程度(介護保険の自己負担分、要介護度に応じて変動)
これらに加えて、医療費、おむつ代、理美容費、クリーニング代などが別途必要となり、月額2万円から5万円程度の追加費用がかかるでしょう。
費用負担を軽減する方法として、高額医療・高額介護合算療養費制度や医療費控除などの制度が活用できます。また、生活保護を受けている方や特定疾病の方に対して、家賃負担を軽減している施設もあるため、実際の費用については気になる施設に直接問い合わせることをおすすめします。

ナーシングホームと老人ホームの違い
ナーシングホームと一般的な老人ホームにはどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)といった代表的な施設との違いを詳しく比較していきます。
ナーシングホームの法的位置づけと目的
ナーシングホームは、主に民間運営の有料老人ホームに該当し、住宅型有料老人ホームや介護付き有料老人ホームの形態で運営しています。
目的としては、医療依存度の高い方に対して、医療と介護を一体的に提供し、看取りまで対応することを掲げています。終身利用が可能で、住み慣れた環境で最期まで過ごせる点が大きな特徴です。
これに対し、特別養護老人ホーム(特養)は老人福祉法に基づく公的な福祉施設です。常時介護が必要で自宅での生活が困難な高齢者に対し、日常生活の支援と介護を提供します。
終の棲家として長期的に暮らせる生活の場を提供することを目的としており、その人らしさを支えるケアを重視しています。
介護老人保健施設(老健)は介護保険法に基づく施設で、病院を退院した後、在宅復帰を目指してリハビリテーションや医療的ケアを受けるための施設です。
病気やケガの治療・リハビリを優先する中間施設としての役割を担っているため、機能回復に重点が置かれています。
人員配置や医療体制の違い
各施設で提供されるケアの質は、配置されているスタッフの人数や職種によって大きく変わります。人員配置基準と医療体制に明確な違いがあります。
特養の人員配置
- 介護職員と看護職員が入居者3人に対して合計1人以上
- 医師については常勤の義務がなく、非常勤で対応している施設が多い
医療面よりも日常的な介護サービスに重点が置かれています。必要に応じて医療機関と連携しながら対応する体制です。
老健の人員配置
- 医師の配置義務があり、看護・リハ職の配置基準も定められている
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が入居者100人に対して1人以上配置
老健は専門的なリハビリテーションを受けられる体制が整っているのが特徴です。医療色の強い施設と言えるでしょう。
ナーシングホームの人員配置
ナーシングホームは法的に明確な施設区分がなく、実際には「介護付き有料老人ホーム」や「住宅型有料老人ホーム」として運営されています。
そのため、一律の人員配置基準があるわけではなく、施設の運営形態によって基準が異なります。一般的な有料老人ホームの人員配置基準は以下の通りです。
- 管理者:入所定員にかかわらず1人以上
- 生活相談員:入所者数が100人又はその端数を増す毎に1人以上
- 介護職員:入所者の数が3人に対して1人以上
- 看護職員:入所者数に応じて決められた数以上を配置する
- 栄養士又は管理栄養士:1人以上 を配置
- 機能訓練指導員:1人以上 を配置
- 介護支援専門員:1人以上 を配置
一般的な有料老人ホームでは日中のみの看護師配置が多い中、夜間も看護師が常駐し、急な体調変化にも迅速に対応できます。難病の方や看取り対応、精神疾患や認知症など、幅広い病状に対応できる医療体制が整っている点が大きな強みとなっています。

入居要件や費用の違い
介護施設を選ぶ際、入居条件を満たしているか、費用負担はどの程度かを確認することは欠かせません。各施設では、入居要件と費用体系に大きな違いがあります。
入居条件
- 特養(特別養護老人ホーム)
- 原則として65歳以上で要介護3以上の方が対象です。
要介護1・2は「特例入所」として、在宅が著しく困難等の要件を満たす場合に限り認められます。
申し込みは緊急度の高い順に入居が決まるため、待機期間が比較的長くなる傾向があります。 - 老健(介護老人保健施設)
- 65歳以上で要介護1以上の方が対象で、在宅復帰支援を目的としています。
医療・介護上の必要性や空床状況等を踏まえて受け入れが調整されます。 - ナーシングホーム(介護付き・住宅型有料老人ホームなど)
- 施設によって入居条件が異なります。
介護付き有料老人ホームは入居時に要支援・要介護の認定が前提です。
一方、住宅型は自立〜要介護まで幅があります。
費用面
- 特養(特別養護老人ホーム)
- 多床室の場合は月額8万円程度から、ユニット型個室でも月額15万円程度が目安です。
世帯所得に応じて居住費・食費の減免制度があり、公的施設のため入居一時金は不要です。 - 老健(介護老人保健施設)
- 特養よりやや高めで、多床室で月額9.5万円程度から、ユニット型個室で月額15万円程度が相場となっています。
- ナーシングホーム(介護付き・住宅型有料老人ホームなど)
- 民間運営が中心のため、費用は施設によって大きく異なります。
入居一時金は0円から数千万円と幅広い価格帯があり、月額費用も施設によって大きな幅があります。
医療体制が充実している分、特養や老健と比べて費用は高めになる傾向がありますが、24時間の医療ケアが受けられる安心感と、終身利用が可能な点を考慮すると、費用対効果は高いと言えるでしょう。
ナーシングホームの失敗しない選び方と準備
ナーシングホームを選ぶ際には、自分や家族に合った施設を見極めることが重要です。ここでは、施設選びのポイントや契約前の確認事項、入居に向けた準備について詳しく解説します。
自分にあうナーシングホームを見つける為のコツ
ナーシングホーム選びで失敗しないためには、以下のようないくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
- 必要な医療的ケアが提供されるかどうか
- 看護師の配置体制(24時間365日常駐しているか、夜間の看護体制があるか)
- 提携医療機関との連携体制
- 立地条件と面会のしやすさ
- 費用の内訳(医療ケアの追加料金はどの程度かかるのか)
施設見学では、実際の雰囲気やスタッフの対応を自分の目で確かめることができます。居室の清潔さ、入居者の表情やスタッフとの関わり方などを観察しましょう。複数の施設を見学して比較することで、自分に最も合った施設を見極められます。
ナーシングホームの契約前に確認しておくべきこと
契約後のトラブルを避けるため、以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。
契約内容の確認
特に以下の項目は後々のトラブルの原因になりやすいため、十分に理解するまで質問しましょう。疑問点をそのままにせず、納得できるまで確認することが大切です。
- 入居一時金の償却ルール
- 月額費用に含まれるサービスの範囲
- 追加料金が発生する条件
- 退去条件と返金ルール
医療的ケアの継続性
現在受けている医療処置が入居後も継続して提供されるか、病状が悪化した場合の対応はどうなるかを明確にしましょう。口頭での説明だけでなく、契約書や別紙の覚書などで文書化してもらうと安心です。
看取りへの対応方針
終末期をどのように過ごせるのか、看取りは施設内で可能か、家族の立ち会いはどこまで認められるかなどを確認しておきましょう。事前に話し合っておくことで、入居後の不安やトラブルを防げます。

ナーシングホームの入居に向けた準備と心構え
ナーシングホームへの入居が決まったら、スムーズに入居を進めるための準備を進めましょう。物理的な準備だけでなく、心の準備も大切です。
- 必要書類の準備
- 施設によって求められる書類は異なるため、事前に確認して早めに準備を始めましょう。
診断書の取得には時間がかかることもあるため、余裕を持って手配することをおすすめします。 - 持ち込む荷物の準備
- 施設によっては持ち込める物品に制限がある場合もあるため、事前に確認が必要です。
使い慣れた家具や思い出の品を持ち込むと、新しい環境にも馴染みやすくなるでしょう。 - 現在利用している医療機関やケアマネジャーへの連絡
- 入居後は施設の提携医療機関が主治医となるケースが多いため、診療情報提供書を作成してもらうなど、
医療情報の引き継ぎを円滑に進める必要があります。
入居後は、施設のスタッフや他の入居者との関係づくりを大切にしましょう。スタッフには本人や家族の希望や不安を率直に伝え、コミュニケーションを積極的に取ることで、より快適な生活環境を作ることができます。
まとめ
ナーシングホームは、24時間365日看護師が常駐し、医療依存度の高い方でも安心して暮らせる施設です。特養や老健と比べて医療体制が充実しており、胃ろうやたん吸引などの高度な医療的ケアにも対応できます。
しかし、これらの看護体制や対応できる医療的ケアの内容は施設差が大きいため、24時間体制の有無・医療対応範囲・看取り可否を事前に確認しましょう。
施設選びでは、必要な医療的ケアが提供されるか、看護師の配置体制、提携医療機関との連携などを事前にしっかりと確認しておくことが重要です。適切な準備を行うことで、本人にあった安心の生活をスタートすることができるでしょう。