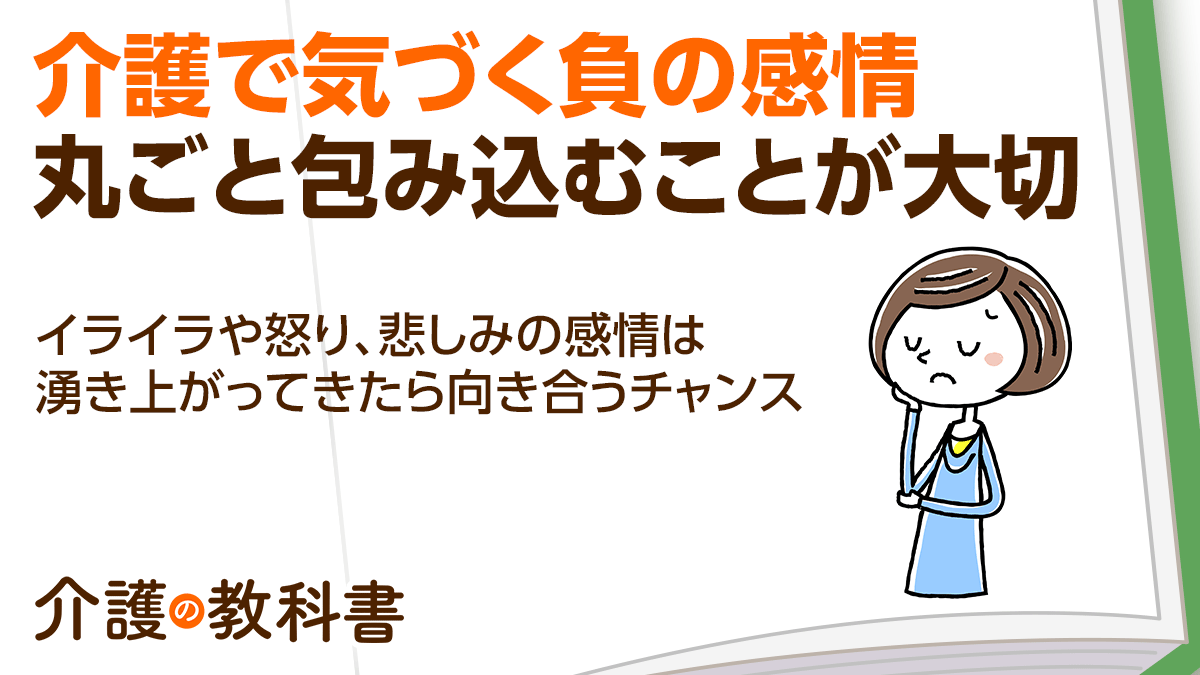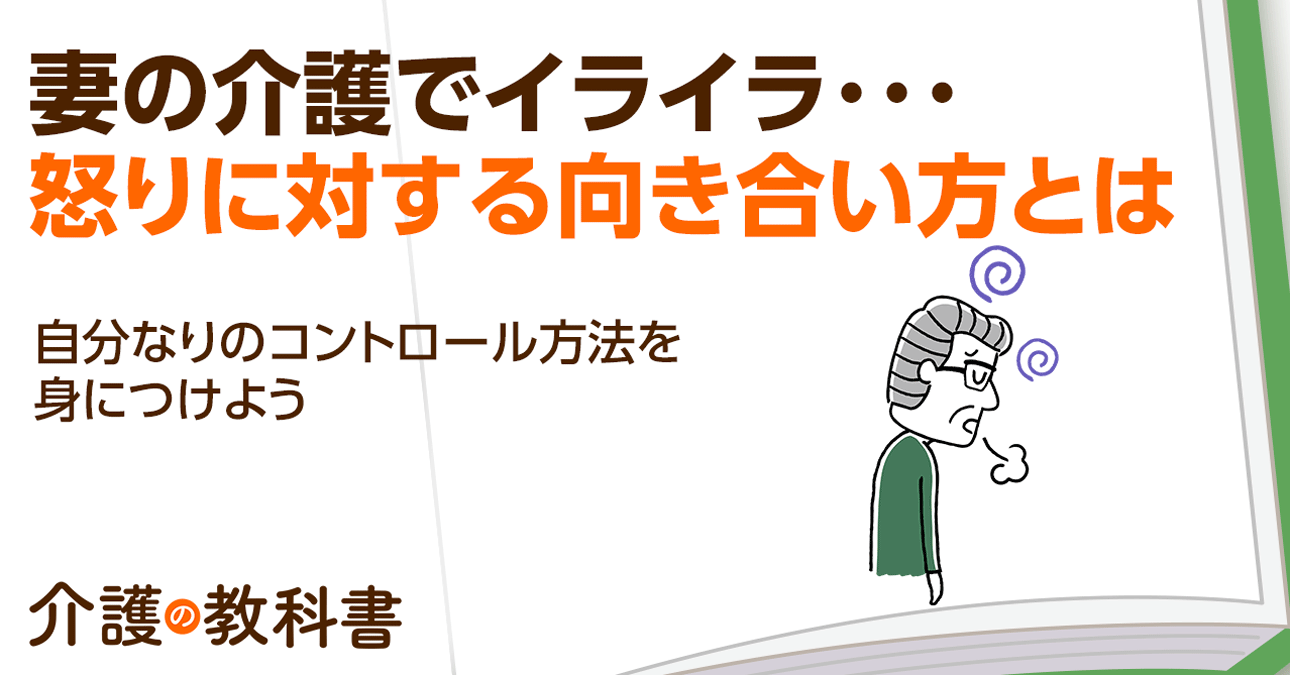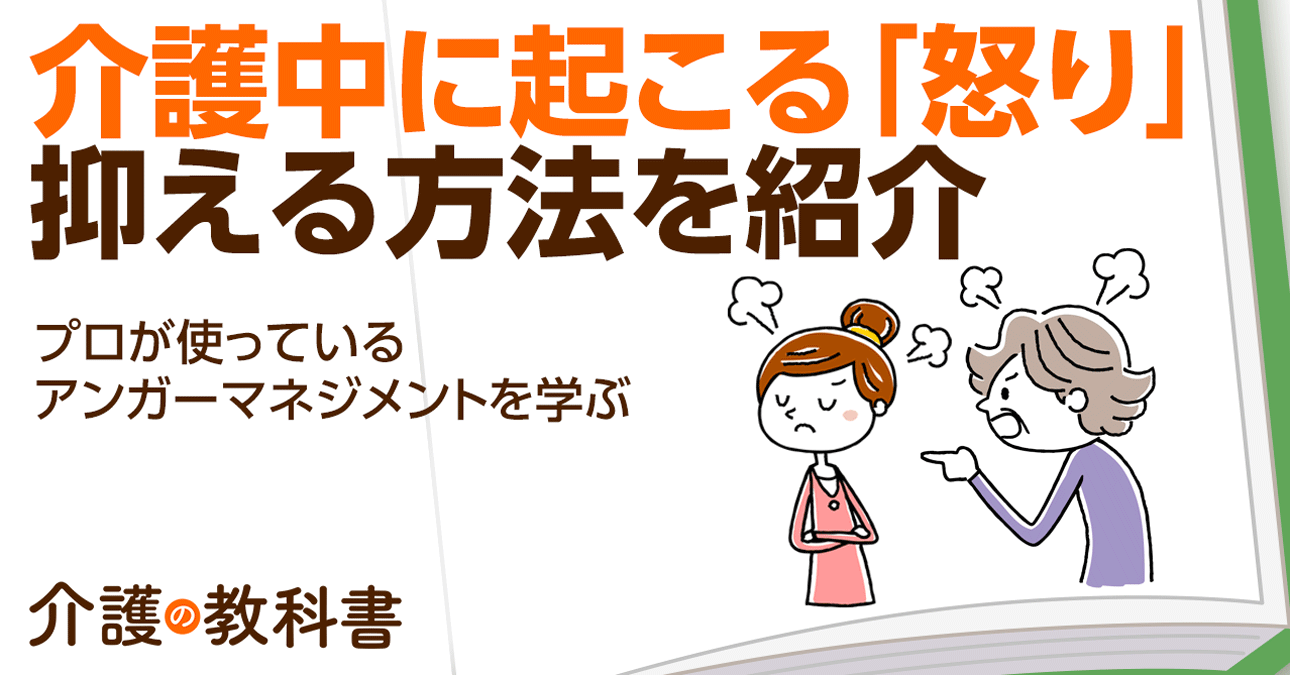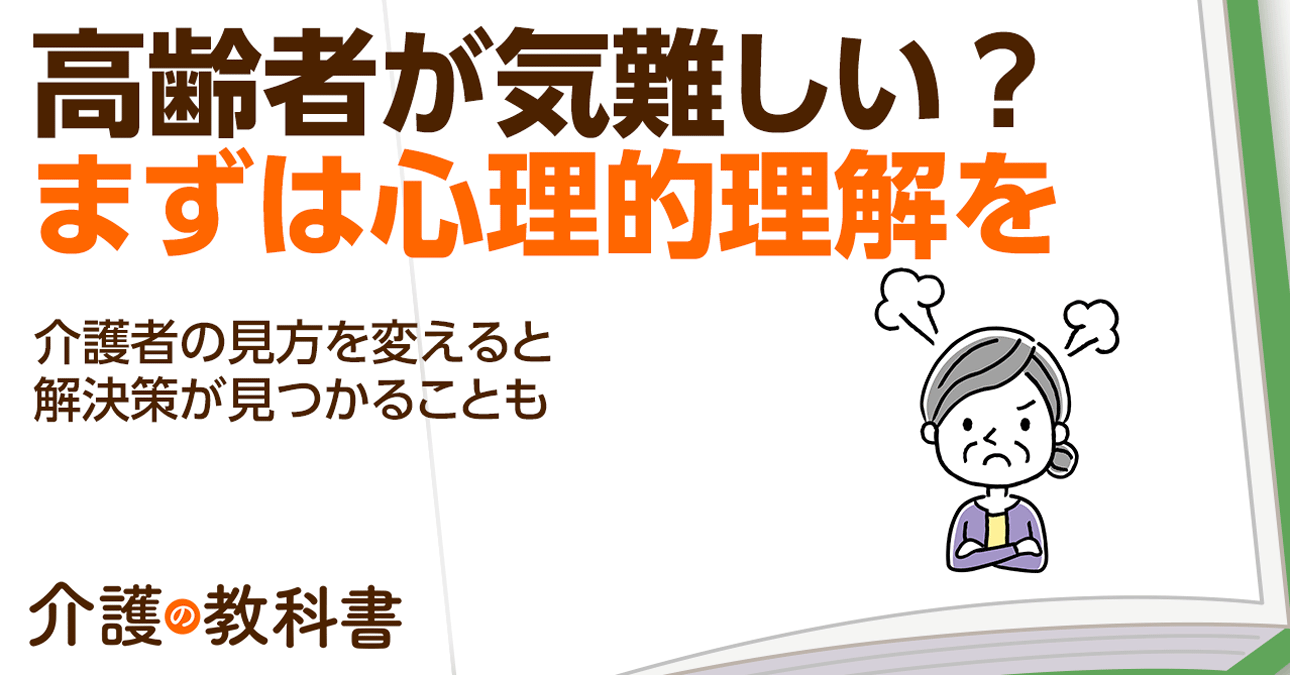介護がきっかけで、幼い頃から積もった親への恨みの感情に気付くときがあります。
そのときに、「親には、お世話になったのに自分はなんて醜い心の持ち主なんだ」とその感情を閉じ込めてしまいたくなるものですが、実はそれが逆効果な場合も…。
今回の記事では、介護がきっかけでわかった母親への複雑な感情とそれと上手に向き合う方法を解説していきます。
ただのイライラではなく、根底から湧き上がる怒りを感じる
実親の介護をきっかけに、これまで奥底にしまっていた自分の感情に気付く場合があります。
そのときに、なんとも言えない不快感が伴うことも多いです。筆者が、過去関わったことのあるRさんの事例を紹介します。
【事例】Rさん(女性・50代)
Rさんは、実母(82歳)と2人暮らしです。母はRさんが幼い頃離婚し、ひとりでRさんと妹を育ててきました。
もともと母はしっかり者で、母子家庭でも娘2人を育ててくれたことにRさんは感謝していました。ただ、Rさんができないことがあると妹と比べて「あんたは頭が悪いわね」などと言ってしまうことも。余計な一言を言ってしまう性格だったのです。
また、母は神経質で何にでも口を出したがる人で、Rさんが結婚を決めたときも母の反対が原因で破談になったことがありました。
妹が結婚して家を出た後もしばらく母と同居していましたが、母を一人置いて自分が家を出るのにも罪悪感を持っていました。
Rさんはいつも自分に自信が持てず、人に意見を言うのが苦手で、人見知りの性格。結婚が破談になってからは、心のどこかではいつもモヤモヤしていたのです。
そんな母が認知症になり、弱った口調でRさんに話しかけると、優しくしてあげたくなる半面、イライラがとまらないのです。
それは、ちょっとしたイライラではなく、心の奥底の傷をつつかれたような感覚でした。
Rさんは何故こんなにイライラしてしまうのか分からず、そんな自分にも嫌気がさすのです。そして、自分の人生を漠然と「むなしい」と思い、悲しくもなりました。
Rさんのように、母との関係の中で「あのときされたこと」を引きずり、傷が癒えないまま、それを抱え苦しむ人がいます。
そして、そんな自分のことを「小さい人間だ」と思い、余計に苦しくなってしまうのです。
今回の事例の要点を整理してみましょう。
- 母親が過干渉であった
- 母の余計な一言でRさんを傷つけた過去があった
- Rさんは母親にいつも従っていた
- 介護が始まって認知症になった母
- 母親がRさんに甘えるようになってから、心の奥底で母親を許せていなかった自分の感情に気付いた
ずっと昔から、Rさんの心の中で眠っていたものです。しかし、このタイミングで忘れていた感情が再び顔を出したのはなぜでしょう。それは、不消化のまま感情を奥底にしまっておいたからです。
過去のトラウマで感情が爆発しそうなときは、辛いものですが、ポジティブに捉えればそれは自分自身を振り返るチャンスです。
ここで、しっかりと自分と向き合えば、これまでの「怒りの感情」と決別することができます。
ここからは、Rさんの事例をもとにアンガーマネージメントを用いた感情のコントロール方法を紹介していきます。
アンガーマネージメントを活用して、眠っていた感情ともう一度向き合おう
アンガーマネージメントは、感情をコントロールするための手法ですが、表面的な感情のコントロールだけでなく、奥底に眠った根深い負の感情と向き合うきっかけにもなります。
そこで、アンガーマネージメントの手法も使いながら、Rさんのケースに沿った感情との向き合い方とコントロールの仕方を紹介していきます。
➀まず、紙に感情を書き出して整理してみる
Rさんがもやもやしたり、イライラするのは、自分の感情が漠然としていて、自分自身で「何に対してどんな感情を抱いているのか」を正確に理解していないことが原因の一つでもあります。
まずは箇条書きで、母への思いを少しずつ書いていきましょう。

最初は悪口でも良いです。
少しずつ感情が書けたら、そこから自分が何を求めていたのかを考えてみましょう。
【例】
頭が悪いなんて娘に言うなんて馬鹿じゃないの!
=自分のことを認めてほめてほしかった。もっと寄り添ってほしかった
怒りの感情というのは、ほとんどの場合、悲しみの感情が変化したものです。
根本の悲しみの感情をまずは自分で思い出すことができたら、あとはそれを癒してあげるだけです。
➁いまの「私」が過去の「私」を包み込む
自分の中にあった悲しみと再び出会えたら、それを包み込んであげる作業をしましょう。
思い出した悲しみに対し、「あのとき私はなんと言ってもらえたらよかったのだろう」と考えてみてください。
自分が過去に言ってほしかった言葉を今の自分が言ってあげるのです。
自分のことを認めてほめてほしかったこと、もっと寄り添ってほしかったことを求めていたのであれば、「あのとき私は頑張ったよね。私はわかっているよ」などと心の中で自分に声をかけてあげてください。声に出してみても効果的です。
➂「すべき」を捨てる
本当は母に甘えたかったけど、それができず、認知症になって自分に甘える母が許せないRさん。
自分がしたくてもできなかったことを平気でやっている相手に怒りを覚えるのは自然なことかもしれません。しかし、母親が自分本位な言動をしてしまうのには、理由があります。
それは、娘であるRさんが「母の言うことを聞くべき」「母のことを喜ばせるべき」と思い込み、母親の言葉をこれまで全て受け入れてきたからです。
娘に受け入れられてきたからこそ、母は何の問題も感じず、Rさんに次から次へと自分の意見を押し付けるようになったのでしょう。そして、娘に甘えることを「我慢」させてきたのです。
今すぐには難しくても、少しずつ自分を苦しめている「すべき」を疑う勇気を持つことが大切です。今一度、自分の中の「すべき」は自分を苦しめているものではないかと見直してみましょう。
母との関係性を見直す
アンガーマネージメントで感情との向き合い方の流れを知ったら、関係性を今一度見直してみましょう。
娘を苦しめる共依存
幼少期は親のことを「神様」のように思い、親の細かい言動一つひとつに大きな影響を受けて育った方もいるかもしれません。
ただ、その感覚がいつまでも抜けないと、精神的に自立できず、親の影響を受けすぎた大人になってしまうのです。
今回のケースで言えば、Rさんから見れば「なんでも口を出して自分の意見を押し付け、私の人生をめちゃくちゃにした母親」なのでしょうが、実は違います。
「母親がそういう人間だった」ではなく、母親の言葉を「受け入れなければならない」と思い込んでいたRさん自身が引き寄せた現実でもあるのです。
- 母親を悲しませてはいけない
- 自分の幸せを優先してはいけない
また、心のどこかでこのように思っているからこそ、母と2人で暮らす選択をしたのでしょう。
母と2人で暮らす選択をしたこと自体が間違っているわけではありませんが、「自分の幸せは優先してはいけない」という考え方のままいけば、Rさんの今後の人生を更に苦しめてしまう可能性が高いです。
なぜなら、「自己犠牲することが普通」という感覚でいると、今後もあらゆる場面で自分の気持ちを優先するのを諦めるようになるからです。

母との理想的な心の距離
一番良いのはいい意味で、親のことを他人として見られる状態です。
自分の「神様」であった状態から、アンガーマネージメントの方法を用いて、自分と別人格の「1人の人間」として見ることで、いままでとは違った関係を築くことができます。
過去の親とのトラブルで、その恨みが未だに晴れない感覚であれば、親の影響を受けすぎているかもしれません。
親のことを「ただの人なんだ」「この性格ならしょうがない」と心から思うことができれば、これまでの関係で親のことを恨んでいたとしても「この人も完璧ではないからあの時は仕方がなかったのだ」と心から許すことができます。
そもそも、親子関係の摩擦というものは、すれ違いにより起こることが大半です。
本当は母親にも母親なりの思いがあっての言動だったのかもしれませんし、母自身が同じような境遇の中育ってきたことが原因であるのかもしれません。
いずれにせよ、育ってきた中での親とのすれ違いは、親の思いと子供の気持ちにズレが生じて起こることであり、それをどちらかが過剰に受け入れたことでエスカレートしてしまった結果です。
自分を大切にし始めたとき、母を人として初めて尊重できるようになる
今回はRさんの主観をもとにした解説でしたが、事例に出てきた母親も、紹介したような性格に至ってしまった原因が必ずあります。
冷静に考えられるようになったら、その背景まで想像できるようになり、母親のことを「まぁ仕方ないよね」と許せるようになるかもしれません。
また、「すべき」の思い込みに支配されての介護は、相手を一人の人として、尊重できている状態であるとはいえません。
怒りの感情は苦しみも伴いますが、決してそれだけでなく、自分自身の不消化な感情と向き合うチャンスです。上手く乗り越えれば、これまでとは違った感情で母や介護と向き合うことができるでしょう。
もちろんアンガーマネージメントの手法を使って、劇的に自分が変わるということはありません。
1人で気持ちを整理することが難しければ、オンラインで受けられるカウンセリングなどを頼ってみるのもおすすめです。
オンラインカウンセリングと検索してみれば、電話やLINEで心を整えるお手伝いをしてくれるカウンセラーさんと繋がることができます。
自分に合った方法で、少しずつ、心と向き合い、自分と相手の両方を大切にできる人生へと変えていきましょう。