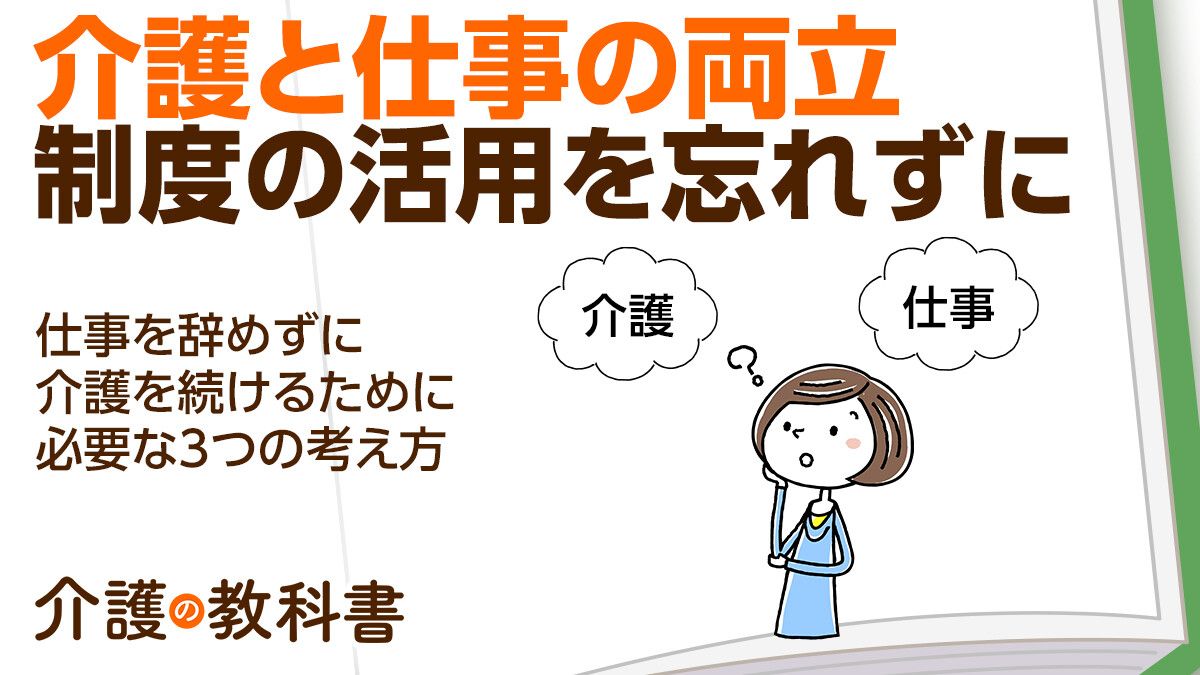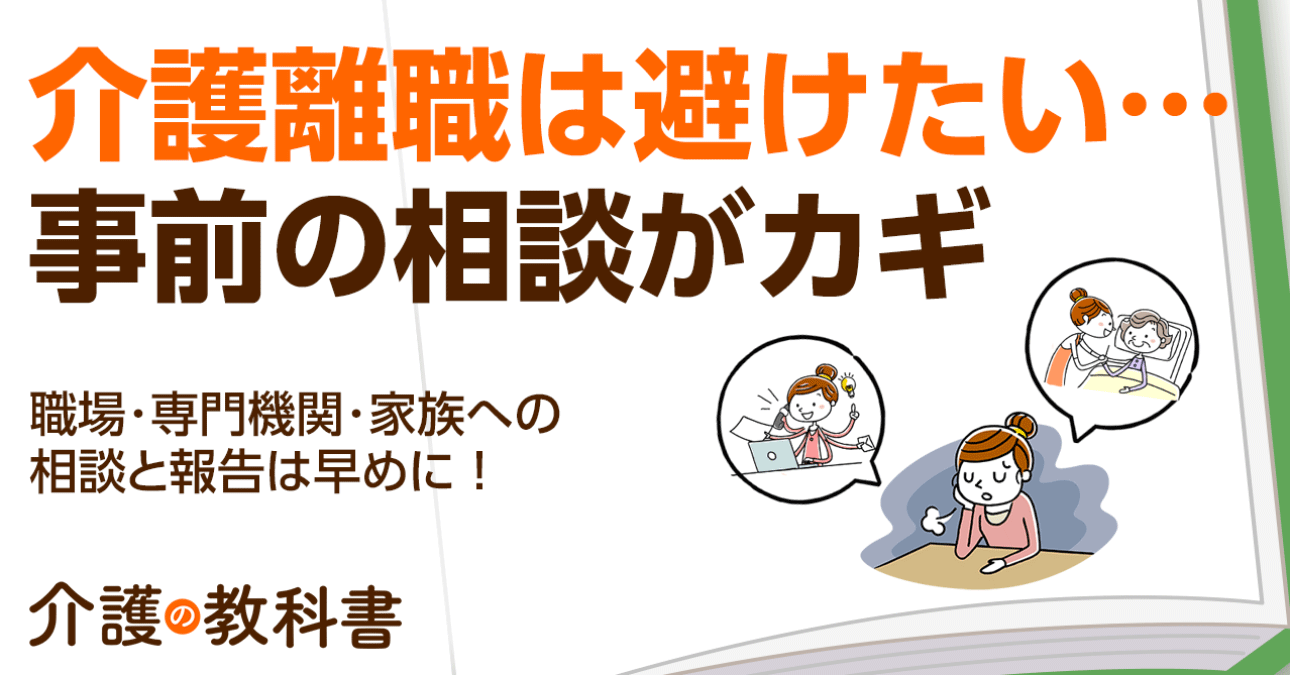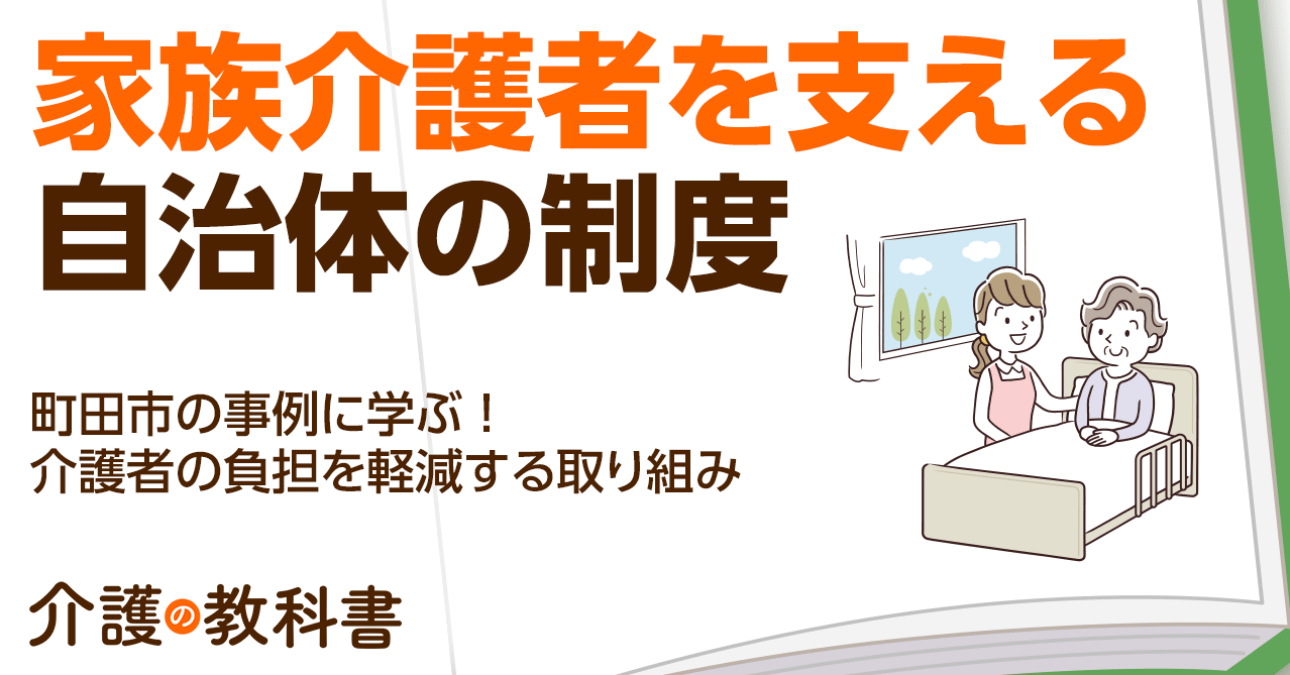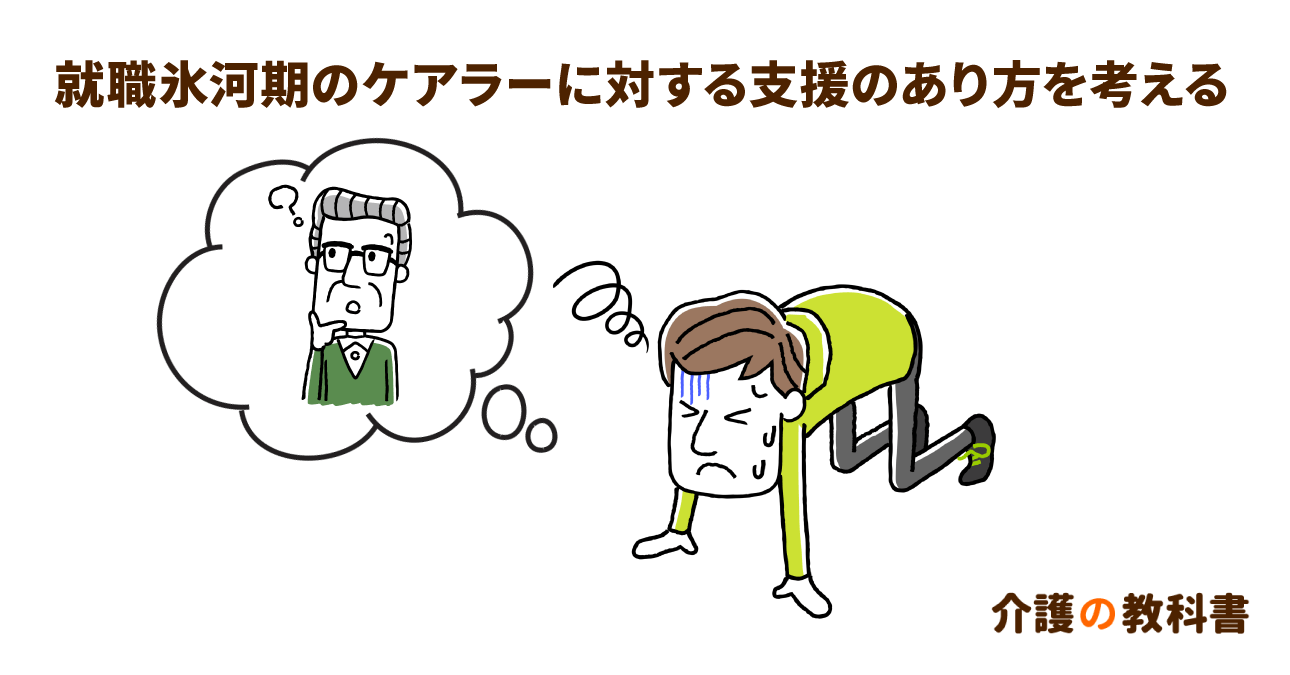「家族の介護が必要になり、会社を辞めて介護に専念したほうがいいのか?」
「介護と仕事の両立をしたいが、どんな方法があるの?」
「職場の人たちに迷惑をかけるようで介護休暇は取りにくいのでは?」
このように介護と仕事の両立に悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
2022年現在、日本は高齢化率29.1%の超高齢社会であり、介護を理由に離職される方は年間で10万人以上いるとされています。また2042年までに高齢者の数が右肩上がりに増えていくとされているので、介護が必要になる人の数も増えていくでしょう。
今回は、介護と仕事を両立するためのポイントを紹介します。
法律を知っておくこと
現在、国は介護離職ゼロを目指して、さまざまな環境を整備しています。
そのうえで重要になるのが「介護保険制度」と「育児介護休業法」の存在です。両者とも時代とともに改正を重ね、少しずつ変化しているので、現在の状況をしっかりとチェックしておきましょう。
介護保険
もともと日本では、親の介護を子どもや家族が行うものという価値観が強くあります。
しかし、時代とともに介護が必要な高齢者の増加、核家族化が進行しました。その中で、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的として2000年に創設されたのが介護保険制度です。
開始されて20年以上が経過し、今ではすっかりおなじみの制度ですが、改めて創設の目的を押さえておきましょう。
育児介護休業法
正式名称は、「育児休業等育児または家族介護をおこなう労働者の福祉に関する法律」です。
その目的は、育児や介護をする必要がある労働者を支援し、仕事と家庭を両立させ、労働の継続ができるようにすることです。具体的には、育児や介護のための休暇を与えたり、就労時間を短縮したり、支援金を給付したりする制度です。
家族に介護が必要となった人には、次のような休暇などが保障されています。
育児介護休業法の具体的な内容
- 93日間の介護休業の取得
- 介護のための短縮勤務等の措置
- 残業などの所定外労働の免除
- 家族の介護を行うための介護休暇(年5日)の取得
これは国に申請するものではなく、直接会社に申請する必要があります。まだご家族の介護が必要でない人も、ぜひ一度会社に確認してみるのが良いでしょう。
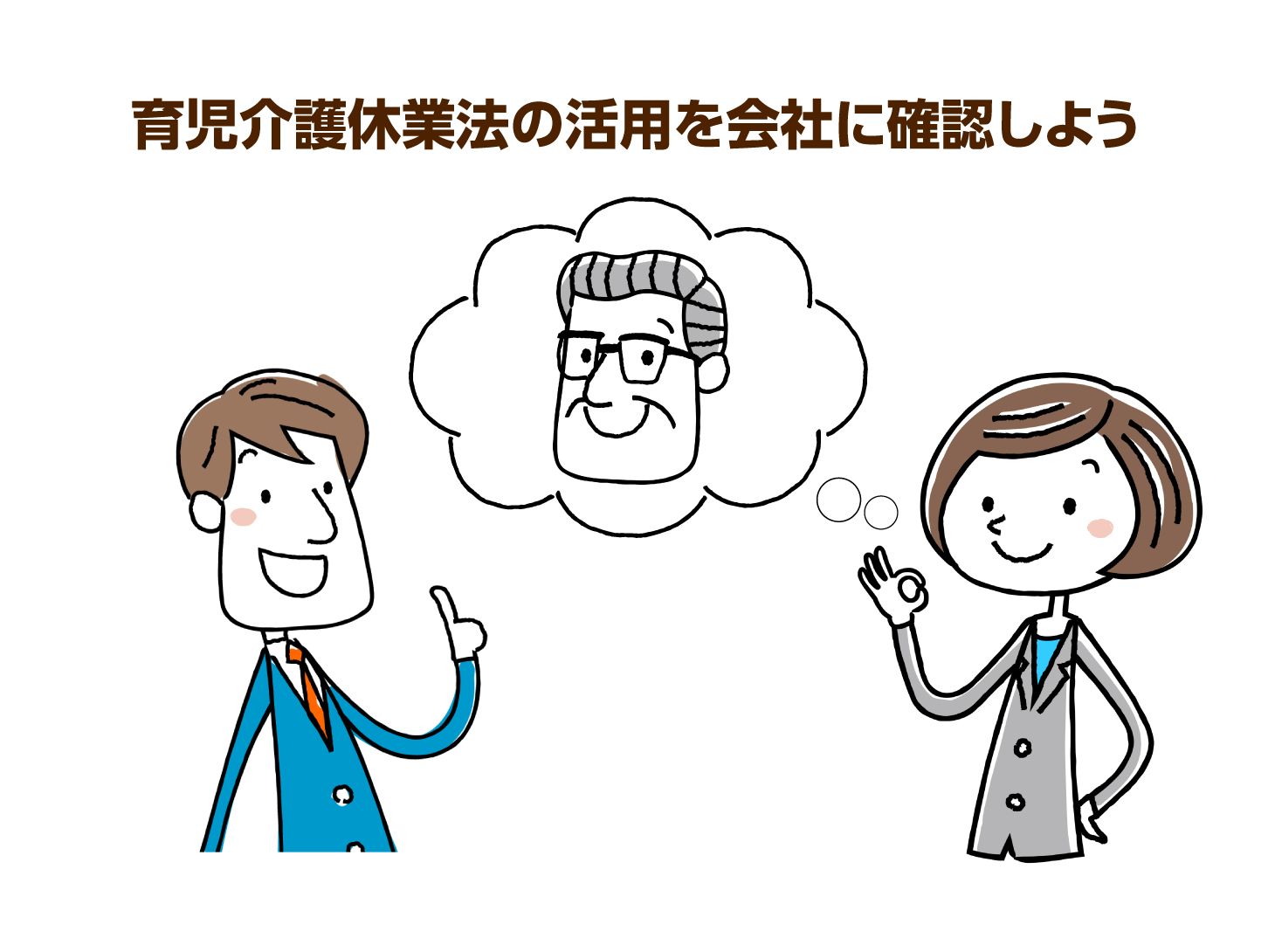
いろんな関係者に相談すること
介護と仕事を両立するための制度を理解できたら、介護について相談できる相手を見つけましょう。
- 地域包括支援センター、ケアマネージャー
- 介護が必要になりそうな場合、まずは近隣にある地域包括支援センターに相談してみましょう。介護保険を利用することになれば、担当のケアマネージャーも付きますので、困ったことがあれば気兼ねなく相談してみてください。
- 家族(協力者)
- 介護と仕事の両立を考えれば、ご家族などの協力者とその理解が必要です。介護に関するすべてのことを自分一人の力で解決するというのは難しいです。また、期間の定めも決まりもない介護生活が始まるのであれば、家族との介護観のすり合わせも非常に大事なことだと思います。
- 会社
- 介護と仕事の両立において、当然ながら会社の理解も不可欠になります。育児介護休業法という法律がありますから、詳細な条件を会社の担当者に確認することが必要です。場合によっては職場の部署の同僚などにもご自身の状況を周知して理解してもらう必要があるかもしれません。
マインドを変えること
介護と仕事を両立するための環境整備が進められていますが、自身のメンタルにかかる負担までは軽減することができません。
しかし、介護者の多くは次のようなことを考えがちです。
「周りに迷惑をかけるかもしれないから、制度の利用には気が引けてしまう」
「家族の介護をするからには1から100まで完璧に役割をこなさなければならない」
このように深刻に考えすぎてしまうと、せっかくの制度をうまく活用できないということにもなりかねません。そんなときに仕事と介護を両立させるための考え方として以下のようなことを意識してみてはどうでしょうか?
- 介護は家族だけでなく社会で支えるもの
-
介護保険が創設された目的は、介護を家族が担うのではなく社会で支えることです。
個々の家庭ごとに介護についての考え方があるとは思いますが、社会制度として仕組みが整備されていることを忘れないでください。そのうえでご自身に負担がかかりすぎないような「介護」を決めても良いのではないでしょうか?
- 自分はマネジメントする側に回ること(すべての介護を自分で行おうとしないこと)
-
介護の負担を一人で全部行おうとするのは非常に危険です。
介護と仕事を両立しようとしているわけですから、介護も行いながら仕事も今まで通りというのは負担が大きいはず。また、育児と比較すると介護はその期間や状況が今後どのように変わっていくかを予想することが非常に困難です。
ご自身は介護の全体の方向性であったり、緊急事態の対応を主に行うと割り切ることが両立するために必要です。
- 完璧主義をやめること
-
何事も完璧にこなすというのはかなり難しいことだと思います。
仕事をしている今までの生活に介護が加わるわけですから、ある程度の「余裕」や「遊び」がないとご自身が辛くなってしまいます。
介護と仕事を両立している間は、「介護も仕事も及第点で良い!」と割り切ってしまうことも大事だと思います。

まとめ
今回は介護と仕事をうまく両立する方法を解説しました。そのポイントは以下の3点です。
- 法律を知っておくこと
- いろんな関係者に相談すること
- マインドを変えること
国は働く皆さんが仕事を辞めることなく、介護ができるような環境を整備しようとしています。利用できる制度は活用して、安心した介護生活を送れるよう準備しておきましょう。