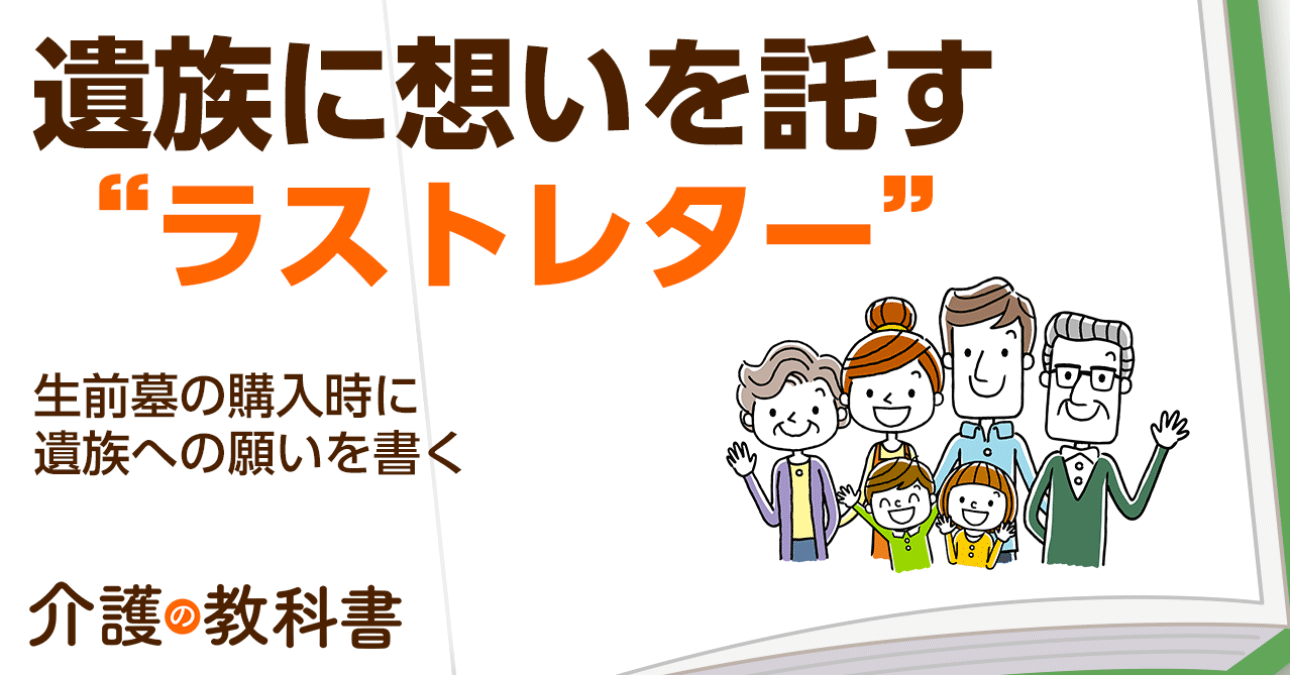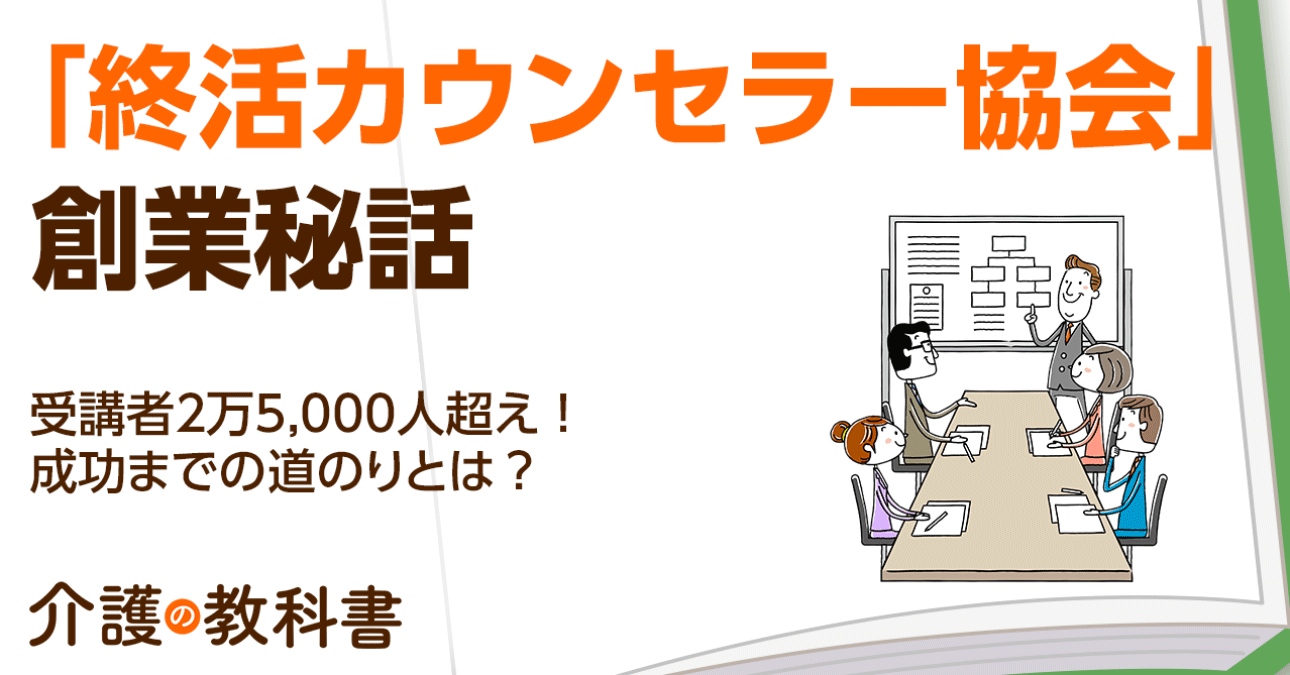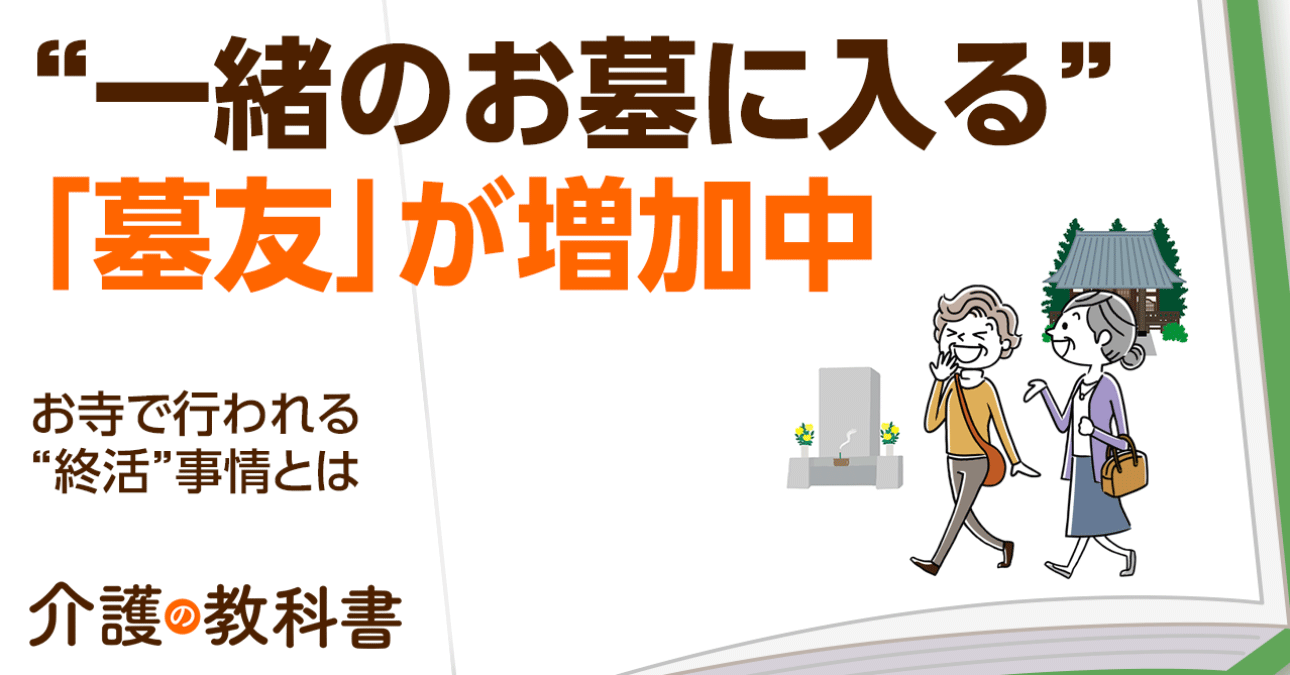ようやく東京23区でも、住民の「終活対策」に本気で乗り出す自治体が出現しました。終活とは、介護や保険、お墓などの準備・計画をして、最期まで自分らしい人生をより良く送るための活動のことです。
今回は各自治体が乗り出している終活サポート事業について、掘り下げてみたいと思います。
豊島区で始まった「終活情報」の登録
東京都豊島区は令和4年4月1日から、区民からの緊急連絡先や延命治療の意向といった「終活情報」の登録受付を開始しました。
この事業は本人が病気や事故、死亡などによって意思表示ができなくなった時、警察・消防・医療機関・福祉事務所及びあらかじめ区に登録した方からの照会に基づき、区が登録情報を開示するものです。
豊島区は池袋駅を中心に商業地が集中しているような印象がありますが、繁華街から少し離れると住宅街が広がり、単身の高齢者が多いお土地柄。
区から委託を受けた社会福祉協議会が令和3年2月に23区初となる終活総合相談窓口「豊島区終活あんしんセンター」を開設したところ、相談者のうち単身世帯が約半数を占めたそうです。
「相談内容に死後事務や遺言、相続等の、死後の手続きに関する相談が多かった」ことで、安心した終末期を実現できる具体的な仕組みの構築が必要だと痛感。できるうちに、準備をしてもらうことを主眼に置いて、実施につなげたというわけです。
「これにより登録者の意思を的確に伝達し、希望に沿った終末期の医療や円滑な死後事務等の実現につなげ、本人の尊厳を守るとともに、今後の人生をより豊かで安心できるものにします」と豊島区のホームページではうたわれています。
登録可能な情報と、情報開示が可能な関係機関は以下のようになります。
| 登録情報 | 登録申請者が登録できる情報 | 区が照会に対し開示できる情報 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 本人 | 後見人 | 警察・消防・医療機関 | 福祉事務所 | 照会可能な登録者 | |
| 1 緊急連絡先 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 本籍 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 3 通院先・アレルギー等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 リビングウィルの保管場所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 エンディングノートの保管場所 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 6 臓器提供の意思 | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 7 献体登録先 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 死後事務委任契約や終活に係る生前契約等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 遺言書の保管場所 | ○ | × | × | × | ○ |
開設開始以降、1ヵ月の相談件数は約20件。10人のスタッフが交代で対応しています。認知度アップに伴い、相談は増加傾向。申請件数は5月17日の時点で3件ですが、内容は自然に終活相談となるそうです。
豊島区終活あんしんセンターのスタッフは、次のように語っていました。
「登録の話を始めてご本人の緊急連絡先がなかったりすると、『任意後見はこういったもの』ですとか、『死後事務委任手続きはこういったものです』と説明して、それを誰に託していくのかを考えていただく、ということはあります。死後は誰がやってくれるのか、とか、先にエンディングノートを、という話になって、それも併せて相談に乗っている感じにはなりますね」
さらに、新事業立ち上げの裏事情も解説してくれました。
初版は2,000部(無料)。そのうちの約1,000部は区の広報誌を見た区民が取りに来たり、高齢者サロンや終活講演会などで配布され、あっという間になくなったそうです。
また、「ただ、もらうだけで手に取っておしまいになってしまうと終活の準備は何も進みません。もらった後に『書く』というところを後押しできるように、エンディングノート書き方講座などを開いて、活動につなげられるようにしていくことに、気を付けてはいます」と、終活を始めるサポートもしていくとのことです。
私が講師を務めている終活カウンセラー協会では、終活について、こう定義づけています。「人生の終焉を考えることを通じて、自分を見つめ、今をよりよく自分らしく生きる活動」。突然の病気や事故で意思表示ができなくなる前に「終活情報」をまとめておくことは、そのなかでも大事なことのひとつといえます。
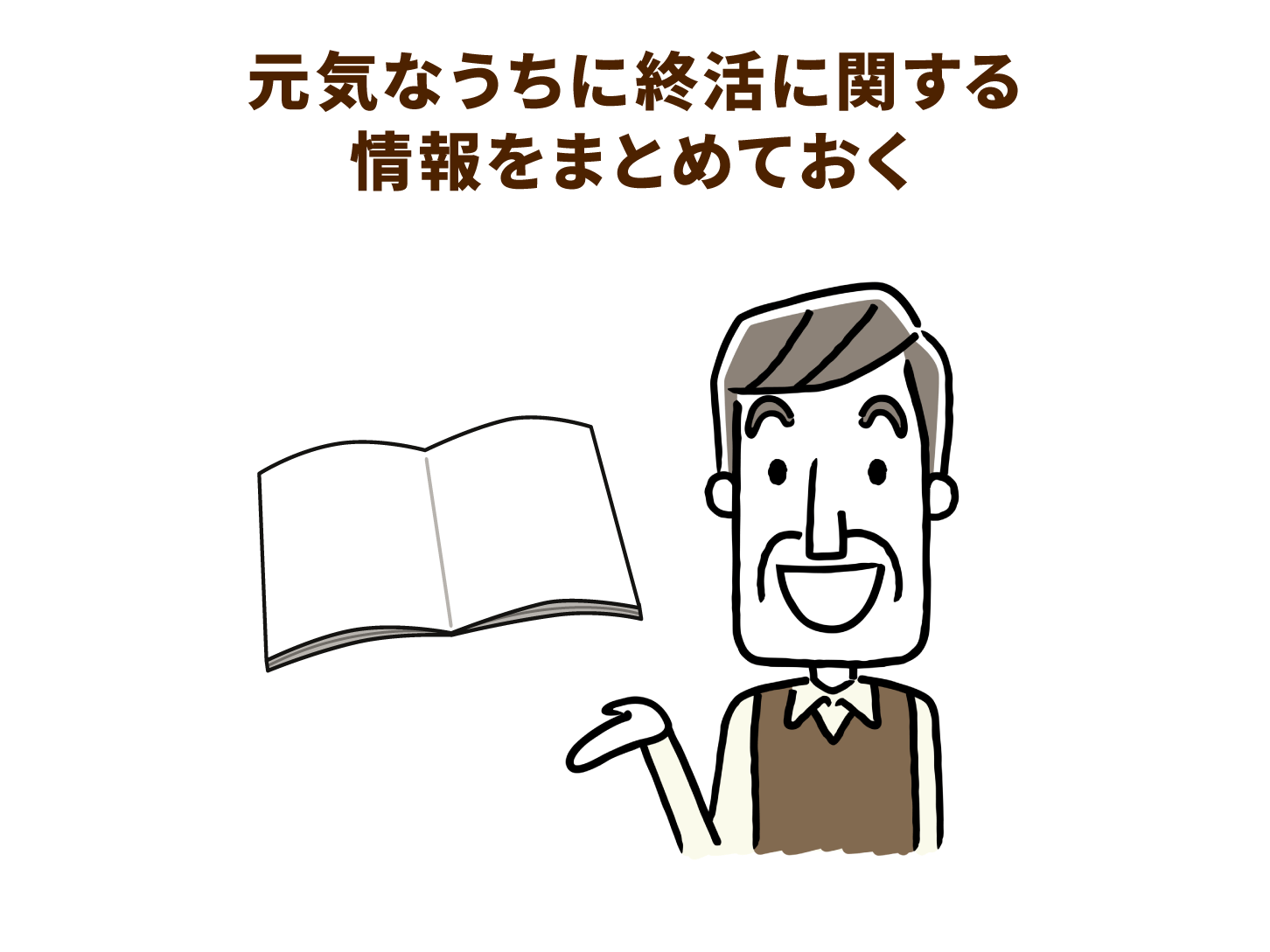
終活情報登録事業の先駆けは神奈川県内の自治体
米ロサンゼルスほか世界各地に23,000人以上が散らばっている終活カウンセラー。そのなかには、地元の行政と深く関わって活動している会員も少なくありません。神奈川県逗子市在住の稲恵美子認定終活講師もその一人。逗子市発行の「ずしエンディングノート」の制作にも携わりました。
この逗子市も、令和2年の10月1日に終活情報登録事業をスタートさせています。担当者は「行政のサポートに期待する市民は多い。本人が元気なうちに、終末医療や介護の希望を書いた、“ずしエンディングノート”を逗子市が預かってくれていることがわかれば、遠く離れて暮らす家族も安心です」と、終活の広がりを話してくれました。
神奈川県内で先行している登録制度。その源流をたどると、横須賀市にたどりつきます。ここで先駆け的役割を果たしたのが、横須賀市役所の北見万幸さん。豊島区でも始まった終活支援事業について、次のように喜びを表現していました。

いざというときに役に立つ登録情報
では、この制度を導入した北見さんの真意はどこにあったのでしょうか。北見さんは、こう明かしてくれました。
2015年から2021年の3月31日現在までで、エンディングプランサポート事業の相談件数は、すでに累計1,150件あり、登録件数は105件(男性57件、女性48件)。身寄りのない横須賀市民で、65歳以上と限定された人のうち39人が、すでに亡くなっているとのことでした。市のお金で火葬することになる墓地埋葬法第9条の対象者に間違いなくなっていた人たちを、39件防止したということになります。
一方の「わたしの終活登録」は平成30年度からの事業で、令和3年度末までの相談件数が累積で1,187名。登録件数は512件です。「約1万1,000人が単身の高齢者ですから、5,000件は登録してほしいですね。コロナでだいぶ減ってしまいましたから」と北見さんは、話していました。
北見さんは最後に、こんなエピソードを披露してくれました。
さらに北見さんは、こう言っていました。

高齢化社会が進むにつれ、注目を集めつつある「終活のチカラ」。行政と終活の関わりも、ますます深まっていくことになりそうです。