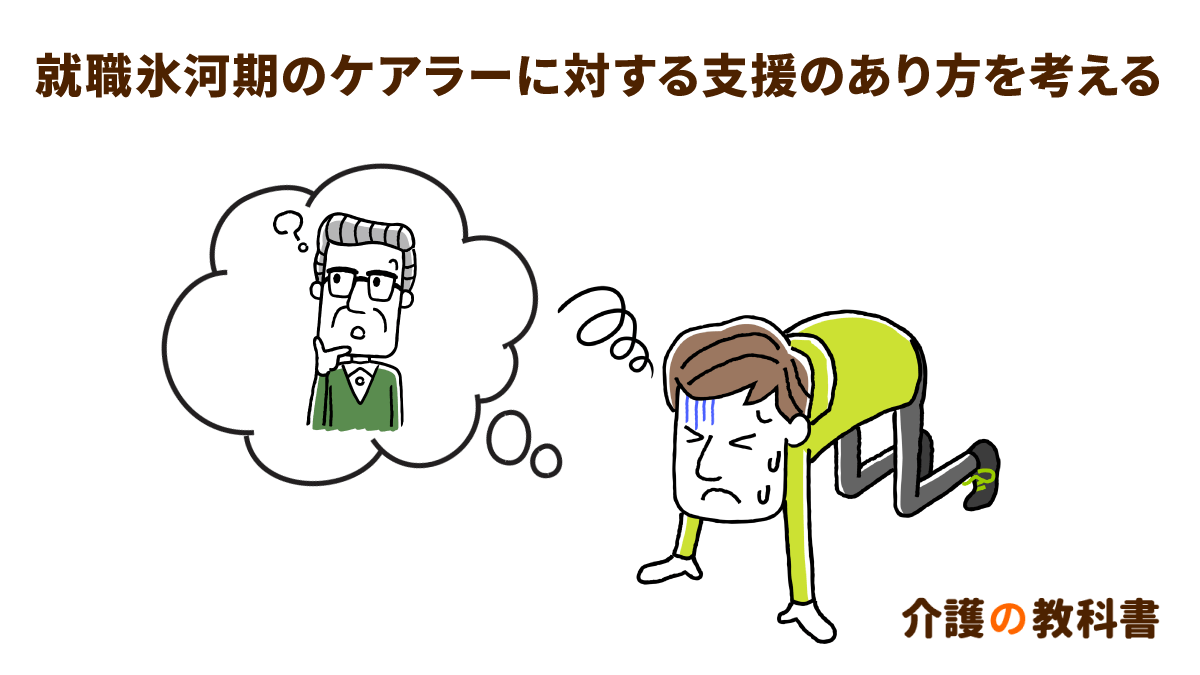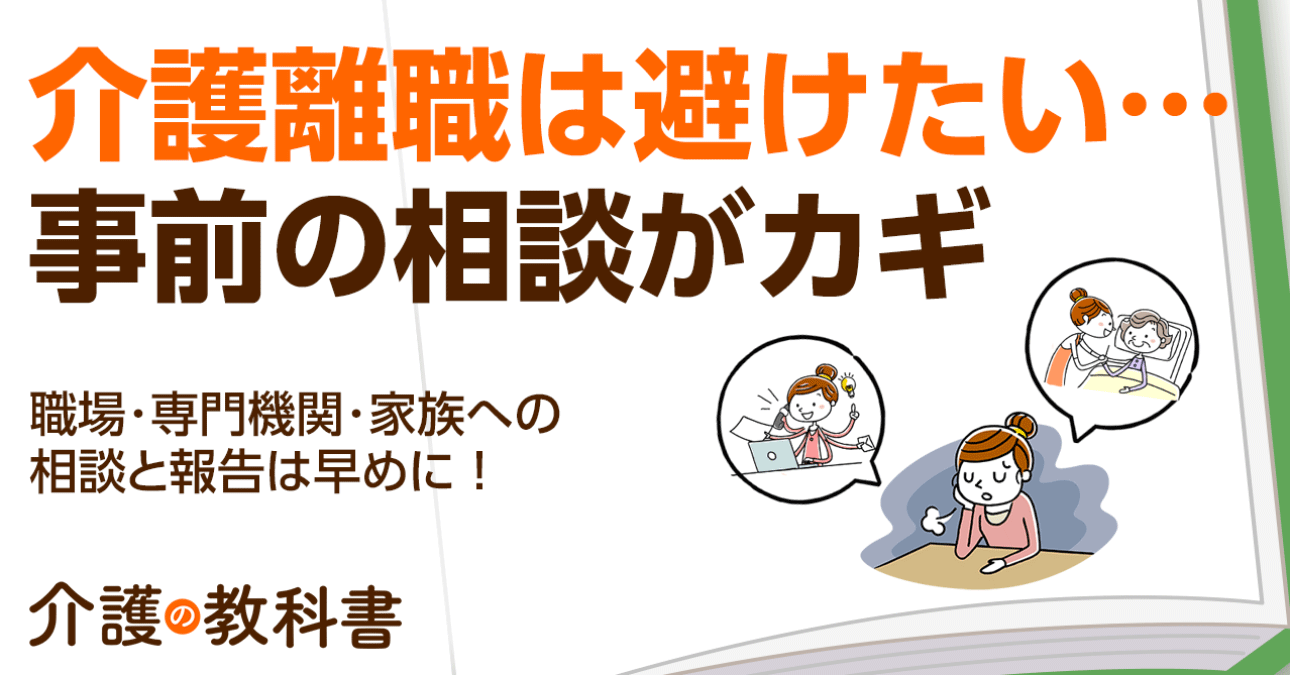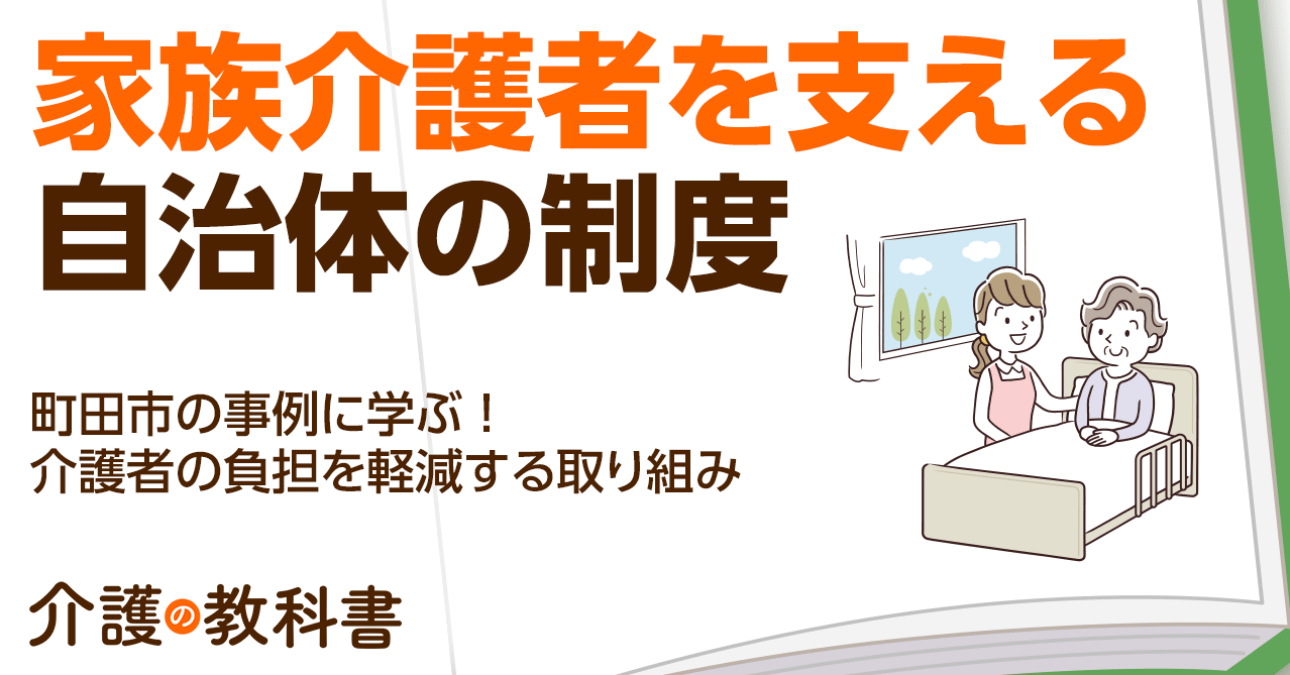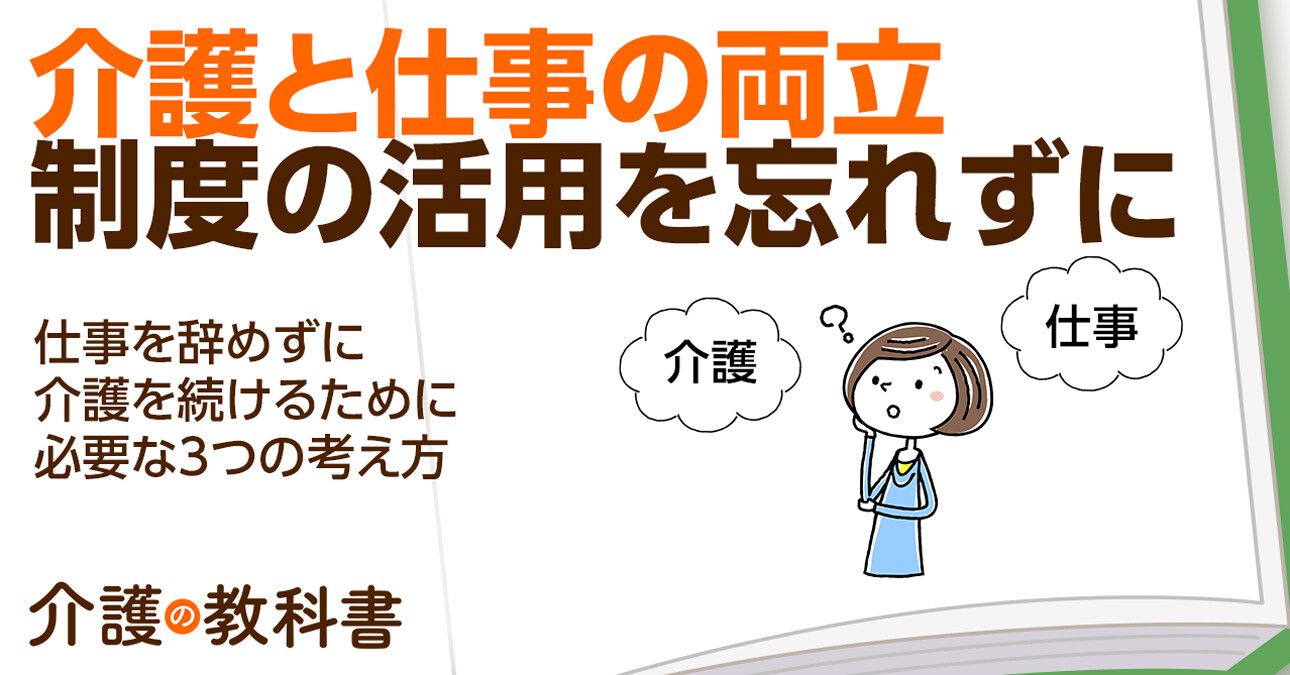読者の皆さん、こんにちは。『おばあちゃんは、ぼくが介護します。』の著者であり、「介護作家」「メディア評論家」「よしてよせての会」代表の奥村シンゴです。
就職氷河期世代のケアラーがいるのはご存じですか?就職氷河期ケアラーとは、バブル崩壊後の1993年~2004年に大学・大学院を卒業。雇用環境が厳しい中、就職活動をし、親・祖父母などの介護に追われた36~45歳を指します。『就職氷河期世代の行く先』の著者・下田裕介氏によれば、111万人が親の介護などで生活不安定者になり、27兆円を超す生活保護費になると試算しており、深刻な社会問題といえます。
私自身も、就職氷河期ケアラーの一人で、就職難、介護離職、介護離職後再就職困難を経験し、今秋に立ちあげた「よしてよせての会」で相談や支援もしています。そうした中で、「応援手当」「就業メンタル支援」と「現在就職氷河期元ヤングケアラーなど介護長期者対策」の3つの支援が必要だと考える理由を紹介します。
就職氷河期ケアラーが正社員就職に後ろ向きな理由
私が大学を卒業する直前の求人倍率は1.09倍で、履歴書・職務経歴書は100社以上に送り、面接にたどりつくのは10社以下が当然という状況でした。大卒でも契約社員・派遣社員・アルバイト・パートといった非正規社員やニート・ひきこもりが急増しました。ちなみに、コロナ禍の2021年の有効求人倍率は、1.53倍ですのでいかに厳しい環境だったかがおわかりいただけると思います。
「正社員でもう就職できへんのか」と不安や焦りがつきまとう中、私はホームページの制作会社に就職しました。「よし、これで少し安心」と思っていた矢先に、今度はリーマンショックが直撃し会社が倒産してしまい、再び就職活動をすることになりました。
放送・通信業務を請けおう東証一部の会社に再就職するも、今度は母親が脳梗塞で倒れ、認知症の祖母をケアするために離職せざるを得ませんでした。母親は脳梗塞、大腸ガン、精神疾患で入退院を繰り返し、祖母は、徘徊・異食・着衣着脱不可と認知症がじわじわ進行していきました。母と祖母の入院後も手続きやカンファレンス、急病時対応、転院などに追われ、気がつけば9年が経過し私の年齢は40歳を過ぎていました。
「結婚したい、子どもがほしい、車・マイホーム・ゴールドカードをもちたい」と夢を見たこともあります。私は、介護や放送・通信業界での経験を活かし、介護作家やメディア評論家として頑張らせていただいてますが、自営業のため収入が不安定です。正社員に就きたい気持ちはありますが、積極的になれない自分がいます。その理由は主に次の4点です。
- 生活が介護で昼夜逆転する生活で不規則になり、午前9時から午後6時のような規則的な生活に戻れるか不安
- 母親や祖母が急変・転院・手続きで入院する病院に行くのが平日の午前から昼間で急に休んだり、公欠をとると離職につながる可能性
- 正社員じゃなく、ブランク期間が長い
- 年下が先輩になり、プライドが許さないときがありそうで人間関係に自信がない
総務省の調査によれば、介護離職後の正社員就職率は20%、未婚率は38%で、バブル世代と比べて年収50万円の格差があります。
さらに深刻なのが、介護離職後の就職活動に関して、「はじめから行っていない」が51.8%、「行っていたがあきらめた」が13.3%で、両方をあわせると65.1%に達しています。そう考えると、私の心情と似た人は少なくなさそうです。就職氷河期ケアラーに対し、「働く意欲を上げる」精神的なケアが重要になるのではないでしょうか。

長期間介護した人への支援が不可欠
日本ケアラー連盟は、本来大人が担う家事や家族の世話などを日常的に行うヤングケアラーを「18歳未満」に推奨しています。それに伴い、自治体が動き出していますが、就職氷河期ケアラーが支援されないのはおかしいように思います。
そもそも政府の支援が遅すぎたのが原因です。就職氷河期最終年(2005年大学卒業)の8年後の2013年に、技術やキャリアが未熟な労働者を雇い入れると助成金がもらえる「トライアル雇用助成金」が創設されました。2019年、安倍政権時には3年間で30万人を雇用させる「氷河期世代支援プログラム」、今年には厚生労働省による「就職氷河期世代活躍支援プラン」と、ようやく就職氷河期にスポットが浴びるようになってきました。ところが、就職氷河期世代の介護者への支援がまったくありません。
「よしてよせての会」では、次のような相談がありました。
Aさんのように介護で困っている就職氷河期世代は数多くいます。そこで、私なりに4つの支援方法を考えました。
- 就職氷河期ケアラー応援手当:非正規・正規・フリーランスなど、就業形態問わず、介護しながら仕事を両立する人たちに毎月一律で5万円の支援金を出す
- 正社員勤続2年ごとに10万円:離職率の低下につながる
- 専用メンタル相談窓口:働く意欲を喚起させて、自信をもたせる窓口
- ヤング・若者・就職氷河期の長期介護者を対象とした就業支援:研修や実践を通じて、トライアル雇用を積極的に実施して安定した雇用につなげる

前述の下田氏は、「2020年から就職氷河期の介護問題がスタートしている」と警鐘を鳴らし、次のように記しています。
家庭環境や経済的な問題で施設に預ける余裕がなく、学校・就職・結婚・仕事がろくにできずに、介護に専念した人たちが損をする社会にならないことを願います。