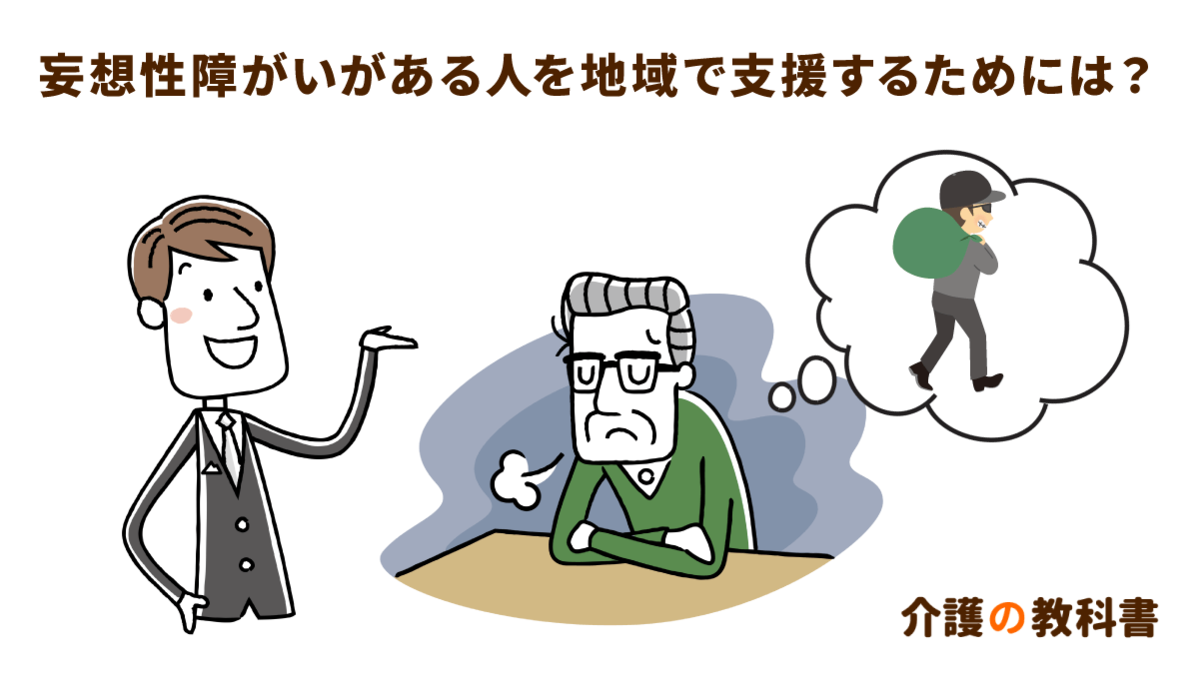千葉県の地域包括支援センターに社会福祉士として勤務する藤野です。
私が包括支援センターに勤務してから独居の女性に多く見られたのは、「妄想性障がい」をベースとして認知機能が低下したことにより、地域での生活が困難となった事例です。こういった例は、この2年間でも6件確認されています。
今回は、こういった症状を持つ認知症の人への支援についてご説明します。
妄想性障がいが近隣住民の迷惑に
まずは、先述の認知機能の低下が引き起こしたと思われる妄想の事例についてみてみましょう。
- 近隣の住民が自宅に侵入して家財を盗む
- 近隣住民が早朝や深夜に敷地内に侵入して家の周りを伺っている
- 知らない若者が知らないうちに侵入して家財を持って行ってしまう
- 近隣住民が家の中をのぞいたり、ものを持って行ったりしてしまう
- 近隣住民がこっそり自宅に侵入してものを盗っていってしまう
これらの妄想によって、精神的に不安定となり、民生委員や警察に頻繁に電話をかけてしまうなどのケースも発生しています。そのほか、「自宅内に人影があって怖い」と早朝や夜間に近隣住民宅に助けを求めに行ってしまうケースもあるようです。
また、このうち3つのケースでは、自宅に何台も防犯カメラを設置していました。当然、防犯カメラには上記のような様子は映っていないのですが、それを見ても高齢者は納得しません。
何度も自宅の鍵を変えていたために、鍵の施工業者の反感を買うようなケースもありました。「自分たちの仕事が信用できないのか」といった心情からです。「自宅に侵入してくる」などと言われたり、深夜早朝に自宅に訪問されたりする近隣住民は、生活のペースが乱され困惑します。
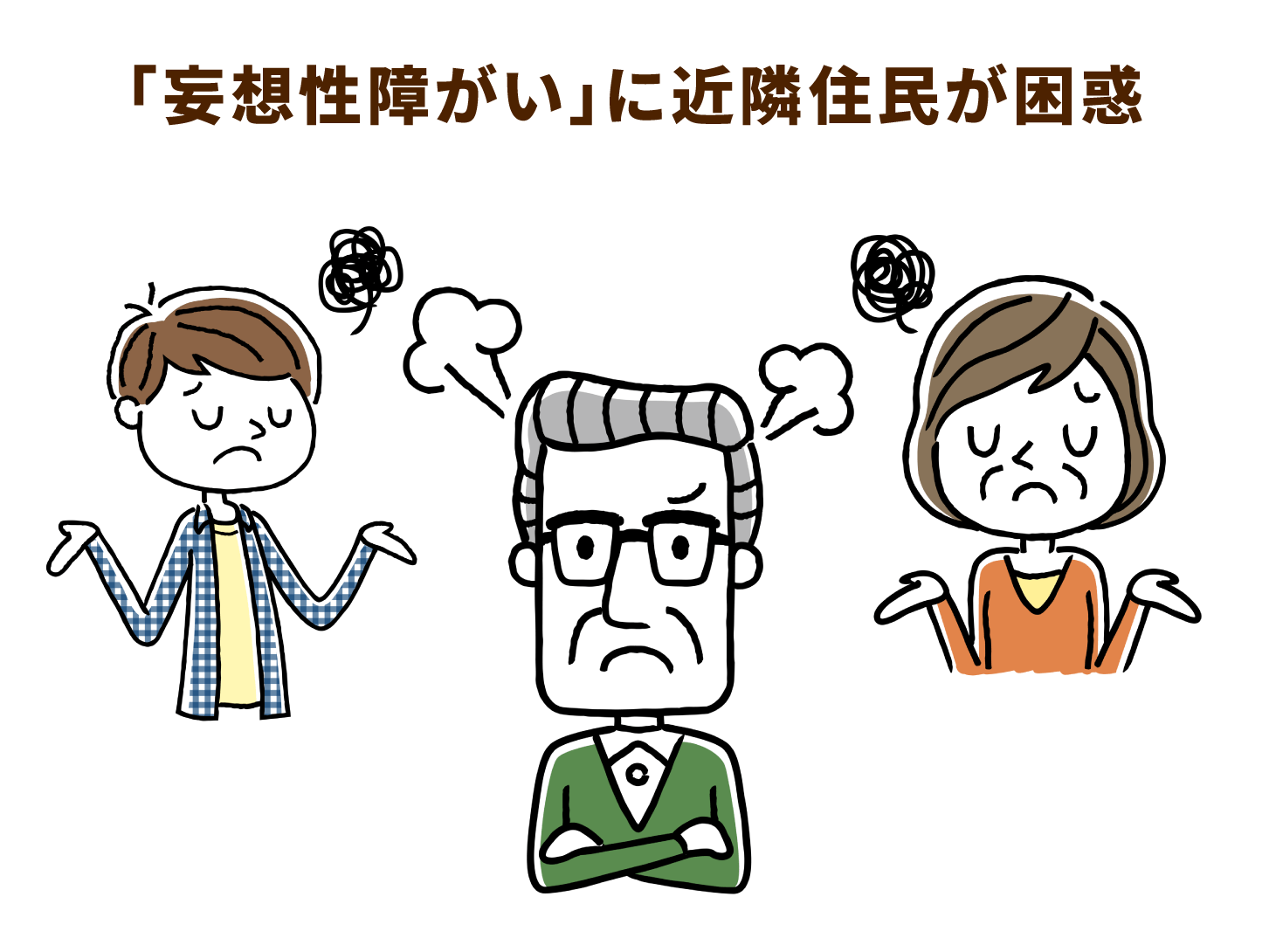
認知症の症状が顕著で徘徊などが見られるケースに関しては、「地域ケア個別会議」を開催し、民生委員をはじめとして地域住民や警察、福祉関係機関の皆さんと対応策を考える会議を開催して情報共有をします。
それぞれ家庭環境も育ちも違うのですが、驚くほど同様の言動を取ります。「自分の衣類を持って行ってしまい、代わりに私のではない衣類を置いて行く」と言っては風呂敷に入った衣類を見せてくれる場面に頻繁に出くわします。こういったことが特に女性の独居高齢者によく見られるのです。
おそらく一人暮らしとなった不安から、認知機能が低下し、妄想性障がいを発症したのだと考えられます。混濁した意識の中で、ちょっとした物音に不安になったり、自分で動かしたものや食べてしまったもののことを忘れたりして、結果的に「他者が自宅に侵入している」といった認識に至るのではないかと仮定しています。
「小規模多機能型居宅介護」をうまく活用しよう
このようなケースの場合、極端な言動が表れたときには、近隣住民が警察に通報して保護され、精神科に入院。退院後に施設入所という流れになることもあります。
それほどの変化が見られな場合に関しては、「小規模多機能型居宅介護」を利用していただくよう働きかけました。小規模多機能型居宅介護事業所は、通いのサービス、宿泊サービス、訪問サービスを一元的に提供しています。また電話によるオンコールにも対応してくれます。自宅での生活を強く希望されていた方には、当初は通所サービスを利用して必要時に訪問サービスを利用するといった形で導入しました。
症状が進行した段階で宿泊のサービスを取り入れ、週に何回かは自宅で生活。宿泊サービス終了後は通所サービスを利用するといった形で、利用しました。
帰宅願望が強い方でしたので、在宅時には訪問サービスを利用して安否を確認しました。症状の進行に合わせて徐々に宿泊サービスの量を増やし、在宅での生活の時間を減らしていきました。最終的には、特別養護老人ホームに入所となりましたが、数年の間、施設と自宅を行き来して生活することができたのです。
地域での生活を継続するには協力体制が必要
認知症の独居高齢者が地域で生活を続けるためには、さまざまな協力体制が必要です。近隣住民に理解いただいたうえで、彼らの生活を脅かす状況は回避していかなければなりません。
例えば、妄想によって工具を手に持ち、地域を徘徊してしまうようなケースもあります。そう言った場合には、保健所と連携して精神科への緊急入院を手配したりもします。その際、千葉県内の精神科医に連絡をしてもなかなか受け入れてもらえず、23時になってようやく受け入れ病院が決まったこともありました。
認知症の症状があり、不安定な精神状態で、親族や周辺住民が対応に苦慮するような行動をとる場合、福祉施設での受け入れはほぼ無理というのが現状です。また、入院もすぐにはできないことが多いのです。
そう言った現実を踏まえたうえで、症状が進む早期の段階で、専門医の診察を受けて医療機関とつながっていることが大切なのです。そうすることで、施設入所にしても入院にしても、その先の動きが違ってくるのです。
デイサービスやヘルパーを利用するという選択も
またデイサービスやヘルパーを上手に利用することも大切です。自宅での生活が困難となった段階での変化に気がついてくれるのは、案外、福祉従事者だったりするのです。
在宅から施設などへのターニングポイントの見極めが円滑に行えるようにするためにも、福祉サービスの活用は有効です。
独居かつ認知症の方がデイサービスを利用することで、意欲が高まり、症状の進行が抑制されたケースもあります。孤独や不安感を低減することが、とても大切だと考えられるのです。

また、ご家族が連れてきた室内犬(餌の手配や動物病院対応はご家族が行っている)と一緒に生活することで、「物音がしてもこの子が吠えてくれる」といったことで不安感が軽減し、落ち着いて過ごすことができるようになった方もいました。
あまり長距離の散歩の必要のない小型犬のお世話をしたり、語りかけて触れ合ったりすることにも、心を落ち着かせる効果があったようです。
こういった対応をされたご家族には脱帽でした。小さなワンちゃんが高齢者の心を癒したのです。認知症を持つ独居の高齢者が地域で生活を続けるためには、ご家族、近隣住民、医療機関、福祉、警察などとの連携と、温かく見守る「目」が必要なのです。