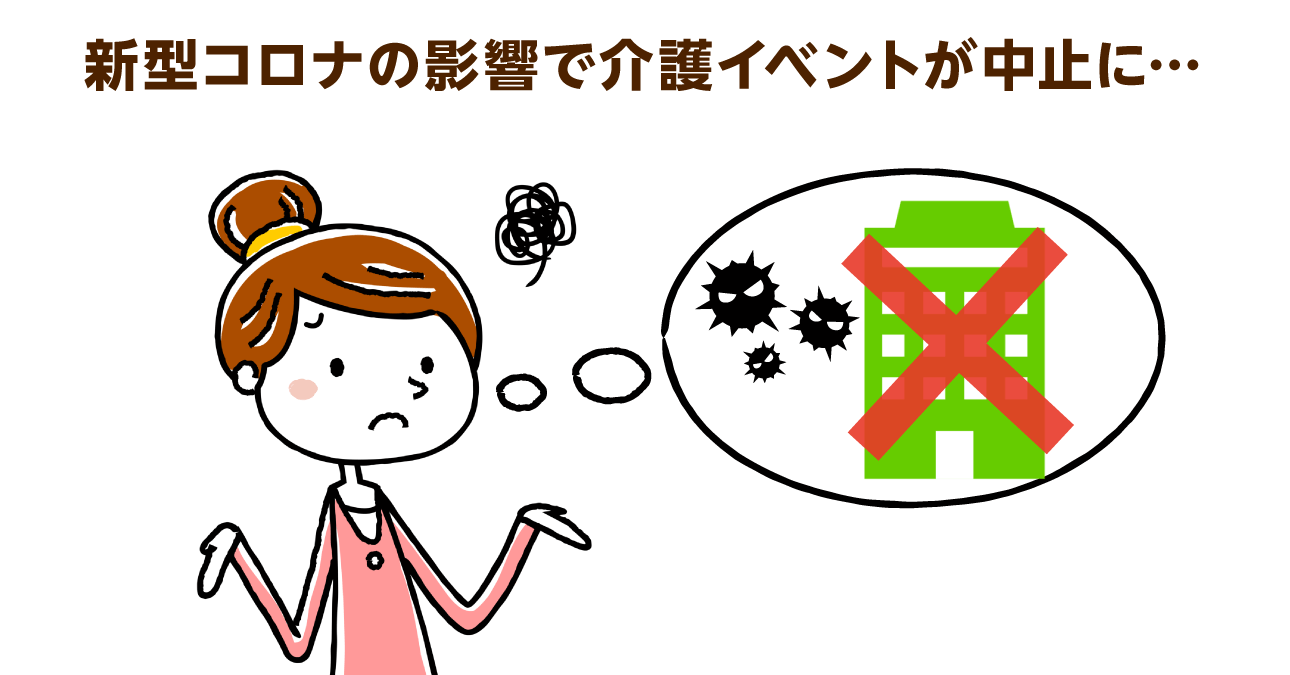皆さん、こんにちは。終活カウンセラー協会で講師をしている、ジャーナリストの小川朗です。
今回は、この連載の145回で紹介した介護職にとって情報交換の場である「ケアの駅」についてお話させていただきます。
「ケアの駅」がスタート
江東区(東京都)で、地域包括ケアシステムの新たなモデルが始まろうとしています。「ケアの駅」が8月21日、本格的にスタートしました。ケアの駅は、訪問看護師である山田富恵さんが温めてきた「地域を走り回るケア提供者や地域の方が、気軽に立ち寄って休息ができて、介護や健康情報を得て相談できる、緩くつながれる場をつくりたい」という思いを実現させたものです。オープニングイベントのタイトルは以下の通りです。
「withコロナを考えよう~予防から看護・介護の目を育てる~」
新型コロナウィルスの感染が拡大する中、医療業界と並んで感染リスクの高い職種の1つに挙げられるのが介護業界です。感染予防は業界が最優先で取り組むべき課題とあって、2日間で40人近い方々が東陽5丁目(東京都江東区)の会場を訪れました。
初日は介護の専門職向け、2日目のイベント最終日は一般向けとなりましたが、その中には地元の長寿サポートセンターに勤めるスタッフも含まれていました。
江東区(東京都)で、地域包括ケアシステムの新たなモデルが始まろうとしています。地域包括支援センターとケアの駅の違い
介護保険法に基づく地域包括支援センターのことを、江東区では「長寿サポートセンター」と呼んでいます。
「地域包括ケアシステム」の最前線基地とも呼べる地域包括支援センターは、保健師や社会福祉士、主任介護専門員などの専門職が、互いに連携しながら「チーム」として活動し、高齢者の方が住み慣れた地域で暮らしていけるよう支援しているのが特徴です。

ここで、その源となっている「地域包括ケアシステム」をおさらいしておきましょう。
地域包括ケアシステムとは、重度の要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けることができるよう、住まいや医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供されるシステムを構築する取り組みのことで、厚生労働省が推奨しています。
地域包括支援センターは最初に介護認定を受ける窓口として、終活カウンセラー検定における「介護」の科目でも外せないポイントの1つ。介護保険を利用しようとする方だけでなく、家族や友人、地域の関係者など誰でも相談できるのが同センターの特徴です。窓口に行くことができない場合でも、電話や自宅訪問による相談にも応じてくれます。
介護保険制度や福祉サービスだけでなく、オレオレ詐欺や虐待、成年後見制度などについても無料で相談に応じてくれるのですから、利用しない手はありません。

一方、ケアの駅はそうした地域の高齢者はもちろん、その地域で働いているケア提供者に対しても大きなウエイトが置かれています。地域包括ケアシステムで顧客とかかわる訪問介護員や作業療法士、言語聴覚士などは1人でサービスに入ることが多く、直行直帰というパターンが多いのが現実です。山田さんはかつて、このように話しています。
「ケア提供者たちはそれぞれが別々の事業所なので、相談しづらい現状があります。昼食なども移動の途中で1人きり、ということも多いです。1人で回って1人で帰りますし、現場でイヤなことがあってスッキリしないときも、愚痴を聞いてくれる相手もいません。実際には顧客に複数のスタッフがかかわっていますが、顔を合わせることがないので、伝言ミスからトラブルになることもあるんです」
ケアの駅は、ケア提供者にとって、最も必要とされている憩いの場所。ここが情報交換の場として機能すれば、なかなかうまく行かない介護・医療人材の質の向上における問題が大きく改善されていくはずです。これからは地域包括支援システムの新しい形を担う存在となることが、期待されます。
地域の高齢者にとっての貴重な情報入手の場に
介護のプロたちが休憩しているケアの駅を訪れることは、インターネット情報に触れることが少ない地域の高齢者にとっても大きなメリットがあります。
山田さんは、次のようにおっしゃっていました。
「実は『在宅医療や在宅介護でどのようなケアを受けられるかわからないから在宅医療の実現は難しい』と思う方が26.5%もいるんです。知らないのに選択はできません。『情報を知りたい』というニーズは高いので、それに応える場を提供したい」
オープニングイベントは、まさにそうした思いが詰まったものになりました。会場には試飲、試食が可能なゼリータイプなどの栄養補助食品がずらり。また、ワンタッチで取り換えが楽な「ぴったりシーツ」の体験など、最新の介護情報が得られるイベントとなっていました。
まず、山田さんが「ウイルス感染症」をテーマに講演。「怖がりすぎず、適当に怖がりながら」接触感染を防ぐ介護の方法について、一般の方々にもわかりやすい言葉で説明しました。会場内でひときわ強い存在感を放っていたのが介護ベッド。ここでは介護する側の一般の方々が、介護される側の立場で食事の提供を受ける体験ができました。介護ベッドについて、山田さんはこのようにおっしゃっています。
「(食事の際に重要な)電動の介護ベッドを、食べさせる側が体験することがないんです。そのためベッド(の角度)を上げても、楽ではない姿勢になっていることがあります。実際にどのような位置になれば食べやすいのか。それを知ってもらいたかった」
実際、介護者は角度なんて気にせずにベッドを起こし、食事の介助をするだけで十分だと考えている人は多いはず。体験した方々には納得の表情が浮かんでいました。
この後、摂食・嚥下(えんげ)障がい看護認定看護師の青木千津子さんが「フレイルと栄養」について講演。健康な状態から要介護状態に至るまでの中間的な段階であるフレイルは、まだまだ一般の方には耳慣れない単語です。青木さんのわかりやすい説明に、訪れた地元の高齢者の方々も、うなずきながら耳を傾けていました。
今回に続く第2回のイベントは「オーラルフレイル」をテーマに10月23日と24日に開催されるということです。お近くの方は、ぜひ足を運んでみてください。