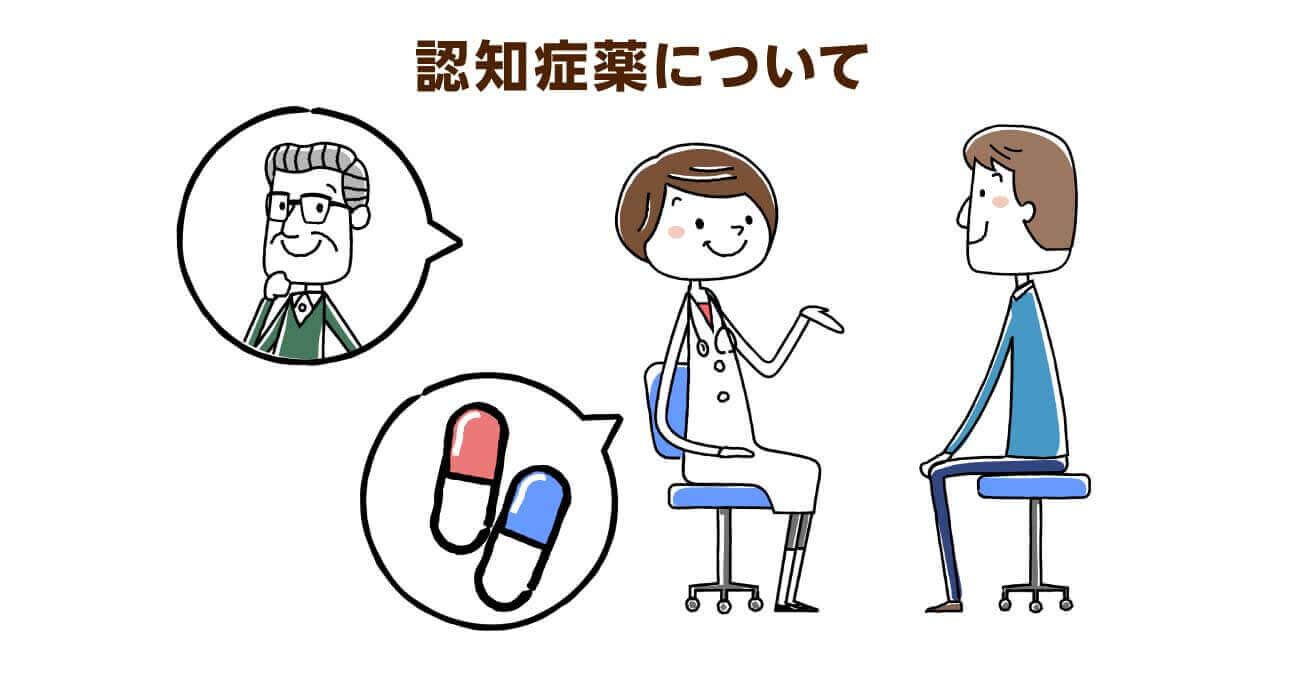みなさん、こんにちは。認知症支援事業所 笑幸 代表の魚谷幸司です。
今回は「要介護認定」についてお話しします。
要介護認定とは
介護保険証は原則65歳になると各自治体より送られてくるのですが、病院で使う保険証と違い、手にしてすぐに利用(使える)わけではありません。
介護保険制度に基づくサービスの利用を希望する場合、必ず要介護認定を受けなければいけません。
要介護認定とは、下記に説明する認定調査と意見書をもとに、介護を必要とする方がどの程度の介護を必要とするかを分けたものです。
ほとんど介護の必要がないとされる要支援1から順に要支援2、要介護1、要介護2・・となりもっとも介護を必要とされる方は要介護5と呼ばれる7段階です。
そしてその段階により、介護保険内で使えるサービスの上限が決められています。
要介護度の決まり方
では、具体的にどうやってその段階(要介護度)が決まるかを説明します。
それは認定調査と呼ばれる調査の結果を基本に、意見書と呼ばれる主治医(かかりつけ医)が記入する医療情報が書かれた書面も確認しながら、最終的に「介護認定審査会」と呼ばれる会で決定されます。
介護認定審査会は医療や保健、福祉の各分野の専門家からなる会で、私の住む大阪府東大阪市では全部で約40の会があります。
次に、そんな要介護度を決めるうえで重要な「認定調査」について見ていきます。
それは調査員とよばれる自治体の職員か委託された人が、介護を必要とされる方のいる場所(自宅、施設、病院など)に出向いて行われます。
内容としては手足の状態に始まり、食事や入浴、排泄、認知症の状態など、実に70近い項目について聞き取りを行ったり、実際にその動作をやってもらいながら進めます。

なお、この調査は、介護を必要とされる方だけで受けることもできますが、より正確な要介護度を決定するためには一番近くで見ておられる方(家族や施設職員など)の同席をおすすめします。
要介護認定には方法を「正確に伝えること」が大切
もし結果が不服なときはやり直すこともできますが、不服なときの多くは「正確に」その方の状態を伝えられていないことにあると言えるのです。
具体的には、ある項目についてできるかできないを回答する質問で、そのことがいつもできるなら「できる」の回答で構いませんが、たとえ少しでもできないときなどがあれば「より正確に」状況を伝えてほしいのです。
どんなとき、どんな状況だとできないのかなど、細かい情報があればあるほど良いでしょう。
介護する側にとってどんな「手間がかかる」かも伝えておくことが大切です。
また、介護の状況について主治医に「正確に」伝えておいてください。
なかでも認知症の方を介護されている方は、医師が認知症であることを把握していない場合もあるので注意が必要です。
医師でもそんなことがあるのか、と思ってしまう方もいるかもしれませんが紛れもない事実です。
アルツハイマー型と呼ばれるタイプの方は、初期のうちは一見普通に「見える」立ち振る舞いができるからになります。
ただ、実際は介護において対応が難しい「手間のかかる」時期でもあるので、それを忘れず伝えるようにしましょう。

最後に一言
決定された要介護度には有効期間があり、期間の終わりが近づくと再び認定調査を受けた結果のもとでサービスを受けることになります。
最後に要介護認定の結果に不服がある場合や明らかに状態が変わった場合についてですが、この場合やり直すことができることになっています。
全く同じ手順を踏んだ上で結果が届くことになるのですが、やり直しによって要介護度が絶対に変わるわけではないので注意が必要です。