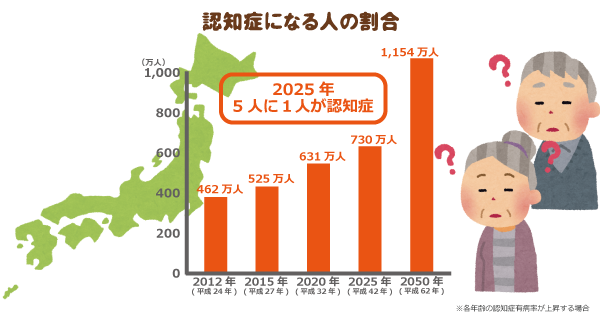みなさん、こんにちは。認知症支援事業所 笑幸 代表の魚谷幸司です。
突然ですがみなさん、認知症の方とコミュニケーションをとっていくなかで大切にしていることは何ですか?
認知症ケアの方法の中には、代表的なケア方法がいくつかあります。
例えば「バリデーション」「ユマニチュード」「パーソンセンタードケア」といったもの。
代表的な認知症ケア
- バリデーション…認知症の方に共感するコミュニケーション方法
- ユマニチュード…介護を受ける人との心の距離を縮めるコミュニケーション方法
- パーソンセンタードケア…認知症の方の視点に立つことで人間性を重視する方法
私自身も上記のような認知症ケアに関心を持ち、よく勉強会に足を運んでいました。
しかしいろんな勉強会に参加していくうちに、こうした方法よりもっと大切なことがあることに気づきました。
それは、「待つ」介護。
つまり、認知症の方がご自身で動作をやり遂げるのを「待つ」ということです。
それではさっそく、「待つ」介護の大切さについて書いていきますね。
認知症ケアで大切な「待つ」時間

親が子どもの世話をしている様子を思い浮かべてください。
親は、子供の成長、自立していく様子を確認しながら、徐々に世話の頻度を減らしていきますよね。
そこでみなさんも一度考えてみてください。
介護の現場で行われていることには、過剰なお世話が多いのではないでしょうか。
私はこの話を勉強会で耳にしたとき、私が日頃から行っていた介護は、そのほとんどが介護と呼べるものではないことに気づきました。
私がやっていたことは、言わば「余計なお世話」だったのです。
介護を受ける人ができることまで、私が代わりにやってしまっていたのですから。
では、なぜそうなるのでしょうか。
それは自分でやった方が早く済むという「効率化」を、介護者の視点で考えているからです。
しかし、介護サービスは介護を受ける人のために行っていることですよね。
つまり大切なのは、認知症の人のペースに合わせることであり、介護を受ける人を主体にサービスを提供しなければなりません。
そして介護を受ける人にペースを合わせるポイントこそ、「待つ」ことになのです。
介護を受ける人が動作を達成できるまで「待つ」。
本人ができることなら、何もしないで「待つ」。
これは簡単に思えますが、実践することは非常に難しいことですよね。
話しかけずにサインを「待つ」ことも大切

何もしないで「待つ」ことは、「介護を受ける人を放置する」ことと捉えられがちですがそうではありません。
例えば、認知症の方に話しかけないことは、コミュニケーションをとることを放棄しているように思われる方もいるかもしれませんね。
以前は私自身も、コミュニケーションの重要性ばかりを意識してしまっていたので、新しく入った職員などに対しても介護を受ける人には自分から話しかけるように指導していました。
しかし、「無理に」話しかけることで相手の気分を害してしまったのです。
よく考えれば当たり前なのですが、介護士と話したい人もいれば、そうでもない人もいます。
無理に認知症の方と話をしようと考えるのではなく、その人自身から何らかのサインを送ってくれるまで「待つ」ことも大切なのではないでしょうか。
認知症の方が出したサインを見落とさないように見守ることの方が、その人自身の意思を尊重していると私は思います。
「待つ」ことは介護を受ける人を理解すること
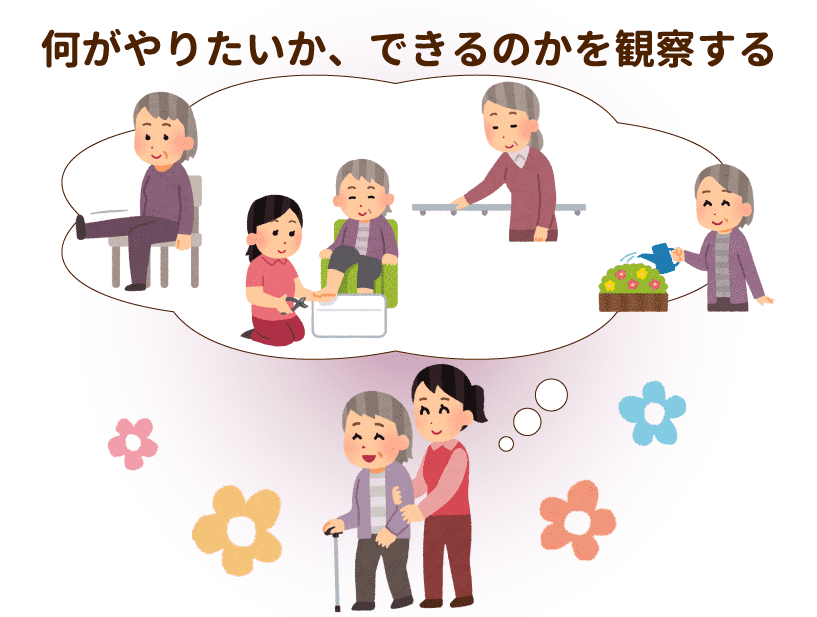
今回は「待つ介護」について考えてきましたが、実践してきた方は少ないのではないでしょうか。
この「待つ」介護は時間がかかってしまいますし、介助してあげた方が早いのでは、と思ってしまいますよね。
しかし長い目で見ると、「待つ」ことこそ認知症ケアにおいて相手を理解するための最適な方法なのです。
介護を受ける人のすべてを理解することは難しくても、理解に向けて努力し続けることが大切です。
その一番の方法が「待つ」ことではないかと考えています。
親切な方ほど、つい余計な介助をしたくなってしまうかもしれません。
しかし、認知症の方ができること、やりたいことをしっかりと見極め、本当に助けてほしいときのサインを見落とさないことこそが、本人を理解するということなのではないでしょうか。
今回のテーマまとめ
- 介護を受ける人のペースに合わせるようにしましょう
- 無理に話しかけず、やりたいことを促されるのを待ってみましょう
- 介護を受ける人のできること・やりたいことをしっかりと見極められるようになりましょう