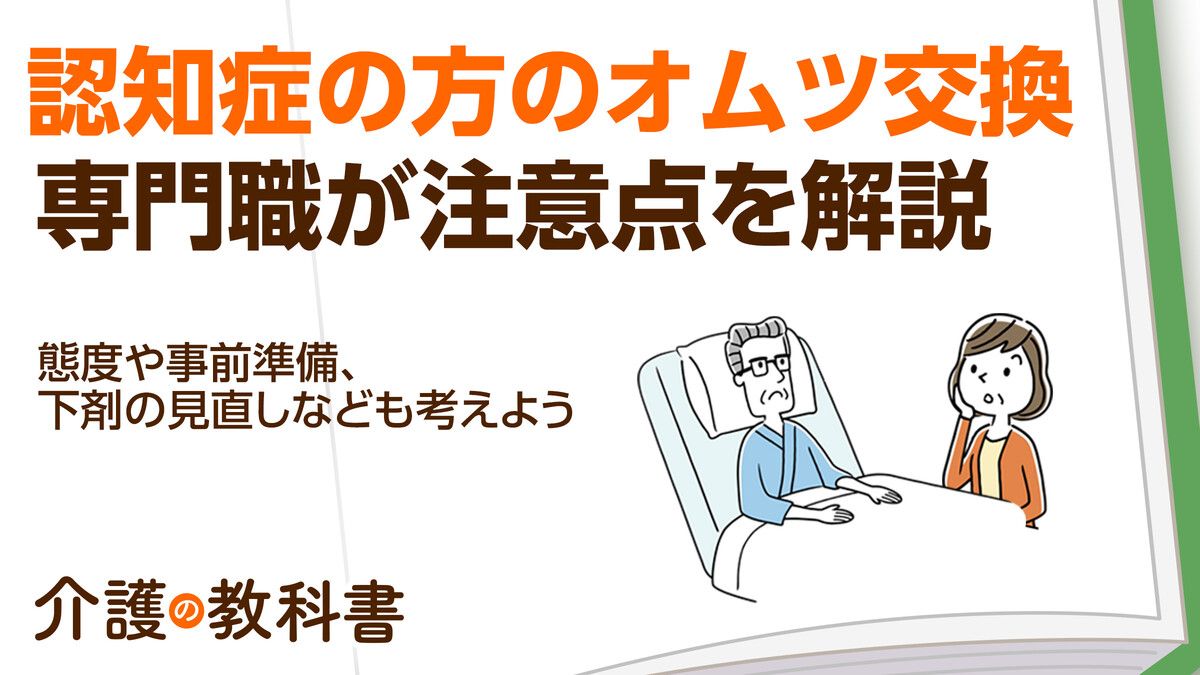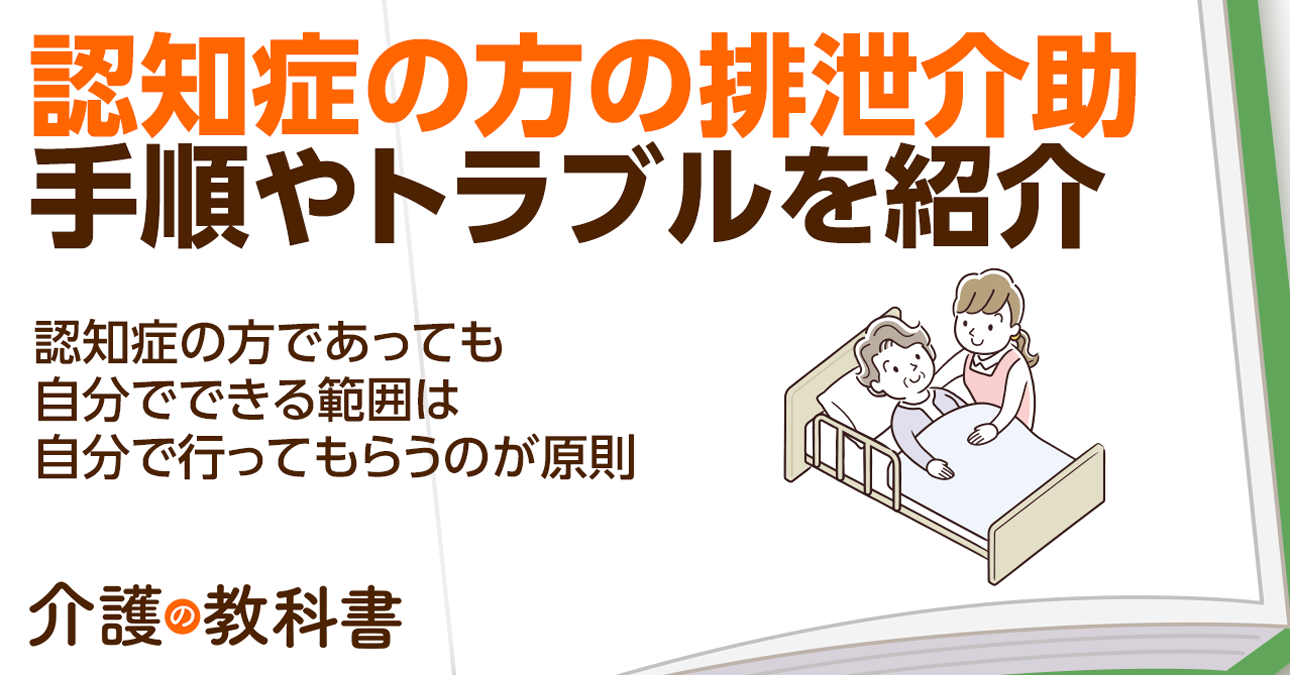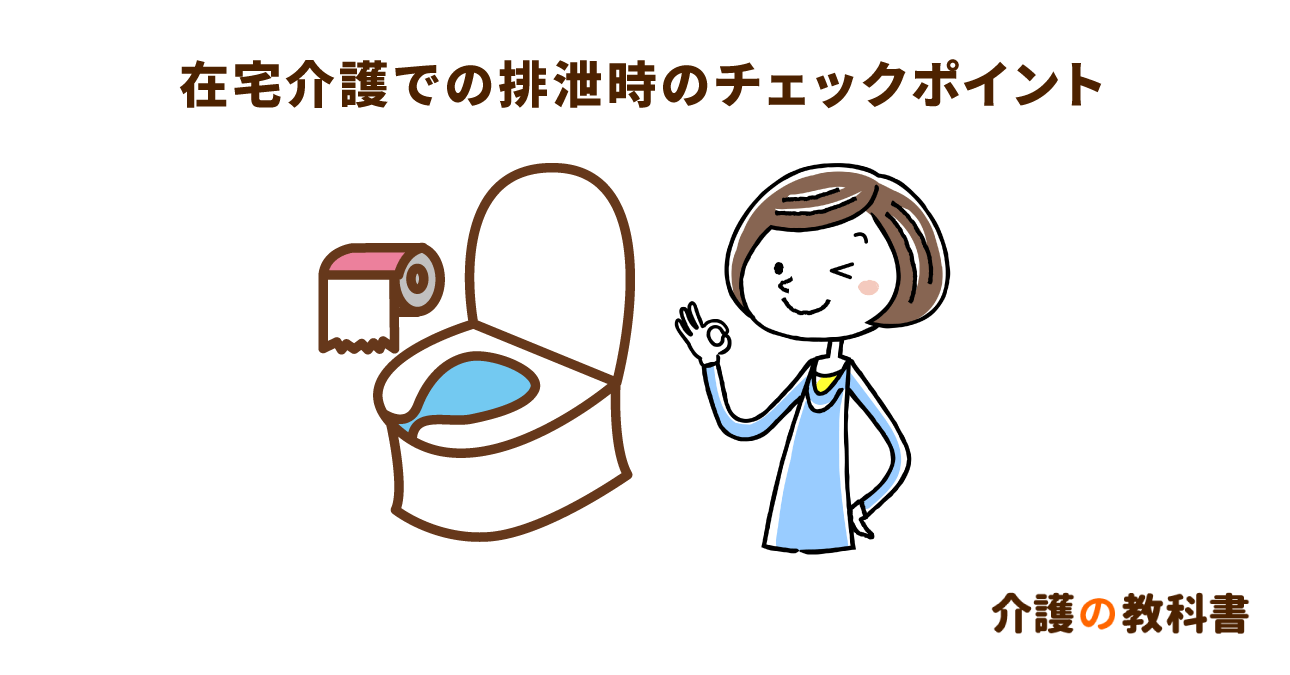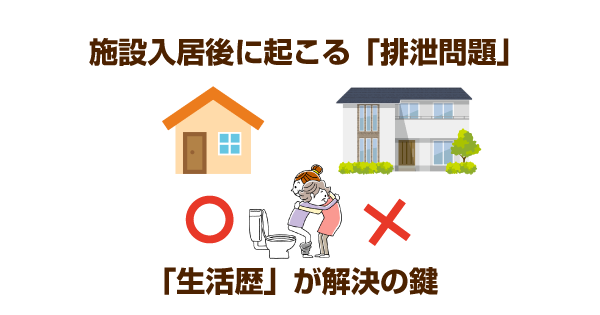ひとえに介護といってもさまざまな内容があります。そんな中、人が生活をしていくうえで必要最低限の食事、入浴、排泄については3大介護と呼ばれ、特に大切だとされています。
なかでも排泄はデリケートな部分が多くあり、対応に十分気をつけなくてはなりません。そこで、今回はオムツ交換について、主に認知症の方との関係で問題となることと、その対応方法についてお話します。
嫌悪感を態度に出さない
まず、トイレには行くものの間に合わないなどの理由で漏らしてしまう、失禁によるオムツ交換です。
この問題に対して最も良いのは排泄のタイミングを見極めてトイレに誘導することです。それによって介護する側の負担となるオムツ交換を少しでも減らすことができます。
ただ、現実には難しいので、程度の差はあれオムツ交換をすることになると考えておく必要があります。その際に問題になるのが、介護者の対応による認知症の方の状態変化です。具体的には失禁が見られたときの介護者の対応が重要になります。
仕方のないことかもしれませんが、その場面に接したとき、専門職と呼ばれる人でさえ、叱責や明らかな嫌悪感を持った態度をよく見かけます。
当たり前のことですが、誰も失禁をしたくてしているわけではありません。
何らかの理由で失禁をしてしまったことに対して、そのような態度で対応されて良い気がするはずはなく、その気持ちを上手く表現できない認知症の方は相手を困らせる言動をとってしまうこともあるのです。
そうならないためにもしてしまったことに対しては大変だったと共感し、感情的にならずにオムツ交換をしましょう。
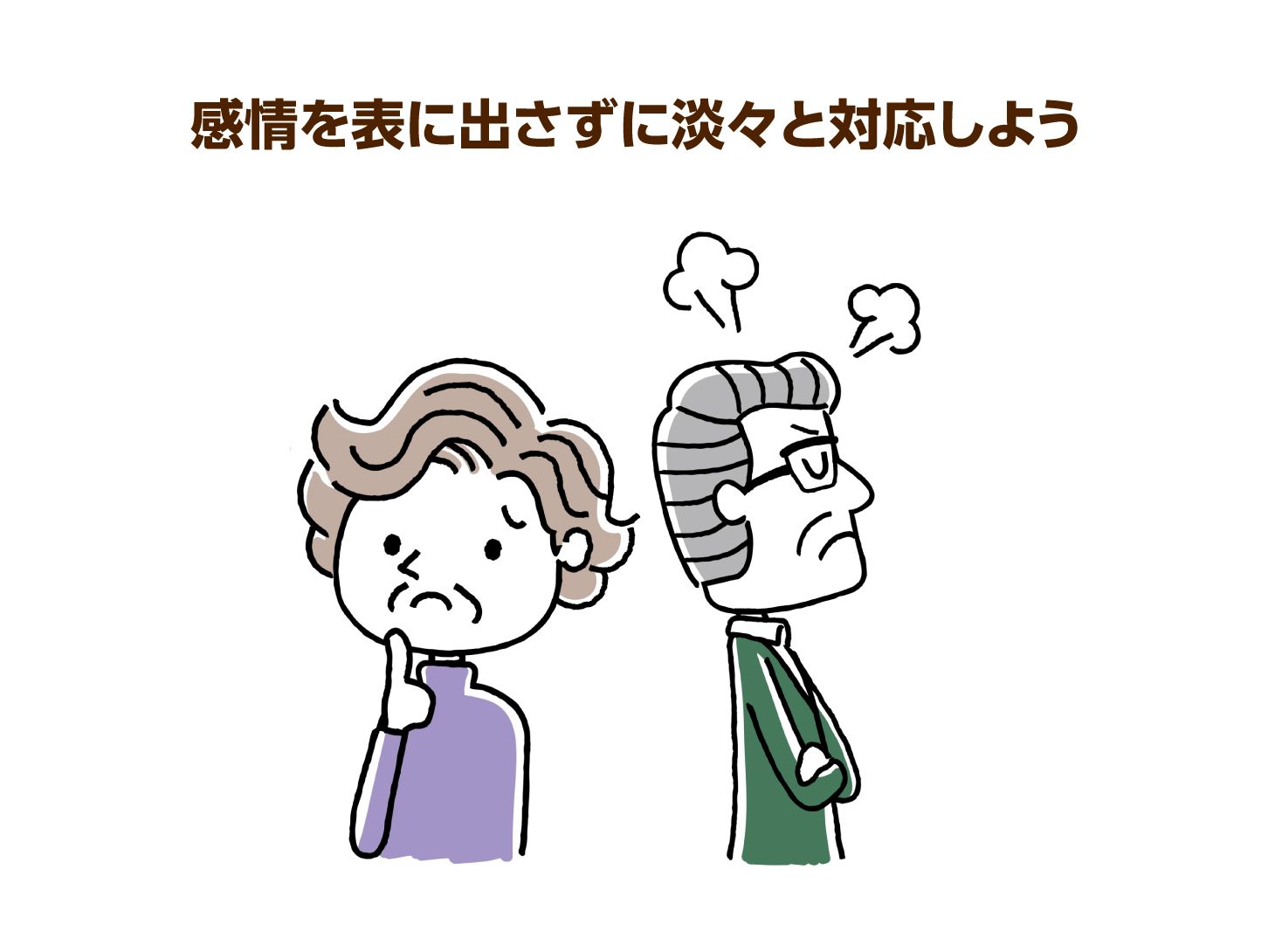
時間がかからないように工夫する
次に、オムツ交換にかける時間の問題です。時間が長くなり過ぎると認知症の方と介護者の両方にとって良いことはありません。
丁寧に対応することは大前提にありますが、そればかりに時間をとられて、陰部などを長く他人の目に晒す状態は好ましくありません。何も認知症の方に限ったことではありません。
そのためには手際をよくすることが大事ですが、交換するうえで必要と思われる物品を近くに置いておくなどの準備もしておきましょう。何かあるたびに場を離れることはできる限り避けるようにします。
そうすることで認知症の方がじっとできずに動いたり、便座に座っていることができず立ったりしてしまい、後始末が大変になることもある程度は防ぐことができるのです。
体勢や下剤の種類を見直す
最後に、後始末でもさまざまな面で苦労があります。それは便の形状や回数によっては何度も交換の必要が出てくることで、介護を受ける本人と介護者の両者にとって問題が生じやすくなる点です。
原因として医学的な問題の場合もありますが、別の面からも考える必要があります。その一つがベッド上など寝たままの体勢でしか排泄が行われていないかという点です。
この体勢では排便がすっきり行われることはなく、体の中に残った状態のままでダラダラと出続けることは負担になります。それが座ってするという当たり前のことをするだけで軽減されるのです。
また、下剤を見直すだけでも変わってきます。私の経験ですが、本人の状態を考えることなく、同じ下剤でも合わない薬を処方されている方を見かけることがあります。
医師に、ただ困っているとだけ伝えている場合は、きちんと細かい状態を伝えることがオムツ交換の負担を軽減するためにも必要です。そうしないと、医師はただ漫然と同じ薬を処方するだけになってしまうので改善が難しくなります。

排泄の問題はとても奥の深い内容です。オムツ交換について考え直す一つのきっかけにしていただければと思います。