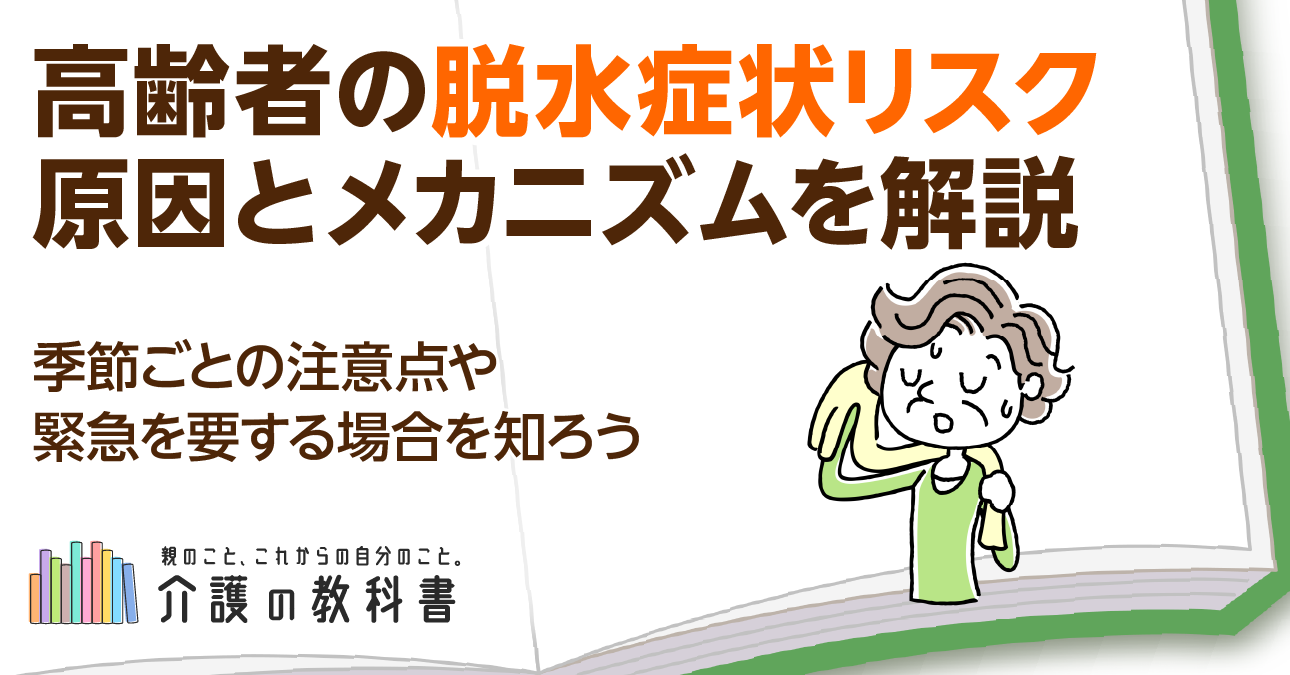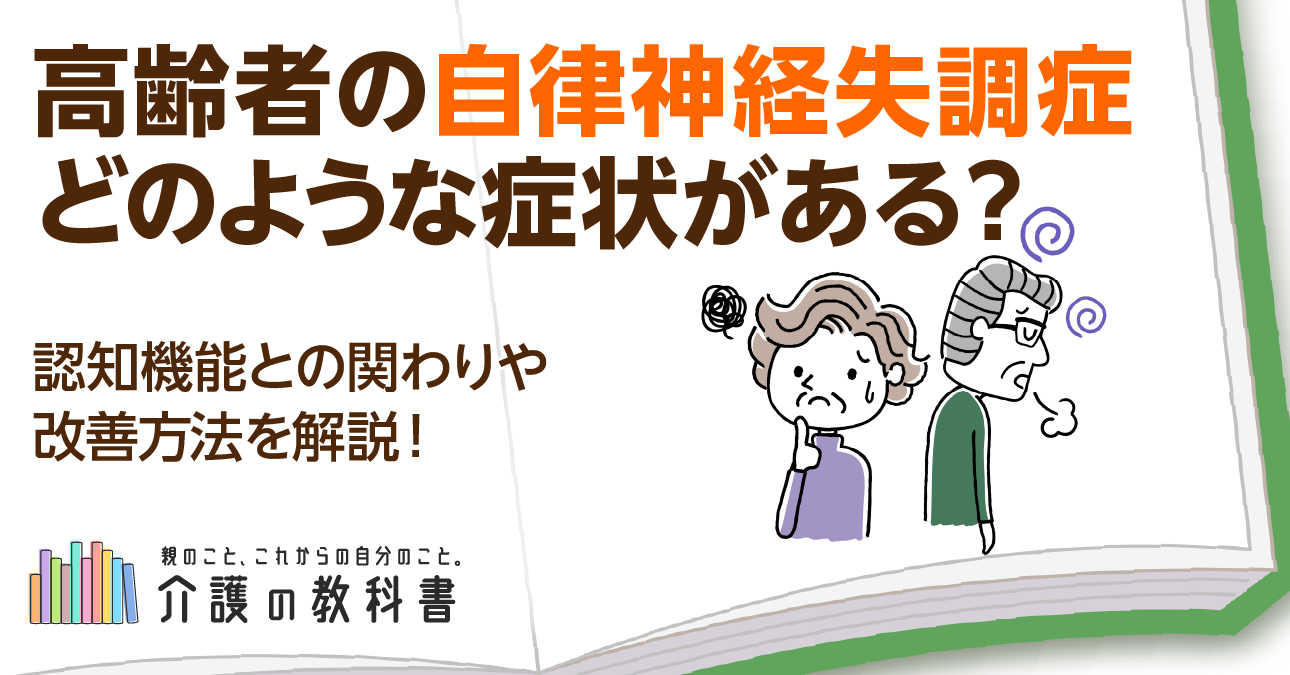定年退職後に「健康のため」「地域に貢献したい」という理由で農業を始める人が多いそうです。
今回は、高齢者が農業を行うことで得られる「心身の効果」や「認知症予防と改善」について紹介します。
農福連携の意味と効果
農福連携とは、身体・知的・精神障がい者、生活困難者の「社会参加」と「農家の人出不足」を解消するために、国や自治体、法人が支援する取り組みを指します。
2019年には、農業だけではなく多様な分野でこの取り組みを広げるために「農福連携」から「農福連携等」と表現が変わりました。
高齢者が行う農福連携は、次の4つに分類されています。
- リタイア農業者型農業
- 高齢のためにリタイアした人が行う
- 定年退職型農業
- 職場が定年になった人や帰農者が始める
- 介護予防型農業
- 認知症予防や介護予防のための農業
- 介護サービス型農業的活動
- 介護施設で社会参加活動として行うもの
高齢者が農業活動で得られる効果に、プレフレイル(前虚弱)の予防が挙げられます。
定年退職すると、友人や地域とのつながりが少なくなり、身だしなみなどに気を使わなくなることが指摘されています。また、運動不足による下肢の筋力低下などが生じ、フレイル(虚弱)の前段階にあたるプレフレイルになりやすくなります。
農作業を通して体を動かしたり、年齢を問わず周囲の人と話をすることで「自分の居場所づくり」「生きがい」「役割」ができます。それによってQOLの維持・向上につながるのです。
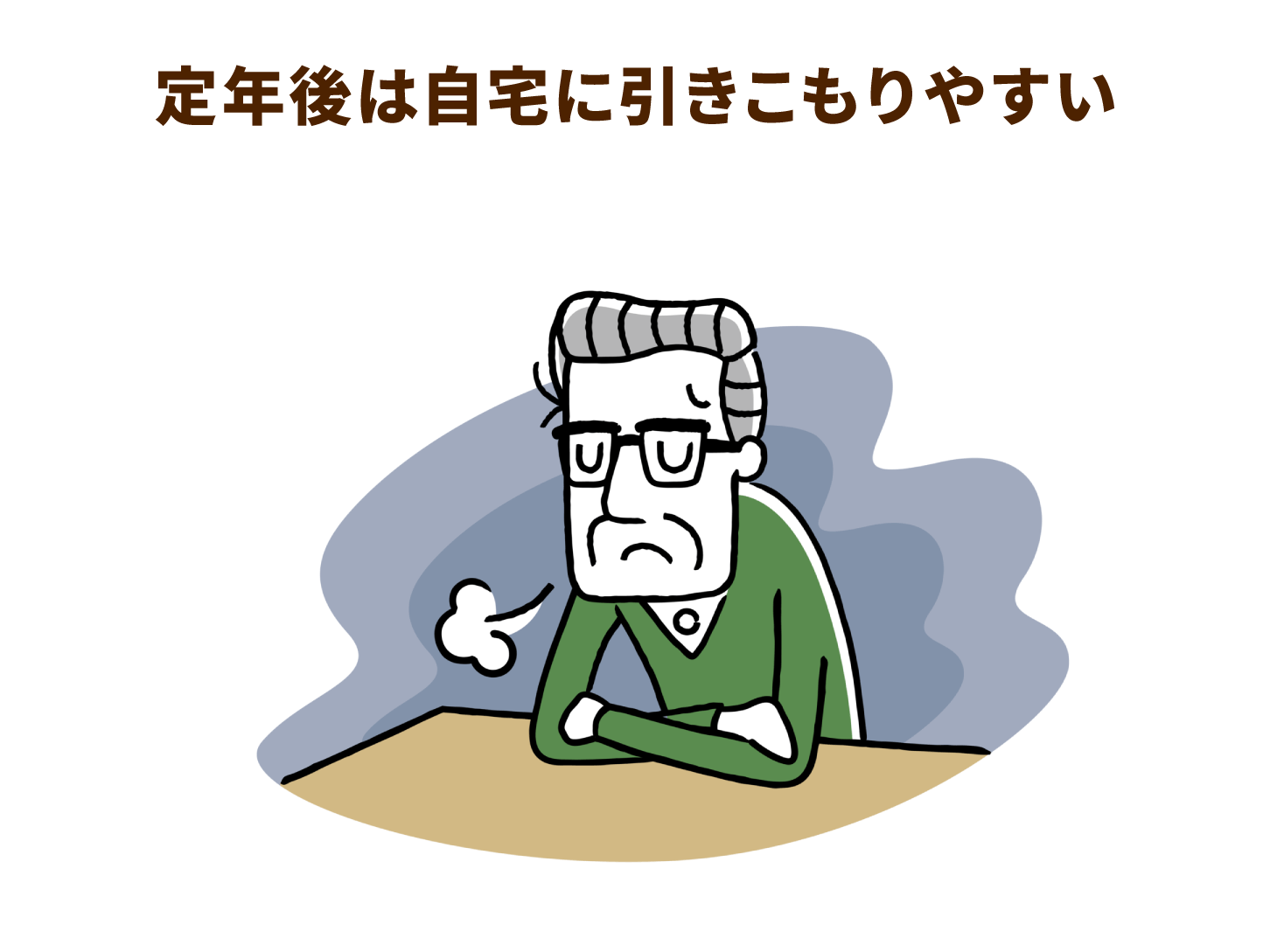
農作業は認知症予防と改善効果も期待できる
認知症予防と改善には、運動・認知トレーニングや十分な睡眠、社会参加が効果的だといわれています。
草取りや畑作業などの農作業は、指先や体全体を動かすることにより血流が良くなり、脳の活性化が期待されます。
また、農作物の栽培方法を、新たに記憶することで、認知トレーニングにもつながります。
さらには、野菜や米などの農産物の栽培、収穫、出荷などを通じて地域住民との交流が広がり、地域での役割なども形成されます。
例えば、介護施設で行っている「介護サービス型農業的活動」では、プランターや市営農園などで花や野菜を栽培。収穫したら昼食時に提供、あるいは加工して地域で販売するなどの社会参加が実践されています。
私が勤務しているデイサービスセンターでも、施設内にある畑で枝豆、ナスなどを入所者とスタッフが一緒に育てています。収穫期には副食の一品として提供しているのですが、利用者様にはとても喜ばれています。
【事例:Aさん 女性 80歳】
Aさんは認知症状があり、普段レクリエーションや行事に誘っても参加をしない消極的な性格でした。Aさんは自身の「もの忘れ」を気にしていて、そのせいで自信を失っていたのです。
ある日、介護スタッフが野菜の植え方を尋ねたところ栽培方法をわかりやすく教えてくれました。
そこで、施設で行っている農業に参加していただいたところ、他の利用者さんと話をする機会も増えて、自分に自信がついたようでした。楽しそうに過ごしているAさんを見られるようになったので、声をかけてよかったと感じています。
【事例:Bさん 男性 80歳】
Bさんも認知症状があり、他の利用者さんとの交流も少なく、自室にこもりがちでした。また、下肢の筋力低下がみられ、転倒リスクが高いために介護スタッフが常時見守りや声かけを行っていました。
当初、農作物の話をしても興味を示しませんでしたが、施設内の畑にできた野菜を見て手に触れると、昔の仕事の話を始めました。
以降、介護スタッフに笑顔を見せるようになり、歩行訓練にも積極的になりました。すっかり心身ともに安定し、生活全体の介助量も減少しました。

地域活性化と共生社会を同時に実現する
以前までの農福連携は、障がい者の社会参加や就労支援を目的に行われてきましたが、高齢者も「地域社会とのつながり」「自分の役割」「生きがいづくり」ができることで、福祉施設や自治体、企業にも取り入れられるようになっています。
高齢者の農福連携を広げることは、農家の人出不足を解消できるというメリットも生まれます。農家にとっても今までできなかった農業ビジネスができるようにもなり、地域の活性化にもつながるでしょう。
一方、参加する高齢者は、農作業をすることにより、社会の一員としての自信を取り戻すことができます。農福連携は、地域活性化と共生社会を同時に実現できる取り組みなのです。