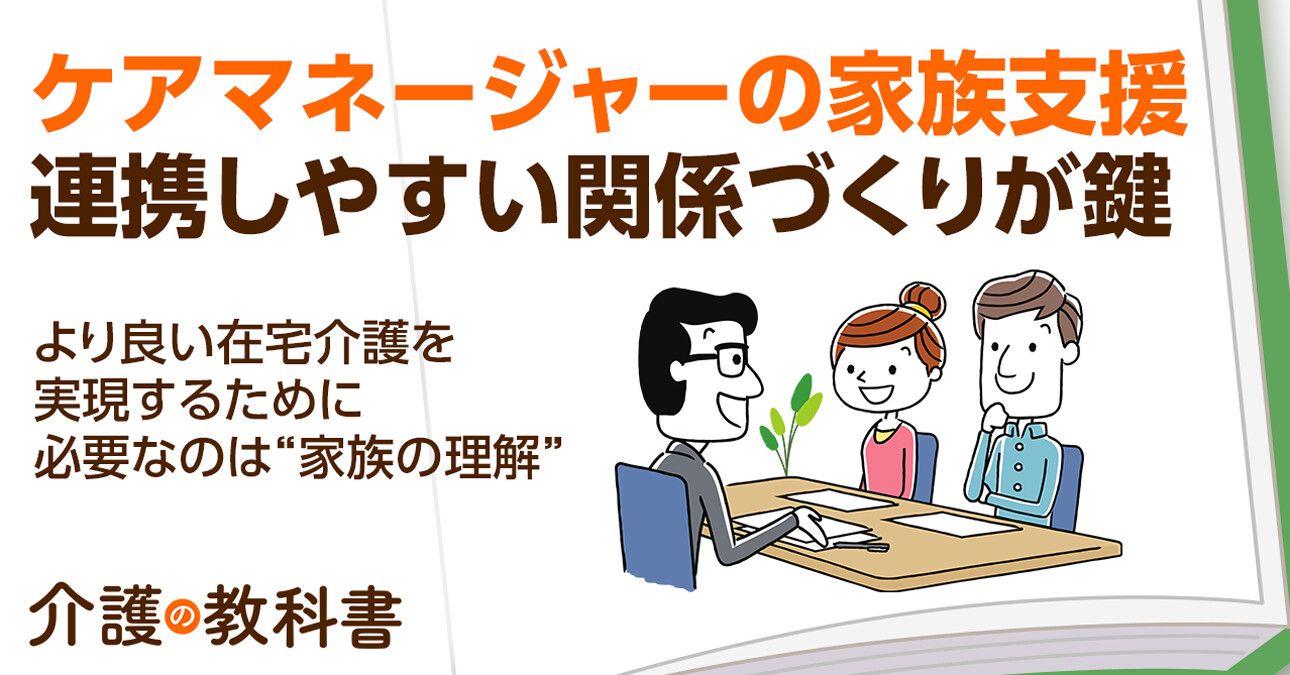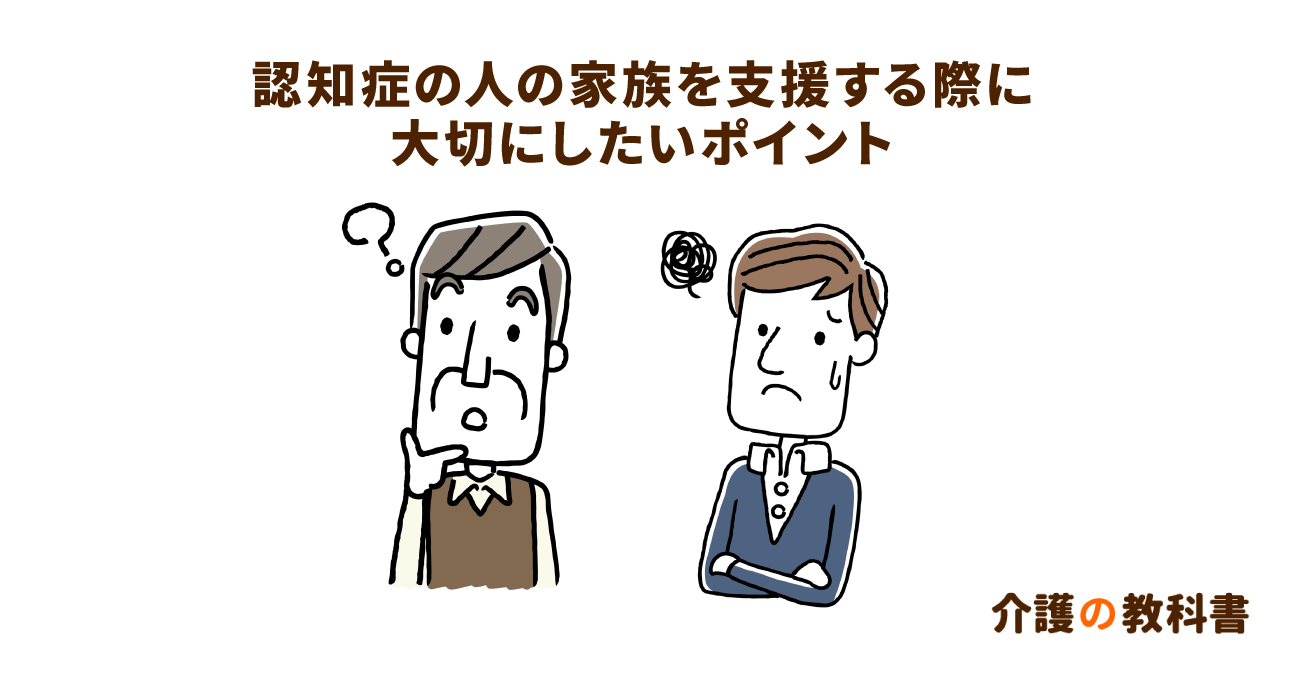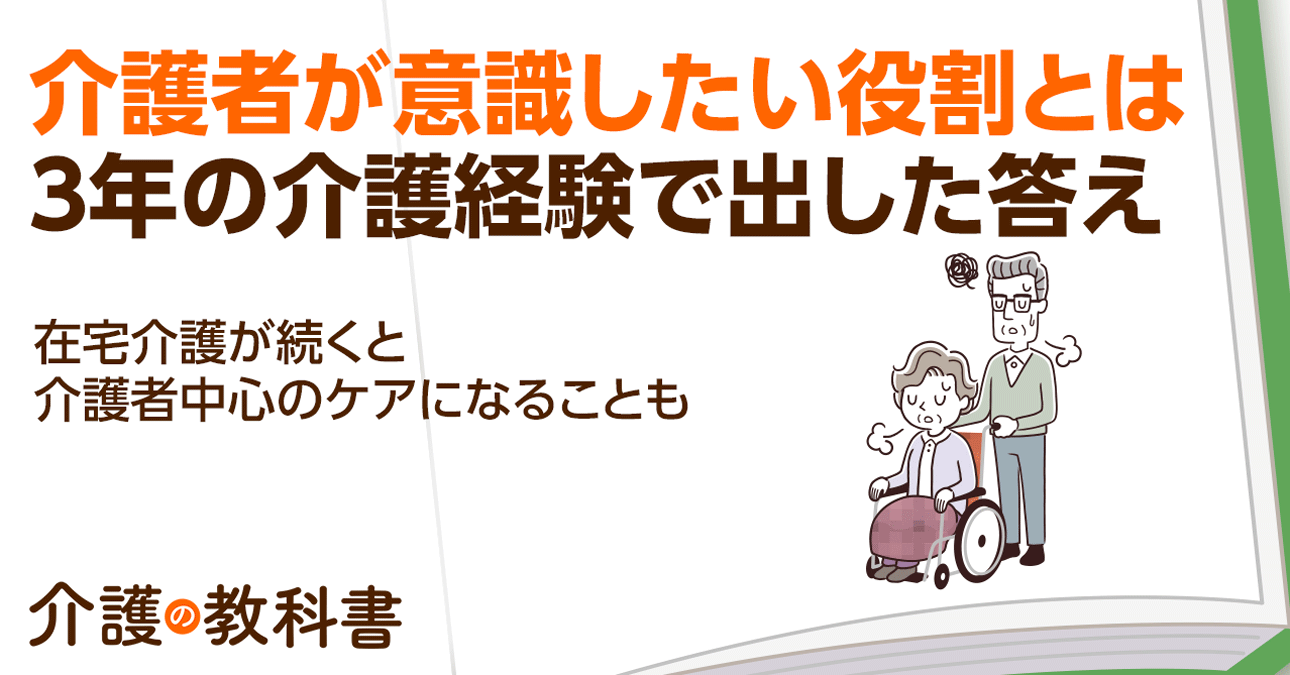認知症の人を支援するには、本人の支援だけではなく、介護者への支援もポイントになります。
そこで今回は認知症の人を介護する家族の思いについて段階別に見ていくとともに、どのような支援をすることが大切なのかをお話します。
認知症の診断時に起こる「ショック」段階
この記事で私が定義する“段階”とは、私が一から考えたものではなく、見聞きする中で感じたことが、障がいの受容過程と呼ばれるものに似ていると感じたことから、その過程を引用しています。
まず最初は「ショック」という段階です。大切な家族が認知症と診断されてから、しばらくはこの状態になります。
医師が家族の思いを少しでもくみ取って話をされるなら気持ちも和らぐのでしょうが、現実はそうでもありません。
ただ告げるか、この先の良くならない見通しのみを伝えられ、気持ちが落ち込んでしまったという話はよく聞きます。
この段階では私のような介護(福祉)職が関わることは少ないため、医師の家族に対する理解が進むことを願うばかりです。

認知症であることを受け入れられず混乱する
次に「否認」「混乱」という段階になります。つまり、家族が認知症であることを認められず、正常な判断がつかなくなる段階です。この段階は、認知症となった人に対するそれまでの思いが大きければ大きいほど出現します。
「子どもの頃に見た頼もしい母」や「優しかった妻(夫)」といった以前の姿とのギャップから生まれます。そして、私の親(配偶者)に限ってそんなはずはないと混乱を引き起こすのです。
この段階になると、医師の心理支援での出番はほとんどなくなり、介護(福祉)職によるサポートが必要になります。具体的には、多くの時間を「聴く」ということに充てることが大切です。
何かしらの答えや意見を求めてくる家族もいますが、私は原則として肯定も否定もしない姿勢でいることが大切だと考えています。
後々を考えて正しいことであれば肯定をしても良いですが、この時期は落ち着いた判断がしにくい中での発言でもあるので、充分に配慮される必要があります。
また否定されてしまうと、たとえそれが結果として正しい判断であっても、支援を考えるうえにおいて、最も大切な信頼関係を失いかねません。
この時期の介護者は、話を聴いてもらうことが大切です。そして福祉職が、その後の支援を受け入れやすいように心理面でサポートしていくと良いでしょう。
認知症の家族を「受容」できるかが大切
次に向かうのが「解決への努力」という段階です。大変だけど、介護を頑張っていこうという時期で、前段階で話を十分に聴いてもらっていると、それだけで前向きになられる方もいるほどです。
また、介護職など支援者の話を受け入れやすくなり、結果として最終段階である「受容」に移り、認知症であることを受け入れられる状態につながっていくのです。
具体的な支援としては、認知症の人に対する正しい声のかけ方や理解の仕方を伝えていくことです。
その一方で、私は同じ境遇にある人たちの集まりなどに出かけ、話を聴くことを強く勧めます。
同じだからこそわかり合えることがある、この大変さや辛さは自分だけではないと知ることが受容につながる一番の近道だと信じているからです。
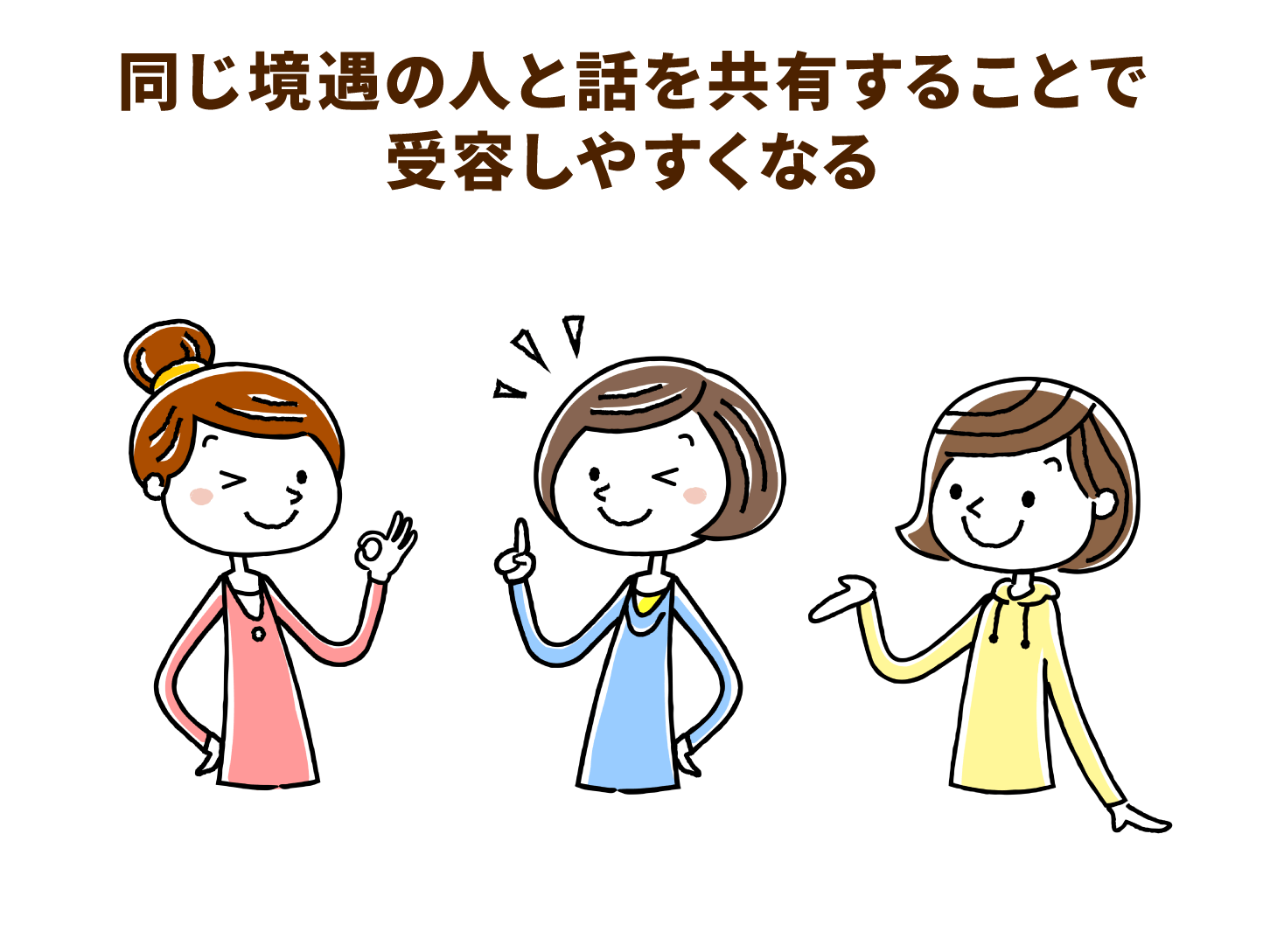
最後に、ここまで段階について順を追ってお話してきましたが、すべてのご家族に当てはまるわけではありません。ショックは受けたがすぐに受容できる家族、支援をしても否認と混乱を行き来だけしてしまうこともあります。
認知症の家族を抱える人は、こうした段階を知っておくことで、客観的に自分を見つめられるかもしれません。