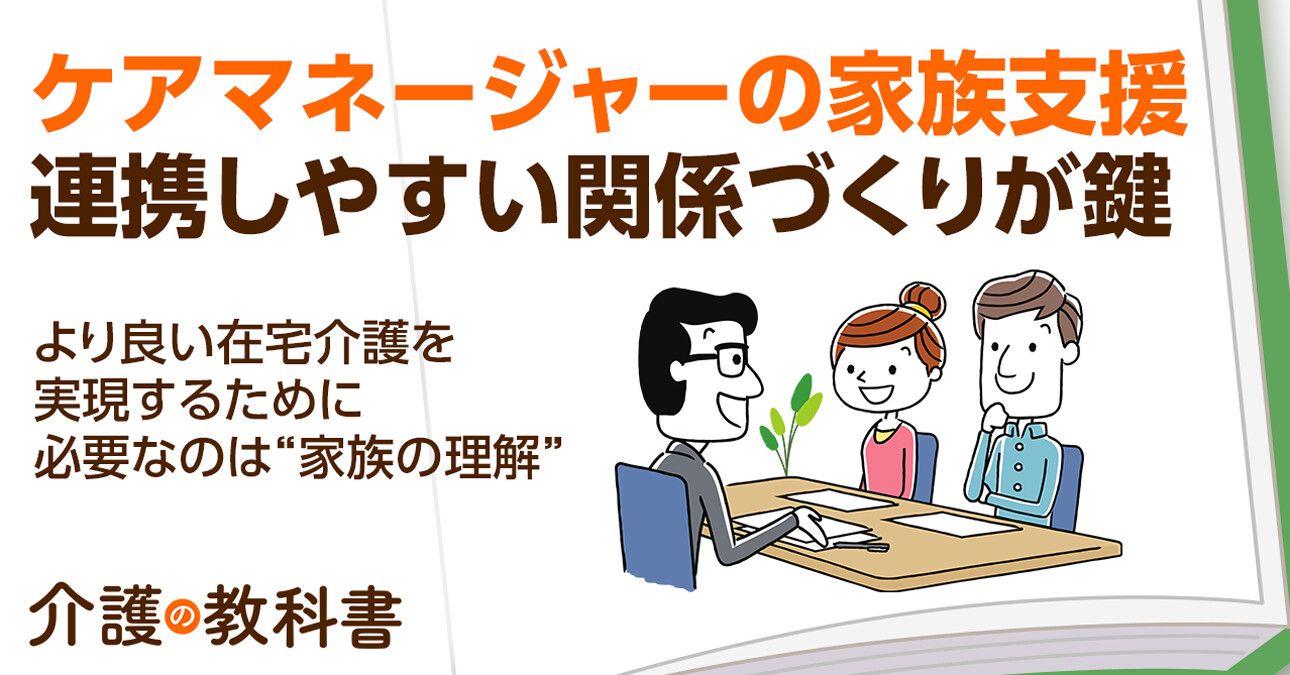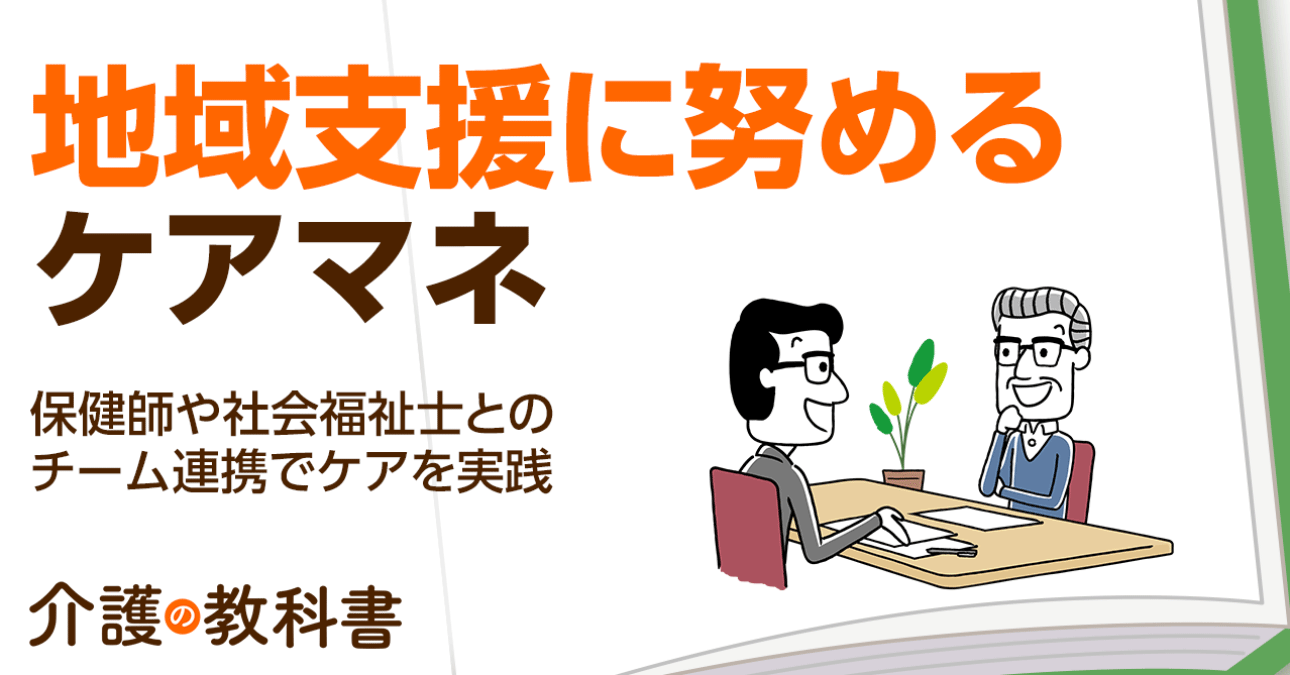皆さん、こんにちは。認知症支援事業所 笑幸 代表の魚谷幸司です。
認知症の支援と言えば、認知症の本人に対してのことを指す場合が多いように思います。しかし、それと同時に介護する家族の支援も大切だと私が世話人をしている「認知症の人と家族の会(大阪府支部)」は考えています。先日「認知症の家族支援とは」と題した意見交換会がオンライン形式で開催され、世話人の一人として参加しました。
そこで今回は、実際に参加してさまざまな意見を聞いたうえで、家族の支援を考えたときに必要だと思われることをお話いたします。
支援者は家族とつながっておくことが大切
まず大切なのは、認知症の人を持つ家族から相談があった場合、その後のフォローを続けることを忘れてはならないということです。そのときだけ支援すれば良いわけではなく、期間をおいて様子を伺うことが大切になります。
そうすることで家族も忘れられていないと感じられ、介護者が陥りやすい孤立感の解消につながります。よくわからないまま介護をしていると、「辛い思いをしているのは自分だけなのでは」という感覚に陥ると聞きます。そうなってしまうと、実際に介護するときに悪い影響を及ぼす可能性が考えられます。
そうならないためにも「聞くことを通してつながっている人がいる」「何か困ったことなどがあったときに頼れる人がいる」と認識してもらうだけで精神的な安定につながります。新聞で目にする介護を理由とした虐待や殺人の多くは、聞いてもらえる人さえいなかったことが大きな原因ではないかと私は常々思っています。

家族の思いを聞く機会をつくる
また、ケアマネジャーには、認知症の本人だけでなく、家族の支援も大切なことだと認識してほしいと感じています。認知症の本人に対してケアプラン(介護計画)を作成する際には、家族の意向を書く必要があるため話を聞くことがあります。ただ、それはあくまで本人に対してのことであり、家族の「本当の思い」は別のところにあるのです。
さまざまな理由から、一人に対してかけることのできる時間が限られていることは十分承知しています。また、的外れで無理な要望を言われる家族がいるのもわかります。
しかし、まずは話を聞き、そして自身の思うことを話して、お互いに思いを伝えることが、それぞれの状況がわかりあう手段になるのではないでしょうか。そして、それが支援の第一歩になります。もし、どうしても話を聞くことが難しい場合は介護者の集まりに出かけることが大切だと思います。
そこでは、家族が専門職と呼ばれる人を前にするとなかなか言えない思いを本音で話されています。その思いを知ることで本人に対する見方も変わり、支援の新たなヒントとなることがきっと見つかります。
介護職員に対する認知症の知識を深める
最後に、施設で働く職員も認知症の理解があると「家族が安心できる」という支援につながります。当たり前のようですが、働く職員、いわば専門職であれば認知症の対応に問題はないとは言えない現実があるようです。
もちろんすべての人ではありませんが、以前に私が聞いた家族の話の中に「認知症対応を掲げている施設ゆえ、きちんとした対応をしてくれると思ったのに、あれなら私がやっても変わらない」との声がありました。一例に過ぎないのかとも思いましたが、今回の意見交換会においても同じような話がありました。
施設には職員を教育する人員が不足していたり、時間的な余裕がなかったりするからではないでしょうか。しかし、それで良いわけでは決してありません。家族が困ったときに頼る場所として、最低限の当たり前の対応くらいはできる体制をつくることを望みます。

家族の支援にきちんと向き合うことで、認知症の本人に対しても良い影響を及ぼすことは間違いないと私は自信を持って伝えていきたいと思っています。