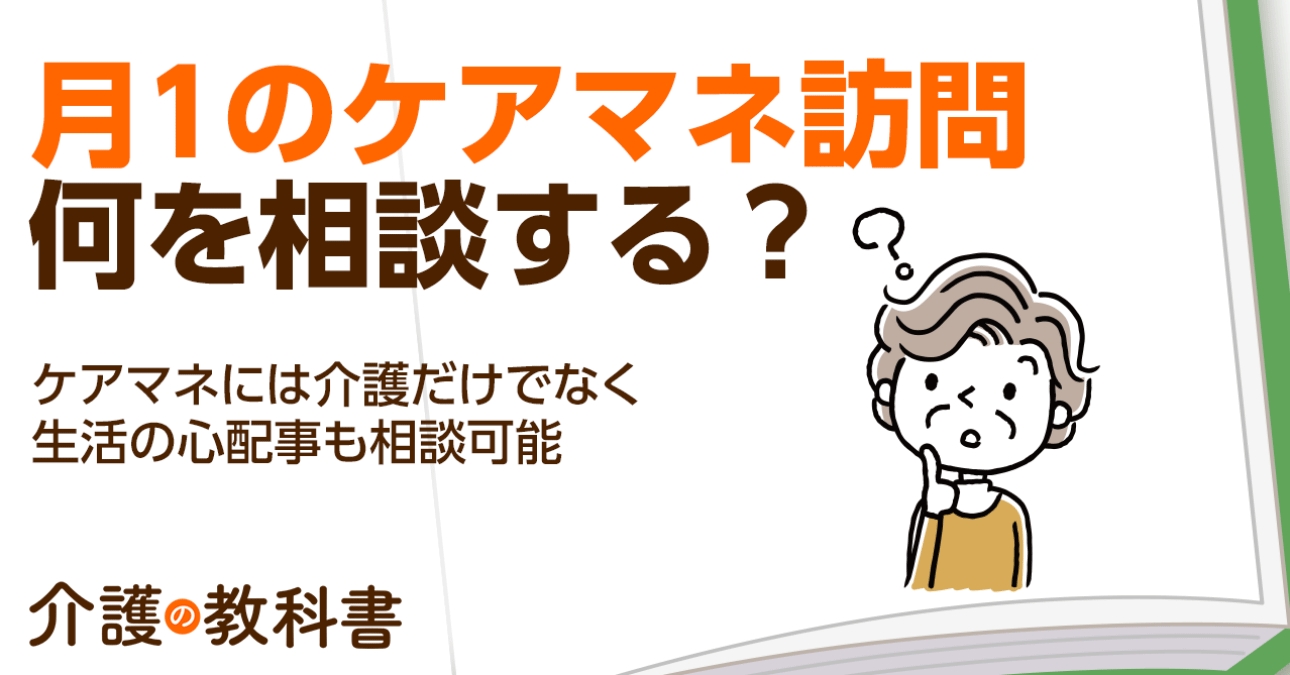株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。
今回は、介護保険法に基づく運営基準や解釈通知などから、特別養護老人ホーム(以下:特養)の特徴や現状の課題などを確認してみたいと思います。
特養の歴史と経緯
特養の源流は、1895年に設立された養老院(身寄りのない生活に困窮した高齢者を保護し、収容する施設)です。養護老人ホームと並び、日本で最初の入居型介護施設で、120年以上の歴史があります。
現行の特養は、1963年に公布された「老人福祉法」で制度化された施設で、2000年に施行された「介護保険法」では、「介護老人福祉施設」として規定されています。
特養は大きく分類すると、居室は多床室で食堂などの共有部も大人数で使用するつくりになっている「従来型」と、居室は個室でユニットと呼ばれる10名前後の少人数単位で生活をする「ユニット型」があります。
また、地域密着型介護老人福祉施設という定員が29名以下の小規模な特養も、地域密着型サービスとして規定されています。
その特養は現在介護保険法の運営基準において、次の基本方針が規定されています。今回は、従来型の特養について確認してみます。
【従来型】
(基本方針)第一条の二
指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2:指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。
3:指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
従来型特養の基本方針には、第194回でお伝えしたグループホームの基本方針と同じ、「その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように…」という文言が入っています。
しかし、グループホームの文末は「できるようにするものでなければならない」ですが、従来型特養は「できるようにすることを目指すものでなければならない」です。これは、グループホームには、自立的な支援を「行うこと」が示されているのに対し、従来型特養は、自立的な支援を「目標とすること」が示されているのです。
この違いの要因は、同じ基本方針の中にある別の文言にあります。
それは、グループホームは「家庭的な環境の下で」ですが、従来型特養は「家庭的な雰囲気を有し」と基本方針の中に明記されている点です。
「家庭的な環境」=「炊事や洗濯などのこれまでの生活で行っていたことができる環境(以下、生活環境)」であるのに対し、従来型特養はそのような生活環境を持っていません。そのため、「雰囲気を有し」=「生活環境に近い状況、生活環境の雰囲気を持っている」ことにしたのではないでしょうか。
ですので、前述した「その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように…」の文末の違いにある「するものでなければならない(グループホーム)」と「目指すものでなければならない(従来型特養)」にもつながっているのだと思います。

従来型特養の目的
次に、従来型特養の原則や基本事項を、運営基準に明記されている「基本方針(第一条の二)」と、「指定介護福祉施設サービスの取扱方針(第十一条)」から確認してみます。法文を要約すると以下の内容になります。
(事業の目的)
●居宅における生活への復帰(可能な限り)
●入所者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指す
●入所者の意思及び人格を尊重する
(事業の目標)
▲要介護状態の軽減又は悪化の防止
(目標の遂行方法)
▲施設サービス計画の作成と当該計画に基づいたサービスの提供
▲要介護状態の軽減又は悪化の防止策を計画的に実施
(提供するサービス)
●入浴、排泄、食事等の介護
●相談及び援助
●社会生活上の便宜の供与その他日常生活上の世話
●機能訓練
●健康管理及び療養上の世話
(留意すること)
●地域や家庭との結びつきを重視した運営を行う
●市町村と連携すること
●ほかの事業者、ほかの介護保険施設と連携すること
●その他の保健医療サービス、福祉サービスを提供する者と連携すること
▲心身の状況等に応じて、妥当適切に支援する
▲漫然かつ画一的にならないように支援する
▲サービスの提供は懇切丁寧に行うことを旨とする
▲入所者又はその家族に対し、サービス提供上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う
(施設の努力目標)
▲自ら提供するサービスの質の評価を行う
▲常に質の改善を図る
(禁止事項)
▲当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下、身体的拘束等)を行ってはならない
▲身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない
※●:基本方針、▲:取扱方針
従来型特養は、終身型の入居型施設のイメージがありますが、介護保険法では「可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に」おいて、サービスの提供を行うとされています。(ユニット型特養も同様。以降も従来型特養とある箇所はユニット型特養も含む)
また、運営基準第7条(入退所)の第4項には、「居宅生活が可能かを定期的に検討すること」が明記されています。
従来型特養は、中重度者や看取りへの対応の充実に期待が寄せられている一方、単なる入居型施設としての機能に留まるのではなく、入居者の在宅復帰支援への取り組みも求められているのです。

そのため、入居者が住み慣れた家に安心して復帰できるように施設(従来型特養)が支援することを評価する「在宅復帰機能支援加算」が設けられています。
また、従来型特養には入所されている方々への支援だけに留まらず、地域住民の在宅生活の継続を支援する機能も期待されています。それが、「在宅・入所相互利用(ベッド・シェアリング)」です。これは、3ヵ月を限度に在宅で暮らしている要介護者が交代で、特養のベッドをシェアするという仕組みで、加算が設けられています。
利用する方は、施設入所と自宅生活を行き来して、施設入所時には在宅生活に必要な機能訓練や体力の維持・向上、栄養マネジメントなどを受け、在宅生活の維持を目指します。ただ、現状の「在宅・入所相互利用加算」は、広域型・地域密着型の特養を合わせても算定しているのは11施設、取得率は0.11%に留まっています。
次回も運営基準・解釈通知などから特養の特徴などをお伝えします。