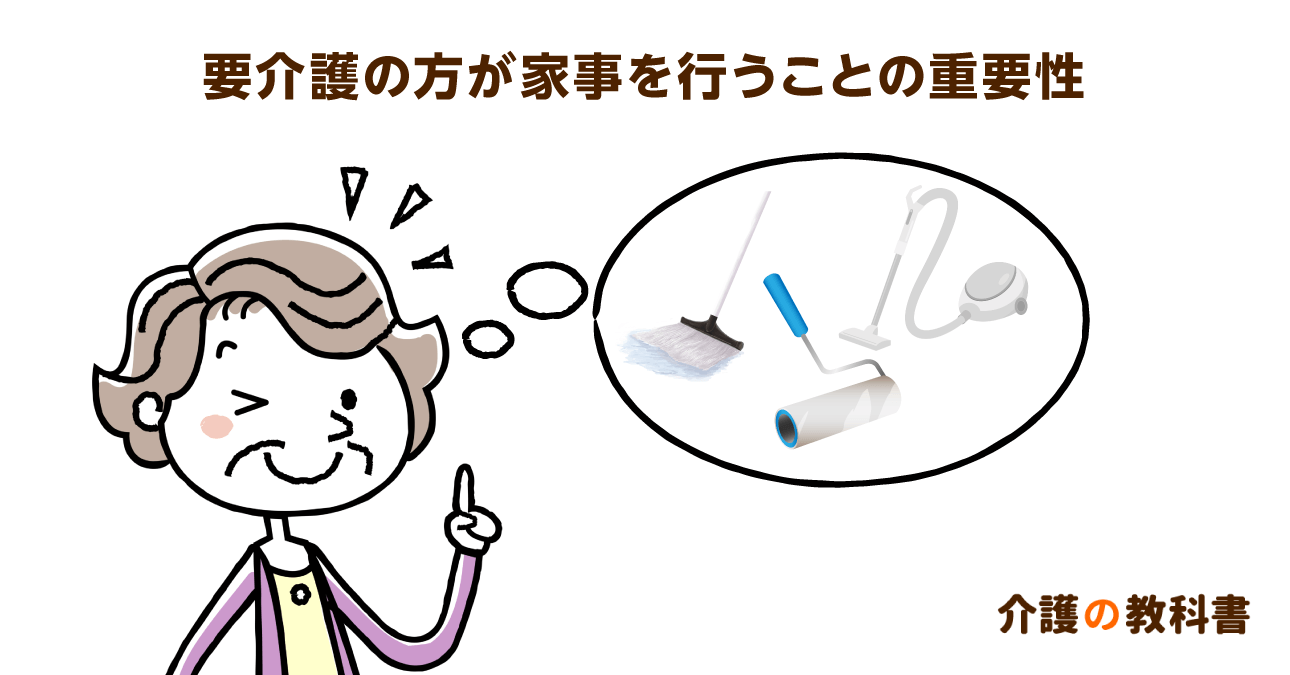株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。
今回は、著者が勤めていたグループホームで「入居者の方が有する機能や能力を最大限活用してもらう」ことを目標に取り組んでいた「自立型の日常生活支援」についてお伝えします。
施設で入浴を行う2人の事例
最後にいつ入浴したかを覚えていないSさん
夕飯を食べ終えて、片付けも済んでしばらくすると、職員が入居者のSさん(女性)に「Sさん、お風呂空いてますよ」と声をかけます。Sさんは「あら、そう」と職員の声がけに応じて自分の部屋に戻り、入浴準備を始めました。彼女は毎日入浴する習慣はあっても(グループホームでは毎日入浴していました)、最後に入浴したのがいつなのかは覚えていません。そして、自分から「入浴する・入浴したい」といった意思表示をすることもありませんでした。なのでSさんには入浴するきっかけをつくる支援(Sさんの場合は職員の声がけ)が必要でした。
しばらくすると、着替えやバスタオル、自分専用の風呂桶を持って部屋から出てきたSさんが、脱衣場に向かって歩き始めました。そんな彼女の様子を職員はさりげなく見守ります。Sさんは前に入浴したのはいつかは覚えていませんが、入居から半年ほどで浴室(脱衣場)の場所は記憶しています。なので、自分の部屋から浴室(脱衣場)に迷うことなく1人で向かうことができるSさんに対して職員が声をかけたり、まるで監視するかのように注視するといったことは必要ありません。
こうして浴室(脱衣場)の前に到着したSさんは、ほかの入居者の方や職員が中にいないかを確認。扉を開けて脱衣場に入っていきます。そんな彼女に職員は「Sさん、ゆっくり入ってきてね」と声をかけます。この時点での職員からの声がけは、Sさんにとって入浴するためのきっかけとなる「支援の声がけ」ではなく、同じ声がけでも、「気遣いの声がけ」に変わっていました。

髪を洗うことを忘れてしまうYさん
別の事例をご紹介します。Yさん(男性)は毎日、夜8時を過ぎた頃に入浴するのですが、そこに常時Yさんを見守る職員の姿はありません。というのも、筆者が勤めていたグループホームは夜8時を過ぎると、夜勤体制に切り替わります。このとき、1ユニット入居者の方9人に対して職員は1人です。その職員は談話室で夕飯後のひとときを過ごしている数名の入居者の方とお茶の用意をしたり、寝床を希望する入居者の方の部屋を訪れて就寝支援を行っていました。
職員はこのような支援の間に2・3回、Yさんの安否・安全をドア越しに映るシルエットや入浴行為の音から確認していました。なので、脱衣室・浴室に常時Yさんを見守る職員の姿はなかったのです。
安否・安全を確認しに行った夜勤職員が浴室のドアを少しだけ開き、Yさんに声をかけます。
職員とYさんの会話
職員「Yさん」
Yさん「なんだぁ?」
職員「髪、洗ってくださいね」
Yさん「おう、そうか。そうだな」
認知症の状態にあるYさんは、髪を洗うことをいつも忘れてしまいます。そのことを知っている職員は、Yさんが浴室に入り、出ようとする頃合いも知っていました。その頃合いを見計らって、「洗髪するきっかけ」となる支援(Yさんの場合は職員の声がけ)を実行していたのです。そして、Yさんに洗髪を促す声がけを終えた職員は、再びほかの入居者の方の支援に移っていきました。
Yさんは、入浴という日常生活行為の中において、「髪を洗う必要がある」ということのみを忘れてしまいます。なので、その後の以下の行為については、「自分が有する能力を使って、自分で頑張る」ことができるのです。
- 椅子または床に安定して座る
- 洗髪にはシャンプーが必要だと想起
- 容器や文字から、それがシャンプーだと判断
- シャンプーの出し方を理解
- 容器からシャンプーを出す
- 手指を使って頭全体を洗う
- シャワーなどを使って髪を洗い流す必要があることを想起し、実行
- 洗い流しが不十分ではないか確認し不十分であれば再度洗い流す
不要な介入はご本人が有する機能や能力を奪う
もちろん、Yさんのように髪を洗うことを忘れてしまう入居者の方はほかにもいらっしゃいます。体を洗うことを忘れてしまう方や、洗ったことを忘れ、何度も洗う人もいました。
最初の事例で登場したSさんは、入浴行為のほとんどを自分が有する能力を使ってできる方です。ですが、浴槽の給湯にある蛇口を閉めることを忘れてしまい、浴室から脱衣室へお湯があふれてしまう恐れがありました。なのでYさんと同じように職員は、浴室のドア越しに時折Sさんの安否・安全を確認していたのです。
このように、入居者の方々は認知症の状態であるために、入浴行為の中で何かしらできないことがありました。しかしだからといって、職員が常に本人に張りついたり、すべての行為をやってあげる(手を出す・介入する)ことはありません(ただし、入浴行為全般に支援が必要な方には支援を行う)。
というのも、いくつか不完全な状態であるからといって、その行為すべてに職員が手を出す・介入することは、「ご本人から『自分が有する機能や能力を発揮きする機会』を奪うことになる」と著者や職員は認識していたからです。そしてそのことは、入居者の方たちを不活性・廃用の道に導いていまう恐れがあることも認識していました。

「お節介」ではなく「支援」を行おう
著者はこんな話を聞いたことがあります。
支援が必要でないことに介入すること、それを「お節介」という。
お節介であれば、その方のことを知らなくても何とかなります。とにかく手を出し、介入すればいいからです。逆に、「自分が有する機能や能力でできることは自分で頑張りましょう。行うのが難しいことはサポートする」というスタイルの日常生活支援は、その方のあらゆる日常生活行為における有する機能や能力、感情、嗜好、習慣、人間関係などを知らなければできません。
「何でもやってあげる」「お節介介護」からの脱却に必要なのは、その方のことを「知りたい」という支援者としての欲なのかもしれません。