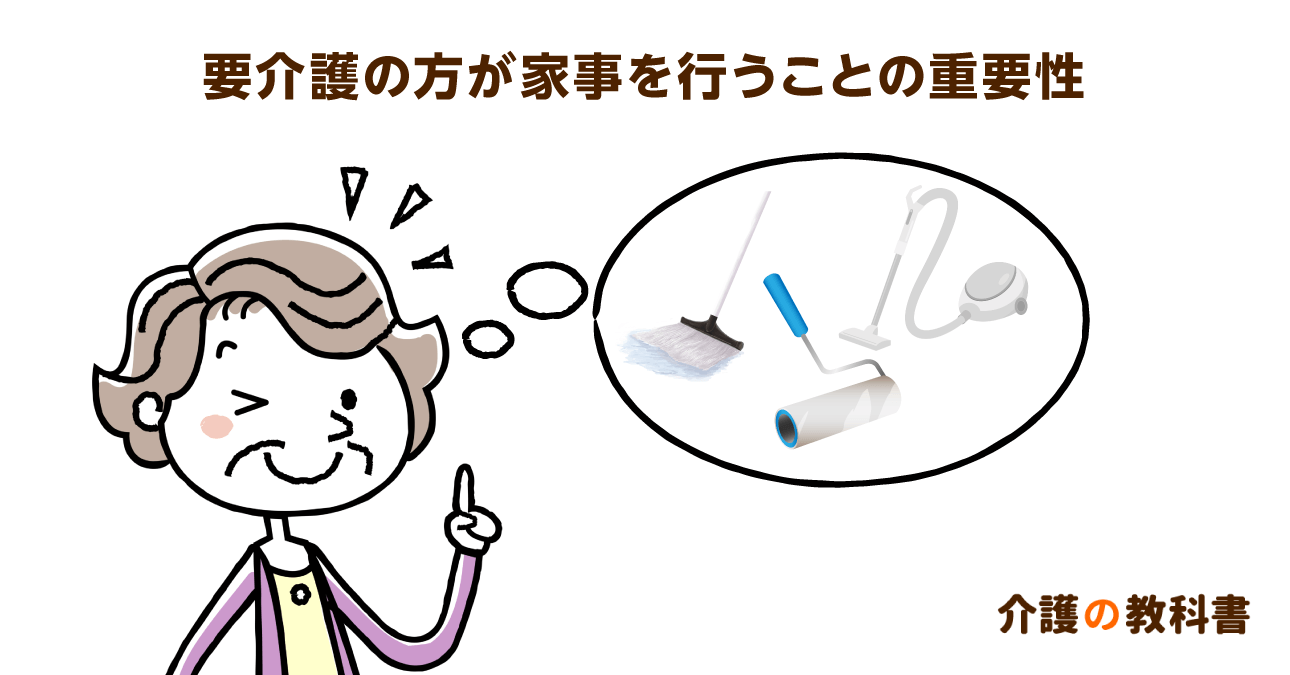株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。
今回は、筆者が勤めていたグループホームでの事例を通じて、介護施設に入居されている認知症の状態にある方の自発的な行動を促す環境づくりについて、お伝えします。
認知症の方が自ら進んで行動した3つの事例
洗濯物を取り込むAさん
ある日の夕暮れのことでした。入居者のAさん(女性)が「日も陰ってきたし、あの洗濯物をしまった方がいいんじゃないかしら」と職員に声をかけてきました。Aさんの視線の先には、ベランダに干してある洗濯物がゆらゆらと風に揺られています。
Aさんのおかげで洗濯物を部屋に取り込んでいないことに気づいた職員でしたが、洗濯物の量は入居者の方9人分。職員1人が取り込むにはかなり苦戦を強いられます。すると、職員の背中越しに「手伝いましょうか」とAさんが声をかけてきました。
職員「いいですか…手伝ってもらっても…」
Aさん「こんなにたくさんあるんだもの。1人じゃ大変ですよね」
職員「助かります。Aさん、ありがとうございます」
施設を掃除するBさん
昼食も終わったある昼下がりのことでした。壁にもたれかかったほうきとちり取りを指差し、Bさん(女性)が職員に「あの~、あそこにあるほうきとちり取りをお借りしてもよろしいですか」訊ねてきました。
職員「ほうきとちり取りですか、どうぞ」
Bさん「ありがとう」
職員「どうかしたんですか」
Bさん「うん…ほらここ、汚いから」
自分が腰かけていた、イス周りの床を指さすBさん。そして彼女はほうきとちり取りを手に取り、床のゴミを集めはじめました。最初は食べかすを集めていただけだったのが、あっちのほこり、こっちのほこりと、ほうきを掃く手が止まりません。さらに、「こっちの方がきれいになりそうだから…」とフロアモップに持ち替え、気づけば彼女は掃除を始めた談話室から廊下の先まで掃除してくれたのでした。
電気ポットに水を補充するBさん
ある日、施設を掃除してくれたBさんが談話室にある電気ポットの給湯ボタンを何度も押していました。「あら、どうしたのかしら。お湯が出ませんね」と言うBさん。職員はポットの水量計を指して、お湯がなくなったことを伝えました。
そこではじめてお湯がなかったことに気がついたBさんは、キッチンに向かって歩き出し、やかんに水を入れてそれをポットに注ぎ込んだのです。
Bさん「これでもう大丈夫ね。でも、お湯になるまで待たなきゃいけませんね」
職員「大丈夫ですよ。すぐに沸きますから」
Bさん「そう。良かった」

日常の中の「モノ」が入居者の自発性を刺激する
ベランダに干してある洗濯物や壁にもたれかかったほうきとちり取り、そして談話室に置いてある電気ポットなどをきっかけに、彼女たちは自発的に行動しました。どれも日常の暮らしの中に存在し、ありふれたものです。
入居者の方たちにとっても決して目新しいものではなく、要介護の状態になる以前の自宅生活で、当たり前のように自ら手に取り、使ってきたものばかり。筆者や職員は入居者の方たちに、一般的な住環境に近い雰囲気を感じてほしいから施設内にこれらを用意していたのではありません。日常の暮らしの中にある品々が、入居者の方たちの「自発性を刺激する環境の一部になる」と考えたからです。そのために入居者の方たちの目に入り、手にとることができるようにしていました。もちろん、安全面を考慮したものを選んでいます。
AさんとBさん。どちらも環境の一部が、彼女たちの自発的な行動につながっていたのではないでしょうか。

「やらせる」のではなく、「やってみよう」と思える環境をつくり出す
以前、ある認知症に関する専門職研修で、グループホームに介護職員として勤務している方からこんな質問を受けました。
「うちの利用者さんは何もやらないんです。どうしたら、食事づくりや掃除をやるようになりますか」
質問者の「何もやらない」「どうやったらやるのか」という言葉の裏側には、「やらせる」という意味が隠れています。おそらく質問者は、認知症の状態にある利用者の方たちに食事づくりや掃除をやらせることが、仕事(介護)の目的になっているのでしょう。
また、国が「科学的介護の導入による自立支援の促進」を推し進めているので、「自立支援」という言葉に影響されているのかもしれません。「自立支援=自分でやってもらう」だから、“やらせなきゃいけない…”と。
筆者は、利用者の方たちに「やらせる」のは、ある言葉の意味である「権力や威力によってその人の意思にかかわりなく何かを無理にさせること」にしか思えません。ちなみに、この意味を持つ言葉は「強制」です。
私たちは基本的に、自分に必要な食事や更衣、移動、排泄などの日常生活行為を自ら行います。しかし、それらは誰かからの「強制」ではなく、自分の意思や感情、意欲(その気)、その行為を行う必然性(理由や目的など)などがあってのものです。そしてそれは入居者の方たちも同じで、私たちと同様にそれまでの長い人生を自発的に動き、主体的に日常生活を送ってきたのです。
だからこそ、「やってみよう・やらなきゃ」と本人がその気になるように「自発性」を生み出す環境を整えること(環境をマネジメントする)も、認知症の状態にある方たちの日常生活を支える私たち支援専門職の仕事なのです。
最後に、今回の記事と第106回もあわせてお読みいただければ幸いです。
「やらせるは強制」「強制は虐待」の道に進まないためにも。