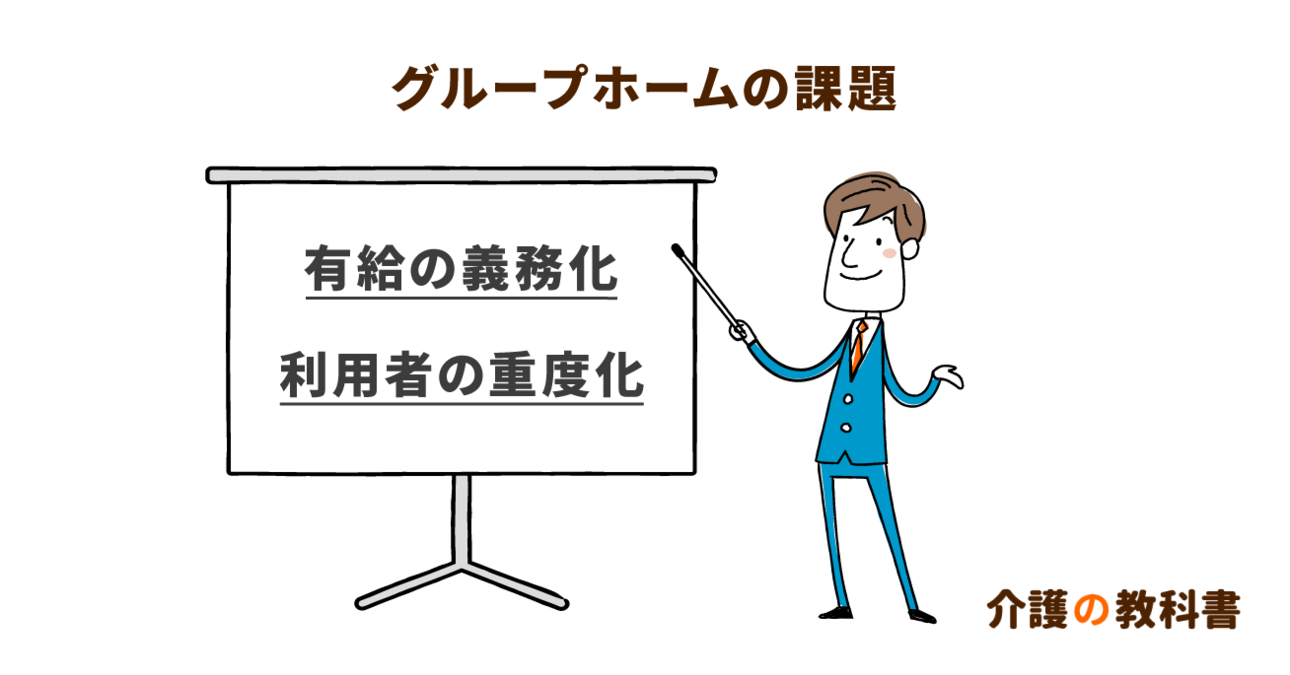株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。今回も、第150回と第153回でお伝えした「人員配置基準における介護ロボットの在り方」についてお話しします。
介護ロボットの導入で人員配置基準を緩和
まずは、「社会保障審議会介護給付費分科会」で出された主な人員配置基準の緩和案を確認してみましょう。
1:特別養護老人ホーム
1ユニットあたりの入居定員数
| 現行 | 緩和案 |
|---|---|
| 10人以下 | 15人程度まで増やす |
日中における人員配置基準
| 現行 | 緩和案 |
|---|---|
| 1ユニットに1人以上の介護・看護職員 | 2ユニットで介護・看護職員の1人体制を認める |
2:グループホーム
夜間における人員配置基準
| 現行 | 緩和案 |
|---|---|
| 1ユニットに1人以上(2ユニットの場合は夜勤者2名要) | 2ユニット以上の場合:夜勤者1名+オンコール対応の在宅待機宿直者1名+見守りセンサー |
認知症介護実践者研修を修了したケアマネージャーの配置基準
| 現行 | 緩和案 |
|---|---|
| 1ユニットごとに配置 | 複数ユニットの兼務可 |
3:全サービスに渡って適用される配置基準の改正案(緩和策)
下記については、介護従事者の育児と仕事の両立を進める観点から、運営基準を見直せないか検討していくそうです。
- 常勤配置を求められている職種(例:施設ケアマネージャーや生活相談員など)の職員が産休や育休を取る場合に、同じ資格を持つ複数の非常勤職員を常勤換算することで、運営基準を満たしたとする特例の導入
- 育休などを取った職員が短時間勤務制度を使って介護現場に復帰する場合、週30時間以上の勤務で常勤扱いとする特例の導入

介護ロボットやICTの活用で介護職員の省力化・生産性の向上を狙う
現役世代が減り続けることを考えると、今後介護人材を確保することがより困難になると予測されています。そこで政府は「介護現場の革新」を必要とし、介護ロボットやICTを活用して、介護職員の仕事の省力化と生産性を向上させようとしています。そして、最終的には人員配置基準の緩和を考えているわけです。つまり、人手不足の解消策として、「機器の導入を条件に介護現場から人を減らす(人員配置基準を緩和)」ということです。
見守りセンサーは万能というわけではない
では、人員配置基準緩和のキーワードである「介護ロボット」について考えてみたいと思います。とはいえ、介護ロボットには明確な定義は存在せず、医療機器のような法的な定義はないそうです。
「何がロボットか?」「どこまでがロボットなのか?」という明確なラインはなく、見守りセンサーから移乗、移動、排泄などの支援機器、そして寝返り支援のベッドまでも介護ロボットに分類されているのが現状です。
異常を感知できても対応には人手が必要
前述した「見守りセンサー」は、夜勤職員の人員配置基準の緩和における議論で取り上げられることが多い機器の1つ。見守りセンサーを導入することで、夜勤職員が必要以上に巡回しなくても良くなりますし、そこに体温や血圧、呼吸などを検知してくれるシステムも加われば尚のことです。その点から、介護職員の夜勤業務の省力化に役立つ介護ロボットだと思います。

しかし、見守りセンサーで夜勤職員(人)の代行ができるのは「見守り」と「通知」まで。検知した「異常」への対応を見守りセンサーは代行できません。なので、「異常」が検知された場に駆けつけ、対応するのは夜勤職員になります。
また、夜間・深夜帯の仕事は見守り(巡回)だけではありません。トイレ誘導やおむつ交換をはじめとした排泄支援や体位変換、何らかの事情で眠らない入居者の方への応対など、見守りセンサーでは代行できない、直接的支援が求められます。
見守りセンサーの活用で夜勤職員の巡回を減らすこと(=仕事の省力化)は可能ですが、だからと言って夜勤職員の配置数を減らしてしまえば、自ずと「異常」などへの対応や、直接的支援の提供も含め、夜勤職員1人あたりの負担は増えることになってしまいます。
さらに、入居系介護施設の夜間帯は入居者の方の「異常」だけでなく、災害や事故、夜勤職員自身の事故や病気といったトラブルに元々脆い職員配置体制です。休憩時間のあり方を含めた労働基準法上の問題もありますから、夜勤職員配置における基準緩和の検討が俎上に載せられること自体に納得できない自分がいます。
介護ロボットは離職防止と定着率の向上のために活用すべき
見守りセンサーの導入は介護職員にとって労働負担の軽減になりますし、減らした分の時間をほかに充てることができます。その点を踏まえると、見守りセンサーは「人を減らすため(人員配置基準緩和)ではなく、人を護るため(離職防止と定着率の向上)に活用すべき介護ロボットなのではないか」と僕は思うわけです。
それはほかの介護ロボットやICTも同様で、まずは介護現場の現状を維持(離職・介護人勢減少の防止)するために、介護現場の労働環境改善に資する介護ロボットなどの開発と現場への導入・活用にすべきではないかと思います。それと同時に、介護ロボットなどによる介護現場の労働環境改善で、介護という職業のネガティブイメージも改善しつつ、就業意欲や意識が沸く職業としていく(人材の誘導)ことができたらと僕は考えます。
また、介護ロボットやICTなどを介護現場にどんどん導入し、介護従事者に「時間をつくる」べきだとも考えています。その時間は人を減らすことに充てるのではなく、現状では不十分と感じざるを得ない要介護者の方々へのかかわり・支援量を増やすことに充てた方が良いと思います。
そのほかにも、支援の質の担保・向上には介護従事者が机のうえで考える(支援を思考・熟考する)時間が絶対に必要ですので、そこに充てるのも良いでしょう。本来介護は、「何でもやってあげること」でなく、「できることが続けられるように」、また「できないと思われていたことを取り戻し・できないことは補う」ことが仕事です。それが、社会福祉法の理念と介護保険法の目的にある「有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援する」ということです。
その点を踏まえると僕は、介護ロボットが要介護者の方の「日常生活行為の全代行を行う機器」として開発されたり、その観点から進化・発展が進んでほしくはありません。

介護ロボットは「自助具」として扱いたい
「自助具」という言葉があります。ある冊子に、「自助具とは、体などが不自由な人が日常の生活動作をより便利に、より楽にできるよう工夫された道具。英語では「Self - help devices」(自らを助ける機器)」とありました。
介護ロボットも「立つ」「歩く」「食べる」「トイレで排泄する」といった日常生活行為や、「バスや電車に乗る」「外食する」といった社会生活に欠かせない行為をできる限り自分で行うための「自助具」として進化してほしいと僕は思っています。