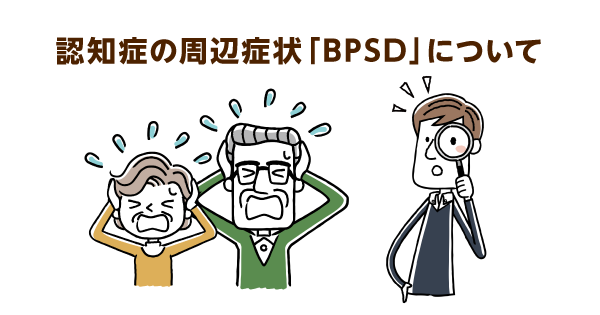こんにちは。株式会社Qship(キューシップ)代表の介護福祉士、梅本聡です。
第138回では、介護への抵抗や暴力の背景にある原因を探り、支援策を練ることが大切だということをお伝えしました。介護への抵抗や暴力に限らず、行動・心理症状(BPSD)と言われる現象に出会ったときには、その背景を考察します。
今回は、「BPSDの背景を考察する際のポイント」をお話しします。
行動や言動に疑問を投げかけると、BPSDの背景が見えてきます
BPSDの方の背景を考察するには、今自分(支援者)の目の前で起きている現象に「何で?」という疑問を投げかけることを癖として身につけておく必要があります。
「何で、ほかの入居者や職員に手がでるんだろう?」「何で、食べた直後に食べていないと言い張ったり、何度も食事を要求するんだろう?」「何で、何度もトイレに行きたがるんだろう?」「何で、何度も外出しようとするんだろう?」
このように「何で?」と疑問を投げかけると答えが見つけたくなります。そして、答えを見つけたいからこそ、背景を考察してみることにつながるわけです。
ちなみに、「何で?」という疑問の投げかけと背景の考察を行わなければ、「歩き続けている」状態は「徘徊している」で、結論づけてしまうかもしれません。つまり、「徘徊=問題ある症状」という扱いになりかねないということです。

内的要因と外的要因からBPSDの背景を考察する
以前、認知症の状態にあるご本人の方々の言葉が綴られたポスターを見たことがあります。その言葉の中の1つに、「徘徊ではない。目的があって歩いている」とありました。
だからこそ、僕たち介護支援の専門職は、「徘徊している=目的もなく歩き回っている」と結論づけ、考察を加えないのではなく、歩き続けている理由を考察していきます。
背景を考察する際には、主に以下の「本人の内にある要因(内的要因、1~5)」と、「本人の外にある要因(外的要因6・7)」の両面から、原因や問題を突き詰めます。
1:健康状態
- 病気・疾患
- 痛み・便秘・不眠・空腹・脱水などの変調や不調
- 薬の副作用
2:認知症の状態
- 中核症状による日常生活を送るうえでの阻害要因
3:身体機能の状態
- 身体機能による日常生活を送るうえでの阻害要因
4:感情・欲望・意欲などの心理面
- 不安・不快・おぼつかなさ・イラつき・怒り・意欲など
5:個性
- 年齢・性別・性格・習慣・生活観・価値観・ライフスタイル・興味関心・趣味・嗜好
6:物的環境
- 建物の造り・器具・物品などにより生じる苦痛や不快感、居心地の悪さ
- 音・光・におい・寒暖など感覚的な苦痛や不快感、居心地の悪さ
7:職員・家族・友人・ほかの入居者などの人的環境
- 本人を取り囲む人々の雰囲気・かかわり方・態度
考えられるBPSDの要因に対し、何が必要で何ができるかといった支援策を熟考して解決策を見出し、実行していきます。
ただ、身体的・精神的負担を抱えながら在宅介護をされている方が、介護支援の専門職と同じようにBPSDに対して疑問の投げかけをして、背景を考察し支援策を考え実行していくことには無理があります。
そのような場合、支援・介護の専門知識・技術を有し、多くの事例を持っている介護支援の専門職を頼ってください。そして、「うちの父が外に出ていこうとして大変なんです」と胸の内を打ち明けるほかに、「何で、うちの父は外に出たがるんでしょうか」と訊ねてみてください。介護支援の専門職は、「何でかな」と外に出たがる背景をとことん探り、解決策をアドバイスしてくれるはずです。

最善を尽くしても解決できない場合は、医師の診断に頼る
しかし、どんなに背景を考察してもなかなか原因がわからなかった方もいました。その方は、自宅での1人暮らしが難しくなり、私がホーム長を務めるグループホームに入居されました。Aさんとお呼びします。
Aさんが入居したグループホームでの食事の準備や洗濯、掃除などは、入居者と職員が相談・協力しながら行っていました。
長年、調理の仕事に就いていたAさんは、そんな環境にあるグループホームにおいて、食材の買い出しや調理の中心的存在でした。ただ、みんなで買物や調理をしていると、些細なことやときにはまったくきっかけがわからないことで怒りだすことが多く、一度怒りだしたらなかなか落ち着きませんでした。ほかの入居者や職員に手を上げることもありました。
私と職員は、「なぜ、すぐ怒るのか?」「なぜ、ほかの入居者や職員に手が出るのか?」何度も背景を考察し、あの手この手で支援策を講じましたが改善せず、怒る頻度も月日が経つにつれ増していきました。
Aさんが入居されて1年。いまだに現象の背景も有効打となる支援策も見出せぬまま、彼女が所属するユニットは何をするにも「とにかくAさんを怒らせないようにする」ことに神経を使うようになりました。いつしか、そのことを中心にユニット全体が立ち回ることになってしまいました。
私たちは、この状態を打破するために、認知症に知見が深い医師の診断を頼ることにしました。そして、MRIや脳の血流を測定する脳SPECT検査、神経心理学検査、問診を終えて医師から伝えられたのは、「認知症は脳を解剖してはじめて診断できるものなので、現時点では予測になりますが、Aさんはアルツハイマー型認知症のほかに脳のこの部分に強い萎縮がみられるので、混合型の認知症でしょう。易怒性がとても強い原因は、そのことが影響していると思います」とのことでした。
また、「薬の内容や量をこまめに調整して『怒り』以外の感情は抑制せずに、Aさんが穏やかにグループホームで暮らしていけるようにしていきませんか」と、薬物療法(体調や状態に適した薬による療法)を勧められました。結果、診断に同席した家族とも相談して薬物療法を選択しましたが、Aさんの易怒性は半年ほどかけて改善し、その後10年以上グループホームでの生活を送りました。
支援専門職員の多くが、現象の背景を考察したうえで環境を整えたり、自分たちのかかわり方を模索します。それは私も同じですが、Aさんの易怒性の背景は病変によるもので、環境整備やかかわり方を変えるだけではどうにもならないものでした。

介護者に原因があるとは限らない
私はこの経験を通じて、ほかに手立てがないと言い切れるまで解決策を追求したのにもかかわらず結果が得られない場合は、「自分のかかわり方が悪いからとは考えてはいけない」と職員に伝えるようになりました。さらに、「考えられるだけの支援策を実践してもどうにもならないときは、信頼できる医師に相談し、薬を服用してもらっても良い」とも伝えていました。
私と仕事をともにしてくれた職員たちは、認知症の状態にある人が、怒る・手が出る・騒ぐ・動き回る・眠らないなどの症状を発症すると「すぐにお手上げ」とし、病院を受診し、薬で押さえつけるようなことはしませんでした。だからこそ、なんでもかんでも支援者に原因があると考えてしまうと消耗しきってしまい、結果的に退職の道を選んでしまうかもしれません。
一生懸命向き合う職員だからこそ、「すべての原因を自分のかかわり方や環境整備にある」と考えるのではなく、医師への相談と薬を服用してもらうという選択肢があることを伝えたかったのです。