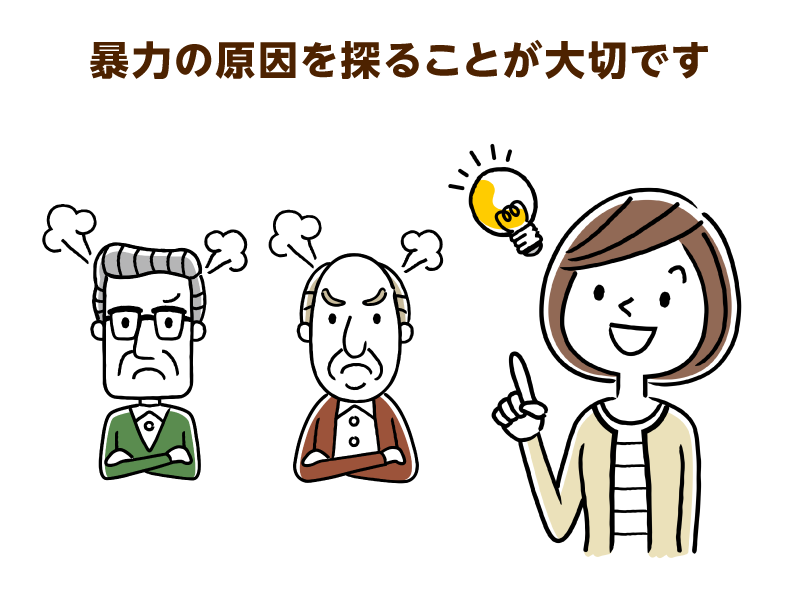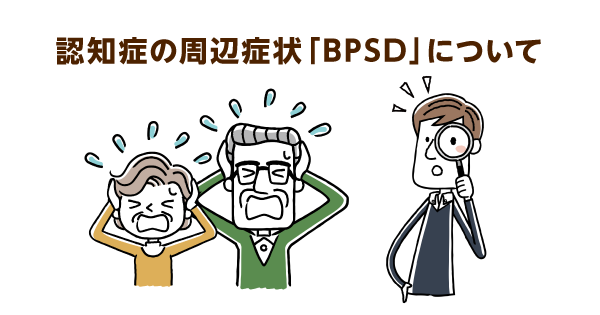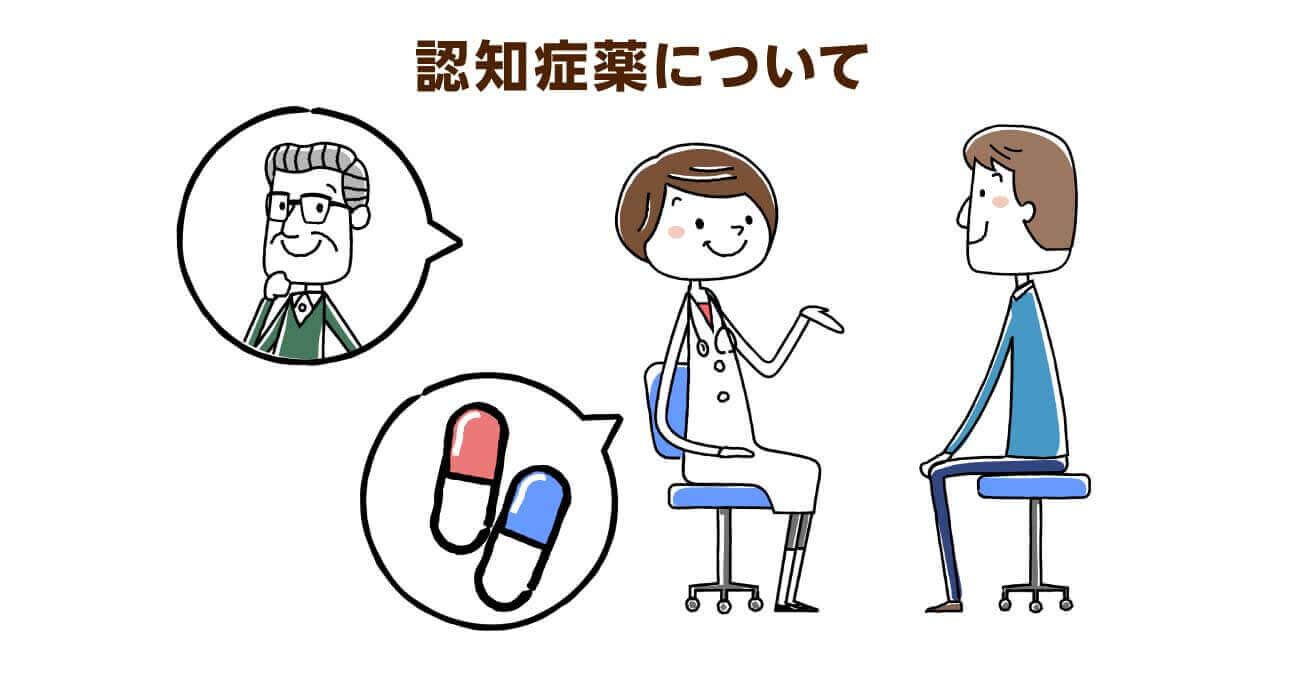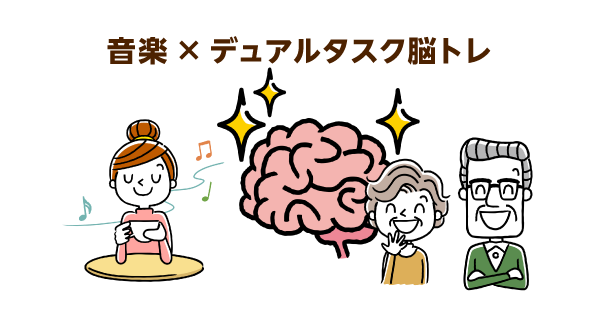こんにちは。株式会社Qship(キューシップ)代表の介護福祉士、梅本聡です。
今回は、「介護者への暴力と介護への抵抗」についてお話したいと思います。
介護への抵抗は「暴力」と呼べるのか
皆さんに質問です。
「あなたがもし、その行為の意味を理解できていなかったり、納得できていない状態で、誰かに服を脱がされる」となったら、どうしますか。
おそらく、ほとんどの方が拒むでしょう。
そして、拒むために「抵抗」し、抵抗するために以下のような行動を取ると思います。
【抵抗するための行動】
- 大声を出す
- 噛みつく
- 殴る
- つねる
- 引っ掻く
- 蹴る
- 頭突きする
では、この状況で取った行動は、「暴力」となるでしょうか。
辞書で「暴力」を調べると、「乱暴な力・行為。不当に使う腕力」「合法性や正当性を欠いた物理的な強制力」とあります。
「不当」は、「正当・適当でないこと。道理に合わないこと。また、そのさま」とありました。
となれば、この状況では「不当に腕力を使う=暴力」とはならず、「抵抗手段として正当な腕力を使った」ということになるのではないでしょうか。
ちなみに「抵抗」は、「外部から加わる力に対して、はむかうこと。さからうこと」と辞書に記載があります。
つまり、皆さんが「自分の理解や納得がないまま、他人に服を脱がされそうになったどうするか」という問いに対して「拒む」と答え「抵抗」するのは、あたり前ということになります。

脱衣所で認識のズレが生じるシーンが多い
私が27年間介護の仕事をしてきて、「嫌ぁぁ!!何するのやめてぇぇ!!」という入居者の絶叫や、人を叩く音、そして介護職員の「痛い!!」という声が最もよく聞こえてきたのは脱衣室です。
そして、「何事だ?」と扉を開けると、大抵そこには、ズボンとパンツを下ろそうとする介護職員と、脱がされまいとする入居者の姿がありました。
介護職員にとっては、入浴することの同意を入居者から得ているので、脱衣を手伝ったことに抵抗され、叩かれるのは不本意なことです。
しかし、入居者は認知症の状態です。
記憶障がいがあるため、入浴することへの「同意=理解」を継続することが難しく、何をするのか、何をされているのかがわからない状況になっているのです。
なので、この場面であれば、入居者にとっては自分が理解や納得をしていないのにズボンとパンツを下ろされそうになっているということになり、抵抗することは正当な行為ということになります。そして、自分が理解や納得をしていないのに、服を脱がされそうになっているということが「本人にとっての事実」なのです。
対して、介護職員にとっては、本人から入浴することの同意を得ているため、服を脱ぐことを手伝うことは正当な行為です。
ですが、同意を得ていることは「支援側が知る現実」で、「本人にとっての事実」と「支援側が知る現実」との間にズレが生じてしまっています。
では、ズレを埋めるためには、支援側が「本人にとっての事実」を否定し、「支援側が知る現実」を突きつけることが最善の策なのでしょうか。
認知症の状態にある方からすれば、「支援側が知る現実=あなた(支援側)の理屈」であるため、納得できない場合が多いのです。
そもそも、支援策を講じるうえで大切なことは、支援側の目に見える事象を対処法で解決しようとするのではなく、事象が生じている原因に対して、アプローチすることです。
ちなみにこの場合では、本人は入浴することに同意したものの、脱衣室に来たときにはそのことを覚えていません。一方、介護職員は同意を得たという認識でいるため、両者間で「入浴の合意」が成立しなくなります。
この状況が発生する主な原因は「記憶障がい」であるため、入浴に同意した記憶が保持されているうちに入浴してもらう必要があります。
【入浴前における「記憶障がい」へのアプローチの例】
入浴することに同意を得てから入浴につながること以外の行為を行うと、記憶が抜け落ちる場合があるため…
- トイレを済ませてから、「お風呂に入りませんか?」と入浴を促す声がけを行う
- 入浴を促す声がけ→同意→脱衣室へお連れする
脱衣室への移動中に入浴への理解が記録から抜け落ちる場合があるため…
- 脱衣室までの移動時間を短くする
- 移動中は「入浴」につながる会話をする

「思い通りならないことはあたり前」支援側に必要な視点
自分の意思に反して他人に服を脱がされそうになっていることに抵抗することは、「介護への抵抗」なのでしょうか。
抵抗する手段として叩いたりすることは、「暴力」という問題行動なのでしょうか。
脱衣室での入居者の行動は、冒頭の質問に対する皆さんの答えである「拒むために抵抗すること」と同じように、自分に迫る危険から身を守ろうとして行った行動です。
だからこそ、「認知症だから介護への抵抗や暴力という症状が出ているBPSDだ」と問題症状扱いをする前に、支援側はまず、以下のような視点を持つことが必要です。
【支援側が持っておきたい視点】
- 原因疾患による脳の器質的変化によって知的能力が衰退しているため、今自分が何をするのか、何をされているのか、ここがどこなのかなどがわからない状況になるのはあたり前
- 「支援側が知る現実に即した行動」=「支援側の思う通りならない」のはあたり前
- 認知症の状態などによって、介護者が知る現実の認識と「本人にとっての事実」にズレが生じる
- 「本人にとっての事実」に即した行動のほとんどが「人としてあたり前の言動」
- 「誰でもいやなことをされたら怒るのはあたり前」
また、行動には必ず原因があります。
故に、支援策を練り上げるには、介護への抵抗や暴力の背景にある原因は何なのかを探ったり、考えることが大切です。
その際、本人を取り巻く環境や支援側のかかわり方が悪くて粗暴な言動が出てしまっていることもあるので、支援側のかかわり方に原因はないか、振り返ってみることを忘れていけません。
ただし、粗暴の原因のすべてが、支援側のかかわり方にあるとは限りません。
私は、行動の原因を突き詰めていく実践を続けてきましたが、どんなに行動の背景にある原因を探ったり、考えたりしても「なぜ、すぐ怒るのか?」「なぜ、ほかの入居者や職員に手が出るのか?」がわからない方もいたからです。
この続きは、次回お話します。