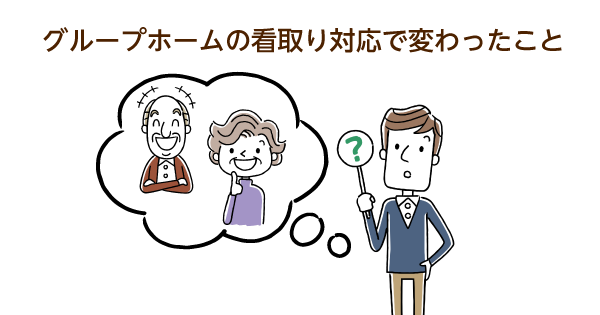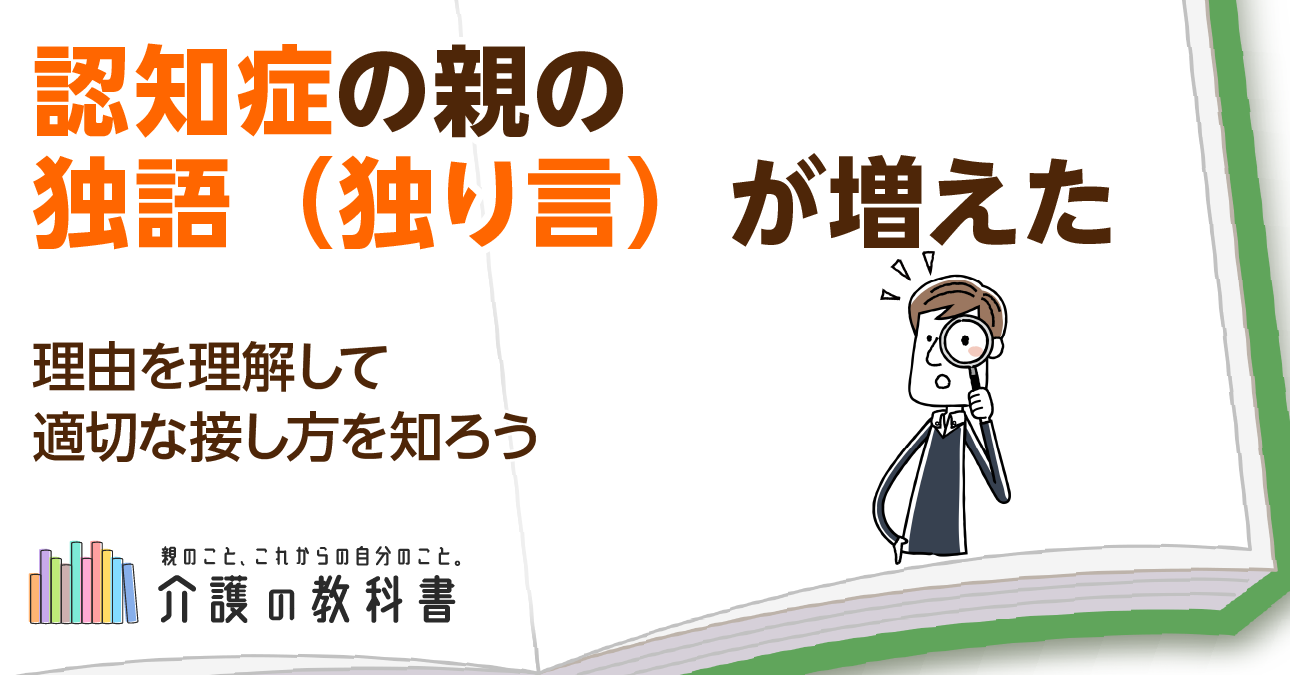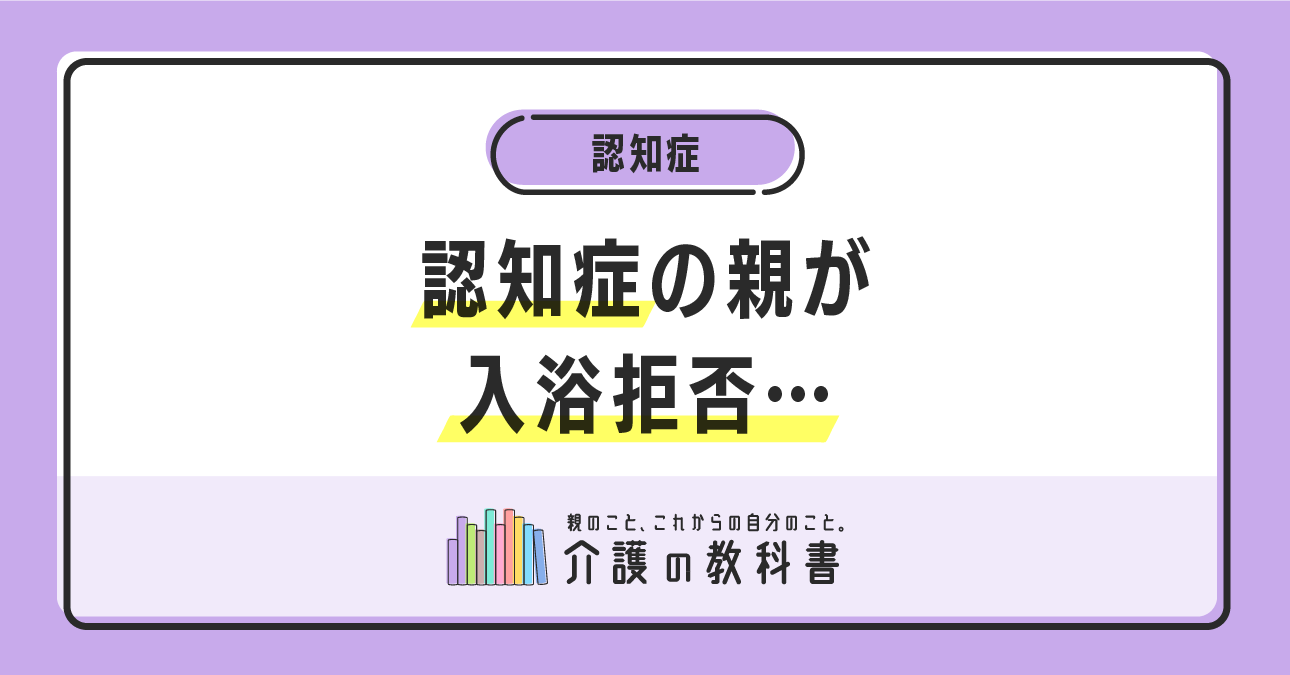みなさん、こんにちは。株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。
今回は、第106回に引き続き、「支援者がなんでもしてあげる介護」ではなく、「能力に応じて、入居者さんが生活行為を自分でできるようにする支援」についてお話します。
特に今回は、認知症の状態にある方の意思や感情、意欲(その気)を「引き出す」ためのアプローチを詳しくお伝えしていきます。
入居者さんに生活行為を「強制」するべきではない
以前、支援専門職の方々の研修で、参加者から「入居者さんに掃除をやらせようとするのですが、やってくれません。どうすればいいですか?」という質問を受けました。
これによく似たものが「食事づくりをやってくれない。どうすればいいか?」で、こういった質問に共通しているのは、支援者側は"やらせる"ことが目的になっているということです。
そのような支援者は、本人の有する能力、意思や感情、意欲(その気)などは関係なく、とにかく入居者さんが「やってさえいれば良い」と考えてしまっている可能性があります。
それは、入居者さんは支援者にやらされているだけ、言いなりになっているだけです。
しかし、本来、成人は日々繰り返す掃除や食事づくりなどの生活行為を、他人から言われてやらされるものではないはずです。

ご飯づくりを断るAさんの事例
僕がホーム長を務めていた認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)でのことです。
ある日、職員が入居者さんに昼食の食事づくりを促す声がけをしました。
職員:「そろそろお昼になるので、みなさんでご飯をつくりましょう」
入居者さん一同:「…」
(聞こえているのに無視をしているのかもしれませんが、どの入居者さんも共同生活室のテレビを観ていて返事すらしてくれません)。そこで職員は個人指名で声がけをします。
職員:「Aさ~ん、一緒にご飯をつくりましょう」
Aさん:「えっ?何ですか」(反応はしてくれましたが、怪訝そうな表情です)
職員:「お昼ご飯をつくるんで、一緒にやってほしいんですが…」
Aさん:「…嫌ですよ。なんでこんな年寄りにやらせるんですか。ほかにも若い人(他の職員のこと)がいるんだから、あなたたち若い人がやればいいじゃないですか」
Aさんの「なぜ私がやらなきゃいけないんだ」「なぜあなたたち(職員)は何もしないんだ」はごもっともなことで、返す言葉もありません。
というのも、Aさんにしてみたら自分がお昼ご飯をつくる必然性(=理由や目的)がないからです。
人は、そのときどきのさまざまな理由から、食事に関する行動に移ります。
例えば、「空腹である・時間をみた・この後の予定を踏まえて・周りの人の食事のタイミングに合わせる」といった状況をきっかけに、「食べるものを考えて決める・食材を手に入れる・食材を調理する、あるいは他人に調理してもらう、食べる、片付ける」といったプロセスを経ていきます。
しかし、この職員は食事づくりを促す声がけを突然しました。
入居者さんにとっては、調理をするという行動に必然性がないのです。
また、「あなたが言うなら手伝おうかな」「大変そうだから手伝うよ」といった心情(人が行動する必然性が発生するような心情)が沸くようなアプローチもしていません。
自分で自分に必要な生活行為が“できるようにする支援”では、まず必然性をつくること、簡単に言うと、その人がその気になるようなアプローチや仕掛けをすることが必要です。
このときの職員は、その点が抜け落ちていたのです。

人が行動する必然性はさまざま
食事以外でも、人が行動に移る必然性は、さまざまなシチュエーションに存在しています。
以下に例を挙げましょう。
- 空腹を感じたり、時計の針で「そろそろ」を確認したりして始まる、食事にまつわるあれこれ。
- キッチンのシンクに山積みになった使用済の食器。誰かが洗い、片づけなきゃいけない。
- 目で見てわかる床の汚れ。汚したのは自分(たち)。汚いから掃除をする。
- これから干すことが一目瞭然の洗濯物や、取り込むこと・畳むこと・仕舞うことがわかる乾いた洗濯物。
- ○○が必要だから買物に行かなきゃ、コーヒーが飲みたいから喫茶店に行こう、天気が良いから外に出かけよう。
上の例のいずれの場合にも、行動に移す必然性があります。
グループホームでは他者とのかかわりから行動の必然性をつくれる
また、グループホームは、介護保険法では認知症対応型共同生活介護といい、その名称のとおり、認知症の状態にある方々が5人から9人で共同生活を営むことを支援する仕組みです。
そのため、「ほかの人が掃除をしているのに私だけやらないのは悪いなぁ」「あなた大変そうだから、私が手伝いましょうか」といった共同生活者(入居者さん)同士が人と人との関係性を感じたり、互いに助け合うといった「他者とのかかわりからの必然性」づくりも可能なのです。
食器拭きを断ったBさんの事例
グループホームでのいつもの風景。
食事が終わり、「それじゃあ、洗い物でもはじめますか」と職員が言うと、Bさんはいつも「はいはい。じゃあ私は拭きあげ(食器拭き)しますね」と言ってくれます。
そんなある日のこと。
昼食が終わり、食器洗いをすることになったものの、Bさんは険しい表情で席から立ち上がろうとしません。
いつもは自分から食器拭きを頑張ってくれるBさんとは、明らかに様子が違います。
実はこの日のBさん、普段寝るときに敷布団の下に置いて一緒に床につく、本人いわく命の次に大切なものである預金通帳(記帳がビッシリの状態で、実際には使うことができない)が朝起きたときに見当たらず、職員と一緒に大捜索をしたのです(預金通帳は、洋服に包んでタンスの引き出しの一番下にしまってあるのを発見)。
いつもは笑顔が多く、ほかの入居者さんや職員とよくおしゃべりをするBさんですが、普段とは違う朝の時間を過ごした彼女は、その後も笑顔を見せず、誰とも話をしようとしていませんでした。
朝のことを把握し、いつもとは違うBさんの様子を承知していた職員でしたが、一度だけ「Bさん、これから洗い物をするので拭きあげをお願いしたいんですが…」と声をかけました。
しかし、「今日はお休みさせてください」と言い残してBさんは自室に向かってしまいました(ちなみに、その後職員のかかわりによって、その日の夜にはいつものBさんに戻りました)。
Bさんが普段、食器を拭いてくれるのはなぜなのでしょうか。
彼女の言動から推し量ってみたところ、彼女が自らすすんで食器拭きをする必然性は、「みなさん大変ですから手伝いますね」という気持ちと、「自分たちが使ったものは自分たちで片づけないと」という考えがあるからのようです。
しかし、預金通帳を探した日は、食器を拭いてくれませんでした。
これは、見つかったとはいえ、命の次に大切な預金通帳がいつもある場所になかったことに、何らかの心理的影響を受けたのだと思います。

人はいつも同じことをきっかけに行動するとは限らない
Bさんに限らず、人にはその日、そのときの感情や体調があります。
「同じ人でも、いつもと同じとは限らない」ということです。
それだけに、自然と繰り返される生活行為が自分で“できるようにする支援”を行うために、必要な必然性ですが、明日もその人にとっての必然性になるとは限りません。
だからこそ、そのときのその人にとっての必然性は、最低でもここ数日から前の晩、そして朝起きてからそのときまでのその人を知り、体調や、今はこんな感情や気持ちを持っているだろうなといったことを踏まえて、つくり出していく必要があります。