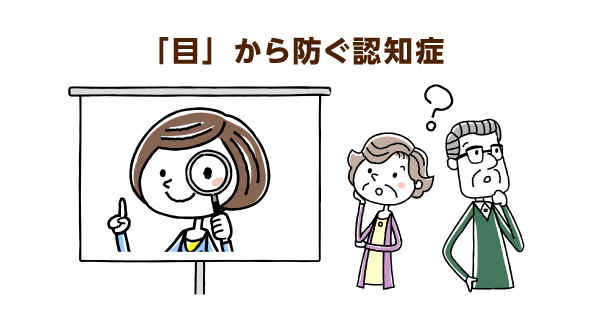こんにちは。一般社団法人元気人の向川 誉です。当法人では、認知症ゼロ社会の実現を目指して、地域の認知症予防活動をサポートする「認知症予防活動支援士」の育成と支援に力を入れております。
2018年7月、「カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法」(通称・カジノ法)が成立しました。この法案成立を受けて、全国3ヵ所を上限として日本初のカジノが開業することになります。
日本の刑法では原則として賭博を禁じていますが、競馬や競輪などの公益を目的とした公営ギャンブルはすでに特例的に認められています。また、民間のパチンコやスロットは遊技扱いですが、店外換金の実態があり、実質的にはギャンブルといえましょう。
ギャンブルには”知的なゲーム”という側面があり、脳を活性化されるので、認知症予防につながるとする主張もあります。今回は、ギャンブルと認知症予防の関係をみていきたいと思います。
ギャンブルは認知症予防になるの?
はじめに、ギャンブルは人によって捉え方が異なると思いますが、今記事の中ではギャンブルの定義を「価値あるもの(お金や時間)を賭けて、より多くのお金や価値あるものを手に入れる行為」とします。
つまり、今回法的に認められたカジノ、競馬や競輪といった「公営競技」だけでなく、パチンコやスロット、株式取引や、FX、オンラインゲームについても「ギャンブル」に類するものとして考えるということです。
ギャンブルと認知症予防の関係を扱った研究はあまり多くないのですが、諏訪東京理科大学の研究によると、パチスロトレーニング(目押しの練習やスロットの遊戯)を実施した中高年の実験参加者では、前頭葉と頭頂葉の働きが活性化し、認知機能に改善がみられることがわかりました。

また、ほとんどのギャンブルには、「あの場面ではこうすればよかった」と過去を振り返ったり、「次はこうしよう」と対策を考えたりする時間があり、頭を使った知的活動をしている面があります。
さらに、ギャンブルで勝ったときや振り返りをしているときの脳内には、ドーパミンという神経伝達物質が分泌されます。脳内にドーパミンが分泌されると、快感やモチベーションが上がるのに加え、学習能力や記憶力といった部分にも影響を与えるのです。
ということは、「ギャンブルは脳を活性化し、認知症予防につながるのではないか」と思いますよね。実際のところはどうなのでしょうか?
認知症予防のポイントは長く続けること!
まず、認知症予防のポイントは「長続き」することです。いくら予防効果が高い方法があったとしても、本人が途中で止めてしまっては意味がありません。
そういった意味では、ゲームごとに内容が変化していくギャンブルはなかなか飽きがきませんので、適度に楽しめる人であれば、娯楽のひとつとして長く続けられそうです。
また、人を引きつける魅力があるギャンブルを動機付けの手段としてうまく活用している事例もあります。
例えば、デイサービスでは「心身機能の維持向上」「介護負担の軽減」などを目的に、さまざまな介護や支援を提供しています。しかし、その目的を達成するには支援を必要とする人に施設を利用してもらう必要があります。
一方で、実際にカジノのレクリエーションを取り入れた施設では、ひきこもっていた男性高齢者の施設利用につながったケースがあります(もちろん、実際に金銭のやり取りはなく、疑似通貨が使われています)。
ギャンプル依存症の中には、認知症やその予備群の人も
これまで施設を利用したがらなかった人が施設に通う最初のきっかけが「カジノ」だったというのはありだと思います。しかし、ギャンブルで認知症予防を考えるうえでのデメリットは、最初は認知症予防を目的にギャンブルを楽しんでいても、それでは満足できず、最終的にギャンブル依存症に陥る人が一定数出てくることです。
先述したドーパミンは、適度な分泌であれば認知症予防に対して良い効果を生みます。しかし、ギャンブルを繰り返して、ドーパミンが過剰に分泌される状態が続くようになると、脳の反応は徐々に変化していきます。ギャンブルに熱中している人の脳では、ギャンブルへの欲求が強くなる一方で、勝ったときに得られる快感は薄まるため、さらにギャンブルを求めるようになるのです。

コントロールできている人はギャンブルを適度に楽しむことができますが、脳の働きが異常になると、中には本人の意思や努力ではコントロールできなくなってしまう人も出てくるのです。
2014年に厚生労働省が発表した統計では、全国に536万人のギャンブル依存症がいると推計されており、そのうちの4割が50代以上といわれています。
肝心なのは、この中には認知症の初期段階やその予備軍の人も含まれていると考えられていることです。認知症の方は「自分にとって不利なことは認めない」「強いこだわりを持つようになる」という傾向があります。
認知症の方の全員にそうした症状があるわけではないですが、この症状が悪い方向に働くと、ギャンブル依存症を深刻化させることになるのです。
自分の好きなことで認知症予防をしよう!
先述した通り、日本には536万人のギャンブル依存症の方がいます。この数字は日本国民の約20人に1人の割合にあたり、諸外国と比べても異常な数字となっています。
この数字を見るかぎりでは、日本全体としてギャンブルをコントロールできているとは言い難く、依存症になった後の対策も世界からは遅れているという指摘もあります。
認知症予防は、結局のところ「暮らしの障害」を回避することが本来の目的です。
もし、ギャンブルで脳を鍛えたつもりでも、ギャンブル依存症に陥って生活がおかしくなる人が増えてしまっては、認知症予防の本来の目的からズレてしまいます。
個人的な見解になりますが、ギャンブルによる認知症予防を考える場合、得られるリターンに対して、取るべきリスクが大きいと考えています。
また、認知症予防は40〜50代から対策を始めるのが効果的なのですが、この年代は仕事や家庭などのことで忙しく、取り組みがついつい後回しになりがちです。
こうした現実を踏まえると、ギャンブルを娯楽のひとつとして楽しんでいる人であれば、認知症予防に取り組むときの動機付けとしてギャンブルを使うのは、ひとつの手段でしょう。
例えば、ギャンブルで認知症予防をするのではなく、例えば、1週間運動を続けたご褒美として、週末にギャンブルを楽しむようにするのです。
運動に取り組む動機付けになるほかに、ギャンブル自体には自ずと制限がかかるようになります。
もちろん、ギャンブルに興味がない人はこの必要すらなく、脳を鍛えられるからといって、必ずしもギャンブルをしなければいけない理由はありません。
認知症予防で大切な「長期継続」を実現するには?
今回はギャンブルを取り上げましたが、認知症予防の方法はギャンブル以外にもたくさんあります。
例えば、楽器演奏や料理、ランニングも楽しみながら脳を活性化させることができます。

また、ボランティアや奉仕活動にかかわって、自分の行為によって相手が喜んでいたり、楽しんでいたりしている姿を見るとき、ギャンブルでの報酬を得たときと同じように、脳内にはドーパミンが放出されて、幸せな感情とやる気に満たされます。 (ギャンブルでなくても、ドーパミンは出るのです)
認知症予防は生活に取り入れて、長く続いてこそ、その効果が期待できます。
ギャンブルに限らずですが、○○が認知症予防にいいからといって、すぐに飛びつくのではなく、自分の好みや生活状況に合ったものかどうかを考えて、選ぶことが認知症予防としては大切 になります。
「そもそも何のために○○をしようとしているのか?」と自分に問いかけることは、頭を使う良いトレーニングにもなります。