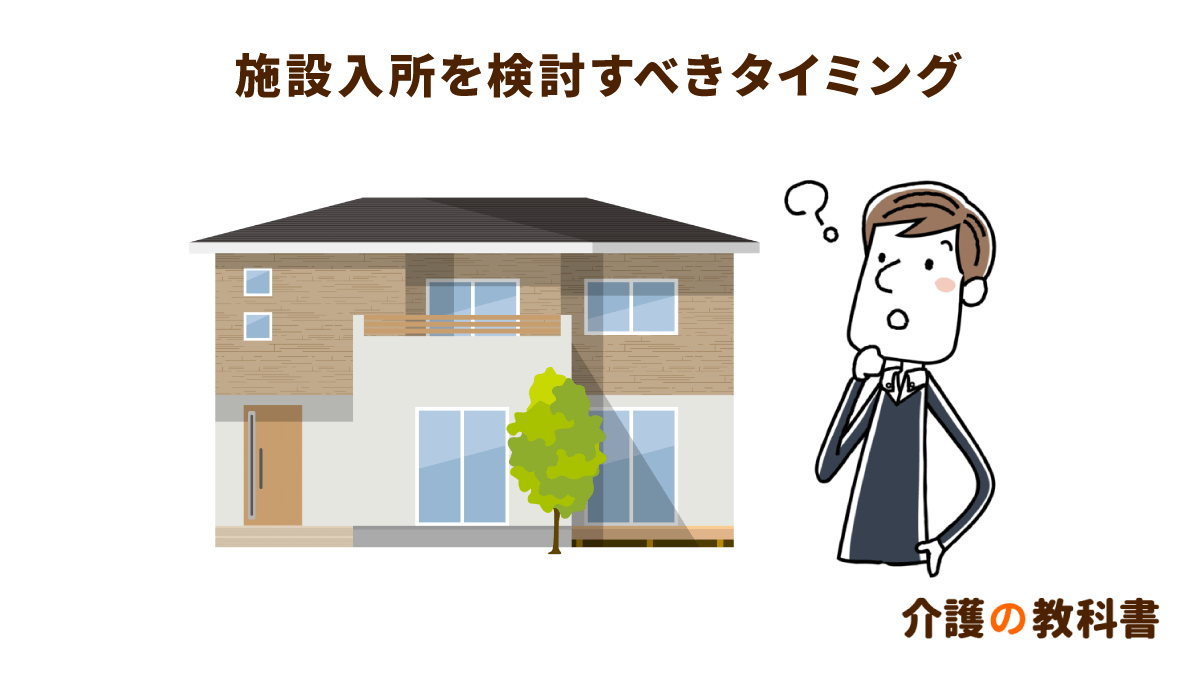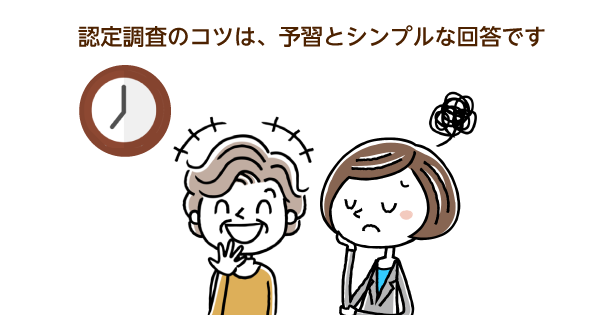ケアプランセンターはぴるす代表の大内田省治です。
今回は要介護者が施設に入所する適切なタイミングを考えます。
60歳以上からでも利用できる入所施設
在宅介護をしている人の中には、施設入所に切り替えるタイミングについて悩んでいる方も多いのではないでしょうか。なぜなら、要介護者の多くは在宅での介護を望んでいるからです。
原則として65歳以上になれば、介護保険のサービスが利用できるようになり、介護施設への入所が可能となります。ただし、次のような施設には60歳から入所できます。
1.軽費老人ホーム
ご家族による援助を受けられない環境下において、自炊することが難しい方や、独立して生活することに不安を覚えている方を対象としています。入所料金は所得に応じて変わり、主に要支援の高齢者を受け入れています。A型・B型・C型(ケアハウス)の3種類があります。
- A型:食事サービスや日常生活に必要な介護サービスを受けることができます
- B型:A型のように食事サービスがない分、料金は安くなりますが、自炊できることが条件になります
- C型(ケアハウス):全室個室でバリアフリー化されていて、高齢者に負担がかからないような環境になっています
「介護型」と呼ばれるケアハウスもあり、その場合は要介護状態になっても受け入れ可能です。介護型ケアハウスの場合は、ヘルパーさんやデイサービスなどを利用しながら生活します。
2.高齢者優良賃貸住宅(高優賃)
高齢者が安心して住み続けられる住宅のことで、市町村の認定を受けた民間主体の賃貸住宅です。
バリアフリーに配慮された住宅になっていて、緊急通報装置を設置し、もしもの時には警備会社などへの連絡体制が整えられています。
所得に応じて入居者への家賃補助もあります。築年数などに応じて、家賃補助期間が変わってきます。なるべく築年数の浅い住宅に入居すると、家賃補助が長く受けられます。
3.サービス付き高齢者住宅
高齢者向けのマンションで、入居の際には不動産賃貸契約が必要です。併設しているヘルパーステーションやデイサービスなどを利用することで、安心して生活できるようになります。
ただし、施設の中には「要介護認定を受けていること」と明記している場合もあるので、事前に入所条件を確認しておきましょう。
40歳以上で入所できるケースと施設
ほかにも40歳以上になれば入所できる施設もあります。以下の介護保険制度で指定されている16種類の特定疾病に該当する方で、要介護認定を受けている方が対象となります。
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群など)
- 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群など)
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血・脳梗塞など)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎など)
- 両側の変形性膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
もし、上記の疾患に該当しなくても、身体障がい者手帳1級もしくは2級を所持していれば、障がい者施設に申し込むことができます。
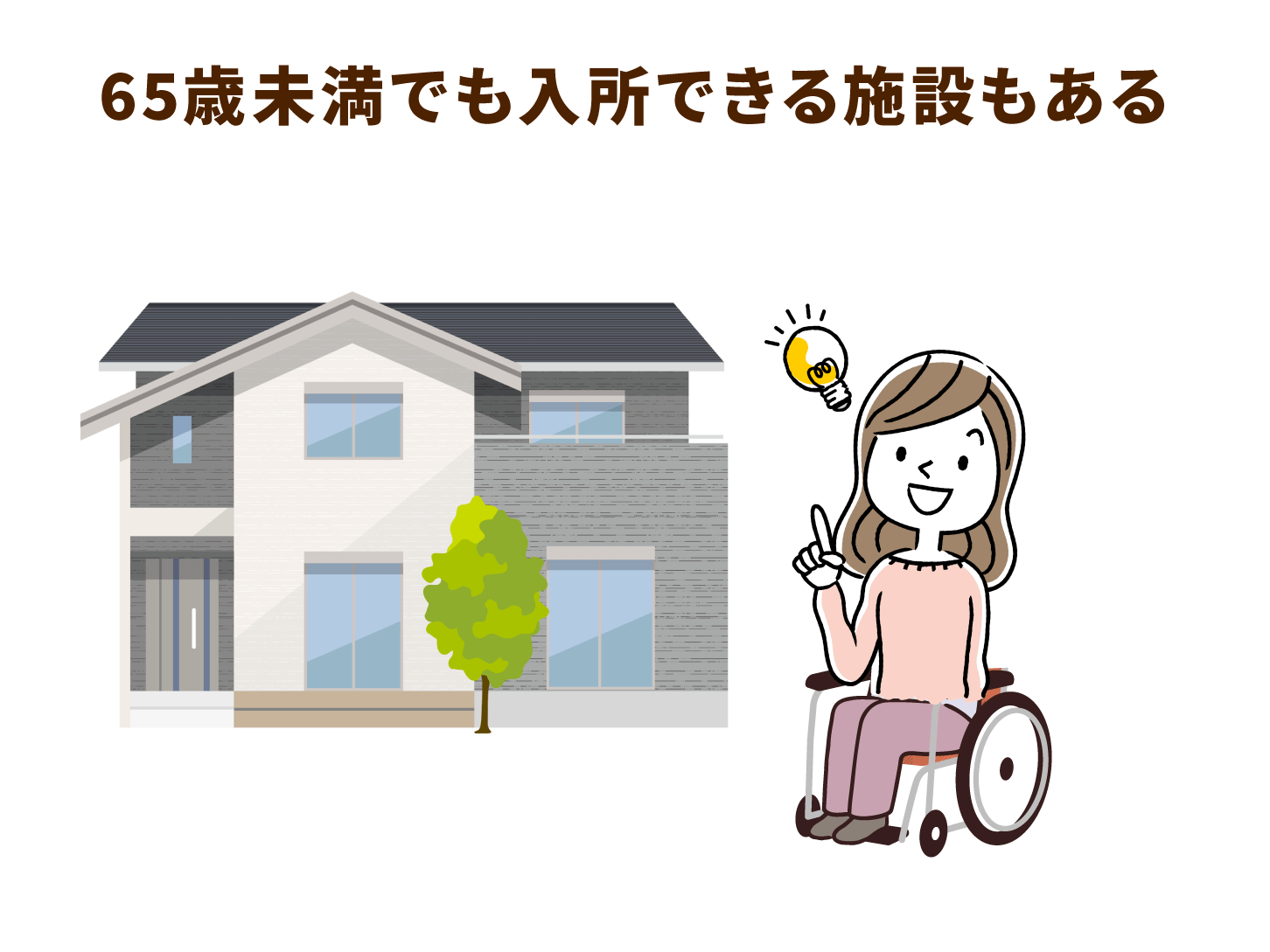
要介護認定が必要なタイミングを考える
まず施設入所のタイミングを考える前に、「要介護認定が必要なタイミング」を考えてみましょう。
もし家族の誰かが、何らかの疾患や病気などによって一人で生活することに不安を感じた場合には、介護サービスの必要性を考えるべきタイミングだといえるでしょう。
例えば、家族が遠方に住んでいて、実家に電話をかけてみた際に「同じ話を何度も繰り返すようになった」「火の不始末が目立つようになった」などの場合や、自宅で転倒を繰り返すようになった場合はいち早く介護サービスの利用を検討すべきです。
ただ、多くの場合は何らかの理由で入院した際に、担当医から「施設入所が必要」と言われてから、要介護認定の申請を行い、入所できる施設を探し始めます。
しかし、個人的にはそれでは遅いと考えます。
例えば、特別養護老人ホーム(特養)の場合、現在は「要介護3」以上の認定を受けていないと原則は入所できません。
また、そのほかの施設についても、入所待ちの施設が多かったりします。
そのため、少しでも在宅生活に不安が出てきたタイミングで、要介護・要支援認定を受け、ケアマネと関わりを持つようにしておくことが大切です。そして、介護サービスを利用しながら、施設に関する情報収集を行っておく必要があります。
施設入所が必要になる前から情報を集める
在宅介護から施設入所へ切り替える際の判断は、素人だけで行うのは困難です。また、医師は介護サービスに関してはそれほど詳しくはありません。
そこで、要介護認定を受けたタイミングから地域のケアマネと関わりを持っておくことで、専門的なアドバイスが受けられます。
ケアマネから受けたアドバイスをもとに、家族で今後のことをしっかり話し合うなどの準備をしておきましょう。
施設の情報収集についてはネットなどでもできますが、最も地域の情報に詳しいのはケアマネです。
ケアマネは普段から施設の空き情報や、どのような特徴があるのかなど、プロの目線で情報収集を行っています。そのため、ネットには書かれていない情報にも精通しているのです。
また、ケアマネは利用者との関わりの中で、身体状況の変化にも敏感に気を配っています。かかりつけ医などと連携して、施設入所のタイミングを図っているのです。
つまり、施設入所のタイミングを図る際には、在宅介護が必要になった時点から考え、ケアマネと協力しながら決断することが大切です。