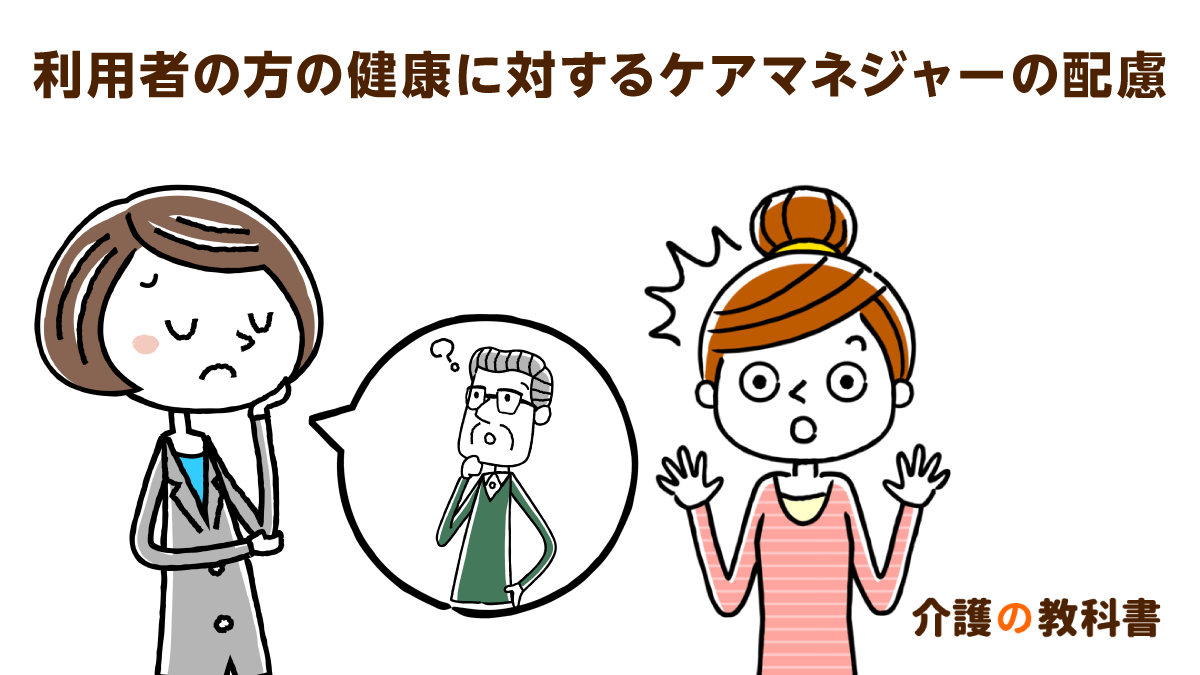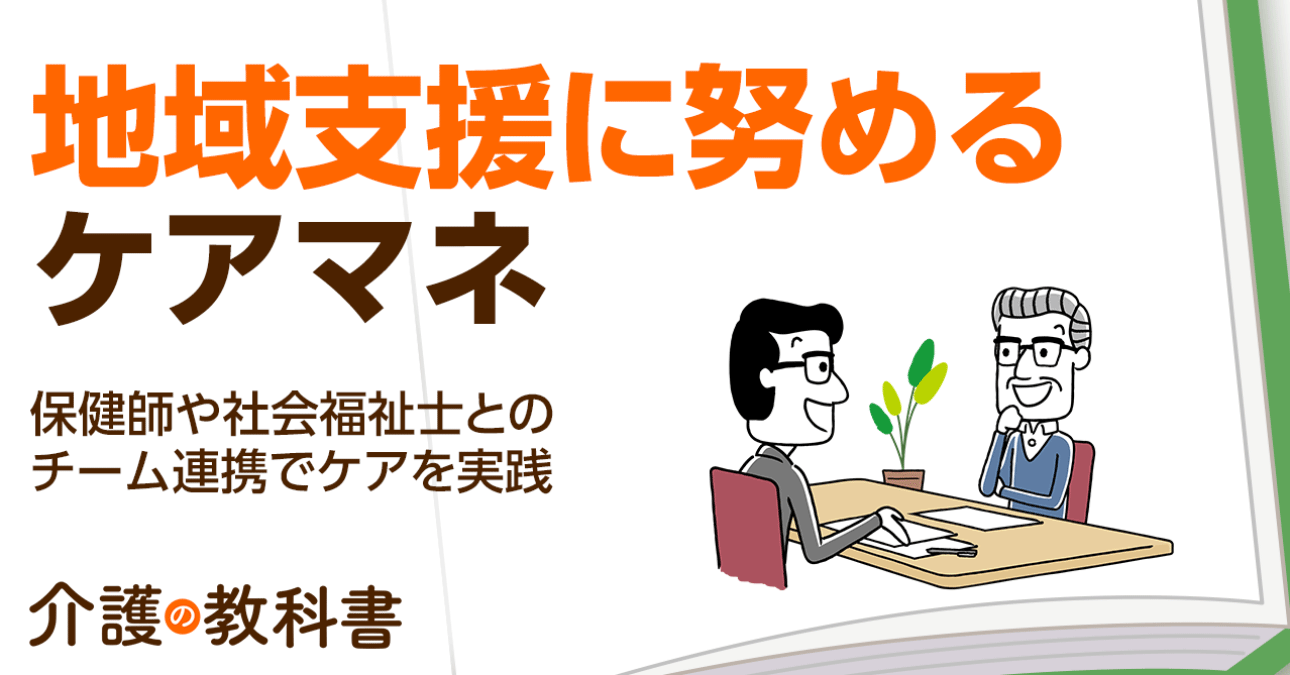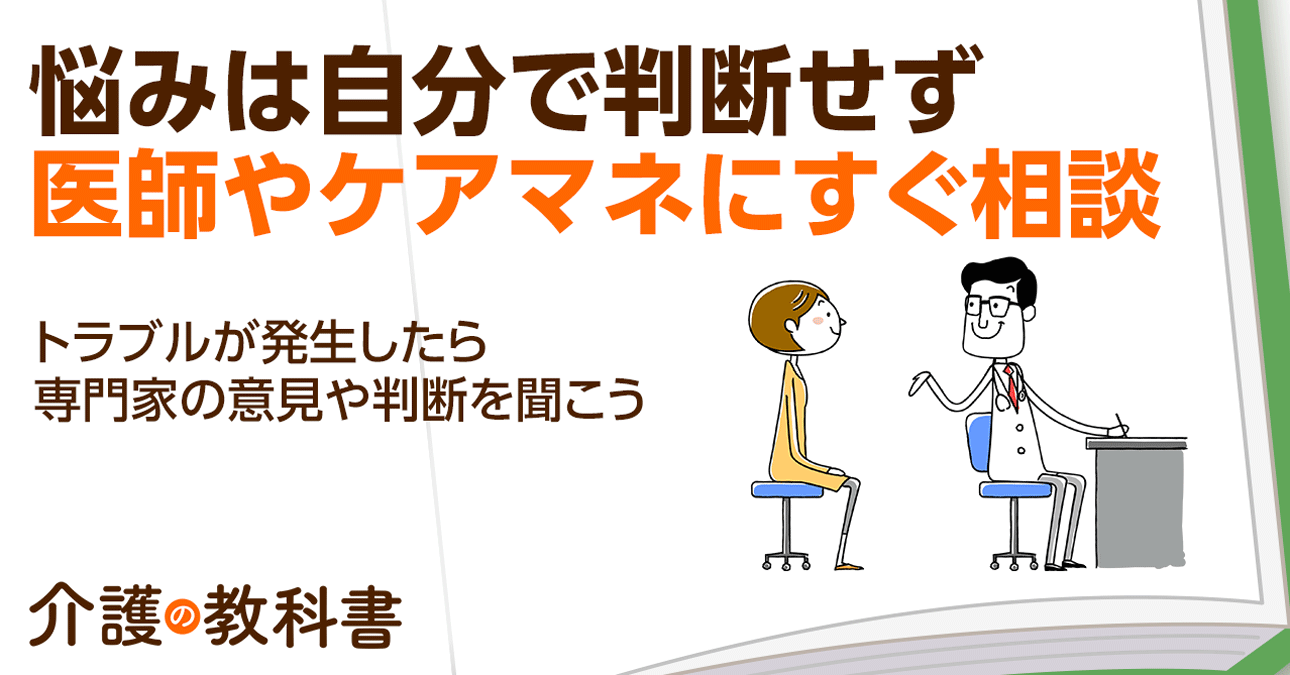こんにちは。ケアマネジャーの小川風子です。
筆者の職業である介護保険のケアマネジャーという仕事は、基本的にはご高齢の利用者の方が相手です。そして、介護保険サービスを利用しながらでないと生活が成り立たない方の支援をする仕事ですので、利用者の方のほとんどはさまざまな理由で障がいや病気を抱えています。
筆者はケアマネのことを、利用者の方が人生の最期をより良く過ごせるために、ケアプランを立てたり生活をフォローをしていく職業だと思っています。実際、利用者の方が健康となりケアマネの支援がいらなくなってお別れするよりも、状態が悪化し入院や入所、ときにはお亡くなりになってお別れすることが多いです。
とはいえ、そのお別れに至るまで何年もかかわっていくことも多いので、利用者の方の状態がはじめてお会いしたときと比べて変わっていくことは少なからずあります。そういった状態の変化に気をつけて、それ以上悪くならないように対応していくのもケアマネの役割です。
今回は、「利用者の方の健康に対するケアマネジャーの配慮」についてお話しします。

介護サービスを調整して利用者の体調を管理
対応と言っても、少なければ1ヵ月に一度しか訪問しない利用者の方の健康状態の把握や変化を、基本的には座ってお話を聞くだけのケアマネが判断できるわけはありません。もちろん家族の方からも話を聞くので、そこで変化に気づくこともあります。しかしそれよりも、本人が利用している事業所やヘルパー、デイサービス、訪問看護やショートステイから「こういった症状が気になります」「最近ご様子がおかしいです」と報告を受けて、気づくことが多いです。
普段の様子を知っている事業所の報告には、まず間違いがないのでとても参考になります。だいたいの事業所は、利用者の方や家族にも状態の変化を報告して受診を勧めますが、すんなりと受診できる方ばかりではありません。
本人や家族の状態に応じてケアマネジャーは以下のことを行います。
- ヘルパーの通院介助を導入する
- 訪問看護に状態を確認してもらい、医師に伝えてもらう
- 居宅療養管理指導で訪問診療をしてもらう など
介護サービスを調整し体調がそれ以上悪くならないよう、必要な医療が受けられるように手配をすることは、ケアマネにしかできない大事な役割です。
病院側と利用者の健康状態についてすり合わせ
本人に受診を勧めて「同伴する家族がいればそれですべて解決」というわけではありません。
高齢世帯の場合、連れて行く家族や本人が医師の話をしっかり聞いて理解することが難しい場合もあります。また理解できたとしても、そこで聞いた話や病状をケアマネや事業所にうまく伝えられないこともあるのです。
「病院に行ったけど、先生が何を言っているのかわからなかった」
「なんでこの薬が出たのかわからない」
そう言って帰ってこられる方は、きっと病院関係者が想像するよりはるかに多いです。患者は医者や医療関係者の前ではしっかりされています。なので、なかなか理解していないことに気づいてもらえないのが現状で、それによって困ることが多々あるのです。
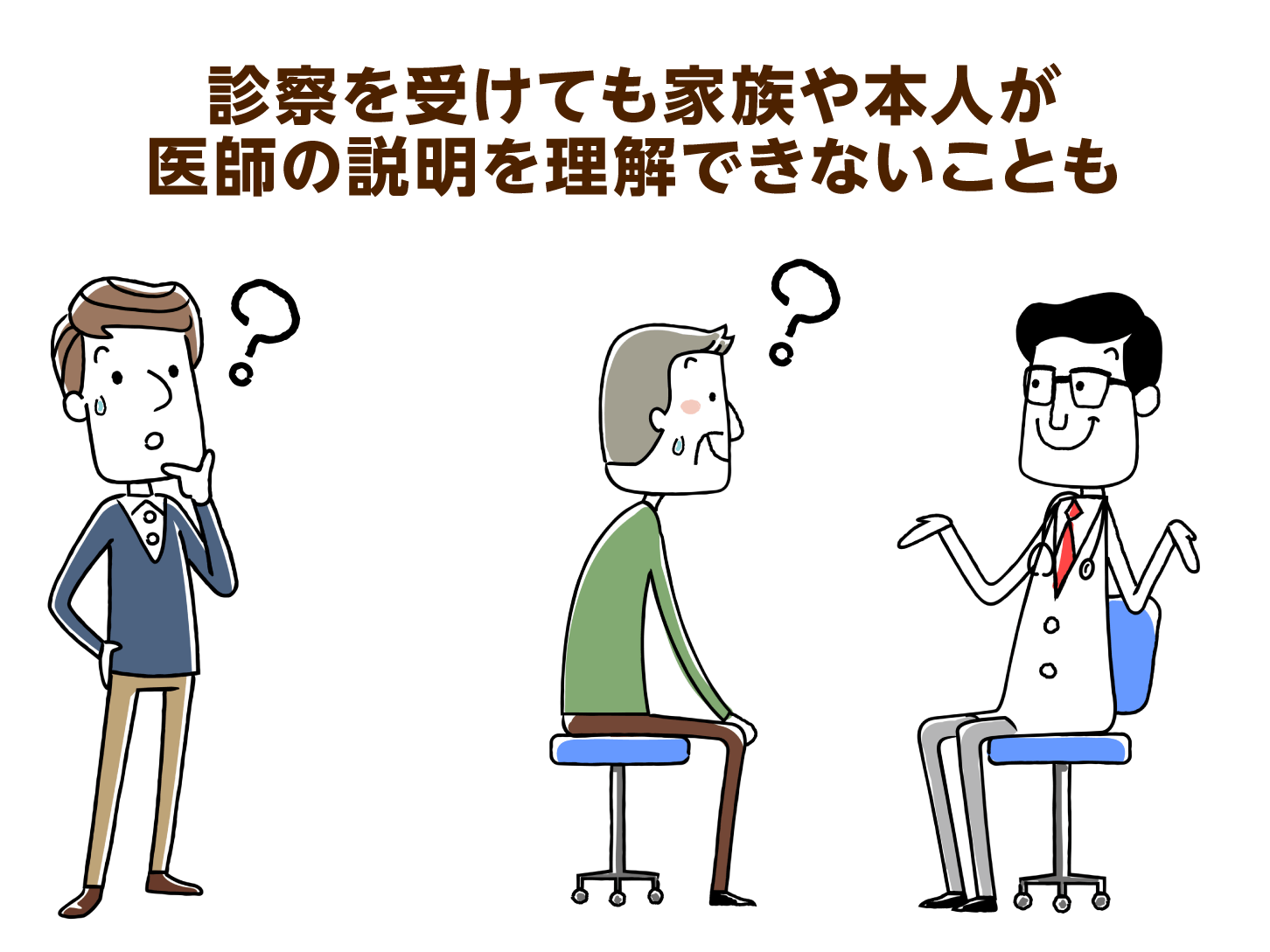
そういった場合、ケアマネから医師や病院の相談員に連絡をしてこちらの状況を伝え、病院の診察結果や詳しい病状を聞くこともあります。例えば、病院とやり取りするための「医療連携シート」や、特定の日にちに病院がケアマネの相談を受け付けている自治体などがそれにあたります。
ここ数年は、以前よりもケアマネが医師の意見を聞きやすくなってきており、通院加算ができたのもそういった流れでしょう。その分、ケアマネの役割は増えてはいますが、「わからないことがわからない」でもやもやするよりは、ケアマネが動いて橋渡しを行い、はっきりしたことを知る方が、のちのち楽なことも事実です。
認知症の発症や進行が気づかれないことも…
「受診を促すレベルの異変には、事業所の方が気づきやすい」と前述しましたが、逆にケアマネから事業所に異変を伝えることが多いのは、認知症の発症や進行です。認知症の利用者の方は、デイなどの他人とかかわるときにはしっかりする方が多いので、外では気づかれないことがあります。しかし、家では認知症の症状が現れるので、家族が気にして困ってしまっているのです。
本人が介護施設や病院で実際と違う話をしてしまい、それによって混乱が生じることもありますので、「そのことは実際はこうなんですよ」とケアマネから伝えます。
家族の方から困りごとを聞いて、「それは認知症かもしれないですね」と伝えることも多いです。家族の方が加齢や性格による言動かと思っているだけでも、ケアマネが話を聞いて認知症の可能性に気づいて受診を促します。認知症はデリケートな病気なので、本人はもちろん家族も認めないことが多いです。とはいえ、放置して良くなることもないので、ときには受診を説得しなくてはいけないこともあります。
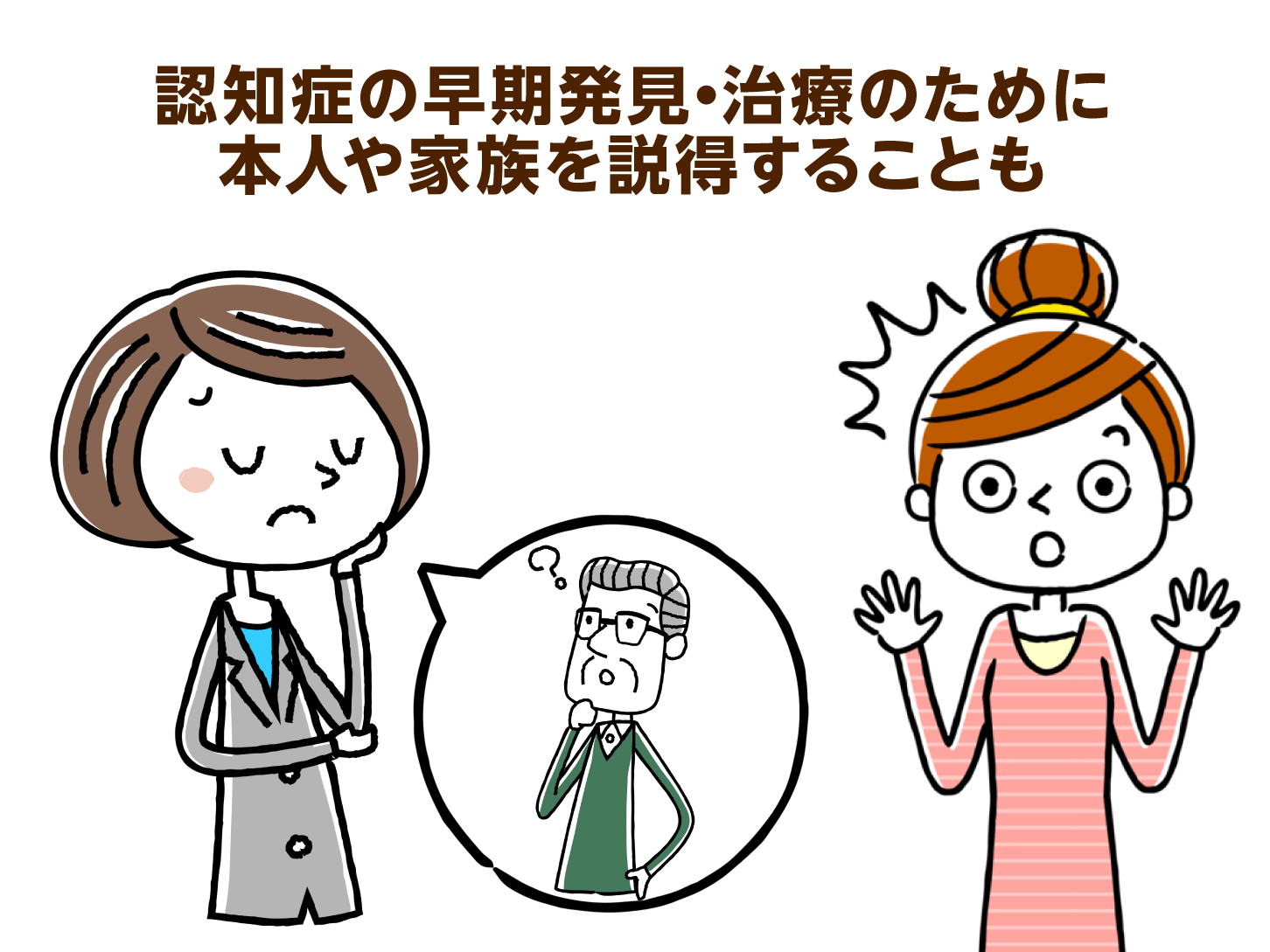
利用者の方の健康のために、ケアマネとしていろいろと動いていることはお話した通りです。
しかしこれを義務として、ケアマネが利用者の方の健康管理に責任を持つというのはまた違う話だと思いますし、荷が重すぎるのは事実。あくまでも業務の一環として、事業所や医療機関にも協力してもらいながら、利用者の方の健康に配慮していきたいと思います。