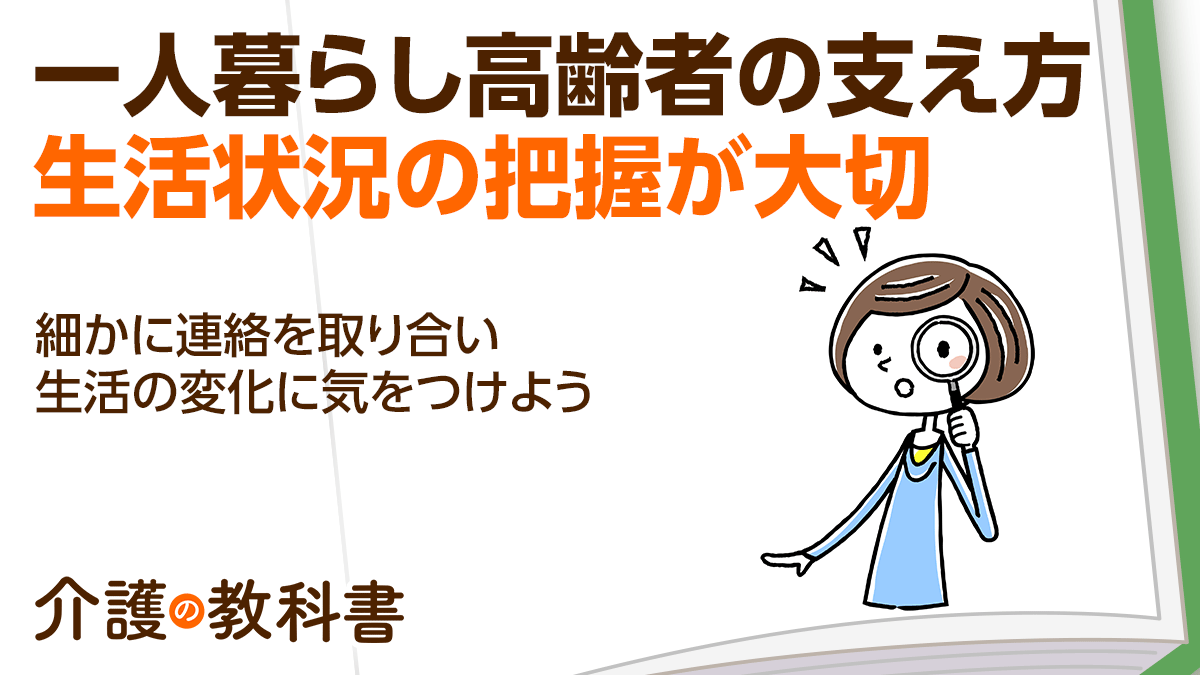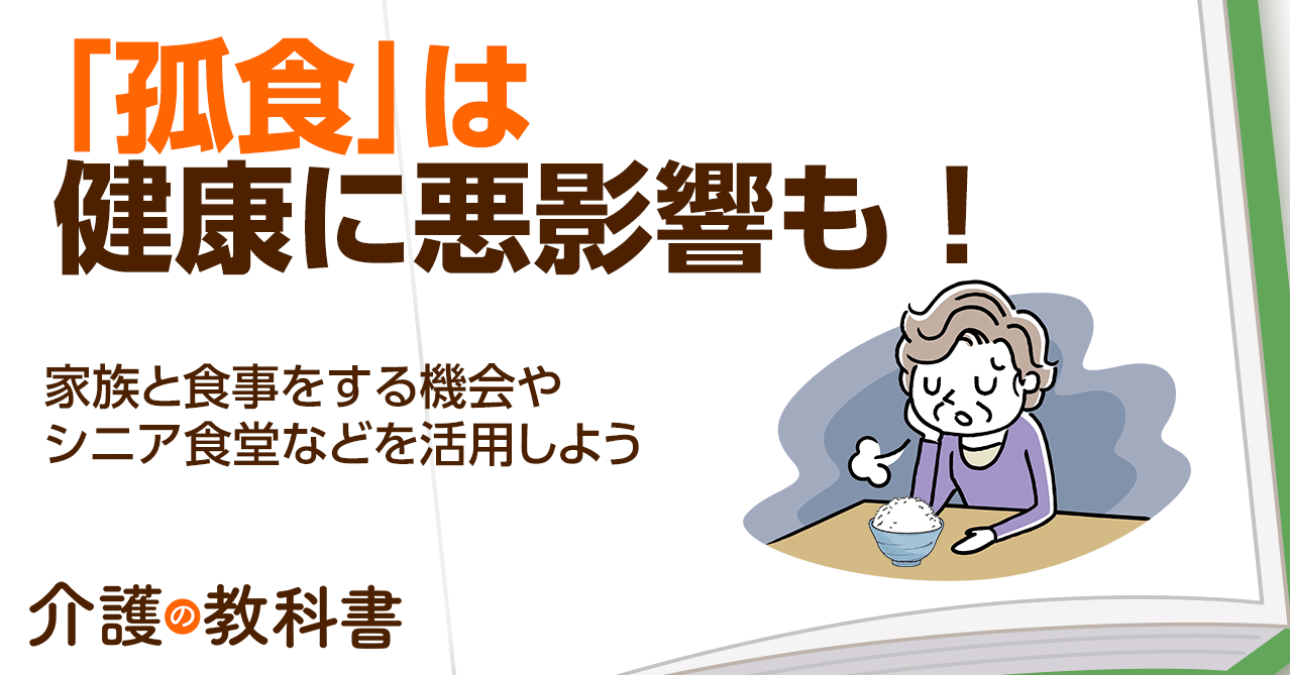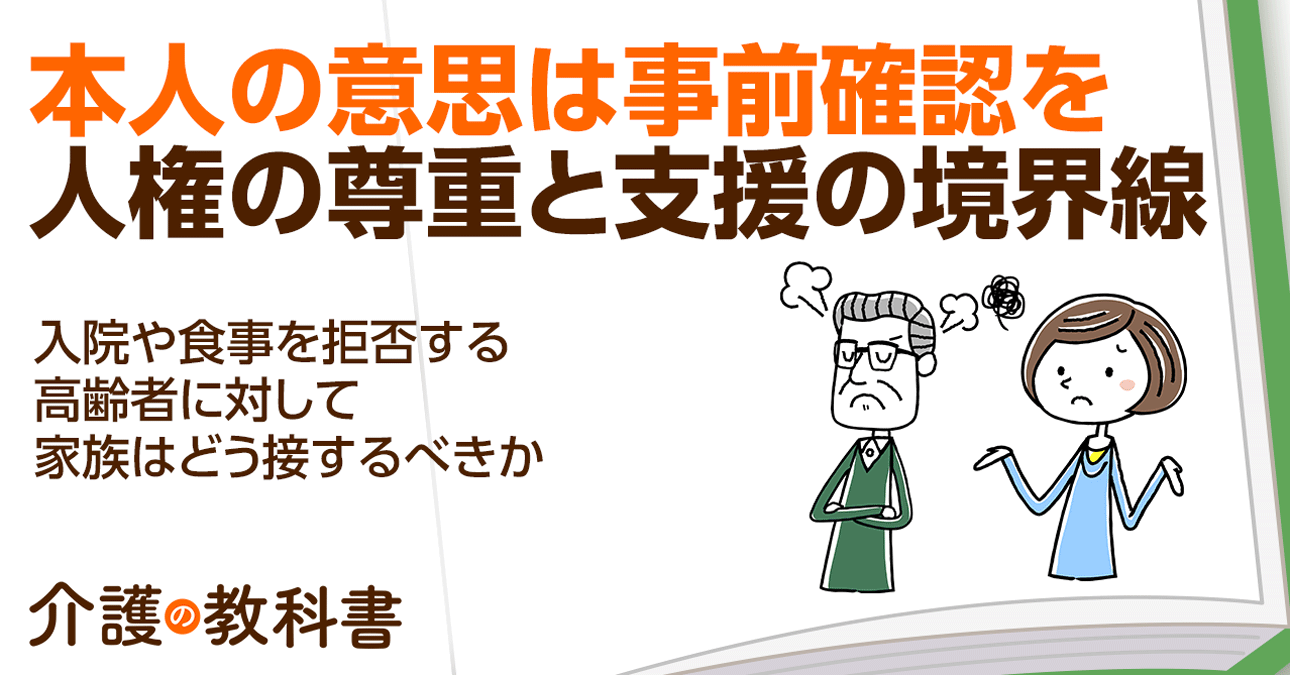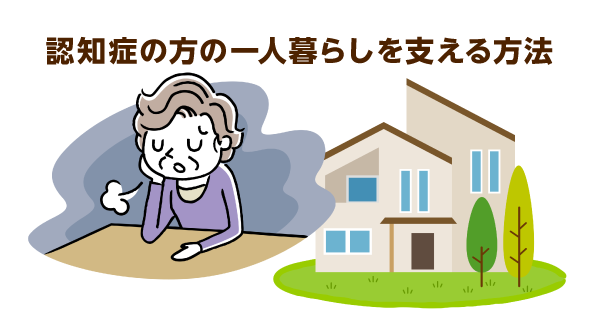仕事の関係などで親を遠方に残して上京し、そのまま生活している方も多いのではないでしょうか。
今回は、一人暮らしをしている親の支援について述べていきたいと思います。
地域の知人や友人に頼る
遠方で生活していると、お盆休みや年末年始、ゴールデンウィークなどの大型連休でないとなかなか帰省できないものです。
また、新型コロナウイルスの影響で、気軽に親の様子を見に行くことも難しいといった悩みもあるかもしれません。
そんな中で、どのように支援していけば良いのでしょうか?
一人暮らしの高齢者は、実家の近所にいる親戚や本人の友人などに様子を見に行ってもらうように依頼して、定期的に安否確認を行うことが大切です。
私が現在担当しているAさんは、持ち家で一人暮らしをされている方で、長女は外国に住んでいます。
元気な頃は小料理屋さんを経営していましたが、店をたたんでからは地域との交流がほとんどなくなり、頼る人がいません。
友人との付き合いもほとんどなく、自分でカートを押して何とか買い物とかには行けていますが、右肩の痛みがひどく、握力も弱いので、調理や掃除をするのに困っていました。
たまたま私の知り合いがAさんを知っていて、その方から要介護認定の申請にかかわってほしいと依頼がありました。現在は「要支援2」の認定をもらい、週に1回ヘルパーさんに来てもらって、掃除などの支援を受けています。

Aさんを訪問すると、いつも言われるのは、外国にいる娘には迷惑をかけられないということです。「亡くなった後、どうしたらいいものか?」といったことを話されます。お墓のことなど、終活にまつわることについて不安を持たれていて、相談を受けたりしています。
亡くなった後を考えてパスワードなどの把握も必要
私が過去に担当していたBさんは、人工透析治療を受けていました。結婚歴がなく、借家で一人暮らしをしていて、生活保護を受けていました。
透析治療を受けている病院の地域医療連携室にいるソーシャルワーカーさんからの紹介にて支援を開始しました。
その方は、要介護認定申請手続きからかかわり、福祉用具のレンタルと、週3回のヘルパー支援を受けて生活されていました。
Bさんの妹が車で1時間半くらいかかるところに住んでいましたが、家族に障がいのある方がいたので、Bさんのことまではなかなか支援できない状況にありました。
透析治療に行く日の朝、介護タクシーの運転手さんに自宅で倒れているのを発見され、病院に救急搬送されましたが、残念ながらお亡くなりになってしまいました。
その後、妹さんから葬儀屋さんを紹介してほしいなどと相談を受け、結果的に私の知り合いの葬儀社につなぎました。
Bさんは自分でネットスーパーを利用して買い物をしていたので、電話回線やインターネットが開通していましたが、解約時には、パスワードなどの情報があまり残っていなかったので、手続きに苦労しました。
このように、親が遠方にて一人暮らしをしている場合、生活面における細かい部分を把握しておく必要があります。
民生委員やケアマネージャーを頼る
もし近所に友人や知人、親戚などがいない場合は、本人が住んでいる地域に「民生委員」と言われる方にお願いすることも重要です。
民生委員とは、厚生労働大臣より委嘱を受けた方で、地域の中で以下のような活動を行っている方をいいます(児童委員も兼務しています)。
- 担当区域の高齢者や障害者のいる世帯、児童・妊産婦・母子家庭などの状況把握。※家庭訪問や地域での情報収集などを行う
- 虐待の早期発見、DV、不登校、世帯の抱える問題の把握
- ニーズに応じた福祉・サービスなどの情報提供
- 支援が必要な方の様々な相談に応じ、助言する
- 福祉サービス利用支援
- 児童の登下校時の声掛け、パトロール活動など
また、賃貸住宅なら、住んでいる建物の管理組合の組合長とか、不動産屋、自治会長などを頼ることも選択肢の一つです。
次に重要なのは、本人が生活をしている中で、どこまで自分で家事を行えているかの把握です。
もし、自分で買い物や調理ができなくなっていたとしたら、市区町村の介護保険窓口などに相談して、介護保険のサービスを利用することを検討しましょう。また、地域包括支援センターに相談する方法もあります。
さらに、親が住んでいる地域に居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)がどこにあるかを把握しておくことも重要です。
最近は、介護保険事業所もホームページなどで解説しているところも増えていますし「ワムネット」といって、独立行政法人福祉医療機構が運営しているサイトから、地域の介護保険事業所を検索することができます。
ケアマネージャーは、介護保険制度のプロではありますが、介護保険以外のことでも相談に乗ることも多く、公的な窓口との架け橋になっています。
中には、自分で独自の異業種ネットワークをもっていて、知り合いの弁護士や司法書士などの士業の方や葬儀社などを紹介してくれるケアマネージャーもいます。
遠方に住んでいる親の支援は、普段から電話連絡を行うなどのコミュニケーションを取ることが何より重要です。そして実家に帰省した際に、本人と終活のことも含めて、充分に話し合っておくと良いでしょう。