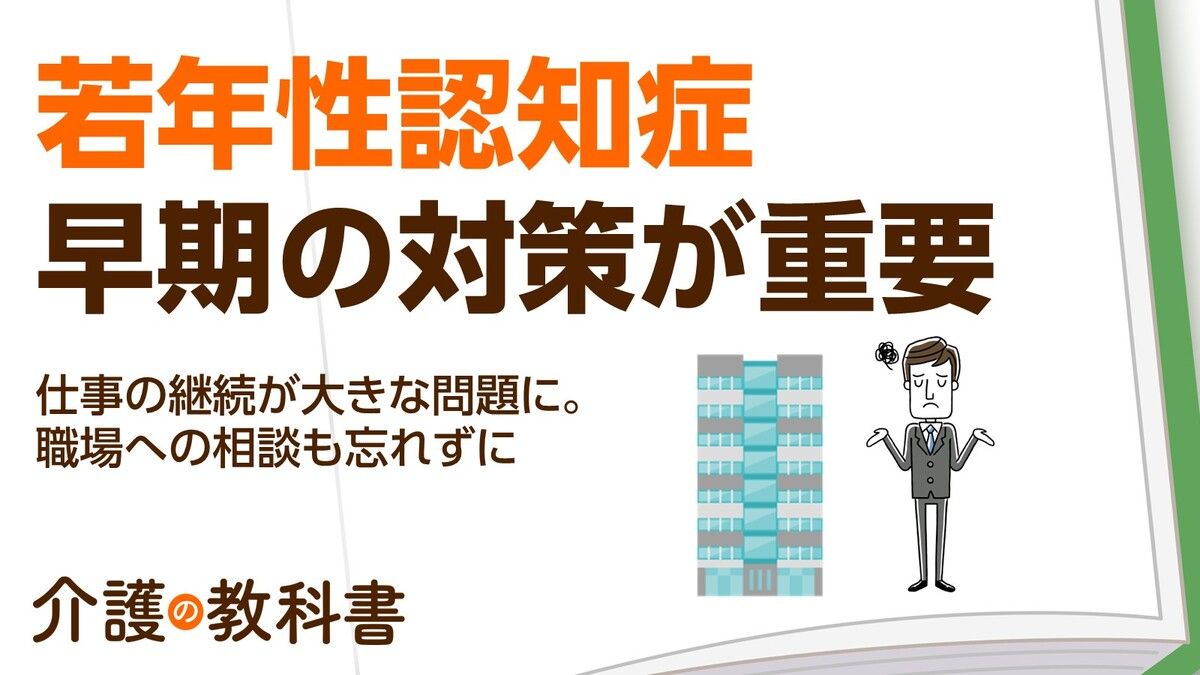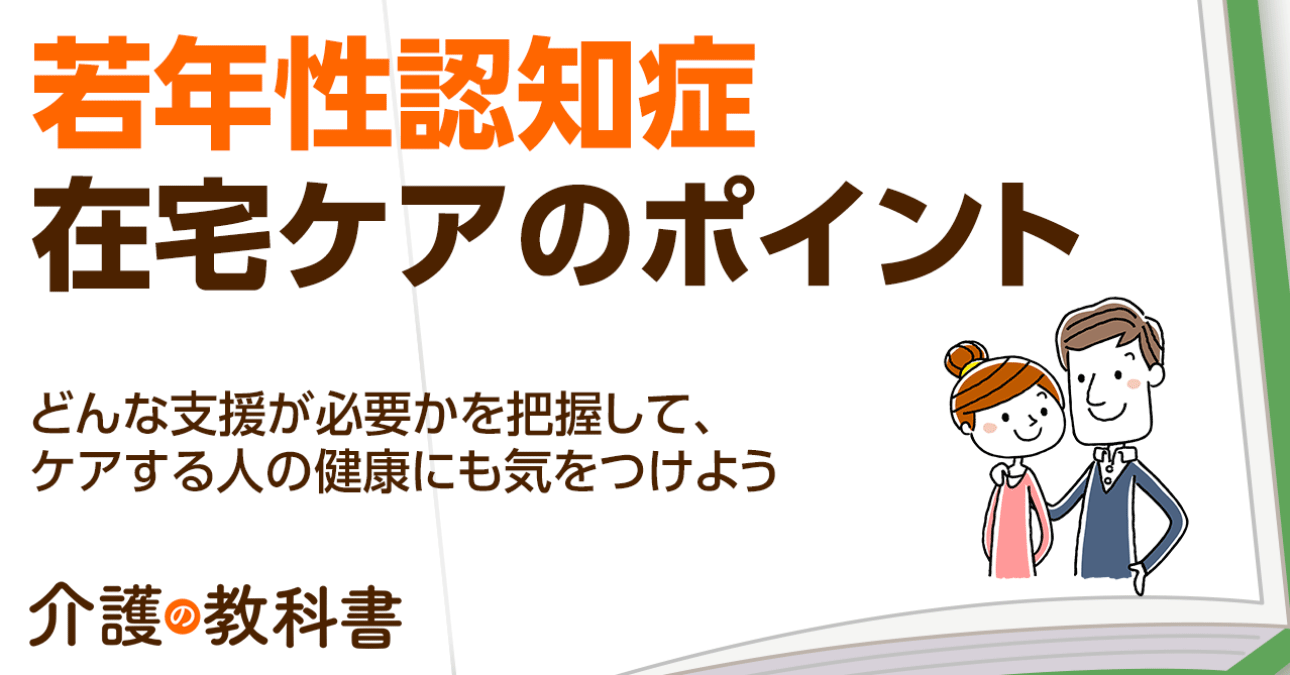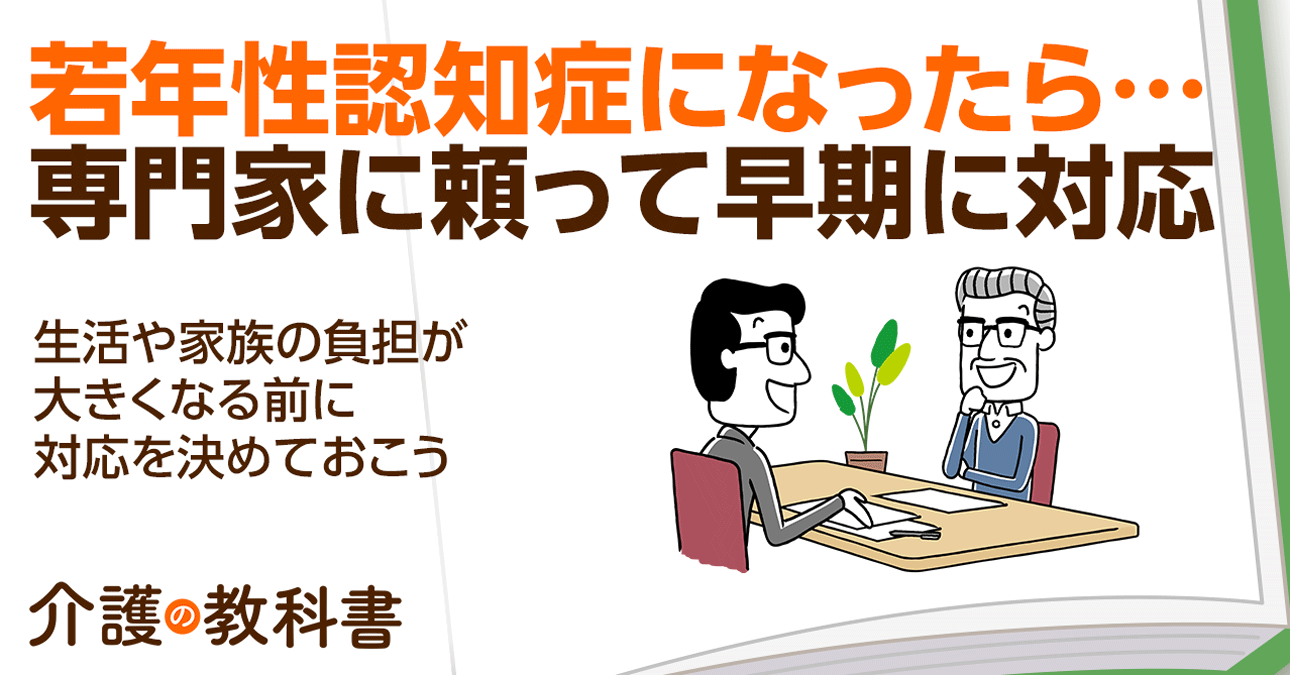認知症は一般的に高齢者に多い病気ですが、65歳未満で発症することもあります。その場合は「若年性認知症」といわれます。
認知症全般に対する理解は少しずつ広がっていますが、「若年性認知症」はまだまだ社会に十分認知しているとは言えないのが現状です。
特に、働き盛りの男性が発症することが多く、仕事を続けられなくなることで家庭にも大きな影響を及ぼすこともあります。
今回は、若年性認知症になったときの対策を考えていきます。
4つに分類される認知症の原因
認知症の原因には、主に4つの種類があります。
- 1.脳血管性認知症
-
脳の血管障がいで起こる脳梗塞や脳出血が原因で認知症の約2割を占めています。
進行速度は緩やかですが、脳血管障がいを発症するたびに悪化するのが特徴です。
また、症状に波があるので「まだら認知症」とも言われています。
- 2.アルツハイマー型認知症
-
認知症の原因の中で最も多く、脳の神経細胞が徐々に減っていく進行性の病気です。
「アミロイドβ」と呼ばれる異常なたんぱく質が影響していると考えられ、進行が進むにつれて脳が少しずつ萎縮していきます。さまざまな症状が出るものの、進行は緩やかであることが特徴です。
- 3.レビー小体型認知症
-
アルツハイマー型認知症の次に多いとされる認知症です。
認知機能の良いときと悪いときといった波を繰り返していきながら進行していきます。
「幻視」といって、実際に見えていないものが見えたり、手足が震えたり、筋肉がこわばるなど「パーキンソン病」のような症状が現れます。
- 4.前頭側頭型認知症
- 人格や社会性、言語を司る「前頭葉」や記憶や聴覚、言語を司る「側頭葉」が萎縮することで発症します。万引きのような軽犯罪を起こしたり、抑制が効かなくなったり、同じ動作を繰り返すなどの症状が特徴です。
若年性認知症は家族の生活への影響も大きい
認知症は発症する年齢によって分類されます。
一般的に65歳以上の高齢者が発症するのが「認知症」と呼ばれ、それ以下の年齢の方が発症するものを「若年性認知症」と呼びます。
若年性認知症の発症年齢は平均51歳と若く、男性に多いので、本人のみならず、ご家族への生活の影響が大きくなりやすいのが特徴です。

認知症の症状によって仕事に支障がでたり、仕事を辞めると経済的なダメージもあるでしょう。また、子どもが成人していない場合には親の病気が与える心理的影響が大きく、教育・就職・結婚などの人生設計が変わることになりかねません。
子どもにとっては、配偶者の親の介護も重なる可能性もあり、介護の負担が大きくなります。
若年性認知症は、企業や医療・介護の現場でもまだ認識が不足していることが大きな問題となっています。
障がい者雇用枠での仕事も視野に
では、若年性認知症の方に対しては、周りの人はどのように対応していけば良いのでしょうか?
まずは、症状について理解を深めることです。
認知症に共通してみられる主な症状は、2つあります。
- 中核症状
-
物忘れや段取りがわからなくなる症状
例)新しい記憶が薄れていく・時間や場所がわからなくなる・判断力、理解力、思考力が低下していくなど
- 行動・心理症状
-
中核症状があったうえで起こる副次的な症状
例)徘徊・妄想・幻覚・不安・焦燥・抑うつ症状など
なお、このような症状については、本人のなかでは実際に見えていたり聞こえていたりしているので、無理に否定しないようにすることが重要です。
40歳以上の方は、介護保険で「第2号被保険者」となるため、以下に挙げる特定疾病に該当すれば、介護保険サービスも利用できます。
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症(アルツハイマー型認知症・脳血管性認知症など)
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血・脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
若年性認知症も特定疾病に該当するので、介護保険サービスを利用できます。
ただ、介護保険サービスの利用者は高齢者が多いため、施設では他の利用者となじめないといった問題に直面するかもしれません。
そこで大切になるのは早期発見・治療すること。早期に発見できれば、認知症状を遅らせる薬を服用するなど対処法があるためです。
仮に今の職場で働き続けるのが難しい場合は、障がい者雇用枠に入るのも1つの方法です。その際は「障害者手帳」を取得する必要があります。
若年性認知症と診断された場合は、まずは勤務先の上司や人事担当者に相談してみましょう。

認知症は、診断された本人が一番辛いものです。ましてや若年性となればなおさらでしょう。
介護者は、本人の言動や行動を無理に否定はせず、傾聴することが大切です。
本人に不安感を与えないように、安心できるような声掛けを行うことも大切です。
周囲が理解することで、本人が落ち着いて生活できるので、認知症に対する理解を深めることが重要です。
厚生労働省も若年性認知症についてのハンドブックを公開しています。
本人や家族にとって大切な情報ですので、ぜひ読んでみてください。