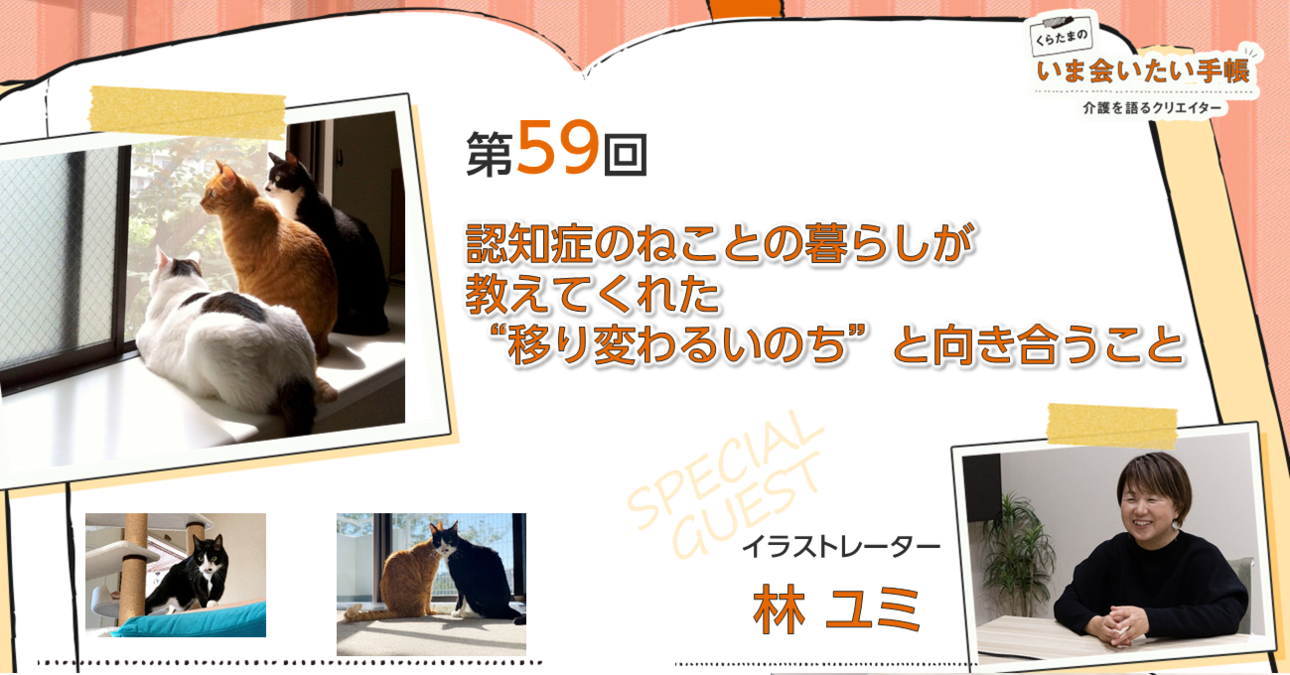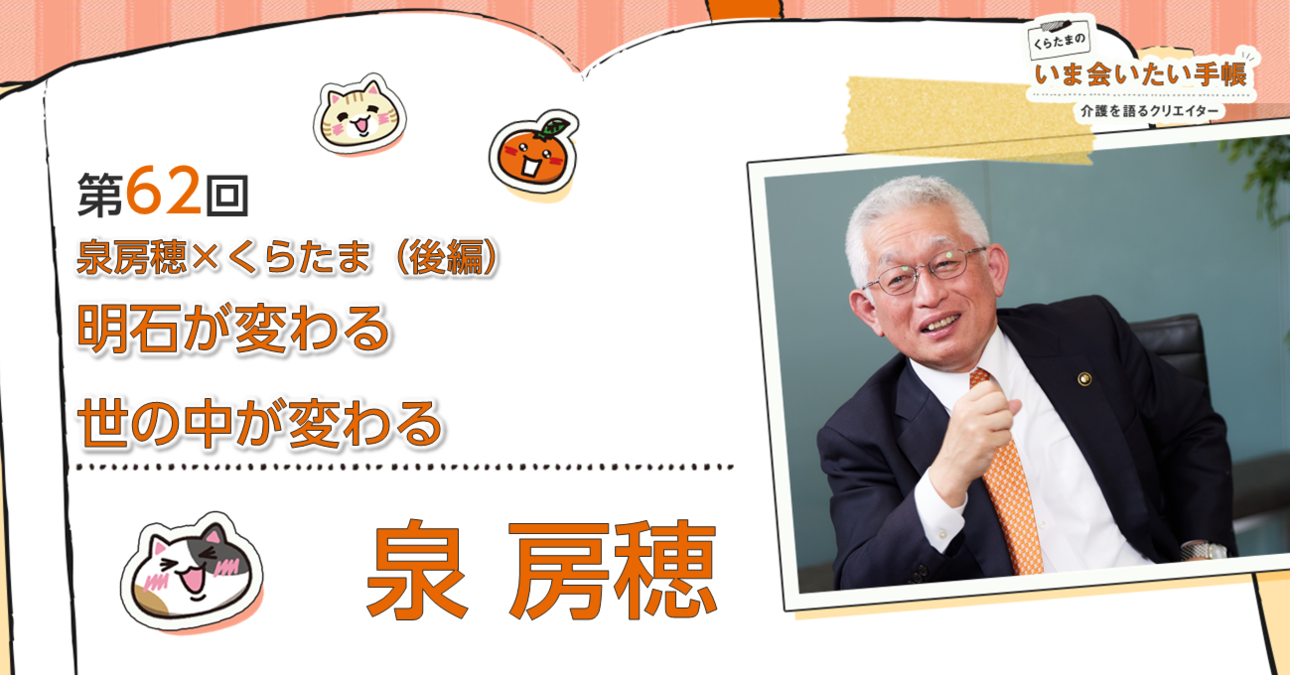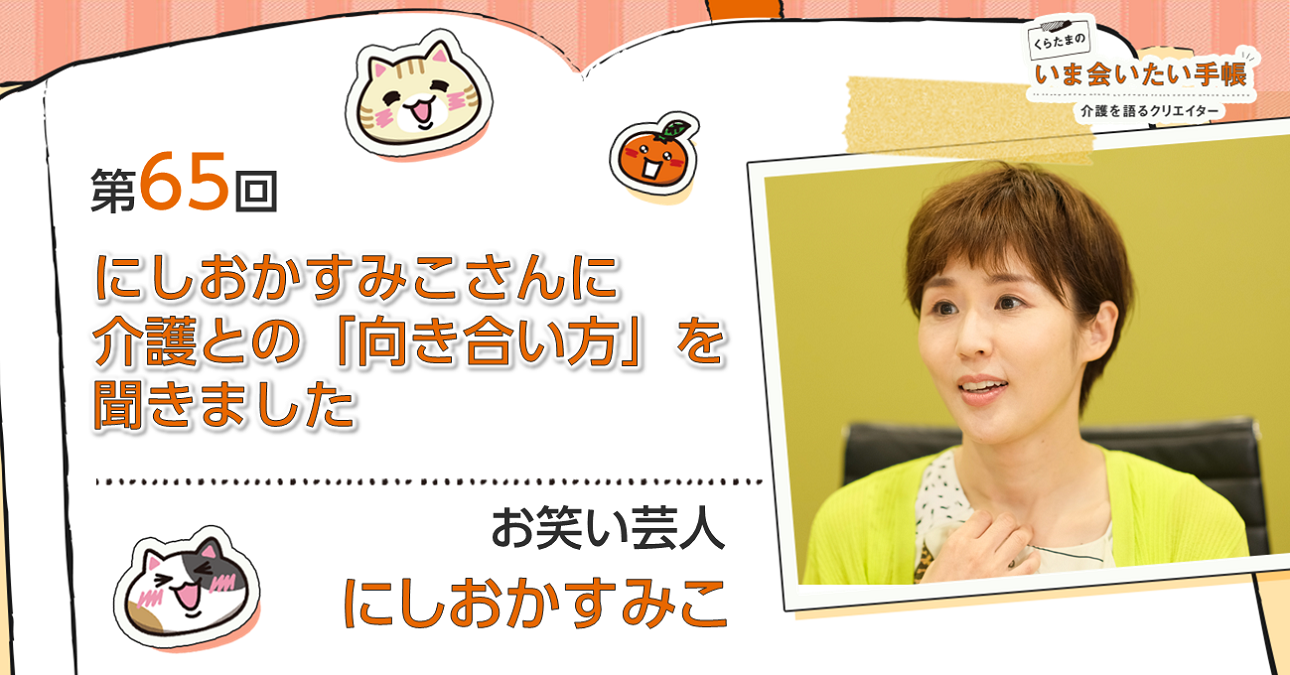ボンちゃんの“変化”に気がついたときのことを改めて伺ってもよろしいですか?
今回のゲストはイラストレーターの林ユミさん。捨てねこの「里親」になり4匹のねこを飼った林さん。ある日、そのうちの1匹のボンが、ぐるぐる回り始めたといいます。動物病院で診てもらうと、認知症との診断が……。ねこが認知症になると、どんな症状があらわれ、飼い主はどんなことに悩むのでしょうか。漫画家くらたまが“認知症ねこ”のリアルを聞きました。
- 構成:みんなの介護
認知症ねこのことについて、マンガのように読みやすく書かれた本書。林ユミさんのやさしいイラストと文章は、……ねこ愛好家じゃない方が読んでも癒やされます。獣医さんによる解説もあるので、「うちのねこも認知症かな?」と思っている人もヒントが見つかるはず。
ボン19歳、ある日突然ぐるぐる回り始めた……
 くらたま
くらたま 林
林明らかにおかしいと思ったのは、ぐるぐる回り始めてからです。今までに見たことがない動きだったので、衝撃でした。それから夜泣きもありましたね。
 くらたま
くらたま急にぐるぐる回り始めたら、どうしていいかわからなくなりますよね。
 林
林そうなんです。抱っこしたらやめるんですけど、私の腕のなかからまた床に降りようとして……。
 くらたま
くらたまそんなふうになっちゃうんだ。
 林
林落ち着いたときに寝かしつければ、そのまま寝てくれることもあるんです。でも、むくって起きて、またタッタッタッタッと歩き出すことも。
 くらたま
くらたま予測がつかない動きをするんですね。
 林
林はい。高い場所でも低い場所でも関係ないんですよ。とにかく足がつくところは壁伝いにズリズリ行くので。広くない我が家を最大限に広く使って歩いてましたね。
 くらたま
くらたまぐるぐる回る理由に、何か思い当たる節はあったんですか?
 林
林ぐるぐる回るのは、人間の“一人歩き”に近いのかもしれないと思っていたんです。動物の場合は、人間と違って、無目的と言われています。でも、私は何か目的があるんじゃないかと考えています。
人間の一人歩きも昔は意味なく歩いていると考えられていました。今は、「一人歩きは過去の記憶に関係しているのではないか」と言われていますよね。
例えば、ある認知症のおばあちゃんは、子どもの幼稚園のバスが来ていた4時ぐらいになると、飛び出していってしまう。そのことを理解したうえでおばあちゃんに接すると、安心して行動にも変化がある、と。それと同じように、ぐるぐる回る理由がねこにもあるんじゃないかって。

ボンにはボンの理由があるはずだ。わたしは、そのそばで寄り添いたい。正解にたどり着けなくても、ボンの理由を考えながら、ともに生活していきたい。医学的には、認知症の動物が歩き続けることは「無目的」というけれど、動物の当事者に聞けるわけではないから、わたしは、わからないと思うのだ。
(『我輩は認知症ねこである』P27より引用)
 くらたま
くらたまうん、ありえますね。
 林
林長年一緒に暮らしていたのに、ボンの徘徊の理由は"想像"することしかできませんでしたが……。
 くらたま
くらたま
 林
林友人が一緒に暮らしていた黒ねこの場合は、彼女が寝ている布団の周りを延々とグルグルしていたという話を聞きました。当時、落ち着いて寝られなかったようです。
 くらたま
くらたまユミさんもボンちゃんの症状が出始めてから、気が休まらなかったんじゃないですか?
 林
林それはありますね。でも、動物のいのちを預かる選択をしたということはボンの老いや病気と、お世話に疲弊する自身を含めてまるっと受け入れる選択をしたということだと思うんです。
彼らの境遇がどうであれ、ともに暮らすことを決めたのは、わたしたちだ。その瞬間から、この家が彼らの世界のすべてになる。彼らの新しい世界でわたしの力は圧倒的過ぎて、それに気づくたびに胃のあたりがざわついた。彼らの生きる環境すべてを任されている。自分がこの「いのち」に、ずっと責任を持っていけるのか。「預かった彼らのいのち」のあまりの大きさと、もろさを思い知った。
(『我輩は認知症ねこである』P44より引用)
“ねこの認知症”はもっと知られる必要がある
 くらたま
くらたまその後、ボンちゃんはどうなったのですか?
 林
林動物病院に電話してボンの症状を相談したら、「年齢から考えると認知症の症状かもしれません」と。その後、診察を受けたら、正式に"認知症"と診断されました。おもな症状としては、ぐるぐる周ったり、歩き続けたり、トイレの習慣や食事の仕方が変わったり、毛づくろいなどの衛生管理ができなくなったりすると聞きました。ねこの認知症の原因は、加齢による脳の萎縮のほか、アルツハイマー型もあるようです。
 くらたま
くらたま人間の認知症の症状と、どこか通じるところがありますね。
 林
林そうですね。ボンは19歳で認知症の症状が出てきましたが、獣医さんによると、11歳~14歳のねこの28%に行動変化が見られるそうです。さらに、15歳以上になると50%だとか。ほかの病気の影響もあるようですが……。

 くらたま
くらたまそんなに……!気づいていないだけで、認知症になっているねこは、もっといるかもしれないですよね。
 林
林そうかもしれないです。
 くらたま
くらたまボンちゃんは認知症になってからどれぐらい生きたんですか?
 林
林認知症になって3カ月で天寿をまっとうしました。でも、認知症ねこの介護をしている方のブログなどを読むと、私よりも大変な思いをしている方はたくさんいらっしゃいます。変化にどう対応したらいいかわからない方も。
 くらたま
くらたま動物の場合、安楽死を選ぶ方もいますよね。
 林
林そうですね。私もボンが認知症になったとき、インターネットで検索したら安楽死についての情報が次々出てきて驚いていました。
……すごく難しい問題です。私自身は、自分以外のいのちを終わらせる選択はない。でも、介護にとても苦しんでいる当事者に対して、頭ごなしに「そんなん、あり得ん!」と旗を振りかざすこともできないなと思うんです。
 くらたま
くらたまよく分かります。
 林
林人間であれば合法ではないことが動物の場合はできるという状況。そこにはやはり、"いのちの扱い"に違いがある以外の理由を探すことはできないと思うんです。ましてや動物は、安楽死をのぞむ、のぞまないの意思表示ができない……。苦しかったり辛かったり、そこから逃れたいということはあっても、彼らねこたちが自ら「死」をのぞむことはないのではないでしょうか。
今は、緩和ケアというアプローチも充実してきています。緩和ケアが施せる病院やクリニックが、より認知され充実していくことが大切だと思います。
 くらたま
くらたま動物を家族のように大切に思っている人にとっても、医療の充実が救いになるかもしれませんね。
 林
林ちなみに、先ほどの黒ねこを飼っていた友人は、認知症という診断をしてもらえなかったんです。3、4年前のことですが、当時は、いぬの認知症は知られていても、ねこは珍しかったので。
 くらたま
くらたま診断が難しそうですよね。
 林
林そうですね。かかりつけの獣医さんも、他の病気の可能性を全部消してから「認知症」の診断をすると聞きました。長生きすると認知症になる確率は高まりますが、“ねこの認知症”という概念自体、あまり広まっていなかったので……。
資料もあまりないので、私は、人間の認知症の本を参考にしました。例えば、筧裕介さんの『認知症世界の歩き方』もその一冊です。この本は、当事者に聞き込みをしたうえで、認知症の症状について書かれています。例えば「お風呂に入るのが嫌な理由は、ただ単に面倒くさいからではなく、脳の変化でお湯を不快に感じてしまうからだ」とか。この本を読んで、ボンの症状にも当てはめて考えることができました。
 くらたま
くらたまそういう背景を考えると、ユミさんの本で「認知症ねこ」という単語が出てきたこと自体、すごくいいですよね。「認知症ねこ」とか「認知症いぬ」という言葉は、まだ生まれていませんから。

 林
林ありがとうございます。実は、動物の認知症を専門に診ている先生はいらっしゃるんです。でも、病院の存在はあまり知られていない……。それに、ペットの認知症の初期症状は気づかないことも多いと思います。おしっこをあちこちでしちゃうとか、よっぽど分かりやすい兆候があれば別かもしれませんが……。
 くらたま
くらたまボンちゃんも、その症状があったんですよね。
 林
林ありました。でも、ボンがあちこちにおしっこをするのは「どこでもいいからやるぜウェーィ」みたいな感じではなく“困った感”があったんです。「あれ?ここかな?」みたいな。おしっこをしたあとに、いつも通り「ニャー」って言って教えてくれていたので。
 くらたま
くらたまそうなんだ。おしっこもそうだけど、ウンチ問題もありますよね。もう昔の話ですけど、うちも、いぬが最期の1年はトイレでできなかったんです。部屋でそのまましちゃうみたいな。大型犬だったから結構でかいんですよ(笑)。当時、おむつはまだしていなかったので。
 林
林それは大変そうですね。うちは、夫のゴローさんがおしっこの時間を記録に残してくれていました。「そろそろ出そうだな」というタイミングに合わせておむつをしていたんです。
基本、ねこは服を着ない。わたしが「おむつ」をはかせることに躊躇していた理由は、ボンのストレスになると思ったからだ。その一方……常に時計とにらめっこをしながら「おしっこする?」「そろそろかな?」とたずねて回るわたし自身が、すでにボンのストレスになっている矛盾も感じていた。
(『我輩は認知症ねこである』P99より引用)
 くらたま
くらたまこまめなご主人ですね。

 林
林もともとボンが腎臓を患ったことがきっかけで、おしっこの量をはかり始めたんですよ。実際に記録に残して確認することで、無駄な心配をしなくてもよくなりました。
 くらたま
くらたまなるほど。
 林
林それから、認知症になると表情は変わりますね。くるくる回るようになってからの写真は、ちょっと伏し目がちなんですよね。人もそうですけど。
 くらたま
くらたま私もいぬを飼ってたときの実感があるので、すごくわかります。顔が全然違いますよね。老犬になると無表情になるというか。
隙間で身動きがとれない!
 くらたま
くらたまボンちゃんの症状で、ほかにも困ったことはありました?
 林
林隙間にはまる症状にも困りましたね。これは、くるくる回り出したことより衝撃でした。
 くらたま
くらたまねこはもともと狭いところに入りたがる習性がありますよね。
 林
林それが、認知症になると、後ずさりができなくなるんです。前が壁になっていたら、そこでうずくまっていました。
 くらたま
くらたまどんな感じなんだろうな。
 林
林見ます?
 くらたま
くらたまえぇー!!こういうことか。これは確かに普通じゃないな。
 林
林そうです。最初は認知症の症状だと分からなくて、「ボンちゃん何やってるの?」と思っていたんですけど。
 くらたま
くらたまフリーズして動けない。

 林
林このままでいると、状況によっては熱中症になっちゃうんです。おしっこも、そこでするしかなくなるし。
秋の20分間の日差しで熱中症に
 林
林ボンは実際に熱中症になったんです。
 くらたま
くらたまえっ!そうなんですか。
 林
林10月だったのですが、すごく日差しが強いときでした。あたたかくて気持ち良かったので、ボンは、いつものように日向ぼっこする場所で寝ていたんです。
少しして様子を見に行ったら、口を開けてゼーゼー息をしている。目を離したのは20分ぐらいなんですけど、明らかに様子がおかしいと思いました。多分、熱中症だなと。でも、そういうときに限って、病院が休診という状態で……。
 くらたま
くらたま暑い場所から動けなくなって熱中症になったんですか?
 林
林暑さを感じてから動き出すまでに時間がかかったんです。認知症じゃなかったら、暑さを感じて場所を移ろうとします。でも、認知症になっているので、暑いと感じるまでに時間がかかる。結果、うまく体を動かせなかったんですよね。
 くらたま
くらたまなるほど!そうなんだ。その後、どうされたんですか?
 林
林とりあえず、濡れたバスタオルで体をくるんで冷やしました。あとは、むせないように、口にお水を当てがう応急処置を。そうしながらも、震える手で救急の動物病院に電話しました。高齢になって、ただでさえ弱くなっているのに、熱中症にさせてしまったことを悔やみながら……。
 くらたま
くらたま病院には行かなくて済んだのですか?
 林
林そうなんです。それが、電話で話をしているうちに、だんだんボンの呼吸がおさまってきたんです。
 くらたま
くらたま良かったですね。熱中症は命にも関わりますからね。
 林
林そうですよね。それこそ、うちの両親とかには口を酸っぱくして「熱中症に気をつけてね」って言ってたんです。それなのに、ボンが熱中症になってしまった……。「うちに限って熱中症はないだろう」と傲慢になっていたと思うんです。
でも、ねこは体が小さい。条件が揃えば、熱中症になるリスクは当然あるんだなと思います。
 くらたま
くらたまそうかもしれない。人間だと20分ぐらいでそこまでの症状は出ない気がするけど、小さい動物ってすぐ体が温かくなりますよね。でも、ユミさんの「これは熱中症だ」という判断、ナイスでしたね。
 林
林ありがとうございます。認知症の症状や応急処置の方法を知っていたのが大きかったと思います。認知症もそうですが、前知識があるとないとで全然違いますよね。天国にも地獄にもなるというか。
 くらたま
くらたまなるなる!生死を分けますよ。
夫が心筋梗塞に。ネットの情報で九死に一生を得た
 くらたま
くらたまうちも知識で命拾いしたことがありました。夫が心筋梗塞になったときのことです。心筋梗塞の症状って、ドラマとか見てると、急に「バタッ」みたいなイメージがあるじゃないですか。
夫の場合は違ったんですよ。朝の7時ぐらいに「なんか胸のあたりが気持ち悪いんだよね」って。「胃もたれかな」みたいなこと言ってたんだけど、何も変なものを食べてない。
 林
林そうなんですか。
 くらたま
くらたま「病院開いたら行くわ」って言ってるけど、普通じゃないんです。いつもの夫と様子が違うなと思いました。
だけど私、夫は健康診断で心臓肥大があると知っていたんです。あやしいなと思ってインターネットで調べると、心筋梗塞は「なんか気持ち悪い」という症状から始まることがあると出てきました。これはマズイ!と思いました。そして、病院を探したら、7時半にうちの近くの循環器系の個人病院が開いてたんです。
 林
林すごい偶然ですね。
 くらたま
くらたまその病院に「ちょっと心筋梗塞かもしれないので診てください」と言って、診療が始まると同時に駆け込みました。家から近いので、夫は自転車で行ったんだけど、心電図をとってもらったら「これは大変だ」と。その個人病院まで救急車が来ました。
でもね、それも運が良かったんです。心筋梗塞でも心臓の波形が乱れていないことがあるんですって。波形が乱れていないときに測っちゃうと、見つけてもらえない可能性がある。「悪いところは心臓じゃないですね」と診断されていたら、死んでいたんです。やっぱ知識って大切ですね。インターネットに助けられましたよ。
 林
林知識のあるなしが、いのちに関わりますよね。
 くらたま
くらたま実際、「もう1時間遅かったら死んでます」って言われました。「9時になったら病院行きなよ」ではダメだったんです。
 林
林そうだったんですか。でも、“気持ち悪い”ぐらいじゃ、なかなか心筋梗塞に結びつかないですよね。
 くらたま
くらたま夫も「心臓?まさかー。食中毒と思う」みたいに言ってたしね。嘘つくなみたいな(笑)。どこが悪いのかの「読み」が適当でもいのちはなかった。
 林
林くらたまさんの前情報がなかったら、ご主人は、医師に「胃の調子が……」と言って、胃の検査をしていたかもしれないんですよね。
 くらたま
くらたましてますね。それに、内科に行ってそんなことを言われたら、まず心臓を調べないとも思うので。ピンポイントで「心筋梗塞かもしれません」と言って心電図をとってもらったことでいのちがつながりました。
親の介護には、同じように向き合えるかな
 林
林やっぱり相手を理解するって大切ですよね。私もねこの認知症のことを知ったうえでボンを看ることができたから、心構えができたんだと思います。私は医者じゃないので、脳のことを勉強しても認知症のことは、やっぱりわからないし、どうにもできない。
でも、ボンの気持ちを傷つけたり、ないがしろにしたり、孤独にすることだけはしたくないなという思いがあったんです。なぜそんな思いになったかというと、おばあちゃんの姿と重なりました。
 くらたま
くらたまおばあちゃん?
 林
林私のおばあちゃんは認知症でした。移動するときに体を支えるなどして、介護を手伝ったことがあります。そのとき、申し訳なさそうな表情をしていたのが今も心に残っています。大好きなおばあちゃんがつらいと思っていたように、ボンもつらいのかなと考えました。人間と動物を一緒にしてはいけないのかもしれませんが……。
まして動物の場合は、言葉が話せない。その分、しぐさや表情からボンの思いをくみ取って接してきました。だからだと思いますが、まるで「長年連れ添った夫婦」のようにボンの“心”を感じていたんです。私の知っているボンの“心”は認知症になってからも変わらなかった。ボンは最期まで"ボン自身"であり続けたと思います。
 くらたま
くらたまそうだったんですね。
 林
林それに、歩き続けるボンを明け方に抱いていると、「自分の親のとき、私、同じように向き合えるかな」という思いにふけることもありました。
 くらたま
くらたまリアルになってみないと、そこはわからないですよね。できることとできないことは絶対ありますから。
 林
林たしかに。ボンは、認知症になったことでお世話が大変になりました。でも、ボンのおかげで気づけたことも、たくさんありました。変化する“いのち”を受容することも教えてくれたし、私と同じように動物の介護をされている人のことを知るきっかけも与えてくれました。
 くらたま
くらたまほんとにそうですね。今の時代、人間の認知症は社会問題になっていますが、人間のパートナーである動物の認知症についても、もっと知られる必要があると思います。それに、ご高齢の家族がいない人にとっても、動物の認知症をきっかけに、人間の認知症について理解を深める人もいるかもしれない……。
ねこの認知症のお話を伺うことで、改めて人間の認知症についても考えることができました。今日は、ありがとうございました。


林 ユミ
イラストレーター。あたたかくやさしいイラストで、児童書を中心に活躍。イラストを手がけた本は『よのなかのルールブック』(日本図書センター)、『赤ちゃんはどこからくるの?』(幻冬舎)など多数。