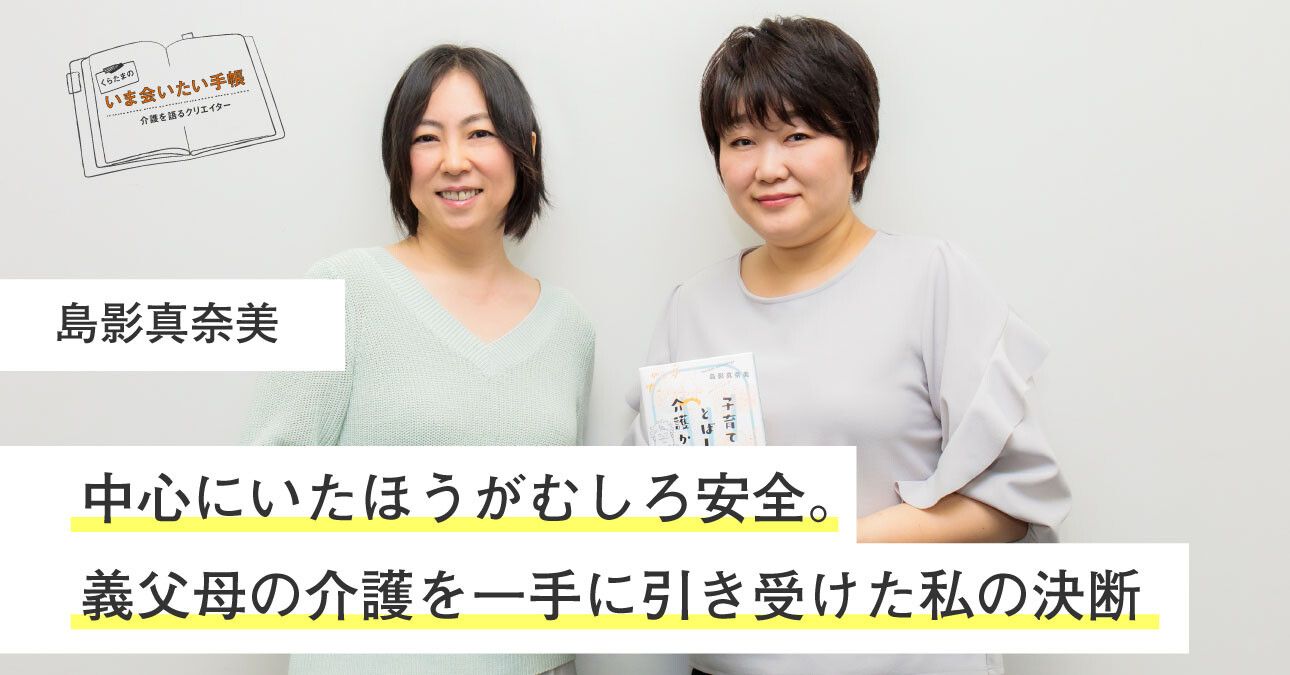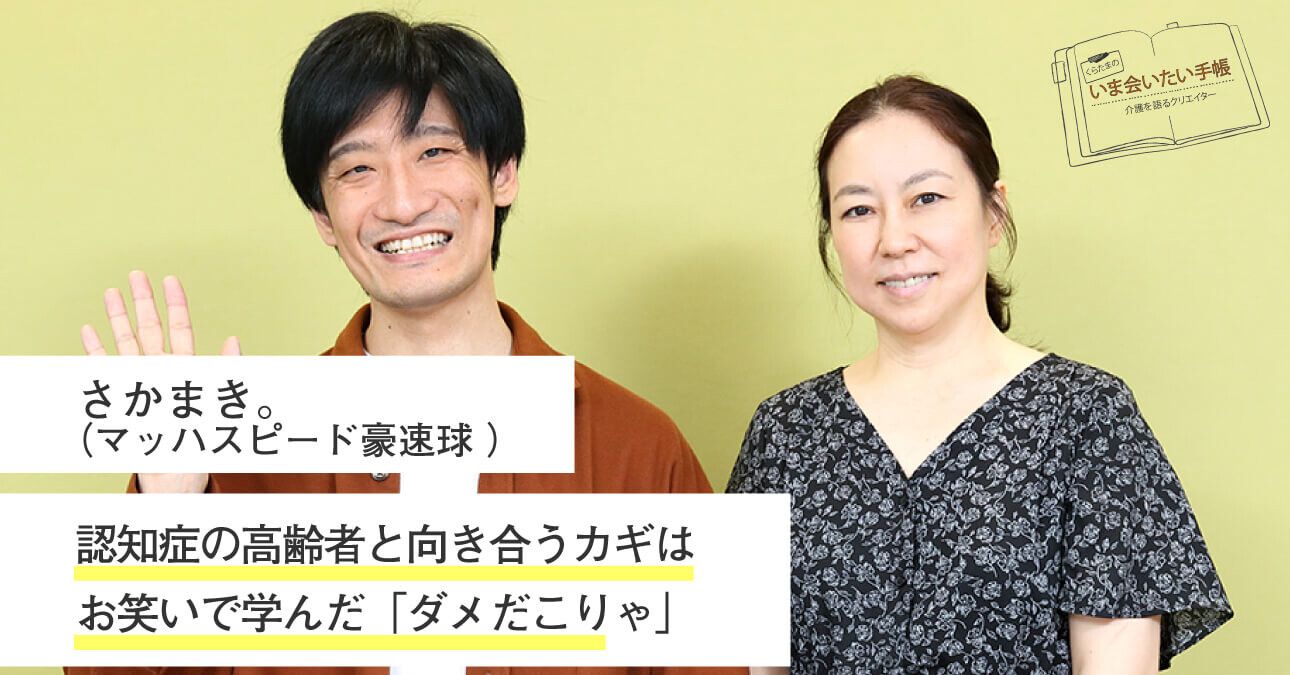とっても久しぶり!島影さんにはじめて会ったのって、けっこう前なのよね。
仕事はやめない、同居もしない。今の暮らしを変えずに親の介護は可能なのか? 決して他人事とは言えないそんな問題に真向から立ち向かっていったのが今回のゲスト・島影真奈美さん。大学院へ社会人入学した矢先に、夫の両親の認知症が立て続けに発覚。「介護のキーパーソン」として別居介護に参戦することに。実体験を元にした介護エッセイ『子育てとばして介護かよ』を発表しました。いったい、どんな苦労があったのか。漫画家くらたまと語り合いました。
- 構成:みんなの介護
31歳で結婚し、仕事に明け暮れた⽇々。33歳で出産する⼈⽣設計を⽴てていたけれど、気づけば40代に突⼊︕出産するならもうすぐリミットだし、い ろいろ決断しどきだな――と思った⽮先、なんと義⽗⺟の認知症が⽴て続けに発覚。「介護のキーパーソン」として別居介護に参戦。仕事は辞めない、同居もしない。いまの⽣活に「介護」を組み込むことに成功した著者の、笑いと涙の「同居しない」介護エッセイ。
突然の義父母の言動に半信半疑
 くらたま
くらたま 島影
島影倉田さんが座談会の会場に赤ちゃんを抱っこしていらしたのが最初ですね。その日たまたま赤ちゃんを見てくれる人がいないから、とかいうことだったと思います。
 くらたま
くらたまそのときに連れて行ったのは、今年ハタチになる上の子なんですよ。あのときのライターさんが島影さんだったとは……びっくり……。
 島影
島影私もショックですよ(笑)。
あのときは、みんなで赤ちゃんを代わる代わる抱っこして、ほのぼのしながら「つらい恋」についての座談会を進めた記憶があります。
 くらたま
くらたまそうでしたね(笑)。
今回、ご著書を読ませてもらったんですけど、けっこう自分から介護に首を突っ込みに行ってますよね?
 島影
島影そうなんですよ……。
 くらたま
くらたまそこが、私の「一番わからないところ」でしたね。旦那とお義姉さんという実子がいるのに「なんで島影さんが?」って。
本によると、最初はお義母さんの異変に気づかなかったのよね?「息子(=島影さんの夫)が浮気してる」とか「息子から3万円を盗られた」とか電話がかかってくるようになったとか……。
 島影
島影最初は、「お義母さんてば、変わったことを言ってるなあ」くらいでしたね。高齢だから通帳をなくしたり、置き忘れたりしたのを息子のせいにしているのかなと。
「浮気」にこじつけるなんて、すごい発想力だなと面白がっていたところもあって。
 くらたま
くらたまボケたとかでなく?
 島影
島影当時は、認知症だとは想像もしていませんでした。
ところが、夫も私も仕事もあるし、特に問題なさそうなので放置していたら、しばらく経って不思議な電話がかかってきました。義父母が言うには「見知らぬ女性が自宅の2階に出入りしている」と。
 くらたま
くらたまなるほど。おかしいと思ったのは、「2階に女性がいる」と言い出したときだったんだね。
 島影
島影認知症の症状のひとつに「幻視」(存在しないものが見える」があることは知っていたので、もしかしたら認知症なのかな?とチラリと想像しました。
ただ、それでもまだ半信半疑でした。
じーっとこっちを見ていたと思ったら、開いていた窓からバッと入ってきてね、そのまま、押し入れのふすまを開けて、スルスルーッと天袋を通って、2階に上がっちゃったの
(『子育てとばして介護かよ』P25より引用)
 くらたま
くらたま「半信」?
 島影
島影可能性を3つ考えたんです。ひとつ目は認知症で、ありもしないものが見えているということ。あとは天袋を抜けるのは勘違いにしても、誰かが家に出入りしているかもしれないと。
 くらたま
くらたまなるほど、その可能性はあるかもと思ったんですね。
 島影
島影はい。老夫婦だけの家にこっそり入ってくる人がいて、お義母さんだけが気づいて、「窓から入ってきた」とか思いこんでいるのかも、とか。
で、3つ目は心霊現象ですね。
 くらたま
くらたま心霊?まったくその発想はないわ(笑)。
 島影
島影お義母さんが霊能力に目覚めた可能性もゼロとは言い切れないだろうなと(笑)。でも、何しろいちばん怖いのは義父母が言う通り、見知らぬ女性が本当に出入りしていることなので、できれば認知症の初期症状であってほしいとも思っていました。
 くらたま
くらたまそりゃそうだわ(笑)。
本を読みながら思ったんだけど、お義父さんはお義母さんの言葉を信じてるでしょ?
 島影
島影そうなんですよ。あとでわかるんですけど、お義父さんはお義母さんが大好きでベタ甘。何を言われてもたいていは否定せずに合わせるんです。
 くらたま
くらたまでも、お義父さんも認知症なんでしょ?お母さんに話を合わせてただけかも。
 島影
島影お義父さんは、「僕は見たことがないけど、家内のものばかり盗んでいくんだよ。本当に厄介なんだ」と言ってました。
それで、お義母さんが急に「またあの人が出てくる気がするわ」って、ホラーっぽいことを言うたびに、、お義父さんが2階を見に行ってました。
お義父さんは紳士なんですよ。妻が不安だと言えば、不安を払拭するために見に行くんです。
戻ってきたお義父さんが「いなかったよ」って言うと、お義母さんは「ずるがしこいわね!お父さまが階段を上る音を聞いたから、隠れたんだわ!」と…。
 くらたま
くらたま……どう判断していいかわからないけど、「認知症が始まった人が、現実と違うことを言ったときに否定しないほうがいい」という話も聞きます。
私なら、「2階に他人なんかいるわけないじゃん!」って絶対言っちゃうけど、傷つくらしいですよね。
 島影
島影そうですね。ご本人にとっては「2階に他人がいる」が真実なので、否定されると傷つくんですよね……。そして「否定された」「傷つけられた」という気持ちは、認知症であってものちのちまで残りやすいと言われています。
私は、お義母さんがどこまで「天然」なのかわからないまま介護を通じてサポートに入るようになったんですけど、夫婦のおもしろトークには笑わせてもらいました。
例えば、貴重品の入っている引き出しがいくつかあって、夫婦でカギを共有している引き出しからはよくモノがなくなるんですね。
でも、別の引き出しから、なくなったはずのハンコがティッシュにきれいにくるまれて出てくるんです。それをやるのはお義母さんしかいないんですけどね。
もちろん、お義父さんしか鍵を持っていない引き出しからはモノはなくなりません(笑)。
介護に関する手続きはすべて自分で
 くらたま
くらたま気になったんだけど、なぜ介護の主体が実子ではないの?
 島影
島影いちばん最初に地域包括支援センターに相談に行くことになったとき、夫は地方出張で都合がつかず、わたしと義姉で行ったんです。
まずは介護の窓口になる「キーパーソン」を決める必要があると言われたんですが、なかなか決まらなくて……。
つい、「私が引き受けましょうか。平日動けますから」と言っちゃったんですよね。
 くらたま
くらたま勇気ある行動ですよ。実子が2人もいるんだから、島影さんは「大変ね」でいいと思うけど。
 島影
島影なんとなく状況が錯綜しそうだなという予感はあって「これは中心にいたほうがむしろ安全かな」と直感的に思ったんですね。仕事の経験上、炎上しそうな案件はプロジェクトの中枢にいるほうが安全というのがあります。
「情報を人づてに知るよりも、自ら把握できたほうがストレスは少ない」という理由が挙げられる。ただ、実は長女にありがちな「わたしがやらなきゃ、誰がやる」マインドが発動しちゃっただけのような気もする
(『子育てとばして介護かよ』P58より引用)
 くらたま
くらたまなるほど。他人任せにしてとんでもないことになる前に、自分で……と。
 島影
島影はい。「介護は実子がやるべき」にこだわって見て見ぬフリをした結果、のちのち大変な思いをするよりは、さっさと関わっちゃおうと(笑)。
認知症は初期対応が大切なので、きちんと診てくれるドクターを探すとか、長期的なことも視野に入れて介護保険制度を利用するとか、そういうことを戦略的にやっておこうと思いました。
 くらたま
くらたま介護に限らずだけど、最初に手をあげるのは大変よね。でも、本を読んでいると、ご家族は明るい人たちだから、悲壮感が漂ってないというか、「困ったな」と思いながら笑っちゃうところもありますね。
 島影
島影そうですね。今回は、「私がやります」的な性格がすごく出ちゃったんですけど、面白いことも多いですね。
例えば認知症の検査でも、お義母さんは聞かれたことに対して「そんな試すようなこと、お答えしたくありません」とピシャっと断るんです。
わからないのをごまかしているのかもしれないけれど、初対面の相手に記憶力を試されるのは確かに不愉快だし、ごもっとも!と。
 くらたま
くらたまそういう診断とか介護保険の手続きは、島影さんが全部したの?
 島影
島影そうですね。仕事柄、制度や手続きを調べるのは得意だし、興味のある分野でもあったので、かなり前のめりになってやっていました。
 くらたま
くらたまさすがだね。旦那から「助かるよ」的なことは言われたの?
 島影
島影感謝の言葉よりも、「そこまでやらなくてもいい」とも繰り返し言われたことのほうが印象が強くて……。あとから聞いた話では、本人は「申し訳ない」と思っていたそうです。それが私にも伝わっていると思ってたというんですが、あんまりピンとこなかったですね。
 くらたま
くらたまそんなもんよねー。
 島影
島影夫は以前から「両親の老後を見るつもりはない。かかわりたくない」と言っていたのに、わたしが勝手に介護のキーパーソンを引き受けてしまったという負い目もあって。
介護を通じて夫との関係も変化
 くらたま
くらたま本からは悲壮感はないけど、離婚も考えたんですよね。
 島影
島影そうなんです。介護については、夫に対してちょっとずつ失望していきました。それまでは、いろんなことを話し合えると思ってたのに、言えなくなってしまったつらさがあったんです。
介護をしたくなかった夫をさしおいて、私が勝手に引き受けてしまったから。
 くらたま
くらたま意味わかんないけど……。
 島影
島影いつもは相談すると、打てば響くような答えを出してくれるんですが、介護については違うんですね。
私も、ほかの話題だったら、「今、こういうことで困ってるから、一緒に考えて」と言えるのに、介護のことだけは「別枠」になっちゃって……。
 くらたま
くらたま彼にストレートな物言いができなくなっていたのね。
 島影
島影そうなんです。今振り返ってみると、夫も初めての介護に戸惑っていたのだとわかるんですが、当時のわたしには、黙り込む彼の姿がとてつもなく不機嫌そうに見えて……。そんな人と話すのはイヤじゃないですか。「だったら自分でやればいいや」と。
何でも言えると思っていたのに言えないのは、付き合いが長いからこそショックでした。
 くらたま
くらたま彼の感覚のほうが、わかるかもしれない。やっぱりかかわりたくない部分は大きかったんじゃないかな。
 島影
島影夫は、私に対して「自分の代わりに介護をやってほしい」ではなく、「仕事もあるんだし、無理して一時の情でかかわらなくてもいい」と思っていたらしいんです。
むしろ、早々に私がギブアップするという想定で、慰めるつもりでいたと、あとから聞きました(笑)。
「介護はできなくていいんだ。僕たちには僕たちの生活があるんだ」と。
 くらたま
くらたまその目論見がはずれたわけだね。
 島影
島影いろいろ介護体制を整えていく私に対して、「大変だからやめればいいのにと思いながら見ていた」時期を経て、「いろんなことをやっている私を孤立させてはいけない」という気持ちが強くなっていったようでです。
ちなみに、私が夫の実家に行くときはついて来てくれるし、病院の外来も一緒に行ってくれるのに、夫が一人で実家に行くことはないんですね。
そのことにずっとモヤモヤしていたのですが、彼は「親の面倒をみるために」ではなく、「私のフォローをするために」ついて来てくれていたんです。
 くらたま
くらたまそれは、あとになってわかったことなの?
 島影
島影介護を進める中で、もしや?と思って、質問してみたらビンゴでした。その発想はなかった!とビックリしましたが、おかげでモヤモヤが薄れました。
 くらたま
くらたま親の介護って、夫婦間の関係性にも影響するね。この経験を経て旦那との関係性は変わった?
 島影
島影変わったと思います。
介護については「自分の親なのに無責任だな」と思ってしまっていたんですが、いろいろ話してみて、彼なりの「理屈」がわかったんです。
それに、「この日は私は都合が悪いから、代わりに付き添いに行って」というところまでしっかり言語化して相談すれば、夫もアクションを起こしやすい。こっちのペースで「すぐ返事がないのは無理という意味」と決めつけず、相手が調整してくれるのを待つのも大切だなあと。
今後、介護以外でも言いづらいことが出てきたときは、これを応用すればいけるなと思っています。
 くらたま
くらたま夫婦を変えてくれたわけね。
 島影
島影そうですね。「一緒に年を取って大丈夫」と思えるような……。いろいろ話すうちに、この人は若い頃からそんなに変わってないんだと気づきました。
周囲に助けを求めるのにも気力がいる。だからこそ、周囲へのSOSは早めに伝えたほうがいい
(『子育てとばして介護かよ』P170より引用)
 くらたま
くらたま全般を通して、そんなに悪いハプニングではなかった?
 島影
島影そうだと思います。もちろん、急な入院など介護の「個々の大変さ」はあります。はじめてのことが次々と起こりますが、決定的に義父母に傷つけられることもなかったんです。
 くらたま
くらたまそれは、皆さんのお人柄なのかな?
 島影
島影そうですね。やりとりの中で、「義父母の気持ちをいかに傷つけずに話をするか」は、かなり強く意識しています。例えば、「認知症だから」「年をとってできなくなったから」を理由に説得をしようとしないとか。
 くらたま
くらたま私は、相手の親でも否定しちゃいそう…。
 島影
島影親が元気なうちは、つい余計なひとことを言ってしまいがちだったりもしますよね。私も、自分の親に対しては、今は「練習中」ですね。
 くらたま
くらたま「練習」って、いいね。
 島影
島影母親に何か言われてカチンと来たり、「そうじゃなくて!」と言い返したくなったときも、なるべくお義母さんとのやりとりを思い出して、「そうだね」から入るとか。
 くらたま
くらたま勉強になるわー。
 島影
島影もちろん、その瞬間はすごいストレスですよ(笑)。でも元気なので練習しやすいんです。つらくなってきたら、「宅配便が来たから」って3分くらいで電話を切ってもいいじゃないですか。
 くらたま
くらたまウソ宅(笑)。クールダウンはいいね。親に対する「導火線」は短いもんね。
お金問題は「手続きのお手伝い」で解決
 くらたま
くらたま介護では、お金の問題って大変でしょ?どう解決したの?
 島影
島影最初の頃は、誰もお金については触れないままで、私たち夫婦が立て替えていたんです。
 くらたま
くらたまだとしたら、旦那に言わないと。
 島影
島影「お義父さんたちに、話してほしい」とは言ってました。
 くらたま
くらたま旦那は何て?
 島影
島影「折りを見て」って……(笑)。
困っていたところに、介護サービスの利用料の銀行口座引き落とし問題が出てきました。
お義父さんが契約していたんですが、申し込みで使った印鑑と銀行の届け出印が違っていたようで、あちこちから「引き落としができない」と連絡が来てしまって。
そこで、「引き落としの手続きをお手伝いする」ということにしたんです。私たちが「払いたいと思ってる」と誤解されたらまずいですから。
それで、お義父さんの説得方法を夫婦で念入りにシミュレーションしたんです。
 くらたま
くらたま島影さんは、ほんとうに気を遣う人だね。
 島影
島影お義父さんはすごくまじめで、以前は自分で確定申告もしていたんです。それをいきなり「預かる」って言われたら、不愉快だろうなと思ったんです。
そこで、「支払いの手続きは、私たちに手伝わせてほしい」と伝えたら、「頼むよ」って言われたので、記帳は私が担当して、残高がわかる通帳の一覧表を作りました。
 くらたま
くらたまそれってとても大事ね。
 島影
島影生活費は、お義父さんから指示してもらった金額を引き出して、日付と金額を書いた封筒に入れて、渡すようにしました。月に1回、通帳の一覧表をお義父さんに見せながら報告会もやって。経理部の部長と部下みたいな関係ですね。
 くらたま
くらたまそれでお金問題は解決?
 島影
島影そうです。生活に不具合がないようにジワジワとやった感じです。
 くらたま
くらたま今はお義父さんたちはどうしているの?
 島影
島影今は有料老人ホームで生活しています。
お義父さんたちが今の生活が厳しいと思っている状態で施設に入ってもらえたので、よかったです。子どもたちの都合だけで強制的に施設に入れたらだめですね。
 くらたま
くらたま反発するよね。
 島影
島影「納得のツボ」を探すということですね。それは親御さんによって違うと思います。
施設は、いろいろなところを見て、最初にかかるお金や毎月かかるお金などをシミュレーションして決めました。
 くらたま
くらたますごい!施設では一緒の部屋で生活しているの?
 島影
島影同じ階ですが、部屋は別々なんです。お義母さんは、自分がもの忘れをすることはケロリと忘れて、「最近、お父さまの物忘れがひどい!」とお義父さんを責めるので……。
あと、時間の感覚があいまいになってきていたこともあって「お茶はいかが?」「甘いものを食べる?」と、しょっちゅうお義父さんをかまうので、お義父さんが疲れてしまっていたんですよ。
施設に入ったら、お義父さんはリラックスできるようになったせいか、見違えるように元気になりました。
 くらたま
くらたまお義母さんと離れたから?
 島影
島影そうですね。マイペースに過ごせる時間が持てたことに加えて、栄養状態が改善されたことが大きかったのではないかと思います。
施設に入ると認知症が進むと聞いていたのに、状態が改善されるケースもあるのかと驚きました。
 くらたま
くらたま食べるのってやっぱり大事なことなんだね。
 島影
島影「食事がおいしい」というのは、入所後の納得感にもつながりますね。
お義父さんは施設に入ってしばらくすると、「実は僕はお母さんとは味の好みが合わない」って言い出して(笑)。
 くらたま
くらたまずっとガマンしてたんだね(笑)。
 島影
島影お義父さんは、今は入院中なんですけど、「退院したら、また施設のおいしいごはんを食べられるな」ってとても楽しみにしてくれています。
- 撮影:荻山 拓也

島影真奈美
1973年、宮城県仙台市生まれ。ライター・編集者。マンガ大賞選考委員。 国内で唯一「老年学研究科」がある桜美林大学大学院に社会人入学した矢先に、夫の両親の認知症が立て続けに発覚。「介護のキーパーソン」として別居介護に参戦。 現在も仕事・研究・介護のトリプル生活を送る。「もめない介護」「仕事と介護の両立」「介護の本音・建前」「介護とお金」などをテーマに広く執筆を行う。近著に『子育てとばして介護かよ』(KADOKAWA)、『親の介護がツラクなる前に知っておきたいこと』(WAVE出版)。