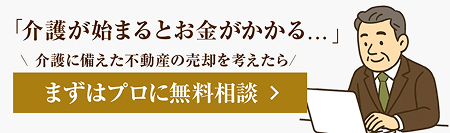まずは、お母さまが倒れられたところからお話をお聞きしてもいいですか?
今回のゲストは、タレントの新田恵利さん。新田さんは、元「おニャン子クラブ」のメンバーとして80年代から活躍。実母の在宅介護の様子を昨年9月に上梓した『悔いなし介護』に綴っています。対談では、寝たきり状態の母の介護を幸せだったと振り返る理由を漫画家くらたまがお聞きしました。親子の絆を感じるお見送りのエピソードには、くらたまも思わず涙…。
- 構成:みんなの介護
元おニャン子新田恵利さんによる介護記。突然始まった在宅介護から6年半、要介護4の母を兄とともに自宅で介護した様子や心情を「介護のお役立ちポイント」もまじえて執筆。つらくなり過ぎず、後悔を残さない介護の心得を考える上でも役に立つ一冊。
骨粗しょう症で退院時には寝たきりに
 くらたま
くらたま 新田
新田母は30年以上前に骨粗しょう症の診断を受けていたんです。骨粗鬆症について詳しい知識が広まっていない時代でした。自分たちにできることは、骨にいいものを食べるぐらいでした。しかし、骨粗しょう症が原因で初めて骨折をしたとき、息をするのもつらい痛さで「骨粗鬆症による腰椎の圧迫骨折」と診断を受けて入院しました。
その後、2回ほど腰椎の大きな痛みに襲われています。その頃は、痛みとの付き合い方がわかっていたので、自宅で療養していました。そして2014年に「入院したい」とまた母が言い出しました。母は良い年齢だったし、私も10年ぶりの舞台のお仕事に必死だったので、入院して診てもらうことにしたんです。

でも、退院したときには立つことすらできなくなっていました…。入院前、痛くても壁伝いで歩けていたにもかかわらずです。病院選びを間違えたんです…。
ウチだけかなと思ったんですけど、いろいろな人の話を聞くと、病院の中にはハズレがあることがわかってきました。数年前にお世話になったときは、すごく良い病院でしたが、経営難で体制が変わったみたいで。
 くらたま
くらたま最初は良かったけれど悪くなってしまうことって結構ありますからね。病院は本当に当たりハズレがあります。ハズレの率もまあまあ高いこともありますよね…。
 新田
新田そうですね。そして急に介護が始まりました。入院する前に介護が必要だとわかっていたら施設を探したかもしれないし、何らかの準備をしたと思うんです。
でも、退院する直前に初めて立てないとわかったから選択の余地はなかった。とりあえず家に連れて帰らなきゃいけない。ちょうど兄が病院に来ていたのですが、介護の知識もないまま母を兄と一緒に運んでタクシーに乗せました。
そして、家に着くなり慌てて地域包括支援センターに電話したんです。そしたら、当日にもかかわらず30分で来てくれておむつのつけ方を教わりました。そこから突然介護が始まったんです。
私は17歳で父が急死した時、後悔しかありませんでした。思春期でしたから父との関係はあっさりしたものです。親孝行どころか、ふたりだけでゆっくりと話をしたことさえありませんでした。その時に誓ったのです。母にはできる限りの親孝行をしようと。
(『悔いなし介護』P14より引用)
突然始まった兄との在宅介護
 くらたま
くらたま心の準備も何もないですね。恵利さんが住んでいるおうちにお母さまも戻られたんですか?
 新田
新田家を建てたとき、二世帯にして母を呼んでいました。兄は独身だったので私の家に一緒に住んでもらって在宅介護することにしたんです。
 くらたま
くらたまそこからずっとお兄さんも一緒なんですね。私も妹が一人いるんですけど、年とってから姉妹で一緒に住むのっていいですよね。夫婦仲が悪いのに一緒に住んでいることでつらい思いをしている人の話をよく聞きます。
 新田
新田同性ならなおさら良いかもしれませんね。
 くらたま
くらたまお母さまは、頭は冴えているのに、動けない状態でおつらかったでしょうね。
 新田
新田そうですね。母は動けなくなる前、旅行が大好きでした。国内や海外のいろいろなところに出かけていたんです。犬の散歩をしたり知らない人とお喋りしたりも好きだったので、急にベッドの上だけというのはつらかったと思います。
でも「なんで歩けなくなったんだろう」とか、愚痴は1度も言わなかったです。前向きに過ごしていました。その明るさには無理がありませんでしたね。悪く言えば、能天気だったと思います。
 くらたま
くらたまずっと動けないままだったんですか?
 新田
新田最初は要介護4だったので、ベッドの縁に座らせたら、ゴロンってそのまま転がるような状態でした。でも訪問リハビリのおかげで1年後には要介護3になりました。自分でベッドから車椅子に移ってトイレにも行けるようになったんです。
 くらたま
くらたま訪問リハビリも頑張られていたんですね。恵利さんは、途中でお母さまを施設に入れるということは考えなかったのですか?
 新田
新田それが、施設という方法があることに気づかなったんです。在宅介護をするのが当たり前になっていたから何も考えていませんでした。介護が始まって3~4年目くらいに、「施設を考えなかったんですか?」って今みたいに聞かれて、初めて気づきましたね(笑)。
それに、母に聞いても「家がいい」って言っていました。「私かお兄ちゃんかどっちかがギブアップしたら、またそのとき考えよう」と兄と話して、そのまま在宅でいました。私一人では母を支えられなかったと思います。
 くらたま
くらたまお兄さんはどんなふうにお母さまの介護をされていたんですか?
 新田
新田母が使っていた寝室に兄が寝て、居間だったところに介護ベッドを置きました。その2つの空間は、障子を開けると一間になります。閉めればプライベート感があるんですけど、兄は閉めようとしなかった。母が兄にずっと何かを話しかけていましたね。兄は「うんうん」って返事はするけど、何も聞いていない。
 くらたま
くらたまちょうどいい距離感ですね。すべてを聞き過ぎるとお兄さんのストレスにもなりそうだから。

 新田
新田そんなんですよ。兄は適度に右から左に聞き流すことができるタイプだったので、うまくいったんじゃないでしょうか。
最期の方は認知症もひどくなっていました。お水を飲ませたら、すぐにまた「お水」って言うんです。1分も持たなくなっていました。
「今日は何曜日?何日?」と試すような質問もやめて、ありのままの母を受け入れようと決めました。色んな意味で母が母ではなくなってきたり、親ではなくなっていくことは悲しく辛いことです。幼い頃からずっと話を聞いてくれた母親は、今はもう自分のことばかりを話すようになりました。
(『悔いなし介護』P170より引用)
兄は独身だったので、母との間に奥さんや孫が入るようなこともありません。仲が悪いわけではないんですが、中和剤になるような存在がいないこともあり、母との会話がなかったんです。
でも介護が必要になってから、母が兄を頼るようになって会話が増えていきました。あるとき、「仕事に行ってくるよ」と言って兄と母がハイタッチしている様子を見たんです。嬉しかったですね。私が見ていても、在宅になって兄と母の絆がとても深まったと感じます。
 くらたま
くらたま介護によって得られた関係性だったのですね。
身体介護は母の明るさに救われた
 くらたま
くらたま恵利さんが介護で一番しんどかったこと聞いてもいいですか?
 新田
新田しんどかったのはやっぱりニオイかな。母は体調が悪いとすぐに下痢になっていました。かわいそうだから「おえっ」て言うのはやめようと思うんですけど、ニオイがきついからどうしても出ちゃうんです。そしたら母が笑いながら「そんなにくさい?」って。
もし、そこで「ごめんね、ごめんね」って泣きながら言われると、「大丈夫!」って言うしかなかったと思うんです。
 くらたま
くらたまそうならず、笑いにできたのが良かったんですね。
 新田
新田そこで、「当たり前でしょ。ママは自分のだからそんなくさくないと思ってるかもしれないけど、くさいよ~」って言ったんです。そしたら「ごめんね~」って明るく言っていました。それに救われましたね。

 くらたま
くらたま恵利さんとの信頼関係ができているからこそのやりとりだと感じます。
 新田
新田そうですね。母が元気な頃からの親子の会話がずっと続いていました。
「ありがとうと言って死ぬからね」の約束を守った母
 くらたま
くらたま最期はお看取りまでされたんですね?
 新田
新田ええ。でも、本当の最期の瞬間は兄一人でした。まさか母のそばを離れて数十分後だとは思っていなかったので、私は二階でお昼を食べていたんです。
そしたら家の中のインターホンが鳴って兄に呼ばれました。私が母のそばを離れた20分後ぐらいのことです。この日は、朝から母の様子がおかしかった。兄のインターホンで「危ない」ということがすぐにわかりました。そして、階段を駆け降りて母のところに行ったら、ほんの1~2分前に息を引き取ったあとでした。
 くらたま
くらたまそうだったんですか…。最期はどんな会話をされたんでしょうか。
 新田
新田二階に上がる前、母に声をかけたらまだ目が開きました。そのとき、右にいた私と左にいた兄を順番に見て、「あー、あー」って言ったんです。「ありがとう」って言おうとするけど、言えなかったのだと思うんです。
母は元気なとき、「私はこれだけ恵利にみてもらったから、ありがとうって言ってから死ぬからね」って約束してくれていました。その約束を守ってくれたと思います。まさか「あー、あー…飴食べたい」とは言わないと思うので(笑)。
私と兄を確認して、言葉を発しようとして発せなくて目をつぶったのが多分最期です。
 くらたま
くらたま言葉が伝わらなくても心が通じ合っていたんですね。恵利さんが明るく話すから…逆にこみ上げてくるものがありますよね。あー、何だか私まで泣けてきました。
母が望んだ最期のウエディングドレス
 くらたま
くらたまお見送りにもお母さまへの思いを込められたのですか?
 新田
新田ええ。特に死に装束にこだわりました。母がまだ元気だった頃、2人でテレビを見ていたら、死に装束の番組をやっていたんです。「ママあれ着たい?」って聞いたら「いやよ」って言うんです。「気に入った着物を着せるっていうけど、ママとくに気に入った着物もないし、何着せればいいの?」って聞きました。
 くらたま
くらたまそこまで踏み込んで話しをしていたとは(笑)。いい親子関係だなぁ。
 新田
新田若いうちからそういう話をしてたんですよー。そして、しばらくしてから母が「ウエディングドレス」って言ったんです。「そっか、昭和一桁生まれはウエディングドレス着てないからなー」と思いました。
 くらたま
くらたまずっと憧れがったのかもしれませんね。
 新田
新田そう思います。その場では、ドレスを売っているお店が浮かんで「あそこで白いのを買っておけば大丈夫だな」って思いました。でも、いよいよ母の最期が近づいてきたとき、死後硬直がある中でウエディングドレスを着せる難しさがあることに気づいてハッとしました。
そして、ネットでいろいろな情報を見ていたらガウンタイプのドレスを見つけました。「これなら自分でつくれるわ」と思ったんです。
 くらたま
くらたまえっ!ウエディングドレスを自分でとは驚き!
 新田
新田実は私、ハンドメイドとDIYが得意なんです。母が亡くなる半年ぐらい前からドレスをつくり始めました。でも、完成させたら死んじゃう気がして…。8割ぐらいで止めていたんです。
そして、もうつくらないと死後硬直始まっちゃうと思って、泣きながらミシンを踏んで完成させました。そして、母に着せてお見送りしたんです。そしたら、周りの人が「すごく良いね」ってほめてくれて…。母の望みだったウエディングドレスで見送れたのは私にとっても幸せでした。でも、唯一悔いが残るとしたら、母自身が見ていないことです。
 くらたま
くらたまお母さま、見せたかったですね。
 新田
新田スピリチュアル的に言ったら身体から抜けて見ていたかもしれないですけどね(笑)。
ドレスは、あまりにもみんなが喜んでくれたので「ほかの方ももっと素敵なドレスで見送れるようになったらいいな」と思いました。介護やお見送りってシニアだけのものじゃないじゃないですか?
最期が素敵なドレスだと、若くして亡くなる女性もきれいに見送れます。そんな思いから、来年母の一周忌に「最期のドレス」のブランドを立ち上げようと今動いています。
 くらたま
くらたますごいなー。いろいろなことをされているんですね。

 新田
新田倉田さんは、ご自分がもし明日死ぬとしたら何着ます?
 くらたま
くらたまえっ?何だろう。考えたことなかったです。
 新田
新田私も。「考えてみたら私、最期に着たいものない!」って思ったんです。
 くらたま
くらたま死に装束については、考えていない人が多いですよね。この連載でも初めて話が出ました。
 新田
新田そうですよね。私も、母とたまたまテレビを見ていたから、死に装束の話になったんです。
 くらたま
くらたまそれもお母さまが残したものの一つですよね。お母さまと話したことが心に残っていて、新しいことにつながっているわけだし。
 新田
新田そうですね。一つひとつの思い出や生き方として、私の中に母は生きているー。そう感じます。
在宅介護だから自然と母の死を受け入れられた
 くらたま
くらたまでも、なかなか得がたい経験をされましたよね。最初は普通にお話ができていたお母さまがだんだん弱っていく。施設に入っちゃったらわからないけど、ずっとその変化の過程を見られていたんですね。
 新田
新田許される環境だったら「在宅はいいですよ」って勧めたいですね。毎日見るから親の死をちゃんと受け入れられる。たまにだと、会うたびにショックじゃないですか。
 くらたま
くらたまどんどん弱っていきますからね。私も祖母のときは、ショックだったなぁ。たまに帰ると別人みたいになっていたから。なんか、また会うの怖いと思っちゃうんですよね。
 新田
新田だけど、毎日のことだと受け入れざるを得ない。覚悟ができていきます。
 くらたま
くらたまたしかに。でも、お兄さんが独身でいてくれたりお家があったりと、いろいろな環境が整っていたのが幸いしましたよね。
 新田
新田そうですね。母の介護があって、兄が独身でいてくれたことに感謝しました。

 くらたま
くらたま恵利さんは、介護のつらさはどうやって乗り越えられたんですか?
 新田
新田最初は、母のためにと思って必死で頑張って介護をしていたんです。でも、潰れそうになって手を抜くことを覚えました。それから何年か介護をしていくうちに、やっぱり自分に後悔のないように母の介護をしようと思ったんです。
 くらたま
くらたま結局そこですよね。
 新田
新田そうですね。母の介護が自分のための介護になりました。父のときは親孝行できないまま急死だったので後悔が残ったんです。
 くらたま
くらたまお父さまへの思いがお母さまの介護の原動力にもなっていたのですね。
 新田
新田ええ。それにもし母が泣きながら毎日暮らしていたら、私も戸惑って重い気持ちに引きずられていったと思います。でも、明るい気持ちで生き続けてくれた。最期は、介護ができて幸せだなって思わせてくれたので感謝しています。
- 撮影:丸山剛史

新田恵利
埼玉県出身。1968年生まれ。社会現象にもなったテレビ番組『夕やけニャンニャン』(フジテレビ)に出演。おニャン子クラブのメンバーとして人気を集める。1986年ソロ・レコードデビューとなった「冬のオペラグラス」は、30万枚を超える大ヒット。2014年に要介護4の実母の在宅介護を兄とともに始める。現在は、タレント・女優・執筆のほか、自身の介護経験をもとにした講演や介護に関するものづくりのプロデュースなど活動の幅を広げている。