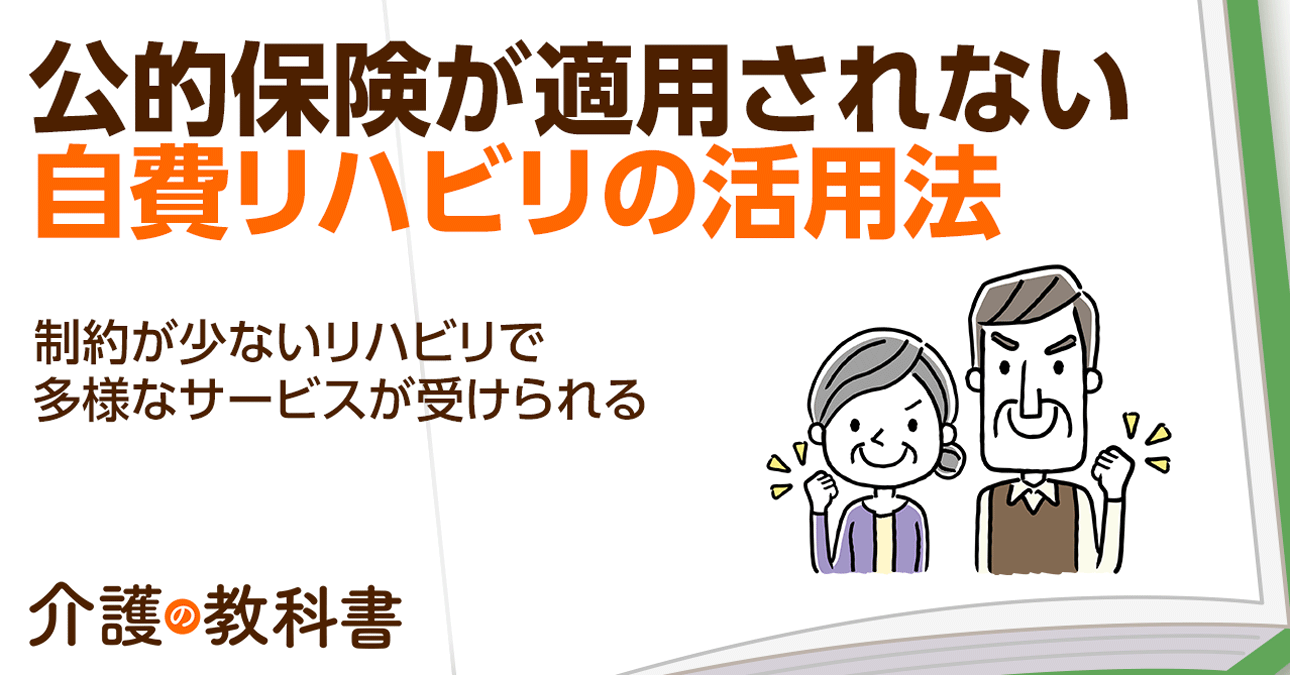こんにちは。理学療法士ブログ「リハ塾」を通じて専門的な体の知識を発信している、運動指導の専門家・理学療法士の松井洸です。
今回は、バランス感覚の観点から見たリハビリテーションについてご紹介します。最近、段差のないところで転倒しそうになりかけた方、体が思うように動かないような…と感じる方、感覚が鈍くなっている可能性があるのでぜひ、参考にしてみてください。
以前、転倒についての記事をご紹介しましたが、介護が必要になった理由の第5位に転倒がランクインしています。割合にすると、約4人に1人は過去1年間で転倒経験があるというデータがあります。
転倒する理由を考えると、バランス感覚が低下しているからという背景があります。本記事では、バランス感覚とはそもそも何なのか?簡単にバランス感覚を測る方法、バランス感覚を良くするリハビリをご紹介します。
バランス感覚?3つの感覚が作用して姿勢を保っている

そもそも、当たり前のように使われている「バランス」という言葉、どういったものなのかご存知ですか? 人が両足で接地している場合、両足のつま先から踵(かかと)とその間の空間を「支持基底面」。その支持基底面から体が大きく外れないように制御する能力のことを「バランス」と言います。
要するに、姿勢を崩さずに制御することを指しており、上手く制御して姿勢を保持できることをバランス感覚が良い、保持できない場合をバランス感覚が悪いと言ったりしています。バランス感覚には視覚、前庭覚、体性感覚の3つの感覚が作用して成り立っています。
視覚は、目からの情報を処理、周囲の段差や障害物などを目から認知しています。
前庭覚は、揺れ、回転、スピードを感知、これが機能することで揺れや回転刺激に体が反応して姿勢を保持することができます。
体性感覚は、視覚や聴覚を除く、皮膚感覚、深部感覚、内臓感覚のことを指します。熱い、寒いなどの温度やふれる、つねるなどの圧や痛み刺激の表面的な感覚を皮膚感覚、足元を見なくても階段を降りることができるように手足の位置がなんとなくわかる感覚を深部感覚と言います。
皮膚感覚が障害されると、外部からの刺激を取り入れることができないため、障害物に当たってもわからないなど周囲の環境に適応できなくなり、深部感覚が障害されると、手足の位置がわからないため、無意識的な姿勢の制御ができません。体中に力を入れて無理やり姿勢を保つようなバランスの取り方になってしまいます。
これら3つの感覚情報を正しく感知できるからこそ、その情報を元に筋肉や関節を動かして姿勢を保持することができます。感覚情報が正しく感知できないということは、暗闇で手足もどこにあるかわからない状態で「倒れずに立っていてください」と言われ、姿勢を保持することができないということ。感覚を正しく感知できること。感覚情報を元に適切に筋肉や関節を動かすことができる能力がバランス感覚が良い状態です。
転倒する方はバランスが悪い状態を表している

簡単に言えば、バランス感覚が悪い方は転倒しやすいということになります。バランスが悪いというのは、外部からの感覚を感知しにくい、感知しにくいからどう姿勢を制御していいのかわからないので転倒してしまうという流れです。では、バランス感覚を悪くしてしまう要因はどのようなものがあるでしょうか? 以下にまとめています。
- 支持基底面が狭い(立ったときの足幅が狭い)
- 前傾姿勢(背中、腰が曲がっている、膝が曲がっているなど体が前に傾いている姿勢)
- 筋肉が過剰に緊張している状態(特に足の筋肉)
- 視力の低下
- めまいが起こることがある
リハビリによって介入できる部分は、上から3つの要因。支持基底面が狭いというのは、関節の動きが悪く、動く範囲が制限されている、筋肉に柔軟性がなく関節の動きが制限されている、このような要因から足を広く開くことができないことが考えられるでしょう。
前傾姿勢というのは、関節自体が動きを制限されていて姿勢が固定されている、筋力が弱く姿勢を真っ直ぐにすることができないのが理由でしょう。背中や腰が曲がると体は前かがみになり、そのままでは前方に倒れてしまうため、バランスをとるためにお尻が後方に膝が曲がるという流れになり、この姿勢自体も倒れないようにバランスをとった結果とも言えます。
筋肉が過剰に緊張している状態というのは、緊張しすぎて感覚のセンサーがうまく反応しない状態。筋肉には今緊張しているのか、緩んでいるのか感知するためのセンサーが備わっており、これがあることで、状況に応じて筋肉を緊張させたり緩めたりすることができます。
もしバランスを崩しても、とっさに筋肉を緊張させたりすることができるので、私たちは転ばずに姿勢を保つことができます。常に筋肉がガチガチに緊張しているのは、センサーが反応していないため、緊張しているのか緩んでいるのかわからない状態。わからないから、常に筋肉を緊張させるという方法でしか姿勢を制御できないのです。
この状態では、筋肉の状態を柔軟に変化させることが難しいため、転んでしまうリスクが高くなります。リハビリによって、筋肉や関節の状態を整えることでバランスを崩しても、すぐに対応できるよう余裕のある体づくりをすることが大事です。
バランス感覚の良し悪しをチェック!(動画付き)

リハビリでも用いる、自宅でも簡単にバランス感覚を評価できる方法を3つご紹介。 複数のテストが当てはまるほど、バランス感覚はより低いことになります。 必ず周囲に障害物などない状態に環境を整えてから実施してください。
ファンクショナルリーチテスト
- 足を肩幅に開いて立つ
- 両腕を肩の高さまで挙げる
- 足を前に出さないように、指をできるだけ前へ伸ばす
3回測定して最後の2回の平均した値を採用する。
バランス感覚低下の基準
18.5cm
18.5cm未満の場合、バランス感覚低下の可能性があります。
両腕を肩の高さまで挙げ、前に出しながら手先を伸ばし、指先がどのぐらい前に動くか。その動いた距離を計測します。わかりづらい場合は、下にある「自宅でできるバランス感覚の評価」の動画、0分00秒から0分44秒を見てください。
片脚立位テスト
- 両手を腰に当てる
- どちらか一方の足を持ち上げ、片脚で立つ
- 腰から手が離れる、立っている方の足がずれる、立っている方の足以外の体のどこかが地面に着いた時点で測定終了
測定時間は60秒または120秒までで終了とする。左右の足、それぞれ2回ずつ測定して良い方の値を採用する。
バランス感覚低下の基準
40歳代→180秒
60歳代前半→70秒
80歳代前半→10秒
それぞれの年齢に応じた基準値より下回る場合、バランス感覚低下の可能性があり、特に5秒未満の場合は転倒するリスクが高いとされています。
継ぎ足(タンデム)歩行テスト
- 腕を胸の前で組む
- 継ぎ足で歩く
最大10歩までを測定し、継ぎ足が保てない時点で測定終了。
バランス感覚低下の基準
ふらつきなしに10歩可能→正常
7~9歩可能→バランス感覚軽度低下
4~7歩可能→バランス感覚中等度低下
3歩以下→バランス感覚低下重度
バランス感覚の低下を予防するために、リハビリによって介入できる部分は3つ(動画付き)
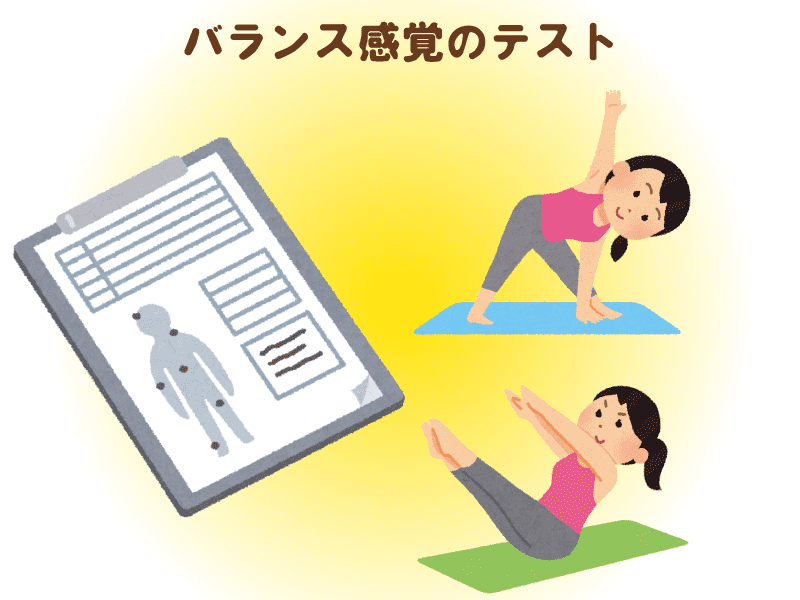
上述しました通り、リハビリによって介入できる部分は以下の3つ。
- 支持基底面の狭さ
- 前傾姿勢
- 筋肉の過剰な緊張
3つに共通する要素としては、筋肉の緊張や柔軟性の低さによって起こる問題であるということ。中でも体幹と足の筋肉がバランス感覚には大きく影響を与えます。体幹の筋肉が弱いと、姿勢を保つことができずバランスを崩しやすいですし、反対にガチガチに緊張していても足と上手く連動して動けないため、これもまたバランスを崩しやすいです。
足の筋肉にも同様のことが言えます。体幹と足の筋肉に着目して、バランス感覚を予防、改善するための自宅でも簡単に実施できるリハビリを以下にご紹介します。
体幹の運動
- 椅子に座る
- みぞおちを軽く押さえる
- みぞおちを中心に腰を丸める、伸ばす
- みぞおちを中心に背中を左右へひねる
- それぞれ10回ずつ程度行う
- ポイント
- 丸めたり伸ばしたりするときは、腰を動かすことを意識
- 左右へひねるときは、背中(胸の真ん中の真後ろあたり)を動かすことを意識
- 肩に力が入らないようにリラックスする
- 素早く動かさず、ゆっくりとできる範囲で動かす
股関節の運動
- 肩幅に足を開いて立つ
- 足の付け根(ビキニラインの真ん中)を指で軽く押さえる
- 押さえた部分を支点に、体を前に倒す
- 元の姿勢に戻る
- 3~4を繰り返す
- ポイント
- 膝は軽く曲げて、踵より膝が前に出ないように注意する
- 目線はなるべく前を見る
- 前方へ倒れるのを防ぐ裏ももの筋肉のハムストリングス、後方へ倒れるのを防ぐお腹の深部から足の付け根に付いている筋肉の大腰筋(だいようきん)を鍛えることができる
バランス感覚のまとめ

- 転倒する理由の1つにバランス感覚の低下がある
- バランス感覚には、視覚、前庭覚、体性感覚の3つが関係する
- バランス感覚を悪くする要因の中でリハビリが介入できる部分は、支持基底面が狭い、前傾姿勢、筋肉の過剰な緊張が挙げられる
- 体幹、足の筋肉の緊張や柔軟性の低下がバランス感覚に影響を与える
いかがでしたか? 自分は大丈夫と思っていても、意外とバランス感覚が低下していることもあります。まずは、今回ご紹介したバランス感覚を測るテストをやってみてください。テストの結果が良好だったとしても、今のうちから予防に取り組むことでバランス感覚だけではなく、より動きやすい体づくりにつながります。
ぜひ、本記事を参考に自分のバランス感覚について、一度考えてみてはどうでしょうか? 最後までお読みいただきありがとうございました。