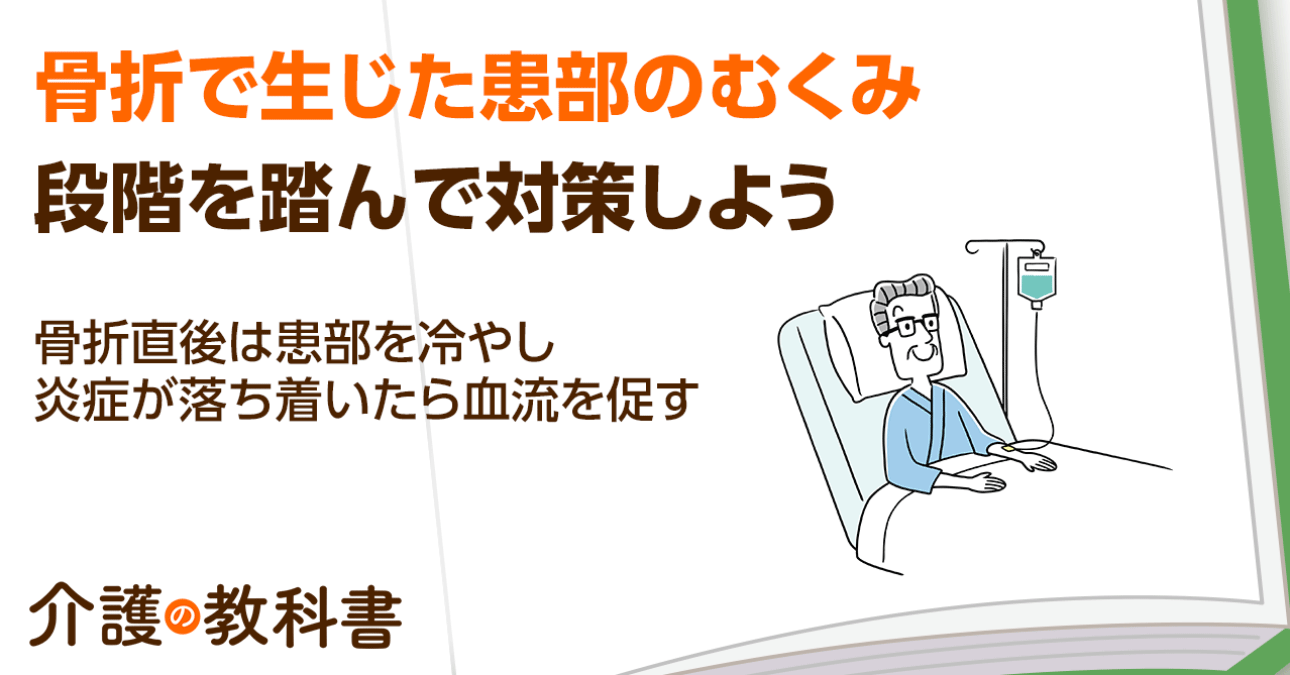東京消防庁が出している「救急搬送データからみる高齢者の事故~日常生活での高齢者の事故を防ぐために~」によれば、救急搬送されている事故の約8割が転倒事故によるものとされています。しかも、その数は年々増えています。
また、『令和元年版高齢者白書』(内閣府)によると、要介護者等について、介護が必要になった主な原因について見ると「骨折・転倒」が全体の12.5%を占めています。
このように転倒する高齢者の割合は比較的高く、骨折は介護の原因にもなることから不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、高齢者はなぜ骨折しやすいのか、高齢者に多い骨折の種類、そして骨折したらどのように対処したら良いか、予防法も含めて理学療法士の視点でお伝えいたします。
高齢者が骨折しやすい理由
高齢者が骨折しやすくなる原因の一つは、骨がもろくなるためです。
骨は、一度成長したらそのままの形を保ち続けると思われがちですが、日々新しく骨がつくられたり壊されたりを繰り返しています。それにより、骨は健康で密度の高い状態を保つことができます。
しかし、高齢者はそのサイクルに歪みが生じ、骨が壊されるスピードが、つくるスピードより早くなってしまうため、骨の密度や量が減少します。これが骨粗しょう症です。
特に閉経後の女性はホルモンの分泌が少なくなることで骨粗しょう症を発症する割合が高くなります。日本では約1,000万人以上の骨粗しょう症患者がいると言われています。
骨粗しょう症の症状と診断
骨がもろくなるだけでは、体に異常を感じることはないと言われています。しかし、骨粗しょう症を発症すると、背中が丸まってくる、腰が痛くなるなどの症状を感じることがあります。また、少しの衝撃で骨折しやすくなるのも大きな特徴です。
骨粗しょう症の診断には、レントゲンや骨密度測定を用います。骨密度が、若年成人と比較して70%未満の場合、骨粗しょう症と診断されます。
高齢者に多い骨折の種類
特に高齢者で注意した方が良い4つの骨折部位
65歳以上の高齢者において、転倒の年間発生率は10~20%で、そのうち約10%は骨折に至るとの報告があります。
転倒した10人に1人が骨折したと考えるとその数は決して少なくありません。そして、高齢者には4つの骨折しやすい部位があると言われています。
- 大腿骨近位部骨折
- 脊椎圧迫骨折
- 上腕部近位部骨折
- 橈骨遠位端骨折
骨盤の下にある左右のでっぱりを大腿骨の大転子と呼びます。その大転子付近の関節で起こる骨折を大腿骨近位部骨折といいます。
足の付け根の強い痛みが特徴で、多くのケースで治療に手術が必要になります。骨折の部位によっては、関節を人工のものに変えることもあります。
背骨の骨折です。背骨は椎体と呼ばれる円柱状の骨が積み重なってできており、その椎体がつぶれたような状態になることを脊椎圧迫骨折と呼びます。
転倒をして尻もちをついた場合などで起こります。ただ、転倒歴がなく普段通り生活しているだけでも圧迫骨折がいつの間にか起こっていることもあります。一般的にはコルセットをして治療を行います。
転んで肩をぶつけたり、手をついたりすることで起こる肩の付け根の骨折です。ギプスやシーネ、スリングなどで固定を行い治療をする方法と、手術で治療をする方法があります。
骨折の程度、年齢、日常の活動量などにより治療法が選択されます。
手首の骨折で、コレス骨折とも呼ばれます。転んで手のひらを地面などに着いた際に起こる骨折です。手首の骨には橈骨と尺骨があり、橈骨だけではなく尺骨も同時に骨折することがあります。
骨折部分のずれがあまりない場合は、ギプス固定で治療を行い、ずれが大きい場合は手術が必要になります。

骨折後の対応と治療
転倒後、骨折しているかどうか、自身では判断が難しいことがあります。しかし、激しい痛みがある場合は骨折の可能性が高いため救急車を呼ぶ、または早期に医療機関を受診しましょう。
その他にも、皮下出血をして腫れている、骨が変形したりくぼんだりしていることがあります。
また、転倒した際に頭をぶつけていることもあるため、吐き気がないか、いつも通り話すことはできるか、歩き方がおかしくないかも合わせて確認してください。
骨折をして、手術やコルセットなどにより治療を進めると同時に、病院では理学療法士や作業療法士によるリハビリテーション(以下、リハビリ)を受けることが多くあります。リハビリには次のような目的とメニューがあります。
【目的】
- 痛みの緩和
- 固まった関節を伸ばす
- 低下した体力や筋力を回復させる
- 体の機能が低下しないための予防 など
【トレーニングメニュー】
- ストレッチや筋力トレーニング
- 立ち上がり練習
- 歩行練習
- 日常生活の動作練習(トイレ、着替え、入浴等)
退院前は、状態に合わせて介護保険の申請を行い、介護保険を使って在宅生活を送るための準備を進めることもあります。
骨折を予防するには
これまで骨折の種類やその後の治療などを見てきましたが、次に骨折の予防法について解説していきます。
転びにくい体づくり
筋力や体力、バランス能力が低下すると自分の体を制御できずに転倒する可能性が高くなります。そのため、日常的に運動をすることが重要とされています。ここで自宅でできる簡単な運動を紹介します。
- ①スクワット
- 両足を肩幅ほどに広げて、足先は少し外側に向けた状態で膝をゆっくり曲げていきます。膝や股関節に痛みがある方は無理せずに、痛みのない範囲で膝を曲げます。10回を目安に行いましょう。
- ②ヒールレイズ
- 立った状態で椅子の背もたれや机に手を置き、かかとを上げてゆっくりとかかとを下ろします。この動作を繰り返します。10回を目安に行いましょう。
- ③片足立ち
- 立った状態で椅子の背もたれや机に手を置き、片足を上げます。その状態で5秒程度止まり、足を下ろします。これを左右交互に行います。
- ④散歩
- 歩くことで筋力や体力をつけることができます。また、屋外を散歩することでビタミンDを生成したり、骨に適度な刺激を加えたりすることで骨が強くなります。
転びにくい環境づくり
また、東京消防庁は高齢者の転倒事故の発生場所のデータも公開しており、救急搬送人員の56%が「居住等場所」となっており屋外での発生件数に比べて顕著に多く、中でも居室・寝室といった生活に慣れている場所での転倒が多いです。例えば、以下のような状況が考えられます。
- 絨毯のへりに足がひっかかる
- 電気コードに足をひっかける
- 暗闇の中でトイレに行こうとしてバランスを崩す など
このように、普段気にしていない場所が転倒の原因になることがあります。そのため、危ない箇所を意識して生活したり、日頃から床を整理整頓したり、暗い場所にはセンサーライトをつけたりして、対応することをおすすめします。
骨粗しょう症の予防
骨粗しょう症の予防には、カルシウムの摂取とカルシウムの吸収を助けるビタミンDの摂取が推奨されています。ビタミンDは日光を浴びることでも体内で生成されるため、意識的に外に出て紫外線を浴びることを意識すると良いでしょう。
また、散歩などの運動によって骨に刺激を与えることで、骨が強くなるという研究もあります。

加齢などにより体力や筋力が低下すると、転倒・骨折のリスクが高くなります。そのため、普段から運動をするように意識し、転びにくい環境づくりを行いながら、バランスの取れた食事を取ることがとても大切です。健康的な日々を過ごせるように、毎日少しずつ取り組んでいきましょう。