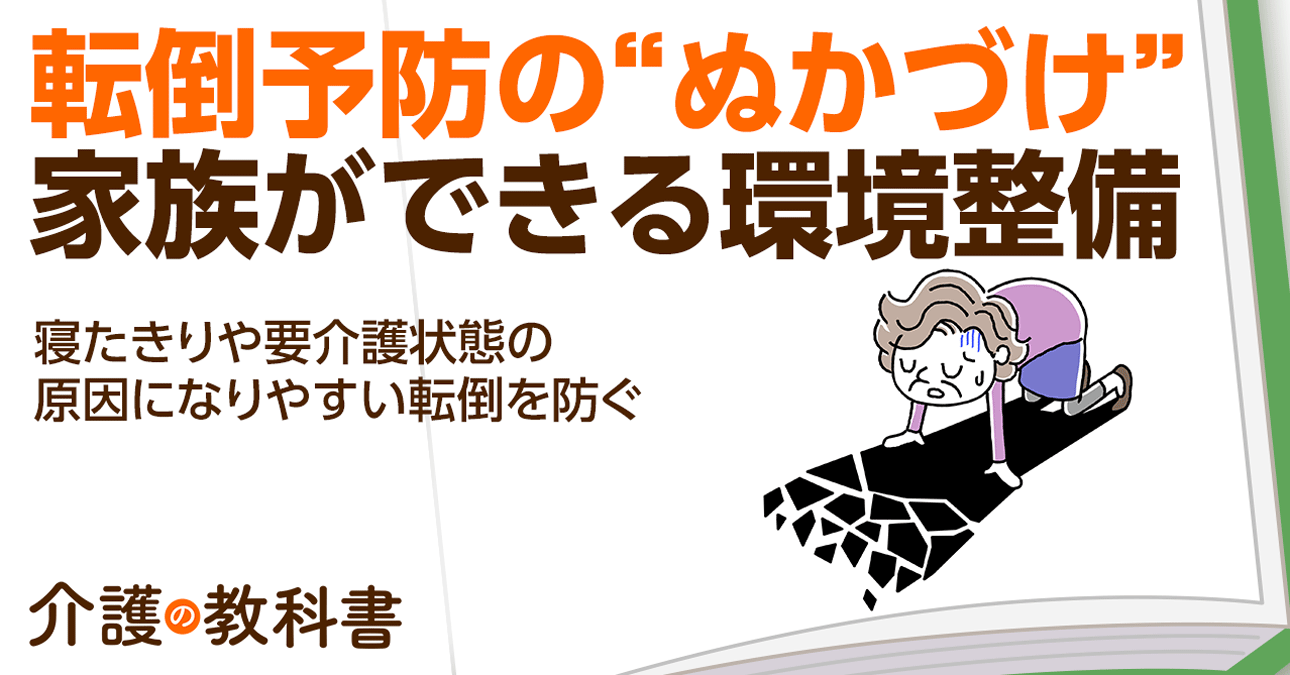高齢者の転倒は骨折など、大きな怪我につながる可能性が高くなります。頭をぶつけてしまった場合、頭に血が溜まり麻痺が出現することもあります。また、転倒が引き金になり介護が必要になることもあります。
「令和3年版高齢社会白書(全体版)」によると骨折・転倒は介護が必要になる原因の13%を占めており、この数字は認知症、脳血管疾患、衰弱にならび4番目の多さになっています。
そこで今回は、転倒予防に注目をしながら、転倒後の対策としてどのようなことを行っていくべきか、再発予防についても理学療法士の視点からお伝えしていきます。
なぜ高齢者は転倒しやすい?
転倒の原因は大きく内的要因と外的要因に分けられます。
- 内的要因
- ①筋力やバランス能力、注意力の低下、姿勢の変化など加齢による影響、②起立性低血圧や脳血管障がいなど、③身体的な影響。睡眠薬や筋弛緩剤などによる薬の影響が挙げられます
- 外的要因
- 段差や滑りやすい場所など環境面のことを指します。高齢者は、加齢による身体的な変化が大きく、薬を服用することも多くなるため、転倒の危険性が高くなってしまいます
そして、高齢者が転倒することで骨折しやすい箇所は4つです。
- 大腿骨頸部骨折
- 太ももの付け根(股関節)の骨折で、治療のため手術が必要になることが多くあります
- 脊椎圧迫骨折
- 背骨の骨折で、尻もちをついたり勢いよく椅子に座ったりすると骨折することがあります。コルセットを巻いて治療するのが一般的です
- 上腕骨頸部骨折
- 腕の付け根の骨折で、肩を地面にぶつけたり、肘や手を地面に付いた時に起こる可能性があります
- 橈骨遠位端骨折(とうこつえんいたんこっせつ)
- 手首の関節の骨折で、転倒した時に手を付くことで起こります
転倒を予防する
転倒してしまうのは、内的要因と外的要因が複合的に絡み合っています。それらのリスクをすべて取り除くことができればよいのですが、薬を中止できなかったり、急激な血圧の変動が起こったりしてしまう可能性は十分あります。
そこで、日々できる転倒予防の取り組みとして、まずは転倒しにくい体づくりをしていくことをおすすめします。ここでは、自宅でできる簡単な運動をお伝えします。
- ①スクワット
- 両足を肩幅ほどに広げて、足先は少し外側に向けた状態で膝をゆっくり曲げていきます。膝や股関節に痛みがある方は無理せずに、痛みのない範囲で膝を曲げます。10回を目安に行いましょう。
- ②ヒールレイズ
- 立った状態で椅子の背もたれや机に手を置き、かかとを上げてゆっくりとかかとを下ろします。この動作を繰り返します。10回を目安に行いましょう。
- ③片足立ち
- 立った状態で椅子の背もたれや机に手を置き、片足を上げます。その状態で5秒程度止まり、足を下ろします。これを左右交互に行います。
- ④散歩
- 歩くことで筋力や体力をつけることができます。また、屋外を散歩することでビタミンDを生成できたり、骨に適度な刺激を加えられたりすることで骨が強くなります。

転倒の原因を確認する
転倒の原因を取り除かないと、再び転倒してしまう可能性があります。筋力やバランス能力の影響も大きいと思いますが、転倒したときの状況確認も重要です。
例えば、夜に転倒したのであれば、睡眠状況はどうだったのか、睡眠薬の影響はないか、電気を消した状態でも足元が見えていたのか、スリッパをしっかり履けていたか、などさまざまな原因が考えられます。それらを一つ一つ確認することで、今後の転倒を予防できる可能性があります。
また高齢者は加齢により、どうしても筋力、バランス能力、体力が低下する傾向にあります。そのため、一度転倒したことによる恐怖心から何もしなくなってしまうと、さらに筋力低下を引き起こし、再転倒するリスクが高くなってしまいます。
もちろん、痛みがあったり強い恐怖心がある場合は無理に動くことは勧めませんが、身体機能を維持するために、可能な範囲で少しずつ体を動かすことが大切です。
寝ることが多くなってしまった方は、起きる時間を多くすることでも効果があります。
転倒のしやすさに対する対策
では転倒してしまったら具体的にどのような対策をしていったら良いでしょうか?
ここでは、転倒後の対策などについて説明します。
- ①薬について医師に相談する
- 薬を飲むとふらつきが強くなる場合は、主治医に相談してみることをおすすめします。薬の減量や薬を一時的に止めるなどの対策ができるかもしれません。
- ②環境を整える
-
転倒した場所や転倒しそうな場所の環境を整えることで転倒を防ぐことができます。
- 床に物が散乱している場合は片付けをこまめに行う
- 電気コードの配線はできるだけ動線上に置くことは避ける
- 階段や上がり框などに手すりをつける
- 室内でスリッパは履かないようにする
- 夜間はセンサーライトをつけるようにして足元を明るく保つ
- 浴室は滑り止めマットを使用する など
- ③歩行・移動補助具を検討する
- 安定して歩けるように、杖や歩行器などを使用することも転倒予防には有効です。杖も歩行器も多くの種類があるため、ご自身の体や生活環境に合ったものを使用するように専門家に相談しましょう。歩行・移動補助具には介護保険でレンタルできるものもあります。
- ④運動習慣を身につける
- 運動を行い、筋力や体力の維持・向上を図ることはやはり重要です。ポイントはいかに習慣化して行えるか。気軽にできる運動から継続していくことで、少しずつ運動習慣を身につけていきましょう。
- ⑤骨を強くする
-
転倒をしても大きな怪我に至らないように、骨を強くするという視点も重要です。骨を強くするためには、カルシウムの摂取とカルシウムの吸収を助けるビタミンDの摂取が推奨されています。
ビタミンDは日光を浴びることでも体内で生成されるため、意識的に外に出て紫外線を浴びることも骨には良い影響を与えます。また、運動を行ない、骨に刺激を与えることも重要です。
骨粗鬆症を発症し、骨がとても弱くなっている場合は、薬や注射により治療を行うことがあります。
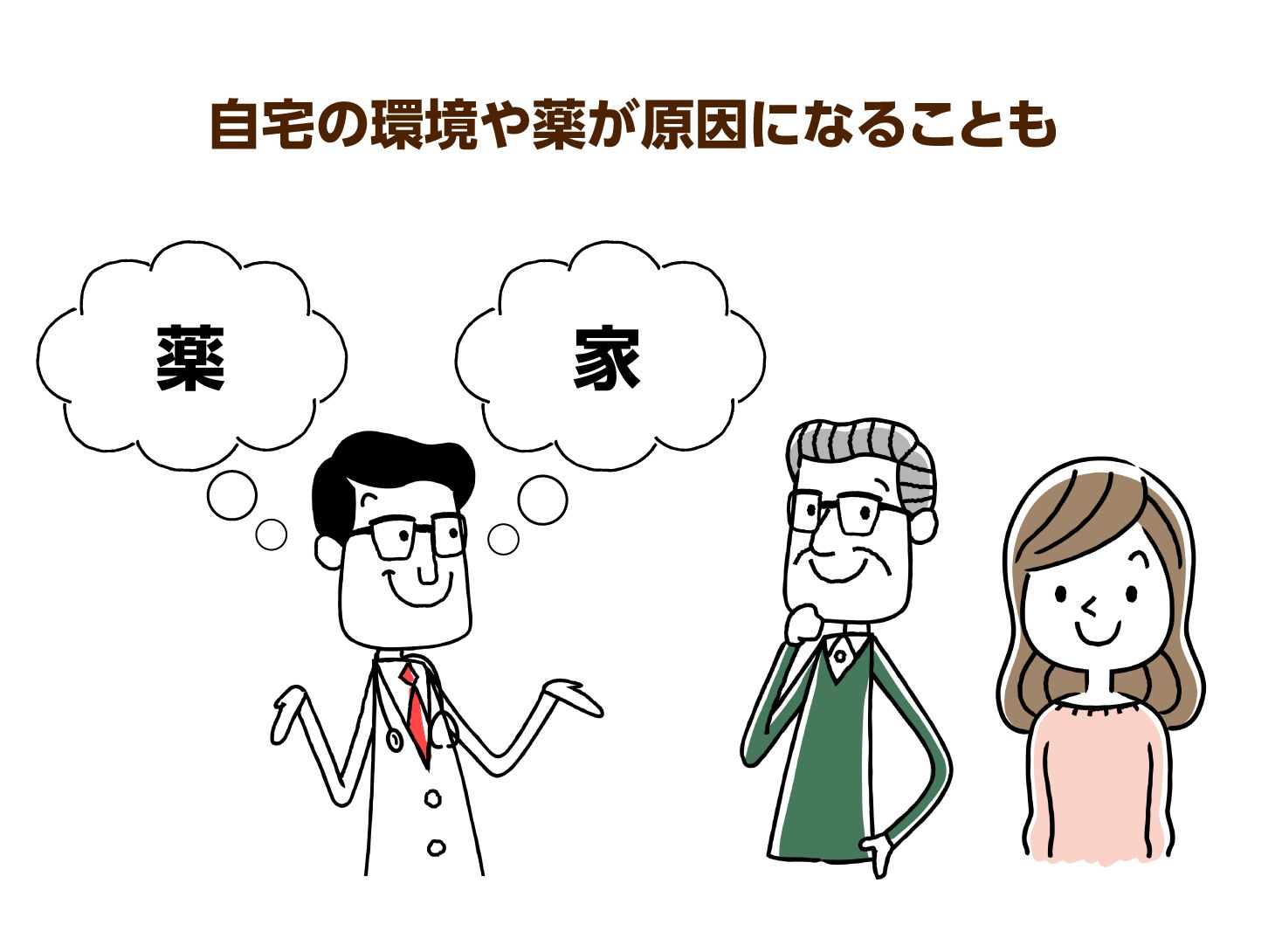
まとめ
いかがでしたでしょうか?転倒といってもその原因はさまざまです。
まずは転倒をしないような体づくりが基本となりますが、運動だけではなく食事や睡眠をしっかり取ることも非常に重要です。
また転倒してしまうと歩くこと、動くことへの恐怖心が生まれて、自信を失ってしまうことがあります。その結果、閉じこもりがちになり、さらなる筋力・体力低下を招いてしまうことも。
できる範囲で動くことを意識しながら、転倒の原因を専門家と一緒に考え、転倒を予防していきましょう。