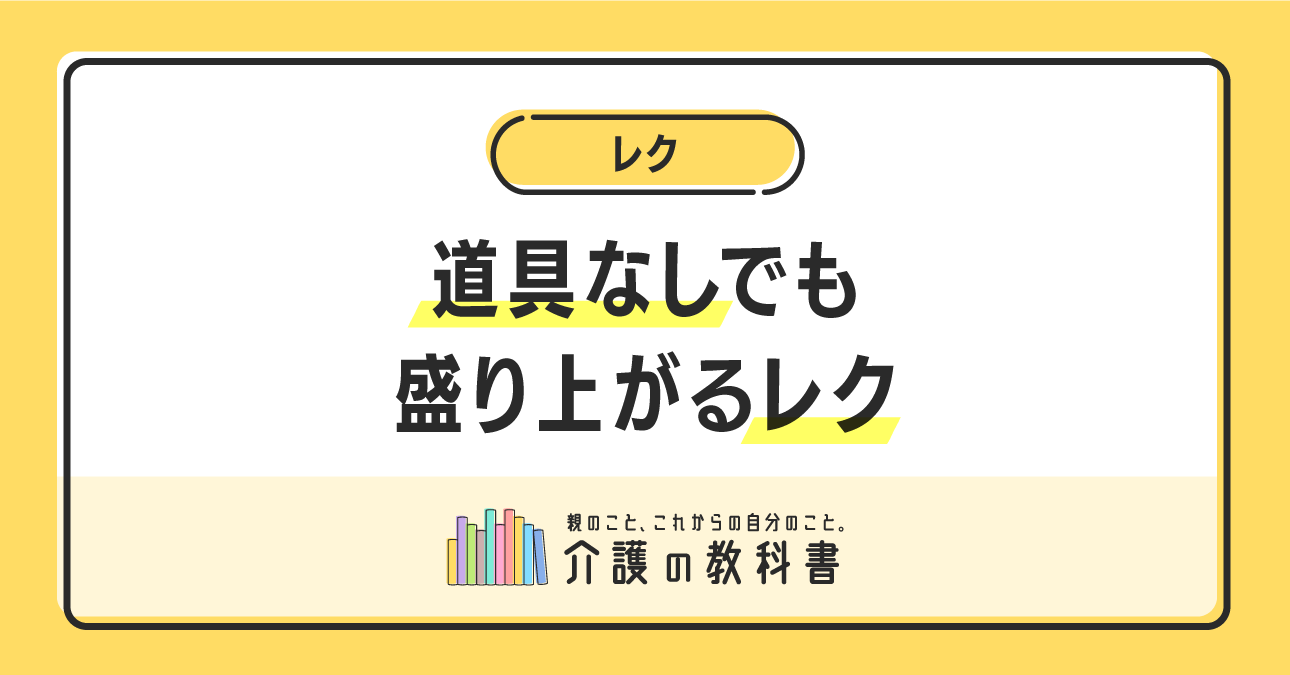こんにちは!「音でタノしむ、音でラクする」をテーマに、高齢者介護現場での活用を目的とした楽器を開発している「ソニフル」の代表“いまたつ”こと今井竜彦です。
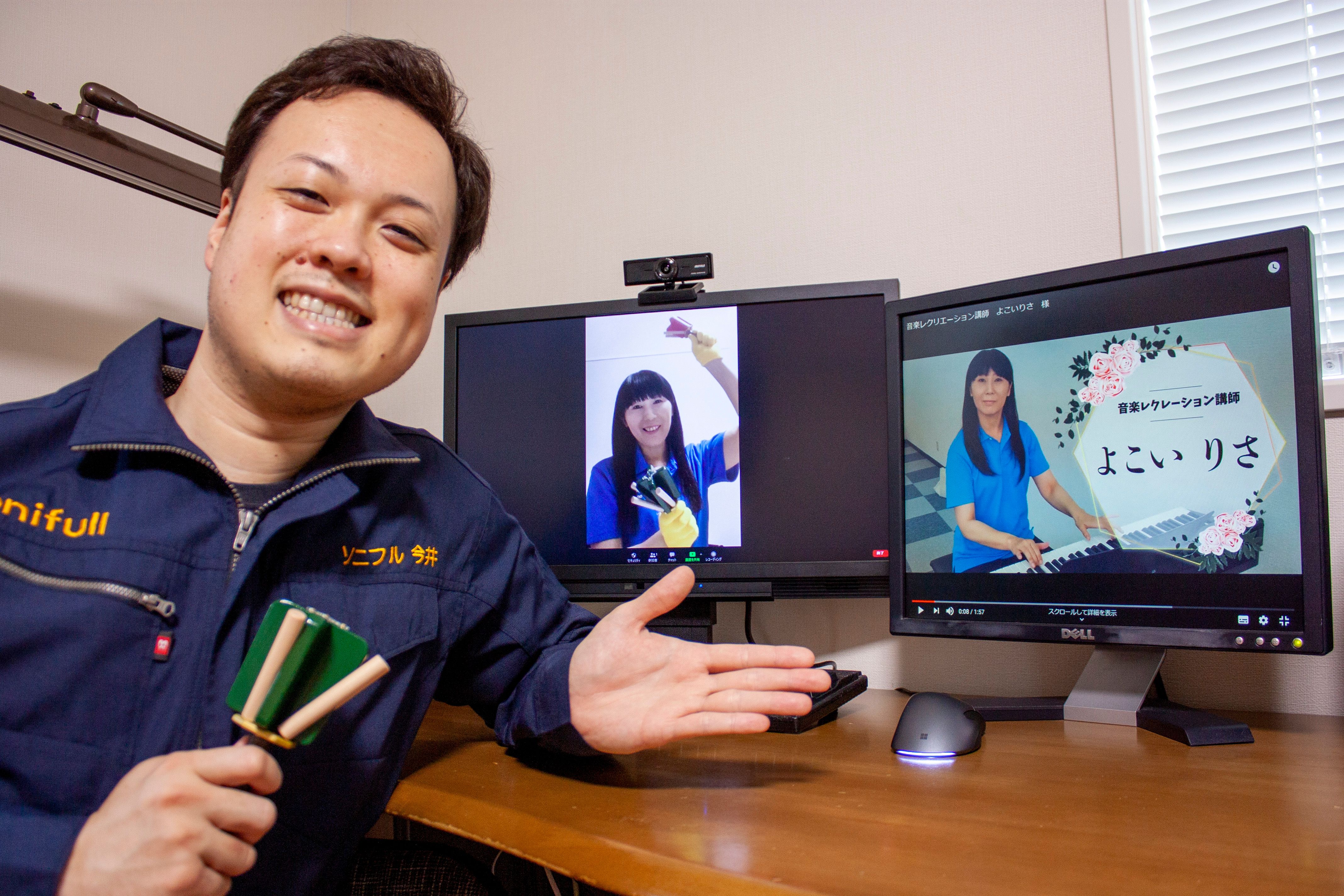
音楽が持つさまざまな「チカラ」をご紹介し、介護の現場にたくさんのステキな時間をお届けします。よろしくお願いします!
今回は、音楽レクリエーション講師の横井理砂先生に「介護現場での音楽レク・体操レクを充実させるコツ」をインタビューしてきました。それではいまたつと一緒に、楽しく学んでいきましょう!
音楽レクリエーションははじめの声掛けが大切
今井:先生はご高齢の方や障がいをお持ちの方に、音楽や体操を用いたレクリエーションを提供されているんですよね。介護施設ではさまざまなレクが行われていますが、介護士さんが音楽レクを行うのは難しいイメージがあるという意見をいただいたことがあります。
音楽をもっと日常に取り入れていただければ、充実した日々になることは間違いないのでとても残念です…。そこで、まずは介護現場で音楽レクを行う際の心構えとして、どんな点に気をつければ良いか教えてください。
横井先生:介護施設をご利用されている方の多くは、仕事の引退や身体機能の低下、親近者の死など、さまざまな喪失体験を経験されています。そのために自信をなくし、老人性うつになられている方もいらっしゃるのです。
そのような方々にも音楽レクに参加してもらうには、ハードルを下げて気軽に過ごしてもらうことが重要です。そのためには、何よりも「はじめの声掛け」が大切になります。この声掛けがしっかりできた回とできなかった回では、結構差が出るんですね。

横井先生:声掛けができなかった回は、参加者の反応や動きが明らかに少なく、一目瞭然。私も心の中で「あちゃ〜」となってる時も結構あったり…(笑)。次の内容に移る際に改めて声掛けを入れますが、やはり「はじめ」にきちんとお伝えすると効果バツグンです。そして、もちろん「笑顔」を忘れずに!
声掛けの例としては、以下があります。
- 無理はしないでください。楽しい時間をつくりに来ました。途中で疲れたり、嫌になったりしたら、休んでください。できるようになったら、またやりましょう。
- 体の動かない方は、私の動きを見てください。頭や心でも、体操ができますよ。
- 歌うところがありますが、声の出ない方、心でハミングしてみましょう。
今井:「レクは参加者がどうするか自分で決められる、自由なものである」ということをお伝えするのですね!楽しく参加してもらわなければ意味がありませんし、これなら実施する側も気負いしすぎずにできそうです。
参加者が活躍していた頃の音楽をかけること
今井:それでは次に、音楽レクの内容でオススメの方法を教えてください。
横井先生:最近はいろいろな音楽レクのネタが、書籍やネットなどですぐに得られる時代になりました。ですので、今回はそれらを用いた活用法についてご紹介しますね。
選曲はどうするべきか
横井先生:「参加者の活躍されていた頃の音楽を」と言ったら簡単ですが、そばにあった音楽というのは人それぞれですよね。ですから、幼き日の思い出や学生時代、社会人となっていく中で、誰にでも人生の1ページを蘇がえらせて瞳を輝かせる、そんな思い出の音楽が必ずあるはずです。
そこで、まずは幅広い世代にあった楽曲からはじめ、徐々に参加者のリクエストを聞いて混ぜていくと良いでしょう。ただし、あまり情動に作用し過ぎる曲は、避けてください。以前プログラム中に、感情が高ぶった車椅子の参加者がグワッと立ちあがって歩こうとしたことがあったので、ヒヤリハットのリスクを下げるためにも重要です。
また興奮しすぎてしまい、夜眠れなくなってしまうリスクもあるので、注意しましょう。なお、カラオケを使用する際は、男性の方も女性の方も一緒に歌いやすくするために「キー」を下げると、皆さんで参加しやすくなります。
高いなと感じたらキーを2つくらい下げて、様子を見て合わせていくと良いと思います。さらに、脳トレに楽曲を使用する際は、利用者様の動きに合わせて、「テンポ」を下げるのも良いですね。CDを流すなど、テンポのコントロールが難しい場合は、動きのテンポを半分に落とせば、ゆっくりとした動きにできますよ。
例として「(×)もしもし (×)かめよ (×)かめさん(×)よ」が早いと感じたら、「(×)もしもし かめよ (×)かめさんよ」といった形です。
※(×)は手拍子等の動き
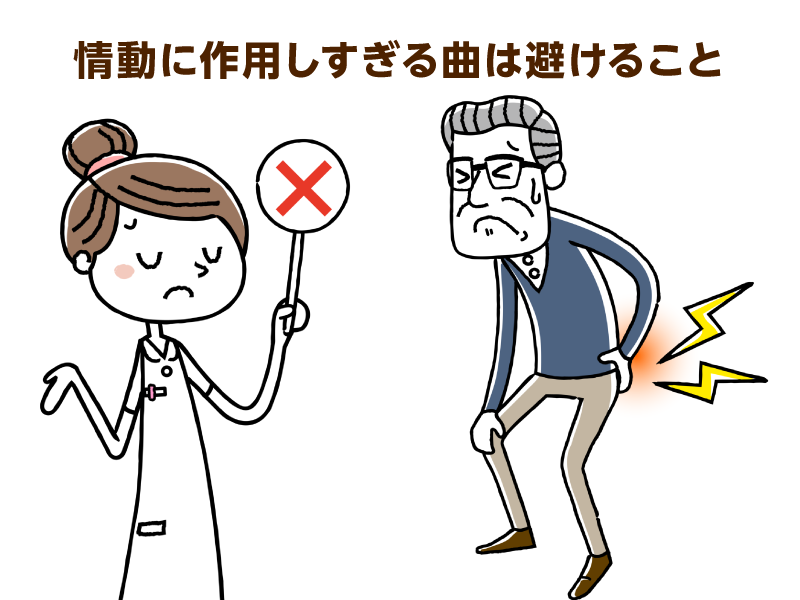
楽器は身体機能にあったものを
横井先生:難しく考える必要はありませんが、音楽レクではCDなどの音源やカラオケを使って楽曲をただ流しておくのではなく、一緒に歌ったり楽器を鳴らしたりと、参加者に寄り添い、一緒に音楽を楽しむことが大切です。楽器は、身体機能に合ったモノを使用することで、より皆で楽しめる音楽レクになります。
鈴やシェーカー、手づくり楽器もいいですし、ソニフルの高齢者向け音楽療法用オリジナル鳴子「良くなる子」は、片麻痺の方や腕や手首が大きく上手く動かせない方、可動域が限られた方でも、ほんの少し動かせれば簡単に音が鳴ってくるので、とてもおすすめです。
音楽に合わせた体操など、身体を動かす場合は、それぞれの持つ身体能力で楽しんでいただけるような工夫が一番大変かと思いますが、一番重要なところでもあります。
それから、より「見やすさ・わかりやすさ」を追求し、現在活躍しているのが、私の秘密兵器「黄色い手袋」。視力が落ちてきている方や認知症の方でも見えやすく、視界に入りやすいので、難しい説明をしなくても自然と動きを真似してくれます。今や私のトレードマークです(笑)
今井:黄色の手袋は、先生の鮮やかなブルーのシャツと相まって、僕も思わず目で追ってしまいます(笑)。日頃から接している介護士さんならば、参加者に寄り添った内容になることは間違いないですし、音楽レクをきっかけに新たな一面に気づける機会になるかもしれませんね!
音楽レクでも「目線」と「支援の姿勢」を意識する
今井:ほかに先生が実施する際に、心がけていることなどはありますか?
横井先生:介護にかかわる方ならご存知の方も多いと思いますが、介護の現場での認知症の方への接し方、話し方を具体化しさらに深く特化した「ユマニチュード」という技法があります。その中から「目線」と「支援の姿勢」が重要と感じ、音楽レクに取り入れています。
実は私自身もつい早口で、トーンが高くなってしまいがちです。なので、皆さんの前でお話する際には、「しっかりと目をみて、簡潔にわかりやすく、優しく低めのトーンで、正面から視界に入り話しかける」ということを、大人数の中でもできる範囲で取り入れられるよう、心がけています。
このような情勢なので体に直接触れることは難しくても、支援する際には目線の高さを合わせてみたり、下から支えて持ち上げたりするような気持ちで側に寄るなど、できる範囲で取り組んでいます。

今井:それでは最後に、先生が感じる音楽レクの楽しさややりがいについて教えてください。
横井先生:それはもう、参加された方が笑顔になり、瞳がとても輝いている姿を見たときですね。ある日、車椅子を利用されている方の隣につき添う職員さんから、「あら~、随分腕が上がるようになったじゃない〜」という言葉とともに、利用者様がニコーッとされて、それはもう感激でした。
それぞれの人生の中にある、大切な宝石のかけらを見せていただいたような気持ちになります。
音楽レクをやることになったきっかけ
横井先生:実は、私がこの道に導かれてきたのも、自身の喪失体験が重なったことからでした。頸椎(けいつい)を故障して、やっと就けた憧れの仕事を続けるのが困難になったこと、突然の父親の死、子供の障がいが理解されない。さらには、口腔内にできた腫瘍を切除したため口の中はスカスカで、人前で歌うなどとんでもないと思っていました(笑)当時を振り返ればすべてに背中を向けていたのです。
そんな「音楽」とともに歩んできた人生だからこそ、レクリエーションを通してたくさんの笑顔を皆さんにお届けすることがこれからの私の使命であり、やりがいなのかなと感じています。
これからも、現場や音楽療法、リトミック、介護レクリエーションなど各方面で学んだ素晴らしい要素を取り入れながら、たくさんの笑顔と健康づくりを目指し、日常生活のあらゆる場面におけるやる気や意欲、生きる喜びに貢献していけるように、活動を続けて行きたいと思います。
音楽を活用して楽しいレクを
いかがでしたか?音楽を活用した楽しい毎日で、新型コロナウイルスに打ち勝ちましょう!
横井先生のホームページやYoutubeも、ぜひチェックしてみてくださいね。 次回もお楽しみに!