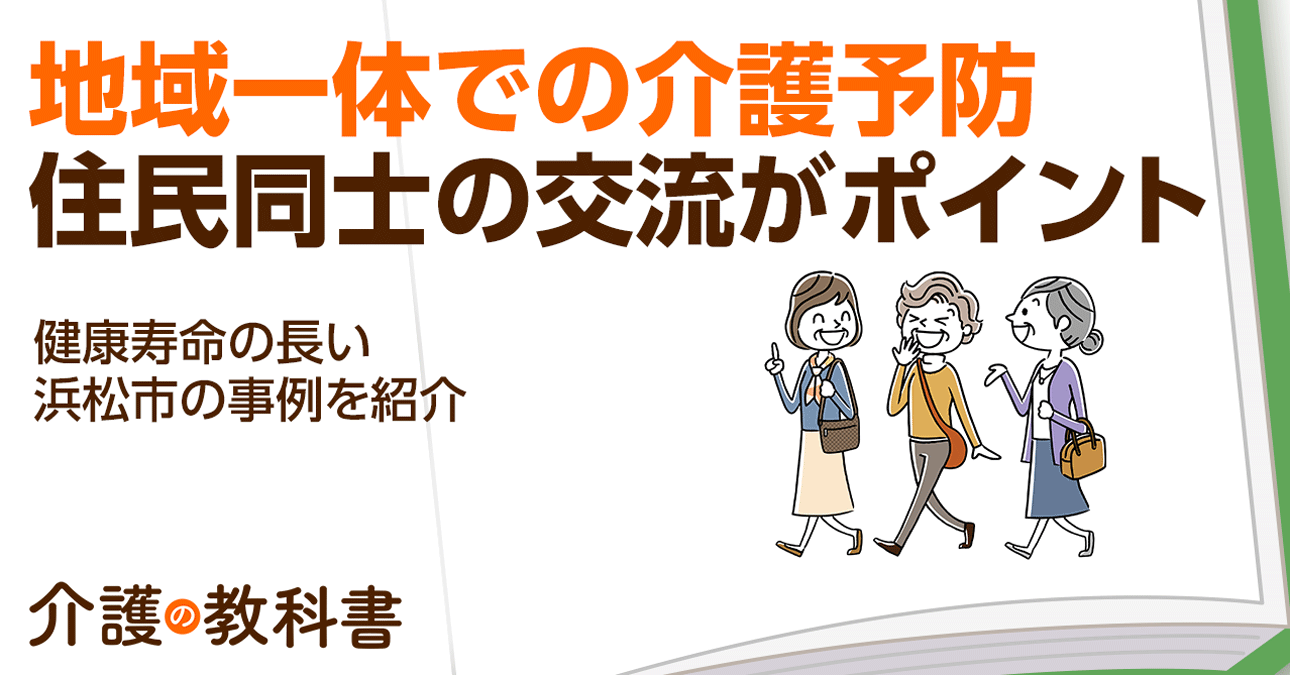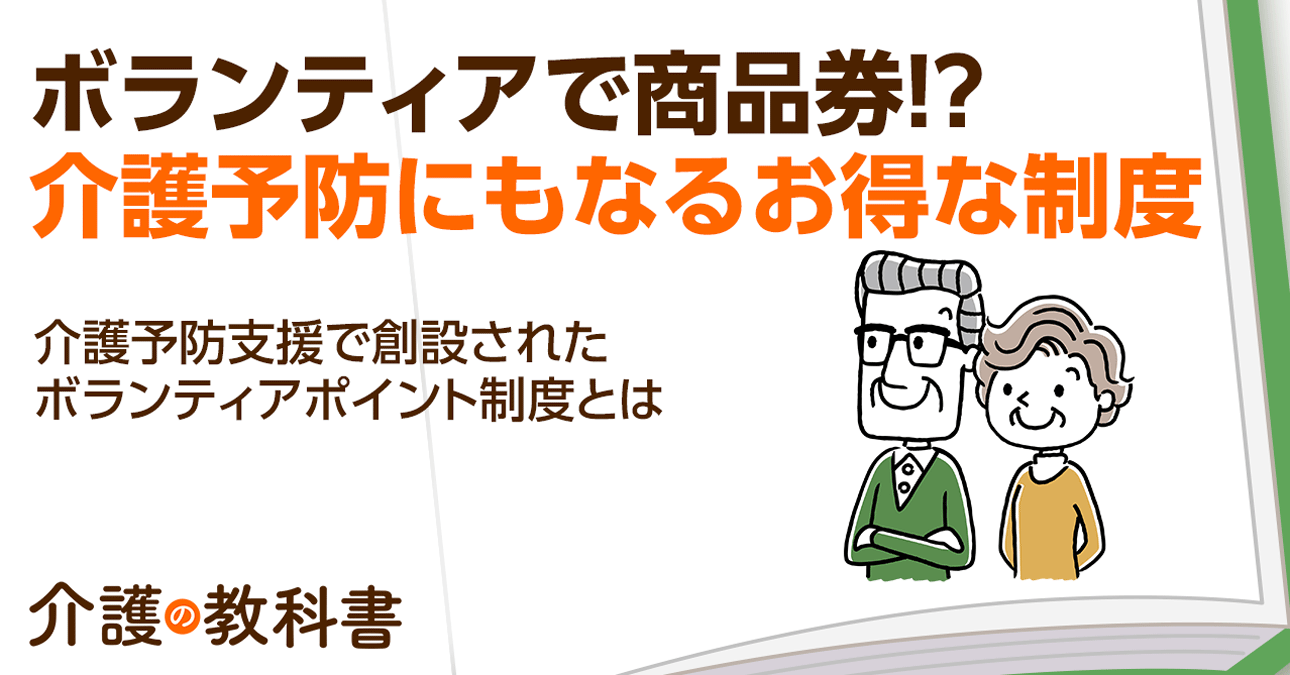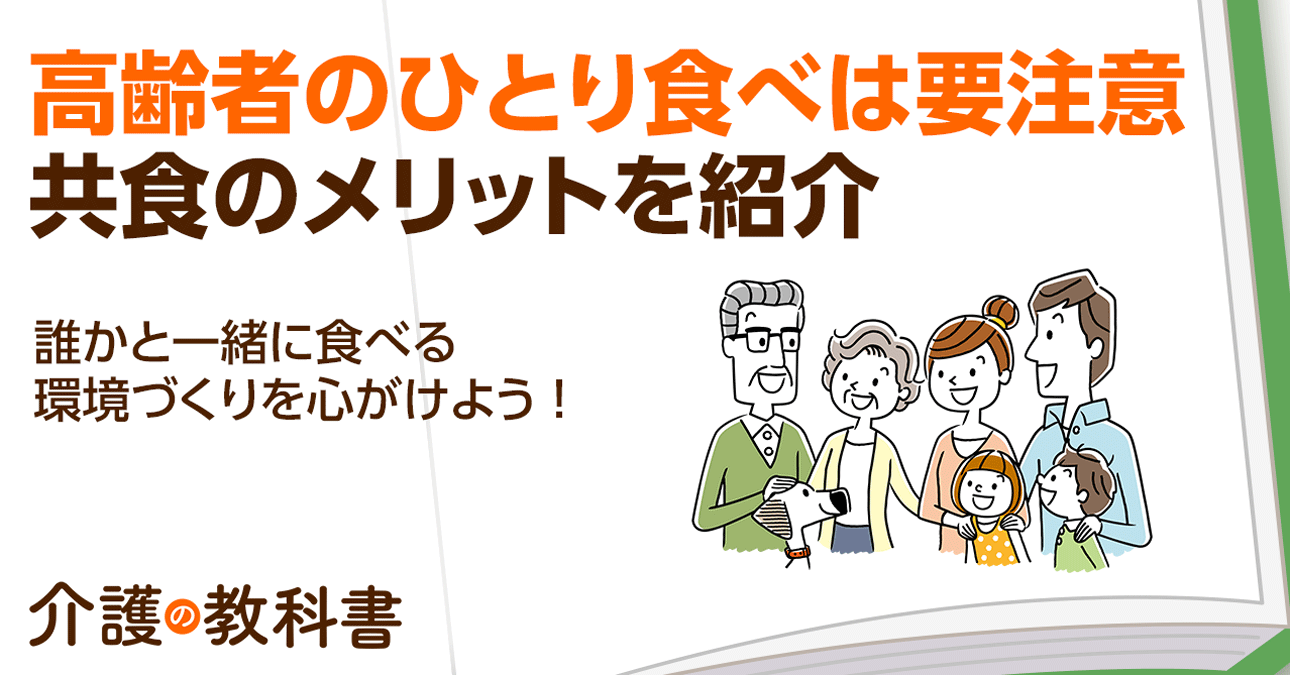くるくるした髪の毛は天然もの、ひよっこ音楽療法ライターの「海月(ミヅキ)ひなた」です!高齢者の介護現場向け楽器の開発・販売を手掛ける『ソニフル』で音楽や音楽療法の魅力を発信しています。
「在宅介護でも音楽を活かした介護を取り入れてほしい!」というのがソニフルの願いです。音楽のチカラで介護に少しでもパワーを与えられたらと思っています!どうぞよろしくお願いします。
今、音楽のレクリエーションによる介護予防が注目されており、その中でも音楽教育の手法として生まれた「リトミック」が認知症予防に良いと言われています。
今回は音楽レクリエーションによる効果や、リトミックについて詳しくみていこうと思うので、音楽のレクリエーションに興味がある方はぜひ御覧ください!
喉が悪いときは声でわかる!鍛える方法は?

「じいさんや…ちょいと川へ洗濯をしに行ってきますからね。」「ばあさんや…わしゃあ…ちょっいと芝刈りに行ってくるかのぉ。」
日本むかしばなしに出てきそうな会話ですね(笑)。さてこれを読んだ皆さんは、脳内でどんな読み方をしたでしょうか?私は脳内で市○悦子さんや常田○士夫さんの声が聞こえてきました。あの独特なナレーションは、おじいさんやおばあさんのイメージを私たちに強く印象付けたような気がします(笑)。
冒頭のセリフを脳内で読んだときに、ハキハキと元気な声が浮かんだ方は少ないのではないでしょうか?多くの方は、細くかすれたような声を想像したかと思います。そうです。声は、年齢を重ねるごとに出にくくなるのです。
「以前は太かった声が細くなった気がする。」 「なんだか声がかすれるようになってきた。」
その原因は、喉が衰えてきているからなのです。高齢者にとって喉が衰えることは、ただ声を出しづらくなるというだけでなく、肺炎にかかりやすくなります。ではどうしたら喉を鍛える事ができるのか?答えはカンタンです。「声を出すこと」ただそれだけです。
喉を鍛える近道は歌うこと!
誰かと一緒に住んでいれば、会話が生まれる可能性は高いですよね、もちろんその方との相性もあるかと思いますが(笑)。しかし、ひとり暮らしの方は会話をする機会が極端に減ってしまいます。
ひとりのときに声を出す事は難しく、電話のときや、外出しないと誰とも話さないという方も多いのではないでしょうか?そんなあなたにおすすめしたいのが「歌をうたう」ということです。
会話をするときよりも大きな声を出そうとするので、より喉も鍛えられて腹筋も使います。歌うことは「軽い有酸素運動」とも言われており、運動ができない方にも、カンタンなエクササイズやリハビリとして効果的です。
また、歌うとスーッと清々しい気分になるなど、メンタル面でも良い作用が期待できます。テレビの昭和の懐メロ特集などでは、必ず歌詞がテロップに出てきますので、一緒に歌ってみるなど、簡単にできることから始めてみてください。最初はちょっと恥ずかしいと思うかもしれませんが、是非実践してみてくださいね。
サークルに参加して前向きに介護予防

せっかく歌を歌うなら、一歩踏み込んで「歌のサークル」活動に参加してみませんか?みんなで一緒に歌うことで、歌による影響はさらに大きなものとなります。音楽療法の世界でも、集団音楽療法というものがあり、効果があったというデータもたくさん存在していますし、老人ホームやデイサービスのレクリエーションで積極的に合唱が取り入れられているのもそのためです。まずは気が向いたときにふらっと参加してみるというのも良いと思います。
実際、シニア世代である私の母は、サークル活動によって新たな生きがいを見つけました。サークル活動をする前と後では性格が明るくなったと話しており、サークルがあるから辛いことも頑張れるそうです。体調不良で行けない場合は無理せず休んだりと、自由気ままに楽しんでいます。
さらに、サークル活動によって人と会うことで会話も生まれますし、コミュニティも形成されます。母も(自分の母の話ばかりで恐縮ですが)最初はサークルでの活動が目的で通っていましたが、だんだん「お昼を持ち寄って一緒に食べる約束をしているの!」「イベントがあるらしくて、係を頼まれちゃったわ」と自然とコミュニティが広がっているようです。
「介護予防」という言葉や「リハビリ」という身体の健康を維持する義務感覚ではなく、「サークル活動」という前向きな気持ちで活動することは、介護予防やリハビリにおいて、大きな効果となって現れるでしょう。
介護予防として注目されているシニア世代の「リトミック」
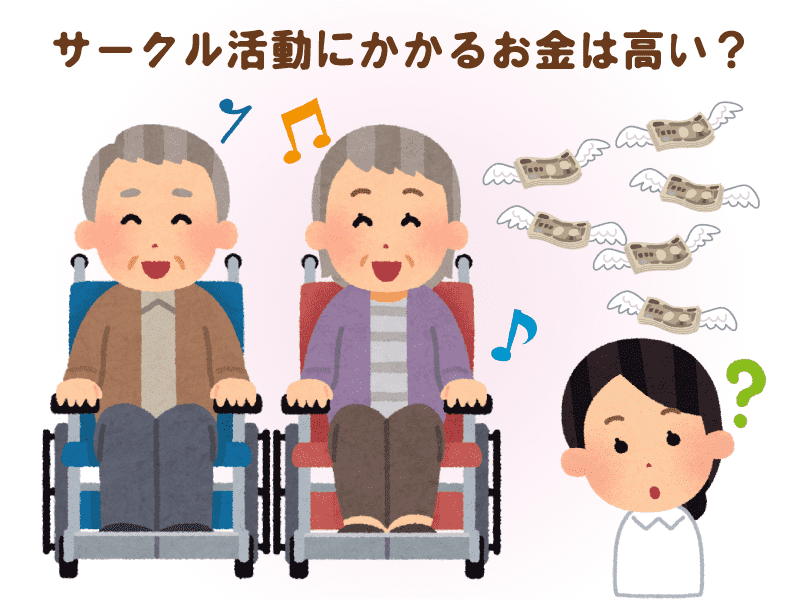
きちんと介護予防として効率的に音楽を活用したい!もっとリハビリ要素があるものにチャレンジしたい!という方には、「リトミック」がおすすめです。
音楽教育の手法として生まれたリトミック。幼児教育を思い浮かべる方も多いかと思いますが、実は舞踏や演劇など、さまざまな分野で活用されているんです。
リトミックは幼児教育の分野では、音楽の技術的な習得よりも、子供の創造性や集中力、自主性や健全な心など、人間が生きていく上で必要な人格形成が第一の目的です。これを、音楽療法の観点から認知症予防に効果的になるよう応用したものが「シニア世代のリトミック」で、音楽を使って「体と心と脳」を刺激します。最近では老人ホームや介護施設などでも多く取り入れられており、人気のレクリエーションの一つです。
また、リトミックの中では「若返りリトミック」が一番有名と言われています。日本で最初の音楽療法学科を立ち上げ、多くの音楽療法士を輩出している国立音楽院が開発した音楽を使った介護予防メソッドです。日本におけるシニア世代のリトミックの歴史は海外よりも短く、まだまだ研究段階のように感じていますが、音楽療法士を育てる学校で研究されているということはかなり信頼性があるように感じます。今後も音楽療法の視点から音楽を使ったレクリエーションが多く生まれてきたら素敵ですね。
サークル活動を行うのにお金はどれくらいかかるの?
ここまでの記事を読んで、「サークル活動をやってみたい!」と考えた方もいるのではないでしょうか?その際に気になるのは、ズバリ「お金」の問題。中には「年金暮らしなのに、趣味にお金を費やすのはもったいない!」と考えている方もいると思います。
歌うことでぱっと思いつくサークル活動はカラオケにコーラス、ゴスペルだとは思います。一概には言えませんが、これらを本格的に習うとなったら高額で、月額1万円程度はかかるでしょう。
もちろん、「毎月1万円も払えない…」という方もいると思います。そんな方でも安心して参加できるのが地域や自治体が行なっているサークルやクラブ活動(生涯学習)です。参加費用も数百円から高くても数千円程度のものが多く、気軽に行うことができます。これらの情報は、町内会の掲示板もしくは、市区町村が出しているフリーペーパー、近くの文化センターなどで情報が手に入ります。
現在、サークル活動においては音楽系の活動以外にも、茶道や華道などの文化系のものや、卓球やゲートボールなどの体育系のものなど、さまざまな種類があり驚かされます。
ところが、インターネットでの情報は少なく、さらに区役所などでも情報を管理していないため、足を使って情報を得るしかありません。見つけるのは難しいかもしれませんが、意外と多くの団体を見つけることができるはずです。インターネット上で情報を探す際は「生涯学習」や「文化センター」というキーワードでも、サークル活動の情報が見つかるかもしれません。
今回は、音楽を生活に取り入れるための具体的な方法について書いてみました。音楽が介護予防に良いことは、音楽療法の視点からも注目されていますので、どんどんチャレンジしてみましょう!いつまでも熱中できる何かを持つことが、一番の介護予防だと思います。年齢を気にせず、積極的に人生を謳歌してくださいね!