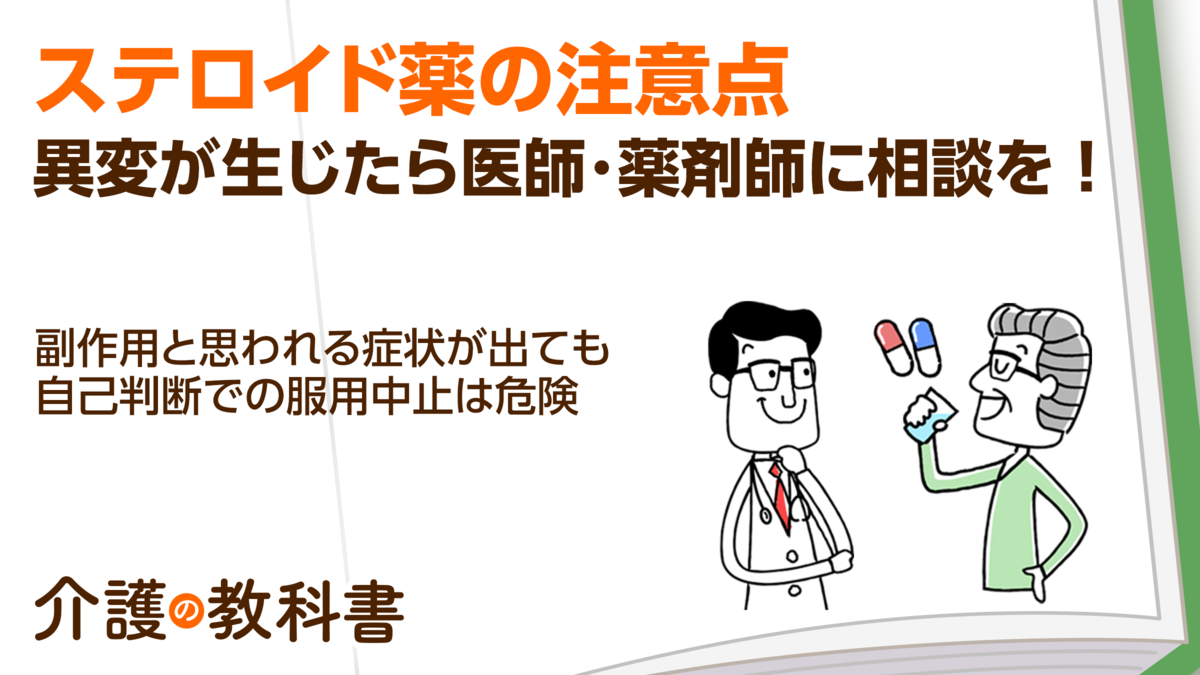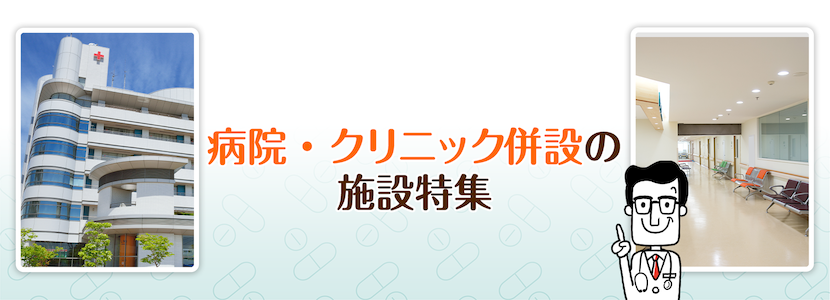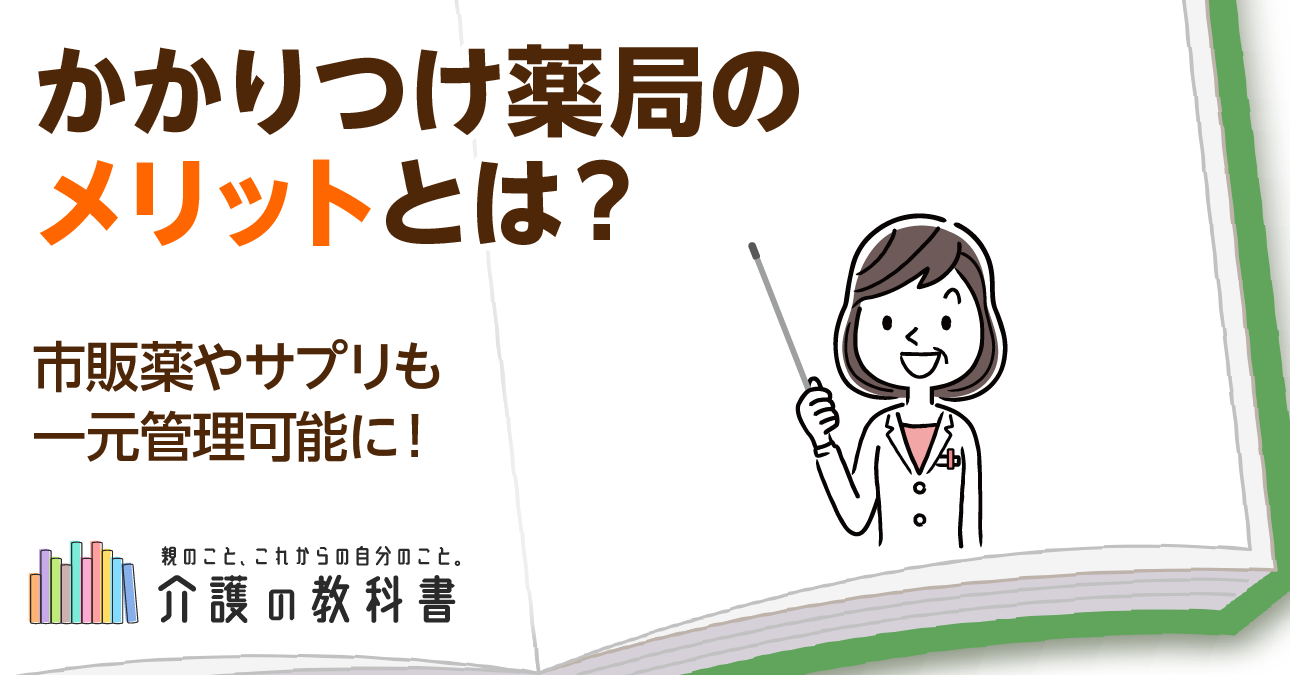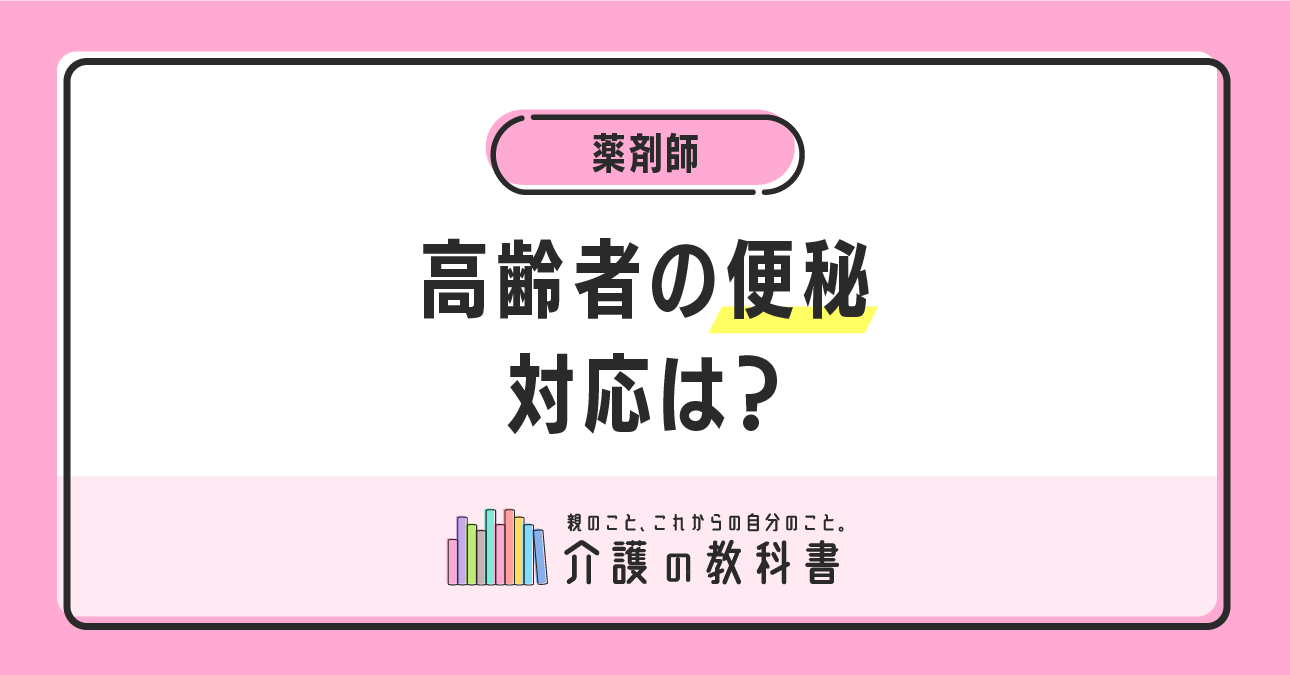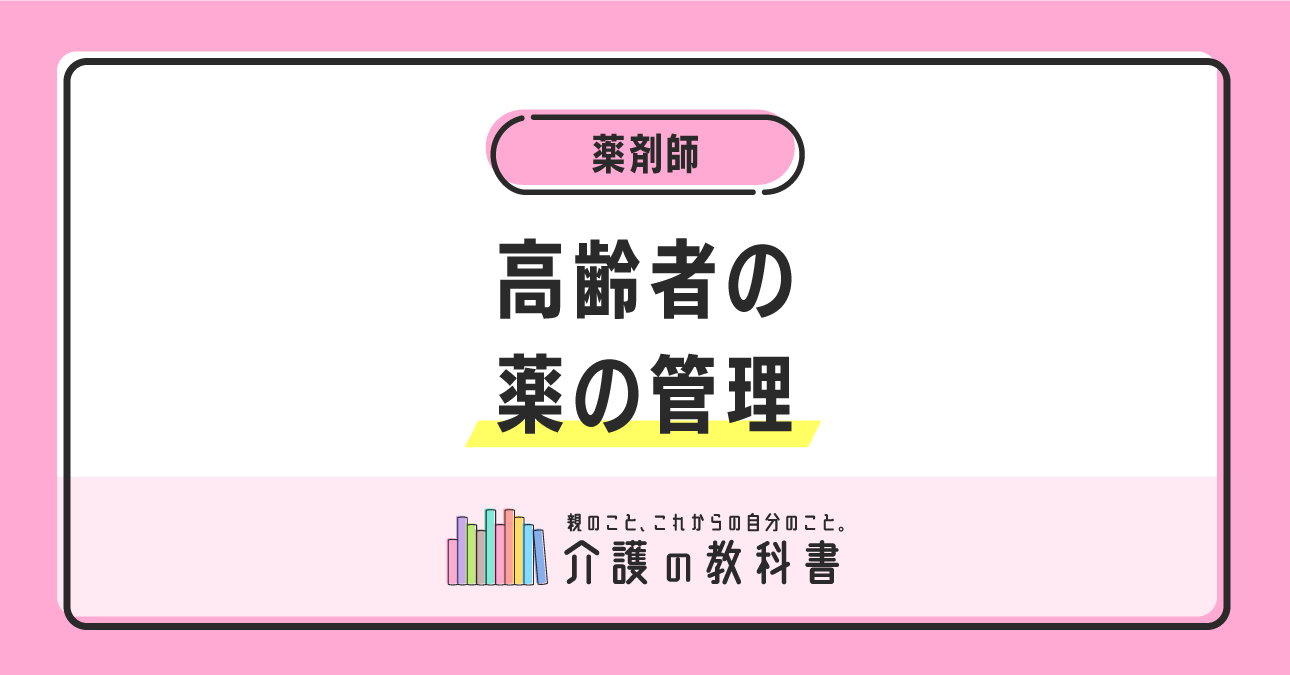私たちの体の中では、数多くのホルモンがつくられています。ホルモンは体の健康維持のためにいろいろな機能を調節する作用があります。
腎臓の上に位置する重さ約5g、そら豆くらいの副腎(ふくじん)と呼ばれる小さな臓器でつくられるホルモンがステロイドホルモンです。
この副腎でつくられるホルモンがもつ作用を薬として応用したものがステロイド薬(副腎皮質ステロイド薬)です。
ステロイド薬にはさまざまな効能があり、抗炎症作用や免疫抑制作用を期待して、多くの病気の治療で使われる一方で、副作用も現れやすい薬の一つでもあります。
今回は、ステロイド薬の正しい使い方をご紹介します。
ステロイド薬の剤型と傾向
ステロイド薬は飲み薬(内服薬)、塗り薬・吸入薬(外用薬)、注射薬などの剤型(薬のかたち)で使われています。
塗り薬は湿疹や皮膚炎のような局所(塗った部分)の炎症を鎮める際に使われ、炎症を鎮める作用の強さで5段階に分かれています。
- 弱い(weak)
- 普通(medium)
- 強い(strong)
- とても強い(very strong)
- 最も強い(strongest)
このうち、ドラッグストアなどで市販されている塗り薬は1~3までの比較的弱いステロイド薬です。4・5の強いステロイド薬は医師の診断により、必要に応じて処方されています。
ステロイド薬は、短期使用での副作用は起こりにくいですが、長期的に使用される場合には注意が必要です。
長期使用することで、皮膚が薄くなったり、皮膚表面の血管が開いて赤みが出てくることがあります。顔のように皮膚の薄い部位では特に起きやすいので注意しましょう。
また、たとえ短期間の使用であっても、皮膚症状に適したステロイド薬を使用しないと症状が悪化することがあります。例えば、水虫の白癬菌にステロイドを使用すると、かえって症状が悪化することが挙げられます。
通常、ステロイドの塗り薬は数日~1週間で効果が得られることが多いです。使用しても症状に変化がみられない場合や改善がみられない場合、塗って良いか判断できない場合には自己判断せずに皮膚科を受診するようにしましょう。
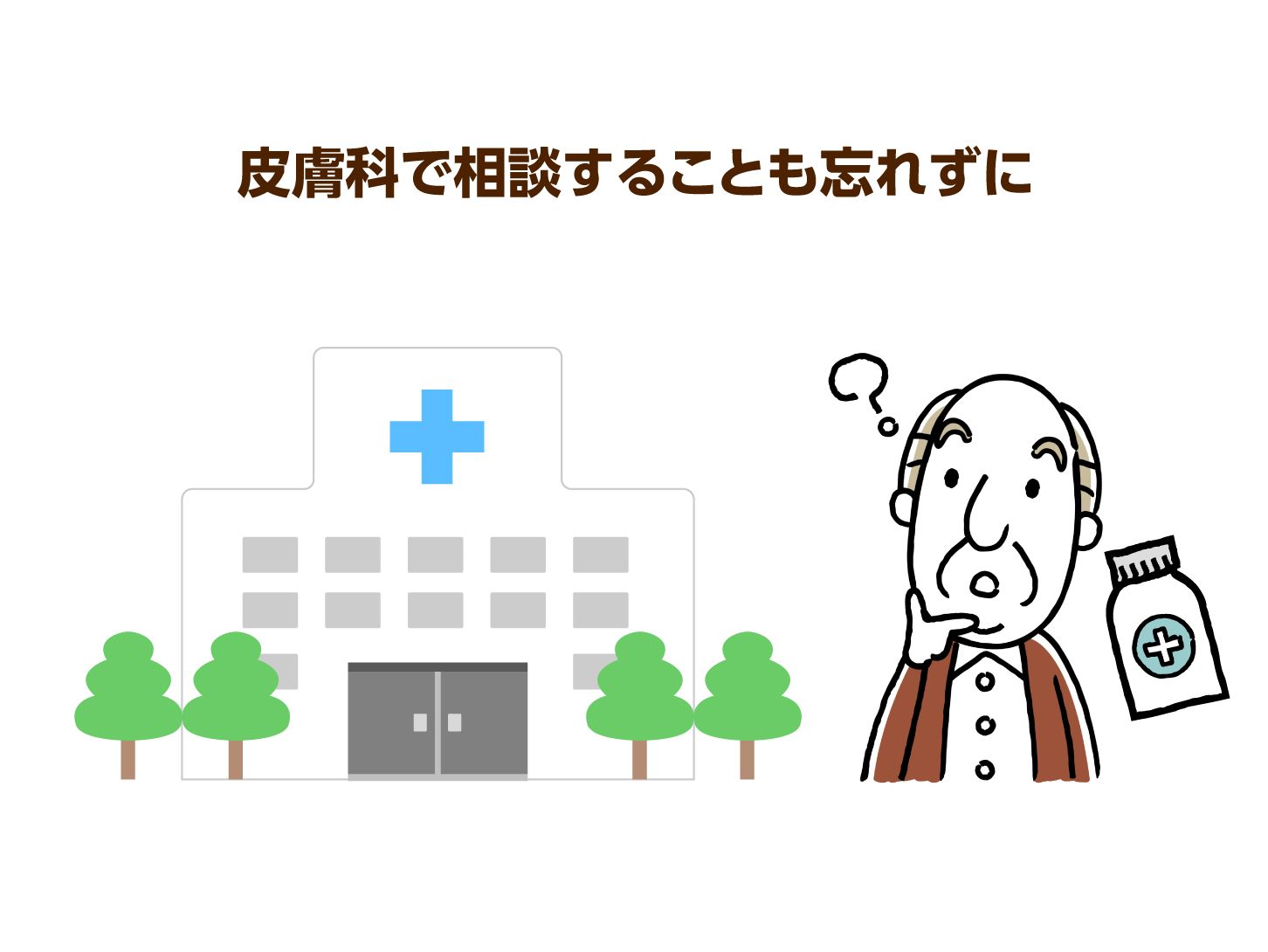
ステロイドの吸入薬には、喘息による咳の発作を抑える作用や、気道の炎症を抑える作用があります。
吸入した薬が口の中に残ると、口腔カンジダ、のどの痛み、声かれなどの副作用が出ることがあります。副作用を予防するには吸入後、口の中に薬を残さないことが肝心です。使用後は必ずうがい(ガラガラ、クチュクチュの両方)をしましょう。
違和感が生まれたらまずは受診を
ステロイド薬の内服薬や注射薬は、関節リウマチ、肺炎、白血病、皮膚筋炎など幅広く使われています。
代表的な副作用として、高血糖、消化器障害、眼症状、骨粗しょう症、感染症などがあります。
高齢者はすでに骨粗しょう症や眼症状(白内障や緑内障)を患っていることもあるので、それらの症状がステロイド薬の副作用で悪化してしまうこともあります。
長期的にステロイド薬を使用される場合には、骨密度の測定や骨粗しょう症治療薬の服用、定期的な眼科受診が必要となることがあります。医師、薬剤師と相談しながら副作用を予防していきましょう。
また、ステロイド薬の免疫抑制作用により、感染症にかかりやすい状態になることがあります。特に免疫力の落ちている高齢者は、日々の感染予防を心がけることが重要です。
副作用の話をたくさんすると、今すぐステロイド薬の使用を中止したい!と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、医師の指示なく自己判断で急に中止してはいけません。
長期間ステロイド薬を使用していると、副腎から分泌されるホルモン(ステロイド)の量が減っていきます。
突然薬の服用を中止してしまうと、体に必要なホルモンが不足してしまい、離脱症状(発熱、頭痛、食欲不振、倦怠感、関節痛、血圧低下など)が起きてしまうことがあります。
通常、離脱症状を未然に防ぐため、ステロイドを中止するときは量を徐々に減らしながら中止する必要があります。
使用中にもしも「副作用かな?」と思ったときは、自己判断で中止せず、必ず医師、薬剤師に相談しましょう。

今回はステロイド薬についてご紹介しました。ステロイド薬は効能効果が多い薬で、現代医療には欠かせない薬です。一方で副作用の報告も非常に多く、使用の際は十分な注意が必要な薬です。
医師、薬剤師から言われた用法用量を守り、正しく使用しましょう。