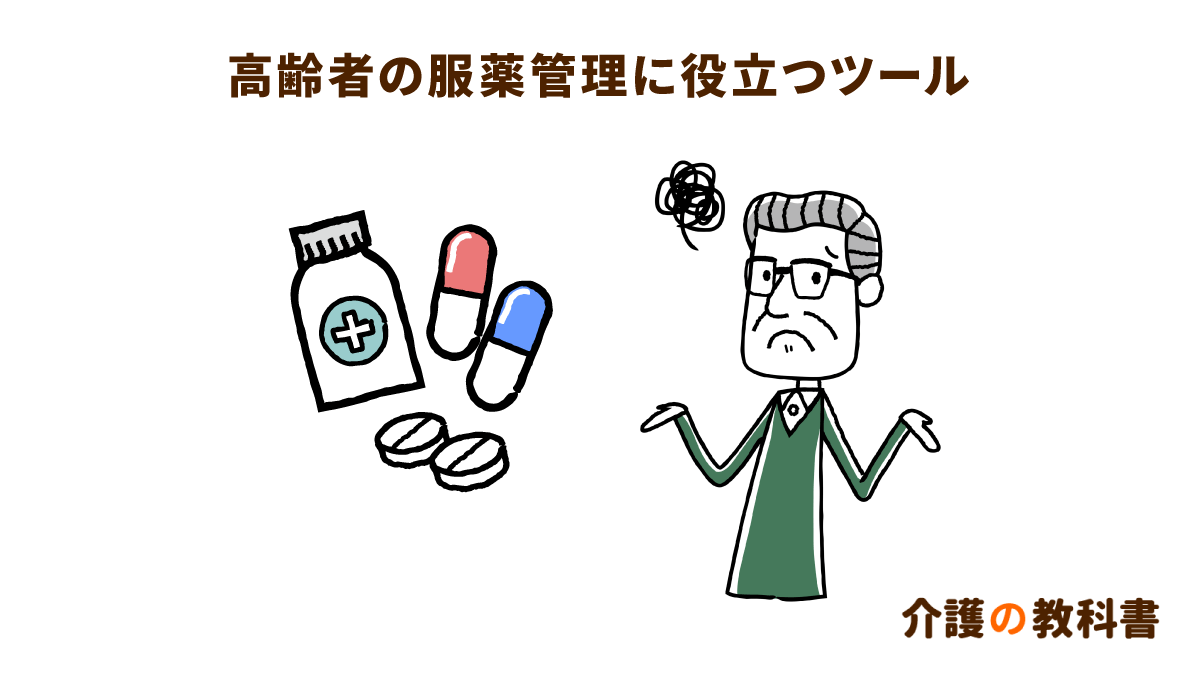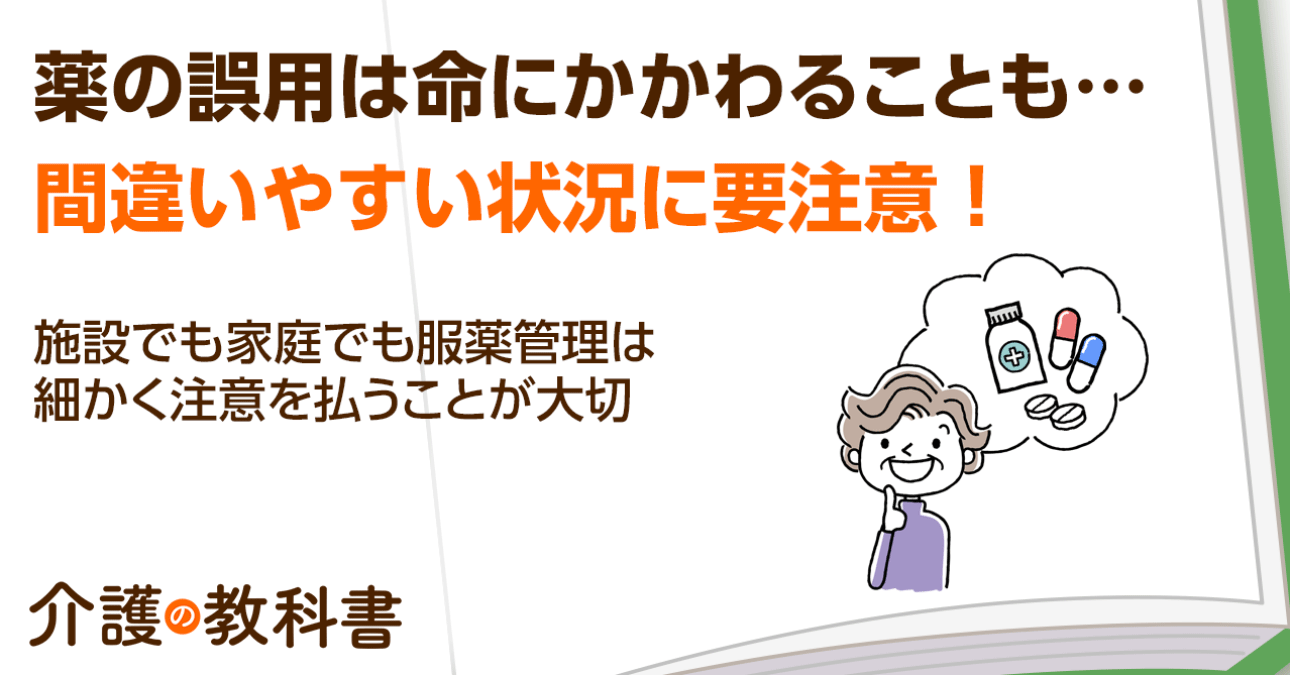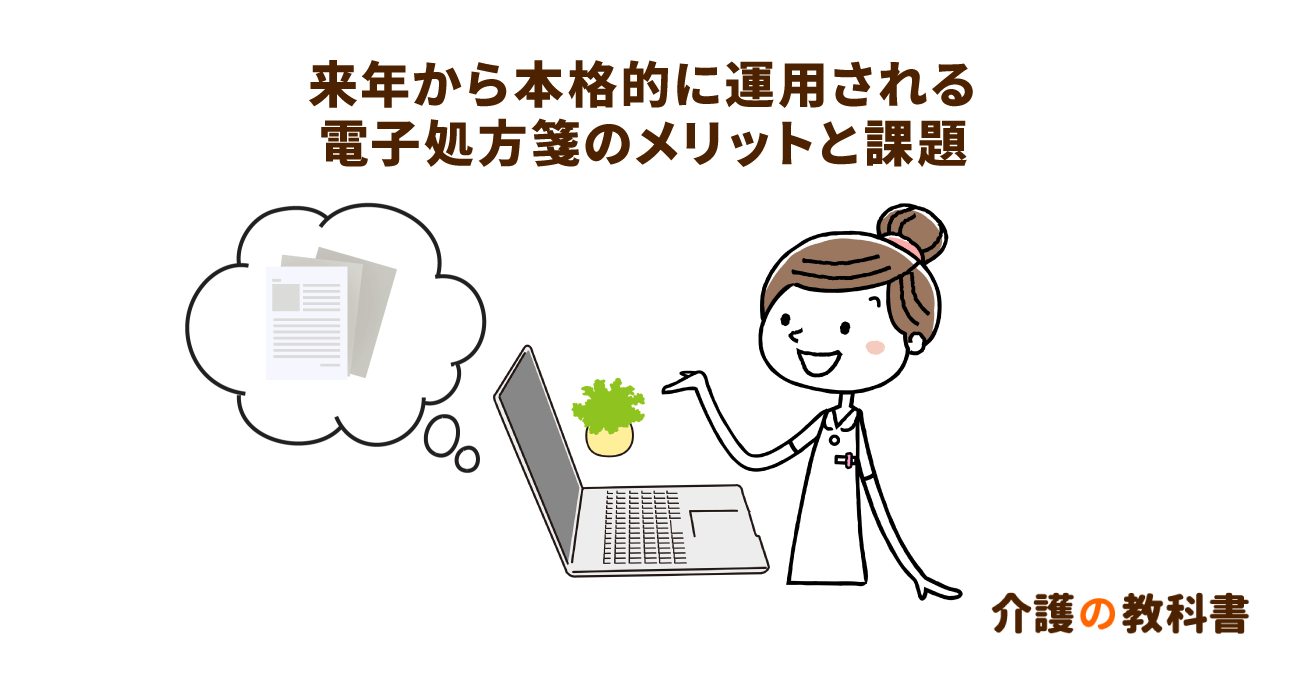介護者にとって介護負担の理由の一つに挙げられるのが服薬管理です。
今回は、高齢者の服薬管理に役立つツールの活用法をご紹介します。
高齢者における服薬の特徴
加齢とともに、抱える疾病数は多くなる傾向があります。疾病が増えると同時に使用する薬の種類も増えるため、管理方法は複雑になります。
通常、私たちが薬を使用するときは、薬袋(やくたい)と呼ばれる袋からPTPシートで包装された薬を取り出し、必要な分だけ用意します。
ところが、高齢者や疾患を抱えた方の場合、この当たり前の準備が困難になってしまうこともあります。
薬袋から決められた時間に決められた分量の薬だけを取り出すには、理解力と判断力が必要になります。認知機能の低下した人は、薬袋から取り出す際に間違いが起きやすいのです。
また、パーキンソン症状による震えや麻痺、視覚障がいによって取り出す行為そのものが難しい人もいます。
薬袋から必要な薬を取り出して準備することが困難な人は、医師、薬剤師に一包化調剤(※)の相談をしてみましょう。
※一包化調剤…服用するタイミングが同じ薬や、1回に複数服用する薬を、1袋ずつパックにする方法

手を自由に動かせず、PTPシートから錠剤やカプセル剤を取り出すことが難しい人は、PTPシートから簡単に薬を押し出す服薬補助具もあります。
インターネット通販などでさまざまな種類の薬取出器が販売されているので、必要な方は試してみると良いでしょう。
お薬カレンダーの活用
一般的に薬は熱や光に弱いものが多く、高温多湿で直射日光の当たるような場所は薬の保管には向いていません。日の光を浴びる窓際や、熱気が籠る冷蔵庫の上や車中などは避けるようにしましょう。
薬を飲み忘れてしまう人に有効なグッズがお薬カレンダーです。
お薬カレンダーは曜日や用法ごとに仕分けポケットが付いており、そのときに服用する薬だけを小分けして管理できるので、飲み忘れや飲み間違い防止に有効です。
一週間タイプや1ヵ月タイプなどさまざまな種類がありますので、生活スタイルや用途に添ったものを選択しましょう。
注意していただきたいのは、お薬カレンダーを使用すれば今まで飲めなかった薬が必ず飲めるようになるわけではないということです。
お薬カレンダーは曜日や用法の認識が難しい人が使うと、かえって誤薬を招くこともあります。違う曜日の薬を重複して飲んでしまう…なんてことがないよう、使う人の状態を見極めることが重要です。
認知症で誤薬が心配だけど、ヘルパーさんに服薬介助してもらいたいときには、お薬カレンダーをご本人の手の届かない場所に保管するなど、保管場所を工夫することで解決できるかもしれません。
一人暮らしには服薬支援ロボットも有効
ほかにも、服薬支援ロボットも有効でしょう。服薬支援ロボットは、設定した時間に光やアラーム音で知らせてくれたり、薬を取り出したことを自動で介護者に案内してくれる機能などが付いた製品があります。
ついうっかり飲み忘れてしまう人や、一人暮らしをしているために服薬の確認を介護者ができない場合に有効です。
これらを用いる際は以下の点に注意しましょう。
- 服薬支援ロボットに配薬する際に入れ間違いをしないこと
- 外出時にボックス内の薬を持参するのを忘れないようにすること
- とんぷくのように臨時で用いたい薬や、目薬や貼り薬といった外用薬などは一緒に管理できないことが多い
服薬支援ロボットを用いれば必ず飲めるようになるのではなく、利用される人によって向き不向きがあるため、導入前に薬剤師に相談されると良いと思います。

このように、お薬カレンダーや服薬支援ロボットのようなツールを上手に利用することで、より安全に服薬管理を行うことができるかと思います。
また、薬の管理でお困りの人は、薬剤師による訪問薬剤管理指導を利用すると、ご自宅での服薬管理について具体的に相談できます。
用法が複雑な処方が出ている場合には、薬剤師と医師とで生活スタイルに添った処方内容に整理することができるかもしれませんし、残薬の整理なども実施しています。
ご自身で通院することが困難な人であれば、訪問薬剤管理指導の対象となりますので、かかりつけの薬剤師や担当のケアマネジャーに相談してみましょう。