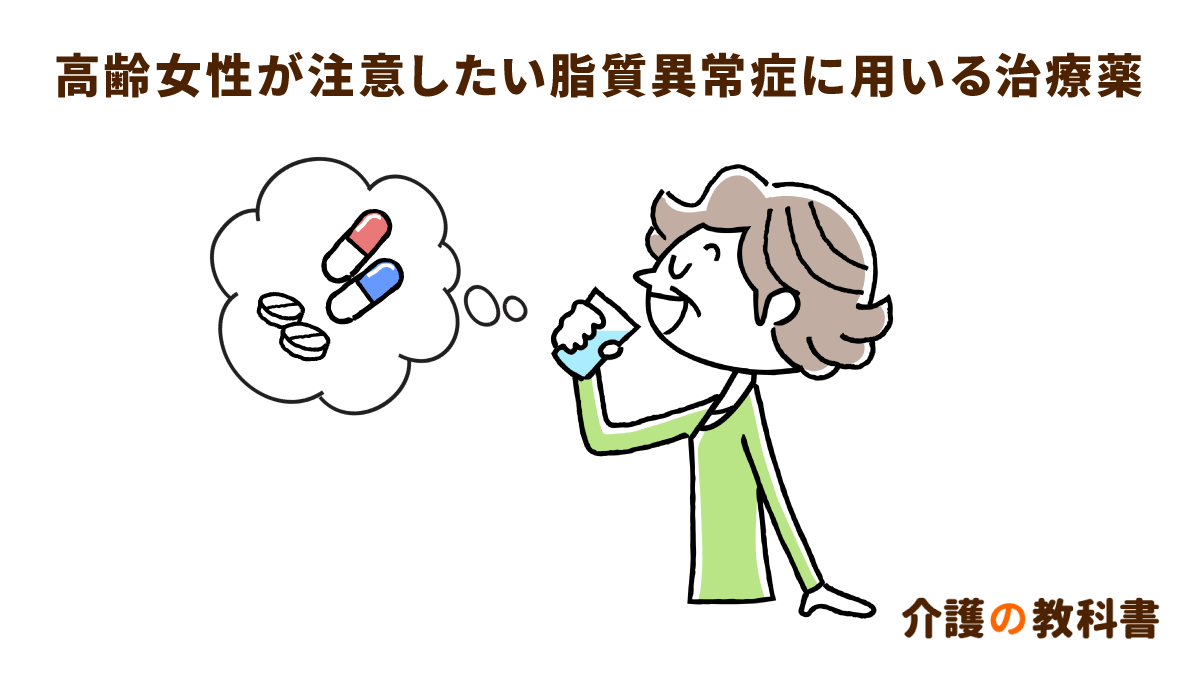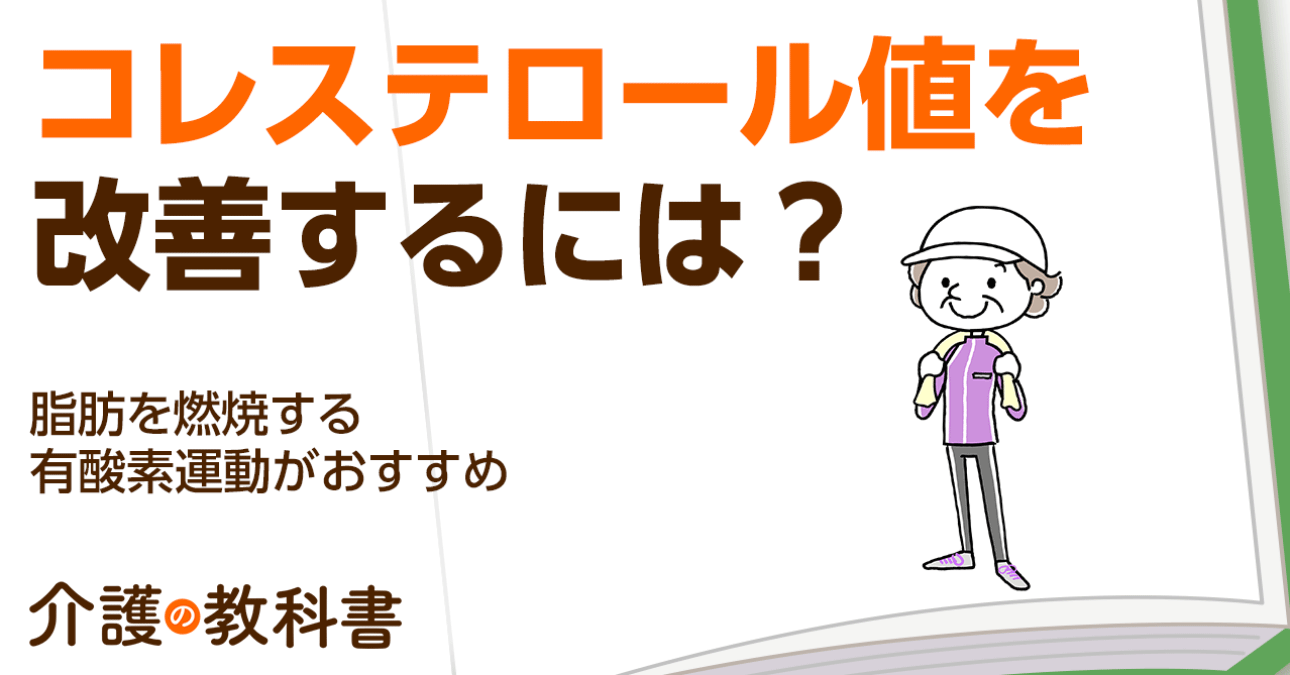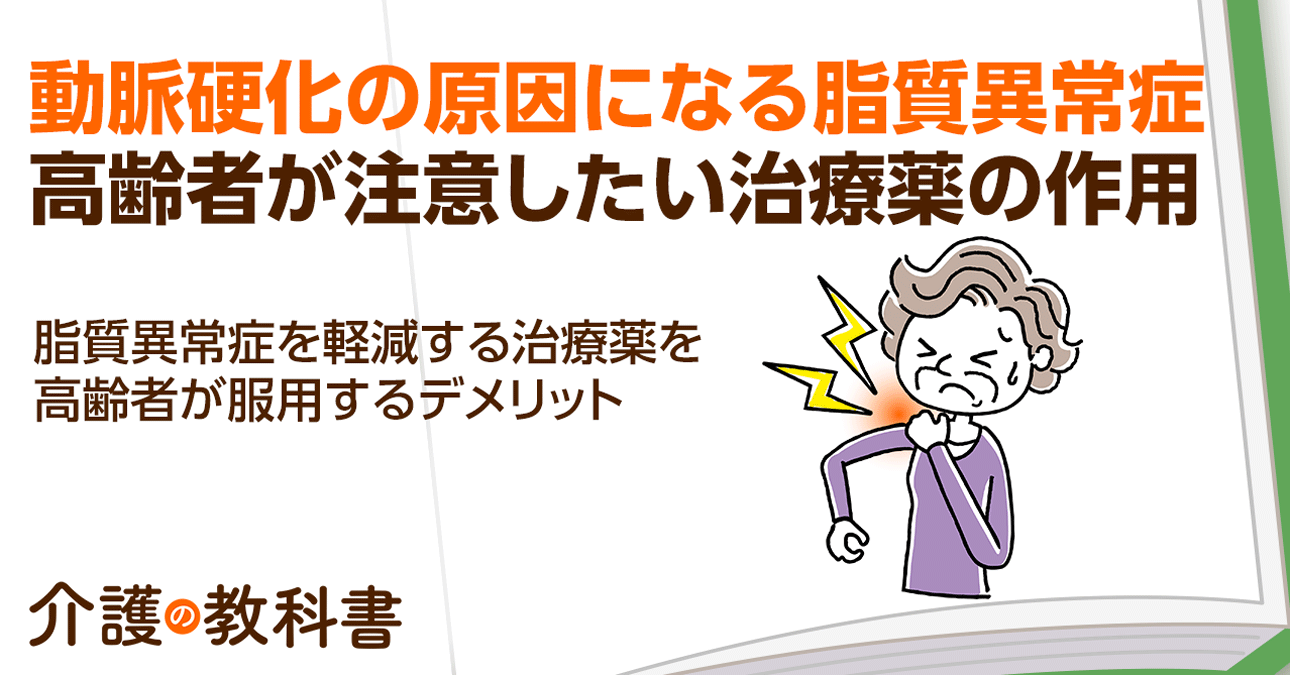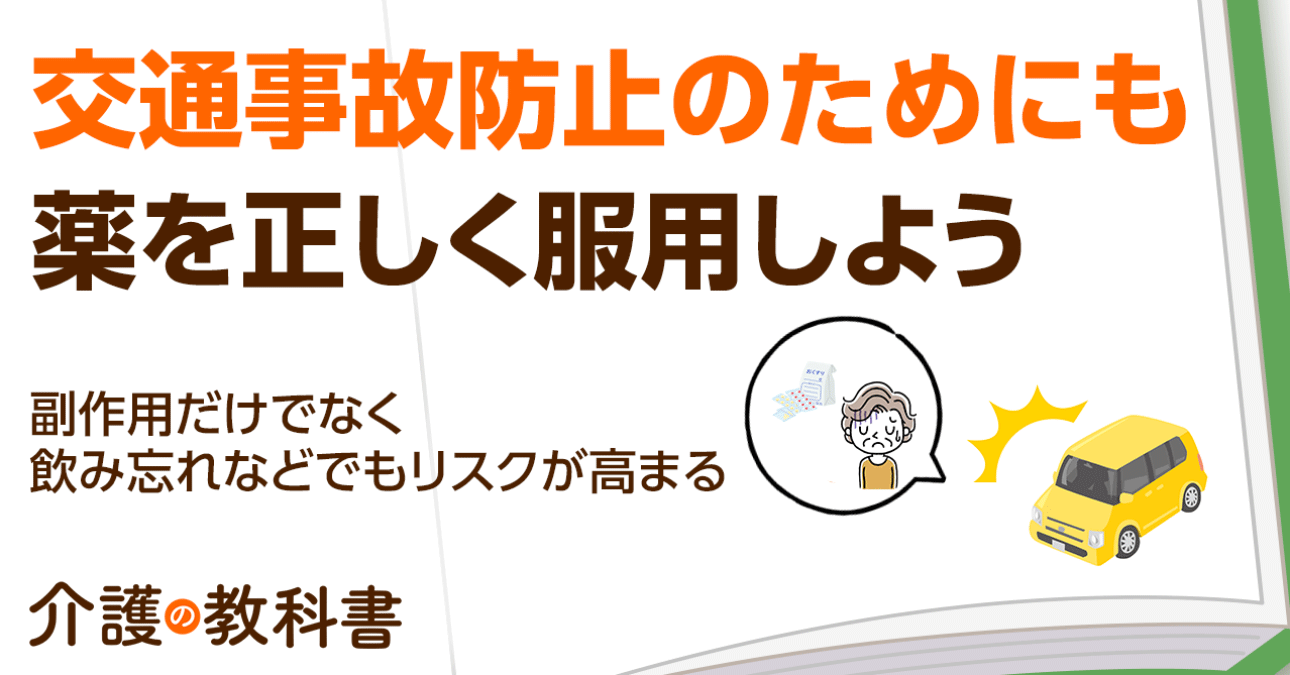血液中の脂質(脂肪分)の値が、一定の基準値から外れた状態を脂質異常症と呼びます。
血液中の脂質には、コレステロールと中性脂肪(トリグリセリド)があり、コレステロールはLDLコレステロール(悪玉コレステロール)とHDLコレステロール(善玉コレステロール)に分けることができます。
脂質異常症の原因はさまざまですが、特に高齢女性で発症しやすいことが知られています。今回は、脂質異常症の原因や治療に用いられる薬について解説します。
脂質異常が起こるさまざまな原因
脂質の異常が起こる原因は一つではありません。良く知られている原因として、「座りがちな生活習慣」「偏りがちな食習慣」「薬や病気の影響」を挙げることができます。
座っている時間と脂質異常症の関連性について、日本人6万2,754人を対象とした研究結果が、日本動脈硬化学会誌に掲載されています。この研究では、男女別、年齢別に座っている時間と脂質異常症の発症リスクが検討されました。
例えば、60~69歳の男性では、座っている時間が1日5時間未満の人と比べて、5~7時間未満で29%、7~9時間未満で16%、脂質異常症のリスクが増加しました。
また、同年代の女性では、座っている時間が1日5時間未満の人と比べて、5~7時間未満で25%、7~9時間未満で10%、脂質異常症のリスクが増加しました。
食習慣では、次に挙げる飽和脂肪酸の多い食品と脂質異常症の関連性が知られています。
- 酒
- スナック菓子
- 赤み肉
- 糖分の多い食品
飽和脂肪酸とは、常温では固形の脂肪分で、乳製品や肉などの動物性脂肪に多く含まれています。一方、常温で液体の不飽和脂肪酸は、植物油などに多く含まれています。
脂質異常を引き起こす病状として、甲状腺の病気や糖尿病、腎臓病などが挙げられます。また、免疫の働きを抑えるような薬(免疫抑制薬)や、利尿薬の中には、血液中の脂質を高める薬があることも知られています。
脂質異常は50歳以降で発症しやすい
一般的に、脂質異常は男性よりも女性で発症しやすい傾向にあり、年齢を重ねるごとに発症のリスクは高まりますが、女性では50歳以降に発症しやすいことが報告されています。
その理由として、年齢に伴う女性ホルモンの変化が挙げられます。女性ホルモンは、コレステロールからつくられているためです。
特に、女性ホルモンの量が大きく減少する閉経後では、血液中のコレステロール値が高くなりやすいとされています。
血液中の脂質が高くなると動脈硬化が起こる
脂質が異常値となっても、すぐに体調が悪くなったり、痛みや吐き気などの症状が出るわけではありません。ただ、LDLコレステロールや中性脂肪の高い状態が続くと、徐々に血管が固くなって弾力が失われていきます。
このように、血管が弾力を失って固くなる現象を動脈硬化と呼びます。
動脈硬化が起こると、血管の内側にコレステロールなどが付着しやすくなり、血管が詰まることもあります。つまり、血液中の脂質が高いと、将来的に心筋梗塞や脳梗塞の発症リスクが高くなるのです。
特に、LDLコレステロールは動脈硬化の強い原因であることが知られており、日本人を対象とした大規模調査でも、LDLコレステロールは心筋梗塞の発症リスクを高めることが報告されています。
中性脂肪もまた、動脈硬化をもたらす原因の一つと考えられていますが、その関連性については、さまざまな研究報告があり、一貫した結果が得られているわけではありません。ただ、日本人を対象とした大規模調査では、中性脂肪が高い人は、心筋梗塞の発症が多いという結果も報告されています。
そのため、糖尿病や肥満など、もともと心筋梗塞の発症リスクが高い方には、中性脂肪を下げる治療が行われることもあります。
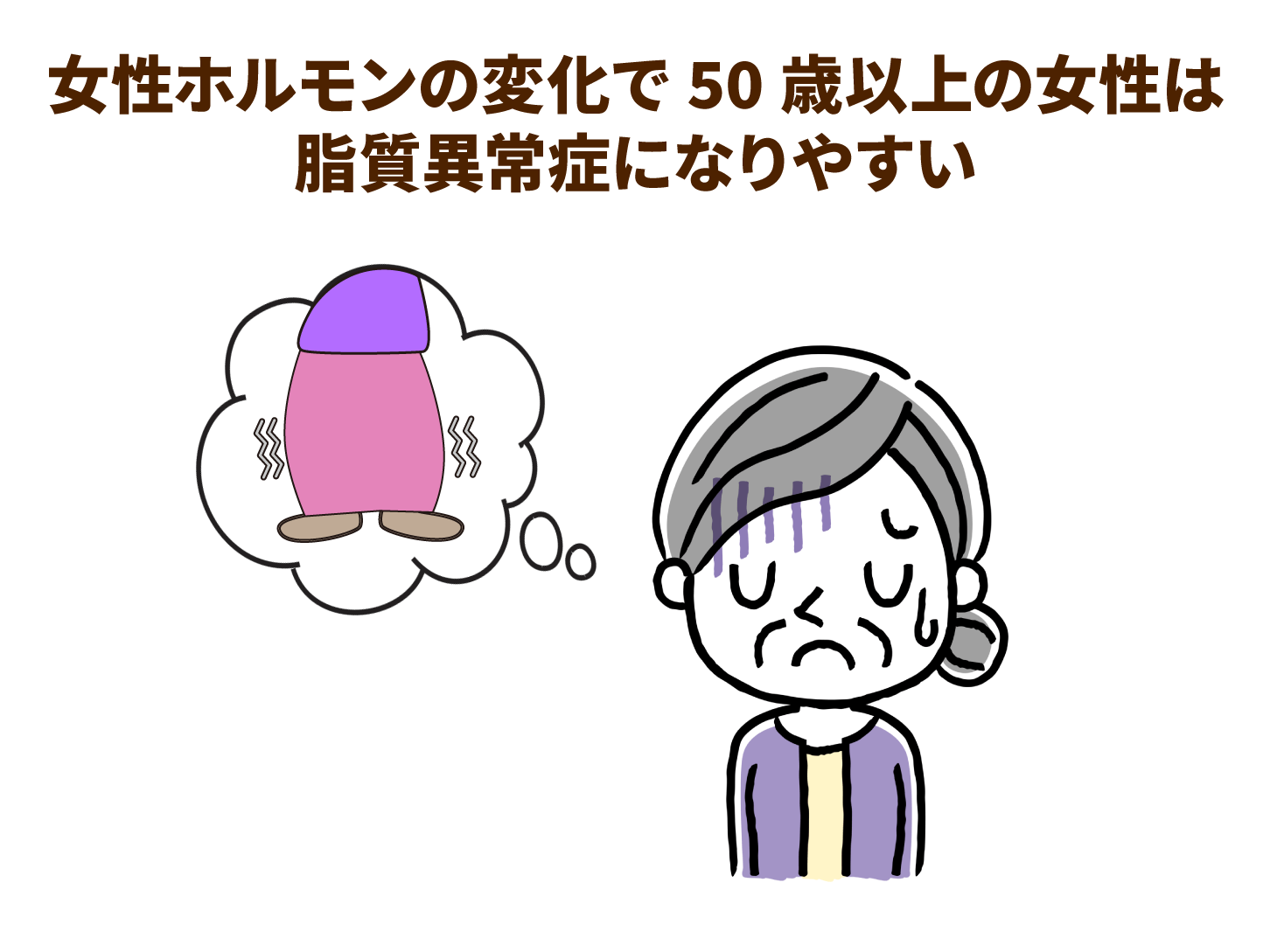
脂質異常症の治療薬とその効果
脂質異常症の代表的な治療薬として、スタチン系薬剤とフィブラート系薬剤を挙げることができます。
日本で使用できるスタチン系薬剤には、プラバスタチン、シンバスタチン、ロスバスタチン、ピタバスタチン、アトルバスタチン、フルバスタチンがあります。
また、フィブラート系薬剤にはベザフィブラート、フェノフィブラート、ペマフィブラートがあります。
そのほか、魚の脂分を主原料として開発されたエイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)、小腸からのコレステロール吸収を妨げるエゼチミブなどの薬が用いられることもあります。
- スタチン系薬剤
- 脂質異常症の治療に用いられる標準的な薬です。特にLDLコレステロールを下げることが知られていますが、脂質の異常を改善するだけでなく、心筋梗塞の発症リスクを約30%低下させることが報告されています。
- フィブラート系薬剤
-
フィブラート系薬剤は、主に中性脂肪を下げる目的で使われますが、心筋梗塞の発症リスクを低下させたとする質の高い科学的根拠(エビデンス)が乏しく、その効果はスタチン系薬剤ほど明確ではありません。
中性脂肪が高いと、将来的な心筋梗塞の発症リスクを高めるので、リスクの管理という観点から、中性脂肪が高くてもフィブラート系薬剤ではなく、最初からスタチン系薬剤が用いられることもあります。
- EPA/DHA/エゼチミブ
- エイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)、エゼチミブについても、心筋梗塞や脳卒中の発症リスクを低下させたとする質の高い科学的根拠は限られています。
ただ、心筋梗塞の発症リスクが高い方ではスタチン系薬剤と併用して用いられることがあります。
脂質異常症治療薬の副作用
スタチン系薬剤やフィブラート系薬剤の代表的な副作用が筋肉痛です。しかし、その多くが薬による直接的な影響(副作用)ではなく、プラセボ効果である可能性が報告されています。
つまり、本当は薬の副作用ではないのに、思い込みで筋肉痛が起こってしまうことが多いのです。
こうした背景には、スタチン系薬剤やフィブラート系薬剤の重大な副作用である「横紋筋融解症」が関係しているものと考えられます。
スタチン系薬剤による横紋筋融解症
横紋筋融解症とは、何らかの原因によって、筋肉の細胞が壊れてしまい、筋肉成分が血液中に溶け出してしまう病気です。その原因の多くは薬によるもので、特にスタチン系薬剤との関連性が知られています。
横紋筋融解症が起こると、強い筋肉痛や脱力感といった症状が出ます。また血液中に流れ出た筋肉成分が腎臓の細い血管につまり、腎機能に障害を起こすこともあります。
薬局で薬をお渡しするときには、横紋筋融解症のような重大な副作用についての説明も行います。
そのため、薬を受け取った患者さんが、「何となく筋肉痛がする」といったような思い込みによる副作用を経験することも多いのだと思います。ただ、スタチン系薬剤による横紋筋融解症の発生頻度は極めて稀であることが知られています。
例えば、アトルバスタチンを1万人に5年間投与すると500~1,000人の心筋梗塞や脳卒中を予防することができる一方で、横紋筋融解症の発症はわずか1人の確率です。
フィブラート系薬剤についても横紋筋融解症の副作用が知られていますが、スタチン系薬剤と同様にその発生頻度は極めて低いと考えられています。
ただし、フィブラート系薬剤とスタチン系薬剤と併用した場合は横紋筋融解症の発生リスクが高まることから、両者を併用投与する際には注意が必要です。
スタチン系薬剤による糖尿病リスク
また、スタチン系薬剤は、糖尿病の発症リスクをわずかに高めることが知られています。2010年に報告された研究によれば、臨床試験データ9件を解析したところ、糖尿病の発症リスクが9%ほど増加したことがわかっています。
しかし、現在では、スタチン系薬剤による糖尿病リスクは、心筋梗塞の予防効果に比べれば小さなものだと考えられています。
また、糖尿病の発症リスクはスタチン系薬剤の種類によっても異なり、アトルバスタチンやロスバスタチンで高い一方、プラバスタチンやピタバスタチンで低いことが報告されています。
糖尿病のリスクはごくわずかであるといえますが、スタチン系薬剤を服用中の方では、コレステロール値だけでなく、血糖値の変化にも注意しておくと良いでしょう。