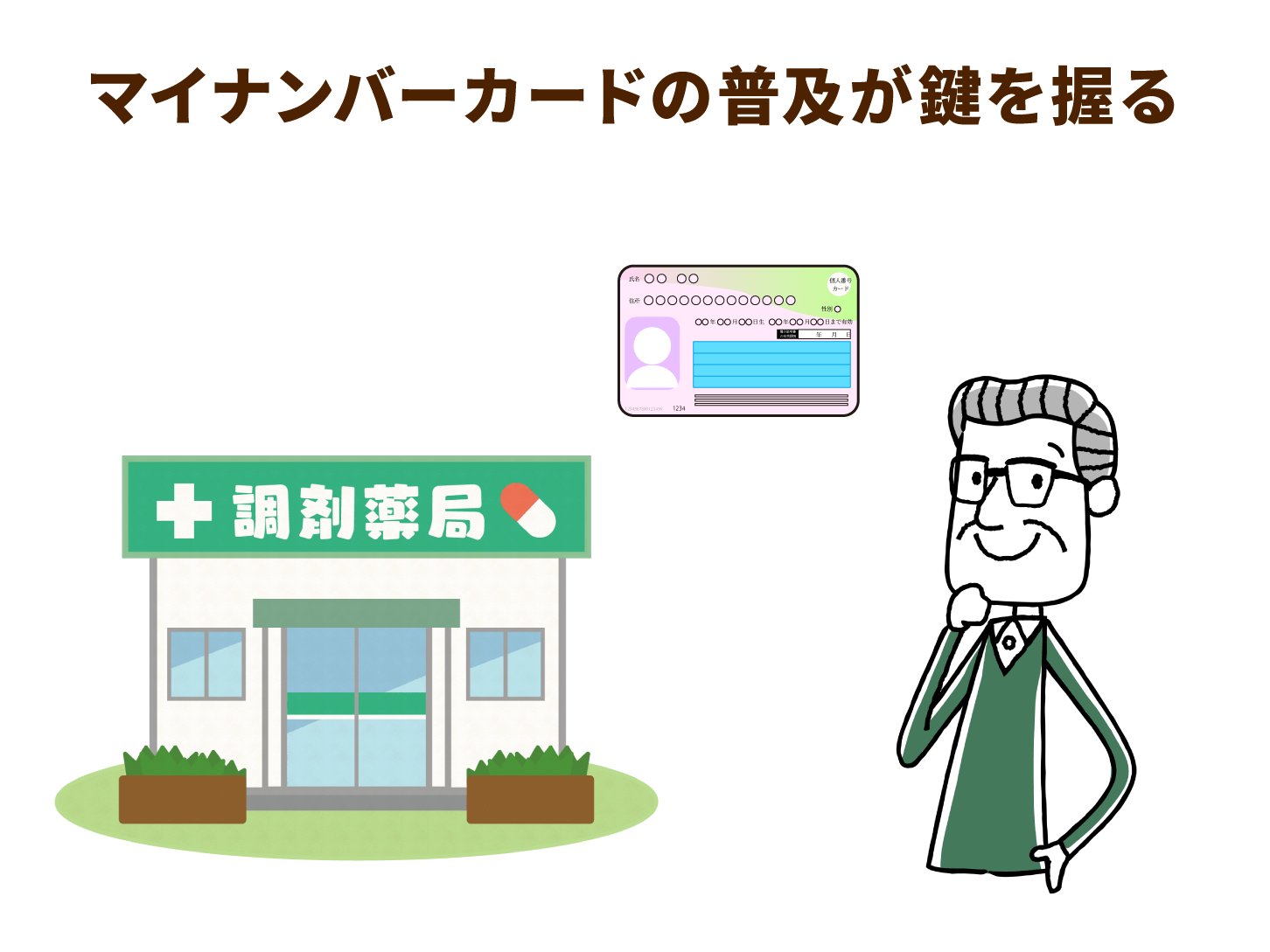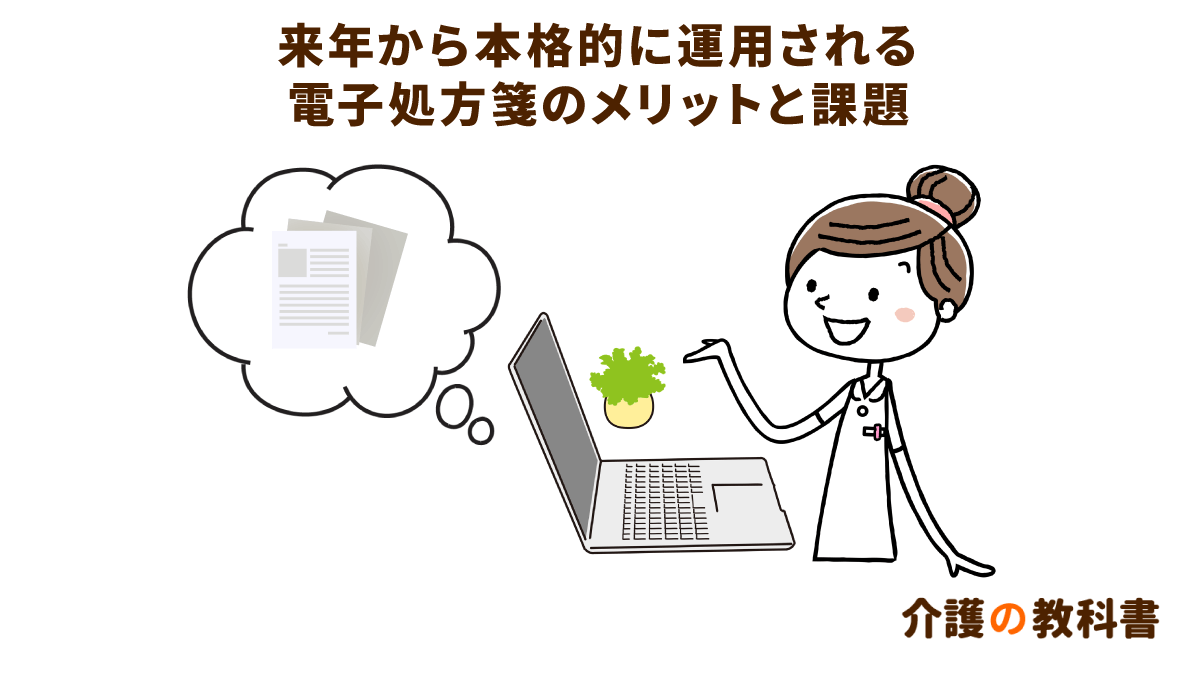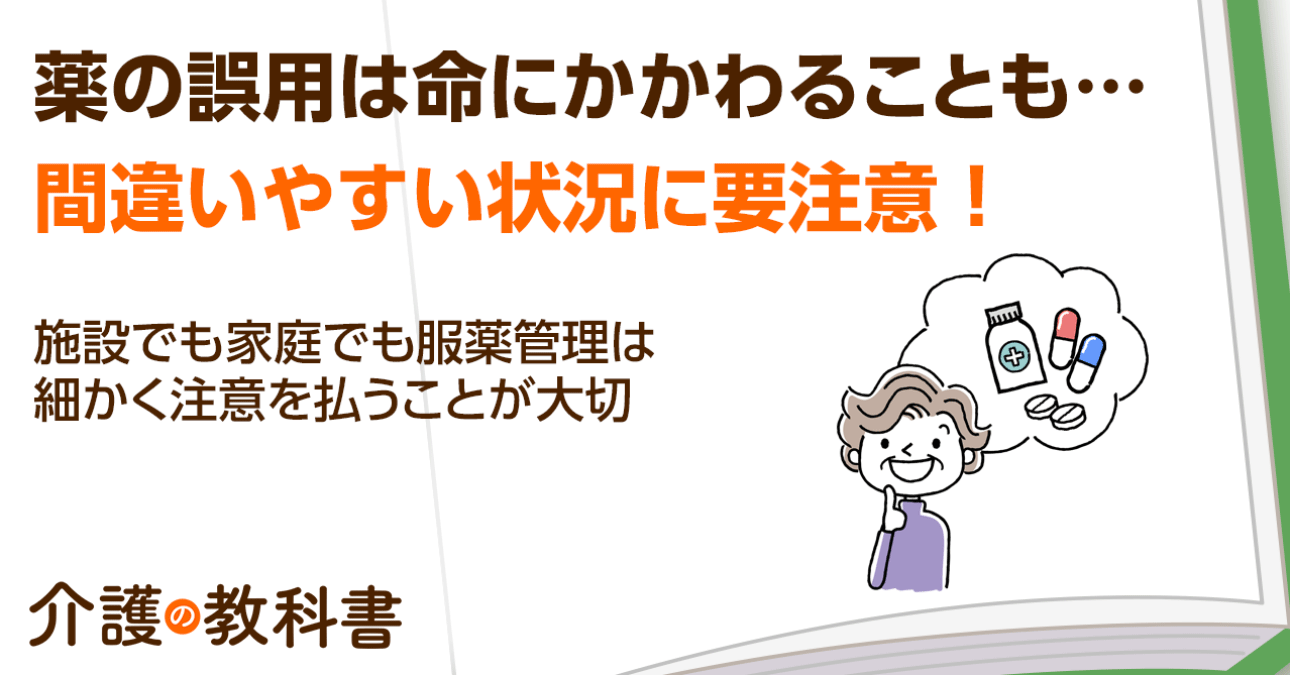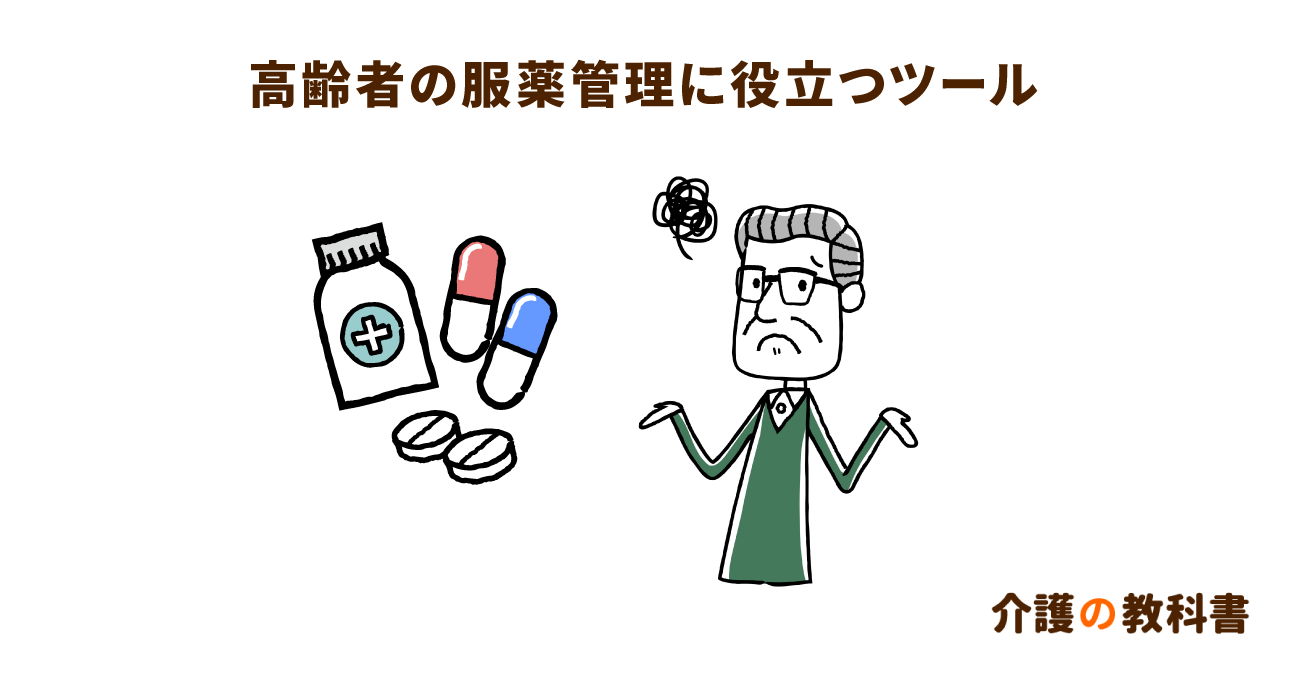病気の治療に必要な薬の種類や飲み方が書かれた書類を処方箋と呼びます。病院で受診すると、診察を担当した医師によって処方箋が発行されます。
患者さんが処方箋を保険薬局へ持ち込むと、その内容を確認した薬剤師が薬の調剤を行います。調剤とは、薬剤師が処方箋に基づいて薬を揃え、調合する業務のことです。
このように薬の処方と調剤を分離し、それぞれを医師、薬剤師という専門家が分担して行うことで、安全な医療の提供を目指す仕組みを医薬分業と呼びます。
インターネットの普及とともに、紙の書類の多くが、デジタルデータに置き換えられています。医療現場でも医師の診療内容を記録するカルテ(診療録)や、薬剤師の調剤内容を記録する薬剤服用歴管理の記録簿(薬歴)が電子化されつつあります。
その流れの中で、これまで紙だった処方箋も、2023年1月から電子処方箋が本格的に導入される予定です。この記事では電子処方箋の仕組みについてご紹介し、そのメリットや将来の展望についてまとめます。
電子処方箋とはどんな制度か
電子処方箋とは、これまで紙で運用されていた処方箋を、デジタルで行う仕組みです。
具体的には、医師の作成したカルテから、薬の処方内容をデジタル上に保存し、そのデータを薬局に送信することで、紙の処方箋を発行することなく、薬剤情報の伝達や管理が行われます。
電子処方箋の仕組みは、マイナンバー制度や健康保険のオンライン資格確認をはじめとする社会制度の電子化に伴って構想されたものです。
医薬分業が急速に拡大した医療現場において、電子処方箋は情報伝達や管理の効率化だけでなく、医療機関同士の円滑なコミュニケーションを促す役割が期待されています。
例えば、複数の医療機関を受診している患者さんの場合、処方箋を電子化することにより、それぞれの病院から処方されている薬を薬局で適切に管理することが可能となります。
薬の飲み合わせや重複の確認を、素早く正確に行えるだけでなく、副作用やアレルギー情報などを病院と薬局で共有することにより、安全で質の高い医療サービスを提供できるようになります。
さらに、処方箋が電子化されることで、紙や印刷にかかわるコストが抑えられ、処方箋の偽造や不正使用、紛失なども防げます。また、インターネットとビデオ機能による遠隔診療が本格的に普及した際には、電子処方箋が必要不可欠となるでしょう。
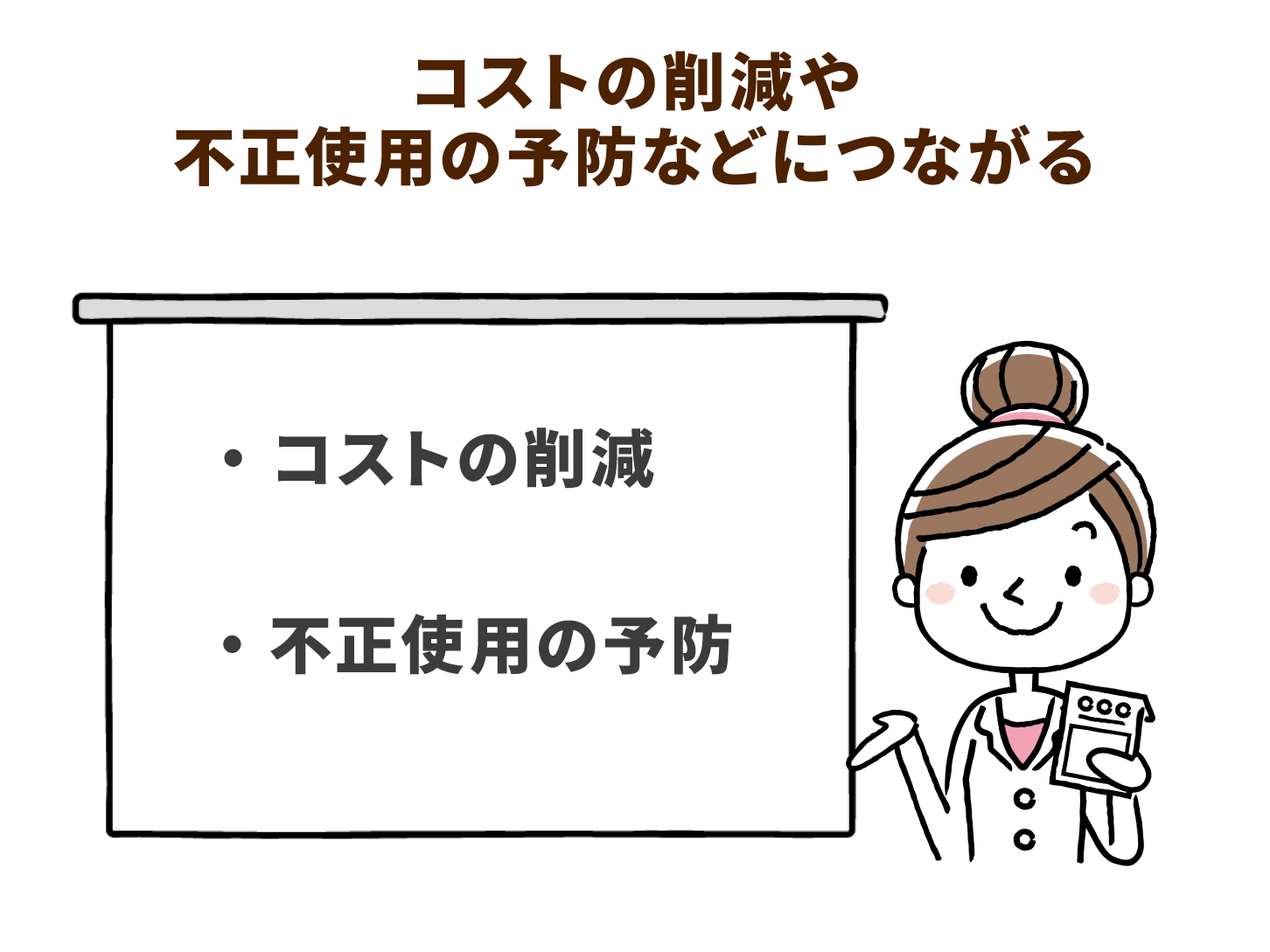
処方箋の電子化は、日本のみならず世界中で同様の取り組みが行われています。日本における医療情報サービスの電子化は、世界各国の状況と比較すれば遅れているといった方が良いかもしれません。
例えば、国民の多くが個人番号を取得しているエストニア共和国では、2008年から医療情報サービスの電子化が進められ、電子処方箋は2010年に導入、現在ではほぼすべての処方箋が電子化されています。
電子処方箋のさまざまなメリット
電子処方箋を導入することで、医療機関同士の情報伝達を容易にするだけでなく、さまざまなメリットが期待されています。
例えば、米国で行われた電子処方箋に関する研究によれば、電子処方箋の導入により、処方に関する記載の誤りが7分の1に減少し、さらに医療費の節約にも役立つと報告されています。
また、厚生労働省が公開している「電子処方箋の運用ガイドライン(第2版)」では、患者さんやそのご家族に対して、次のようなメリットが提示されています。
- 遠隔診療の際、処方箋の原本をスマホなどで受け取ることが可能になり、結果的に医療機関での待ち時間が短縮される
- 薬局から調剤情報をもらって、患者自らが服薬情報の履歴を管理できる
- 電子版お薬手帳などとの連携によって、患者や家族が管理する服薬履歴などを、ほかの医療機関などへの提示が簡単になる。生活環境の変化などにより医療機関や薬局を変更した場合でも、継続的な診療が簡単になる
- 患者が公共機関(自治体など)に情報を預けることで、在宅医療や救急医療、災害時に、患者の服用している薬剤を医療関係者が知ることができる
電子処方箋の導入によって、病院と薬局の間で情報のやり取りが容易になることから、これまで主に電話やFAXで行っていた医療機関同士の問い合わせは、大きく減少することでしょう。結果的に、調剤を速やかに行うことが可能となり、患者さんの待ち時間が短縮するのです。
また、電子版のお薬手帳をご利用されている患者さんは、電子処方箋の仕組みと連動させることによって、ご自身でも薬の情報管理が可能となります。災害時や緊急で医療機関を受診した際でも、服用している薬の名前や治療中の病名などを正確に医療スタッフに伝えることができます。
データヘルスが進む中での薬局のあり方
安倍政権時代の2013年6月に閣議決定された日本再興戦略では、「国民の健康寿命の延伸」が重要施策の一つとして掲げられていました。健康寿命とは、健康上問題がなく、日常生活が送れる期間のことです。
そして、その健康寿命の延伸を実現するために立案された事業計画にデータヘルス計画があります。2018年度からは第2期データヘルス計画が開始され、2023年度までの6年間がその期間となっています。
データヘルス計画は、健康診断の結果やレセプト(医療機関でかかった費用のうち、健康保険組合などが負担する分の請求書)の情報に基づき、医療費の状況把握、健康に関するリスクの分析、保健事業の効果が高い患者さんの抽出などを行います。
つまり、やみくもに事業を行うのではなく、データを活用して科学的にアプローチすることで、効率的かつ効果的に実施する事業計画なのです。
健康や医療、介護に関連した事業を展開する多くの企業がデータヘルスに関心を向けています。
保険薬局でも、データヘルスに関連した取り組みが期待されています。例えば、健診データに基づいた医療機関の受診勧奨プログラムの提供、血液検査のデータに基づいた生活習慣の改善アドバイス、後発(ジェネリック)医薬品への切り替え提案などをあげることができます。
一方で、処方箋の電子化やデータヘルス計画の実行にあたっては、マイナンバー制度の普及が急務です。総務省によると、マイナンバーカードの交付率は42%にとどまっており(2022年3月22日時点)、電子処方箋の実用化までに交付率をさらに高める必要があるでしょう。
また、病院や薬局などの医療機関においても、電子処方箋に対応するための設備を導入したり、システムを入れ替えたりなど、解決しなければならない課題は決して少なくないように思います。