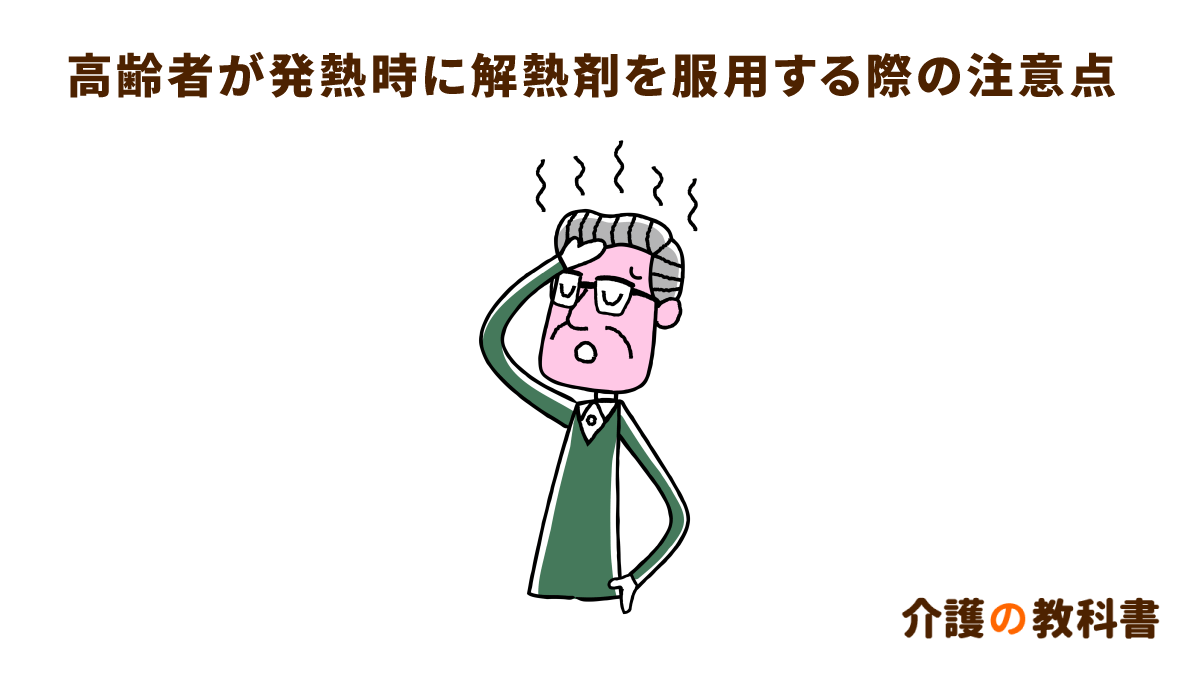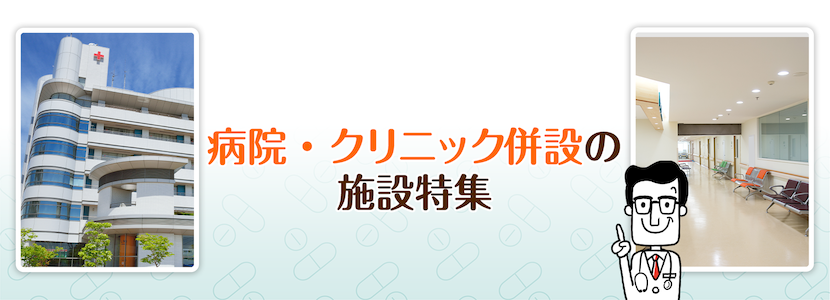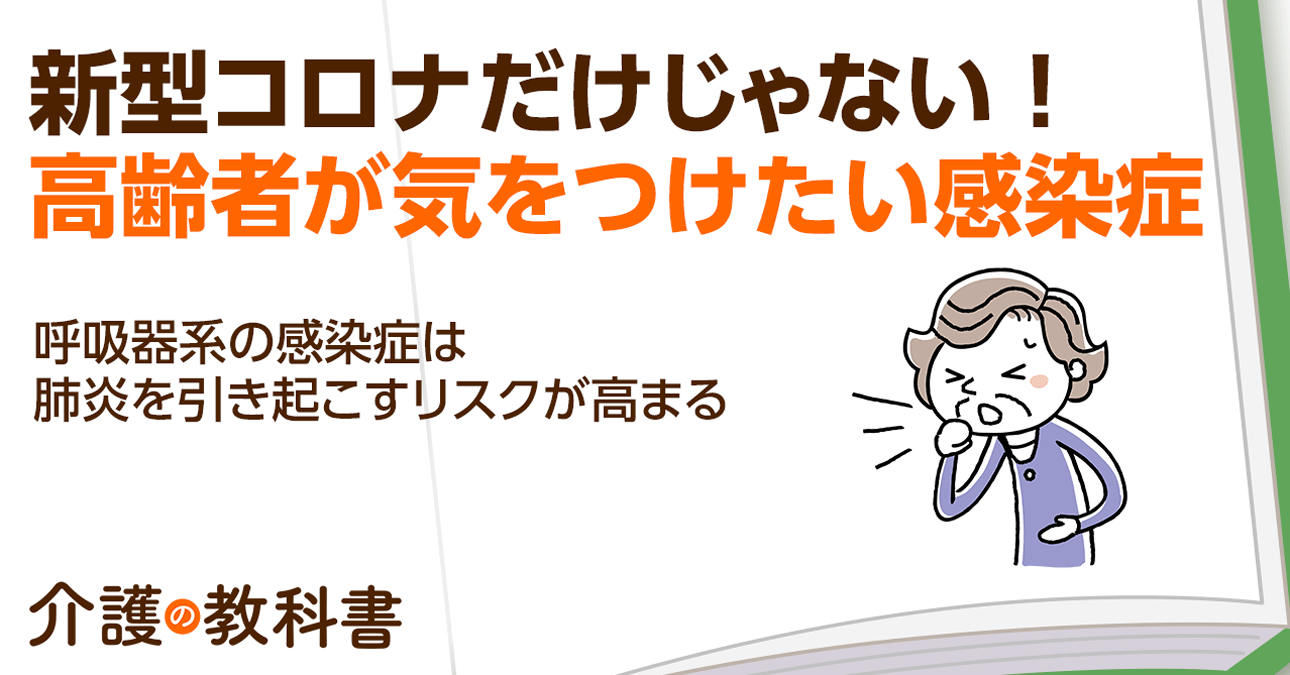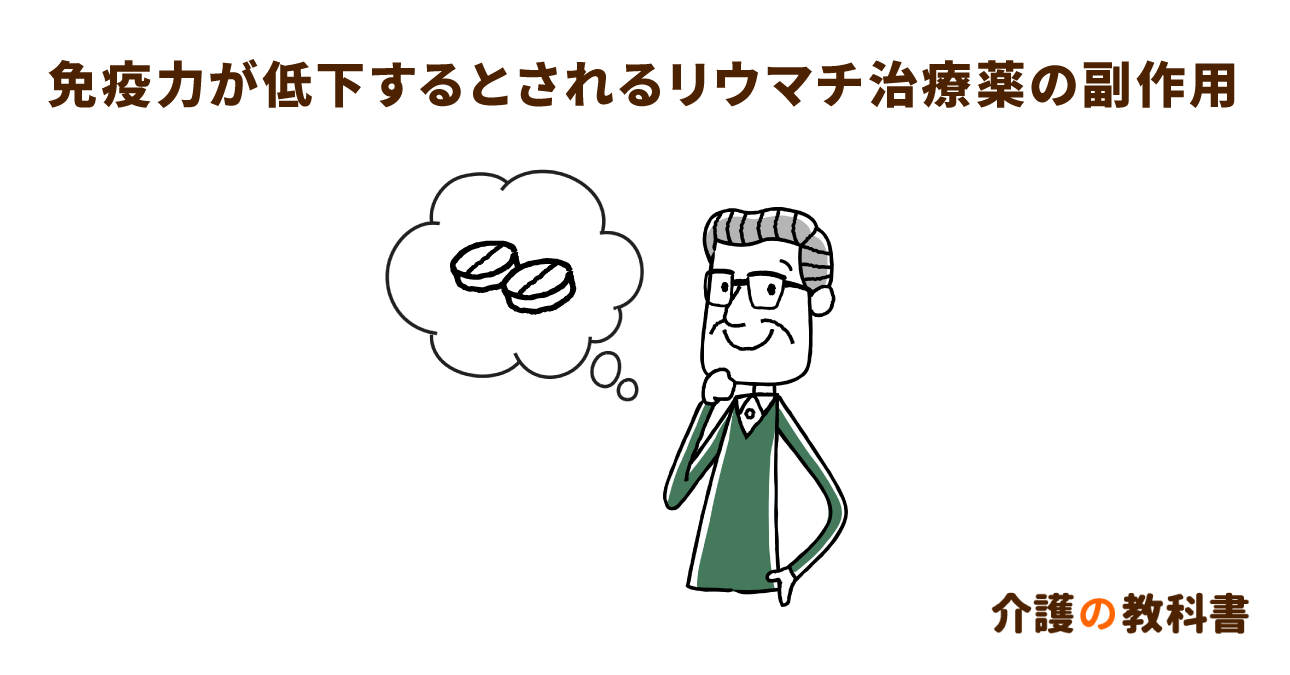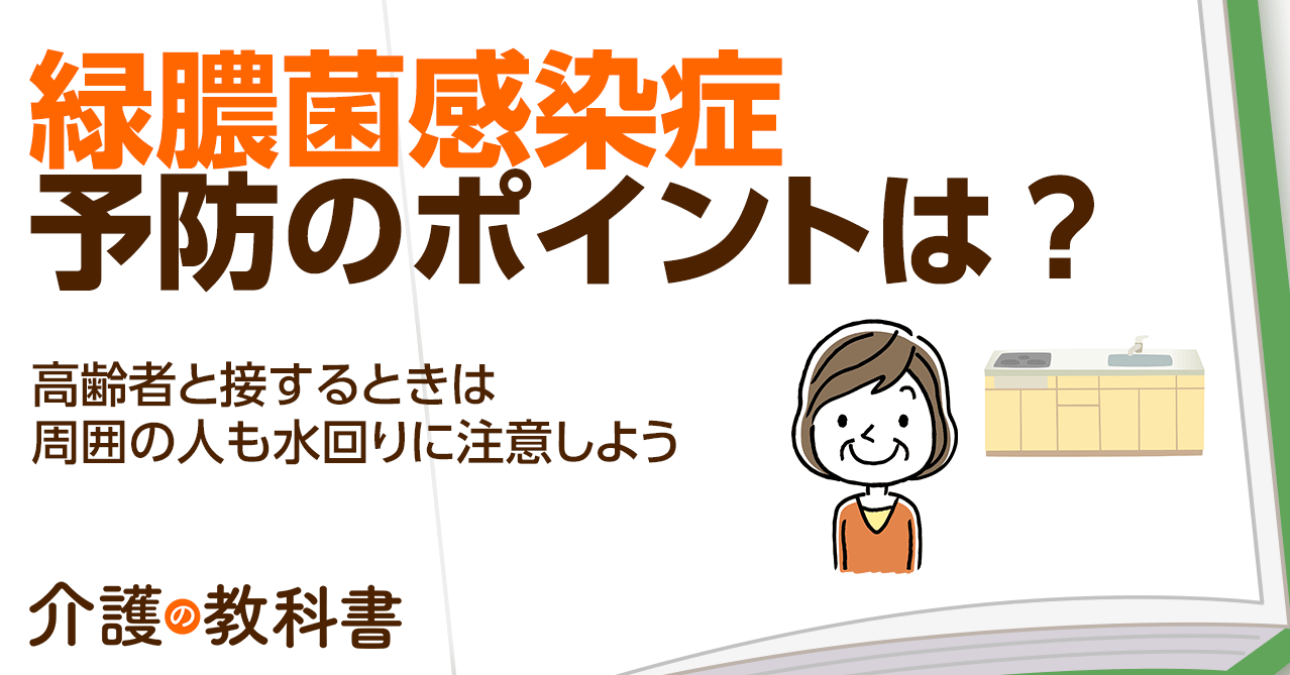高齢の方は風邪やインフルエンザなどの感染症に罹りやすく、重症化しやすいと言われています。年齢を重ねるにつれて、細菌やウイルスに対する防御力が低下し、感染をきっかけに肺炎などを起こしやすいからです。
発熱で病院を受診した人を対象に、年齢別に熱の原因を分析した海外の研究によれば、若い方では風邪などの一般的な感染症が多かった一方で、高齢の方では軽症者の数が少なく、入院する方が多いと報告されています。
発熱は感染症の代表的な症状の一つですが、高齢の方では発熱が見られないことも少なくありません。また、感染症とは異なる原因で発熱することもあります。そこで今回は、高齢者の発熱の特徴と、解熱剤を使用する際の注意点について解説いたします。
発熱のメカニズムを知ろう
正常な体温(平熱)はどれくらい?
人の体温は、血圧や血糖などの数値と並んで、健康状態を知るための大切なバロメーターとされています。のどの痛みや鼻水などの風邪症状や、体のだるさ(倦怠感)を感じたら、薬を飲むよりも先に、体温を測る人の方が多いのではないでしょうか。
体温で健康状態の良し悪しを考えるためには、「正常な体温」を知る必要があります。この正常な体温は「平熱」とも呼ばれ、一般的には36.5℃前後が目安とされています。
2019年に報告された学術論文によれば、正常な体温はわきの下の検温で35.01℃から36.93℃でした。また、この論文では60歳以上の方では60歳未満の方と比べて、体温が0.23℃低いことも報告しています。
高齢の方ほど、正常な体温は低い傾向にあります。ただ、体温は個人差も大きく、37℃を超えているからといって、必ずしも健康状態が悪いというわけではありません。
発熱の原因は?
発熱はさまざまな病状によってもたらされますが、感染症は最も一般的な熱の原因になります。ウイルスや細菌、あるいはこれらの微生物が体内でつくり出した物質に対して、免疫機能が働きかけることで発熱が起こります。
しかし、海外の研究によると、高齢の方の2~3割は感染症に罹っても発熱しないとされています。歳を重ねるにつれて、免疫の反応が鈍くなっていることから、熱が上がりにくいためだと考えられます。そのため、病状の悪化に気づくのが遅れ、感染症が進行してしまう危険性もあります。細菌やウイルスに感染しても熱が出ないことは、感染症が重症化しやすい理由の一つなのです。
発熱は感染症だけでなく、関節リウマチや花粉症などの免疫機能に関連した病気、肺炎や気管支炎、あるいはがんなどの炎症を伴う病気でも起こります。また、ごくまれに薬の副作用で発熱することもあり、これを「薬剤熱」と呼びます。
どんな人が発熱しやすいのか
東京都内5ヵ所の診療所で行われた研究によれば、高齢の方の中でも介護の必要性が高い患者さんで発熱の受診が多く、その理由の大半が肺炎や気管支炎でした。
また、在宅医療を受けている65歳以上の方を対象とした日本の研究でも同様の結果が示されています。105人を対象としたこの研究では、1年間で約半数の人が発熱し、介護が必要な人ほど発熱が多かったと報告されています。また、発熱の理由は肺炎や気管支炎が最も多く、次いで尿路感染症(膀胱炎)や皮膚の感染症でした。
なお、肺炎は感染症だけでなく、食べ物でも引き起こされることがあります。特に嚥下(えんげ)機能が低下している方では飲み込んだ飲食物が、胃の中ではなく、気管支やその奥の肺に入ってしまい、炎症を起こすことがあります。このように、食べ物や飲み物が上手く飲み込めないことで引き起こされる肺炎を「誤嚥性肺炎」と呼びます。
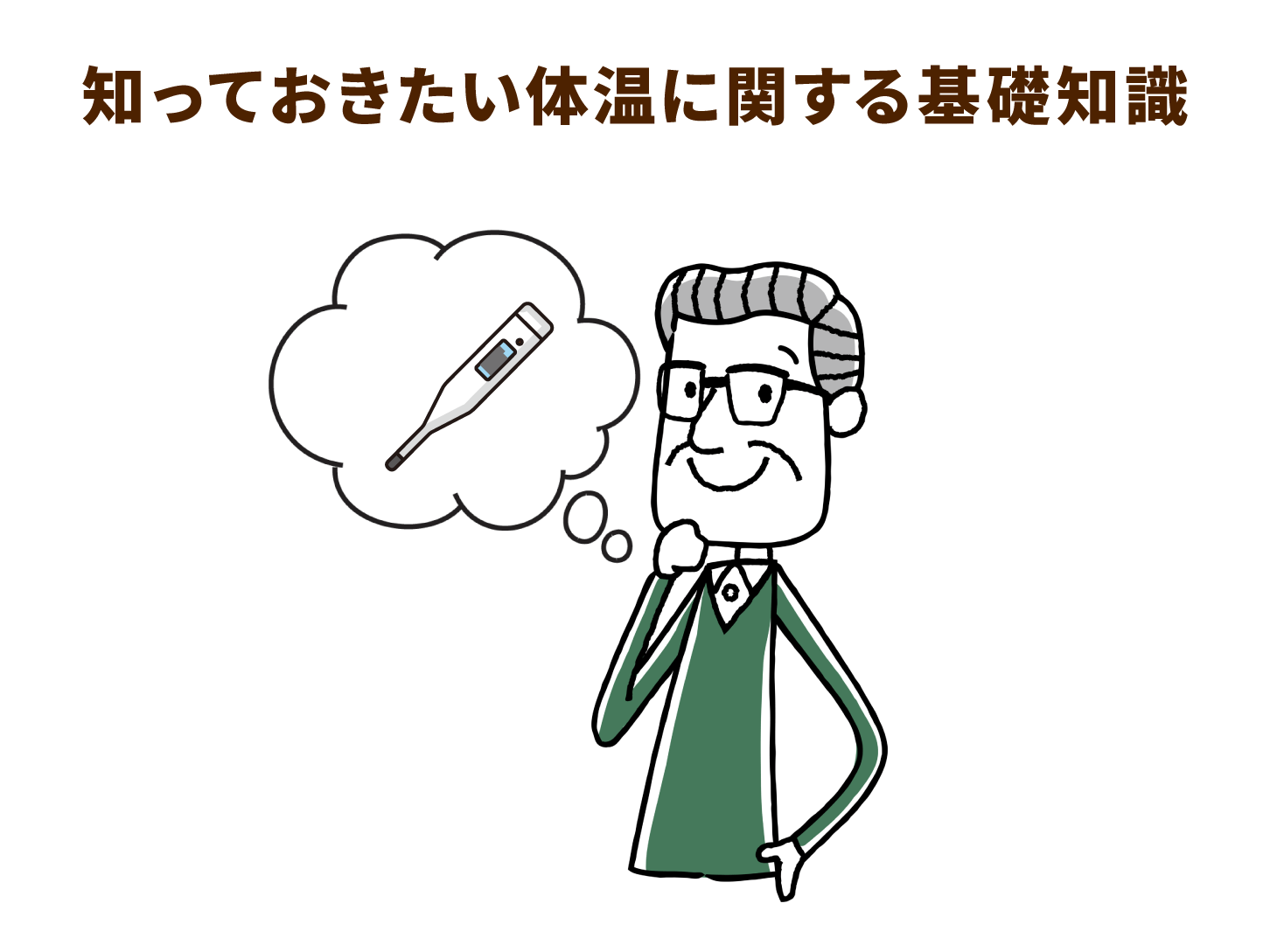
発熱したら解熱剤を使った方が良い?
解熱剤は熱を下げる効果を期待できますが、病気の原因を取り除くものではありません。そのため、一般的な風邪では無理に解熱する必要性はほとんどありません。
発熱は病状に対する適切な体の反応であり、特に感染症では発熱によって免疫機能が高まり、症状が早く治る可能性さえあります。実際、風邪に罹った人を対象とした日本の研究では、解熱剤を服用しない場合に比べて、服用した方が風邪が早く治るどころか、むしろ長引く傾向が報告されています。
また、体温は健康状態のバロメーターでもあります。病院を受診する前に自己判断で解熱剤を飲んでしまうと、医師の診察時に「発熱」という重要なサインが見逃されてしまい、病気の発見が遅れてしまうこともあり得ます。
自己判断で解熱剤を使っても良いケース
一般的な風邪の症状であれば、解熱剤を使っても良いように思いますが、正常な体の反応ですから、熱で体がだるく、つらいと感じているときだけ服用すると良いでしょう。
なお、2019年末から感染が拡大した新型コロナウイルスによって、一般的な風邪なのか、新型コロナウイルス感染症なのか、あるいはインフルエンザ感染症なのか、一般の方が判断することは難しくなっています。
のどの痛みや鼻水のほか、長引く高熱、息苦しさや頭痛、味覚障害、関節の痛み、ひどい寒気など、いつもと違う風邪だなと感じたら解熱剤を飲むことは避け、速やかに医療機関を受診しましょう。
医療機関を受診した方が良いケース
一般的な風邪は熱だけが出ることは少なく、同時に鼻水や咳、喉の痛みなど、さまざまな症状を伴います。つまり、熱だけが出ているという状態は「ただの風邪」ではないことの方が多いといえるでしょう。
高齢の方では、感染症以外にもリウマチなどの膠原病やがんなどの病気が原因で発熱することもあります。また、微熱が長く続いてる場合には結核(結核菌による感染症)も疑われます。
熱だけが出ている場合は自己判断で解熱剤を使用することは避け、できる限り速やかに医療機関を受診しましょう。
解熱剤を使う際の注意点と、市販薬の選び方
体の中ではさまざまな物質がつくられますが、炎症を引き起こし、痛みや発熱のもとになる体内物質にプロスタグランジンがあります。解熱剤は、体の中でプロスタグランジンがつくられるのを防ぐことで解熱作用をもたらすと考えられてます。
解熱剤に共通する一般的な副作用が、胃炎や胃潰瘍などの胃症状です。痛みのもとになるプロスタグランジンにはさまざまな働きが知られており、胃の中では粘膜の表面を保護する役割を担っています。
解熱剤を服用すると、胃の粘膜にあるプロスタグランジンの働きも弱まり、胃が損傷しやすくなってしまいます。そのため、胃痛や胸やけなどの症状、場合によっては胃の粘膜が炎症を起こしてしまったり(胃炎)、ひどい場合には胃潰瘍まで進行してしまうこともあります。
解熱剤は胃に対する負担を和らげるため、空腹時を避けて服用することが一般的です。食後に解熱剤を服用すると、即効性が期待できないという研究報告もありますが、食後に服用した方が胃への副作用リスクを大きく減らすことができます。
解熱剤の中でも、アセトアミノフェンと呼ばれる薬剤成分は、プロスタグランジンの合成を阻害する働きが弱く、胃に負担をかけにくいと考えられています。高齢の方が市販の解熱剤を飲む際には、アセトアミノフェンだけを配合した解熱剤が良いかもしれません。