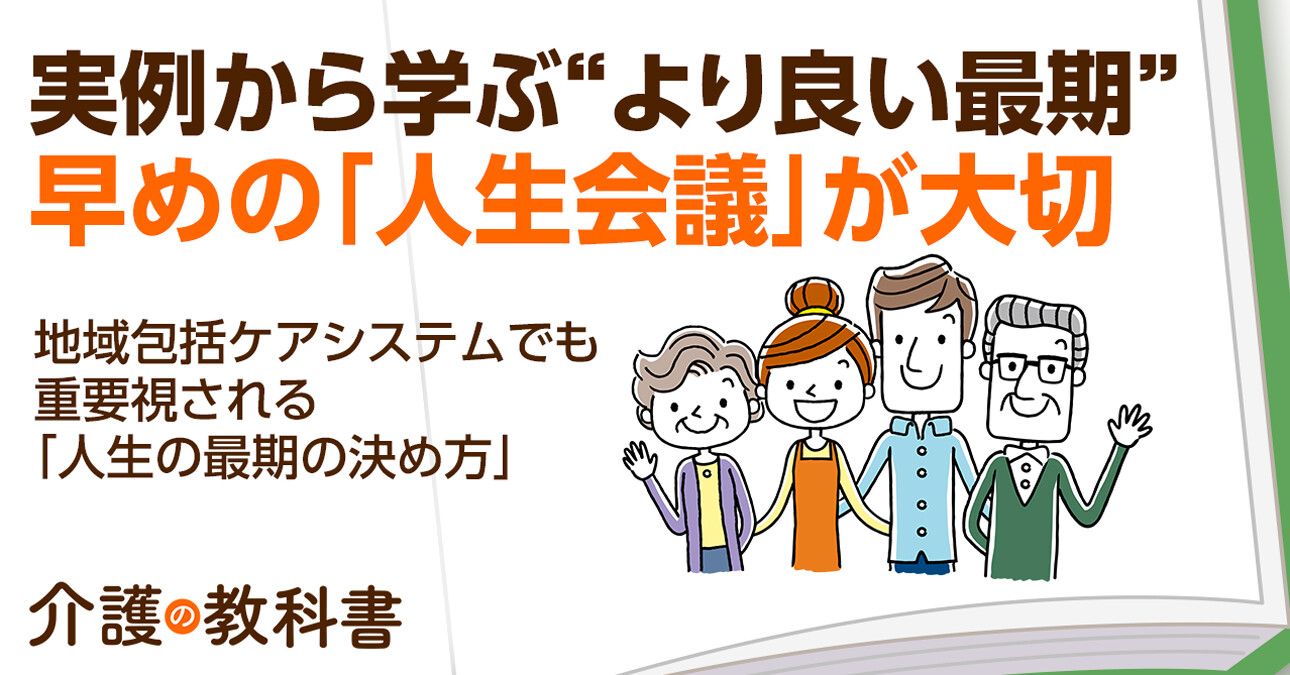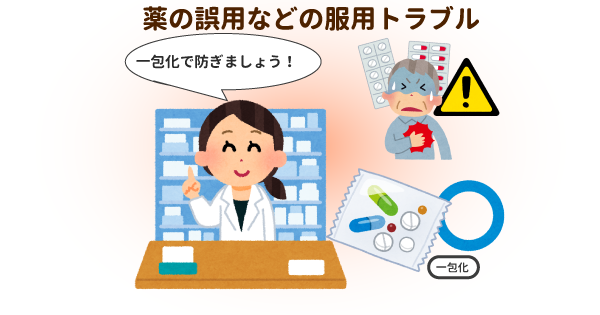病院を退院し、在宅医療に入るときに行う医療・介護連携会議のことを、退院時(退院前)カンファレンスと呼びます。
訪問看護師やケアマネージャーの仕事に従事している方は、参加経験がある方も多いかと思います。その会議に薬剤師の参加はあったでしょうか。実際にはまだまだ薬剤師の参加が少ないのが現実です。
今回は退院時(退院前)カンファレンスに薬剤師が参加することで得られるメリットについてご紹介いたします。
自宅での看護を希望する末期がん患者
以前私が退院時(退院前)カンファレンスに参加したときのことです。
その人は、がんによる痛みが出ており、医療用麻薬を使用していました。また口から食べ物を摂取することが難しく、中心静脈栄養と呼ばれる注射での栄養補給をしていました。
病院からは緩和病棟に入院し続けて看取りまでしていただける提案もありましたが、本人とご家族から「家にもう一度帰りたい」という強い希望がありました。
医師からは、「医療用麻薬と中心静脈栄養の治療を在宅で行うことができれば退院できます」と言われました。
このようなとき、ご本人やご家族の希望や想いだけを優先して退院を急いでも、在宅療養の準備が整っていなければ結局は本人、家族や周囲の人を苦しめてしまいます。ケアマネージャーと一緒に病院での治療を在宅で継続できるような環境を整える必要がありました。

カンファレンスで話し合われること
そこで病院の医師や病棟看護師、地域医療連携室の看護師、本人、ご家族、ケアマネージャー、私(薬剤師)で集まりました。これが退院時(退院前)カンファレンスです。現在の治療内容と病状確認、在宅療養に移行する際の課題について検討する会議を行いました。この会議では、痛みの訴えが今後も増える可能性があること、中心静脈栄養を行わないと脱水症状にもつながってしまう恐れがあることの説明がありました。
退院後は、在宅訪問医師や訪問看護師に医療面を支えていただくとともに、医療用麻薬の扱いや中心静脈栄養の手配には薬局薬剤師の関与が必要です。
医療用麻薬や注射薬のような特殊な医薬品類は取り扱うことのできる薬局が限られているだけでなく、たとえ扱うことができても、薬局や医薬品卸に在庫が常時存在するとは限りません。薬がなくて治療できないということにならないよう、使用する薬がわかり次第、薬局は早い段階で医薬品卸に注文をかけておく必要があります。
また、病院で使用できる注射薬でも、在宅医療では使用に制限がかかる注射薬も存在します。そのため、医師がどのような注射薬を使用して治療方針を立てているのかを事前に確認し、場合によってほかの薬に変更しておく必要があります。
薬剤師がカンファレンスに参加していると、その場で医療用麻薬の種類や使用頻度を確認し、中心静脈栄養に用いる液剤の種類の確認、点滴速度、点滴に用いるチューブなどの医療材料・衛生材料の確認、ほかに併用している薬の確認など、医師・看護師と一緒に細部にわたり打ち合わせを行うことができます。
薬剤師が参加するメリット
薬や物品の確認以外にも、薬剤師が今までの治療経過を把握していることは副作用の防止にもつながります。
医療用麻薬は副作用の発現を防ぐために定期的に種類を変更しながら治療することが多く、病院での治療経過や使用薬を薬剤師が把握していると、在宅医療に移行してからも引き続き副作用を予防しながら治療継続することができます。
このほかにも、在宅での薬の管理方法や服薬介助者の有無などの確認も必要です。在宅医療は病院のように朝昼夕就寝前と、必ず看護師さんが服薬介助してくれるような環境ばかりではありません。自宅に服薬介助者がいないようなときには、薬剤師から医師に対して処方提案を行うことで、服薬回数を1日4回から2回、1回へ減らすことができるかもしれません。たとえ入院中は頻回の服薬をしていても、薬の内容を精査して服薬回数を減らした状態で退院できることもあるのです。
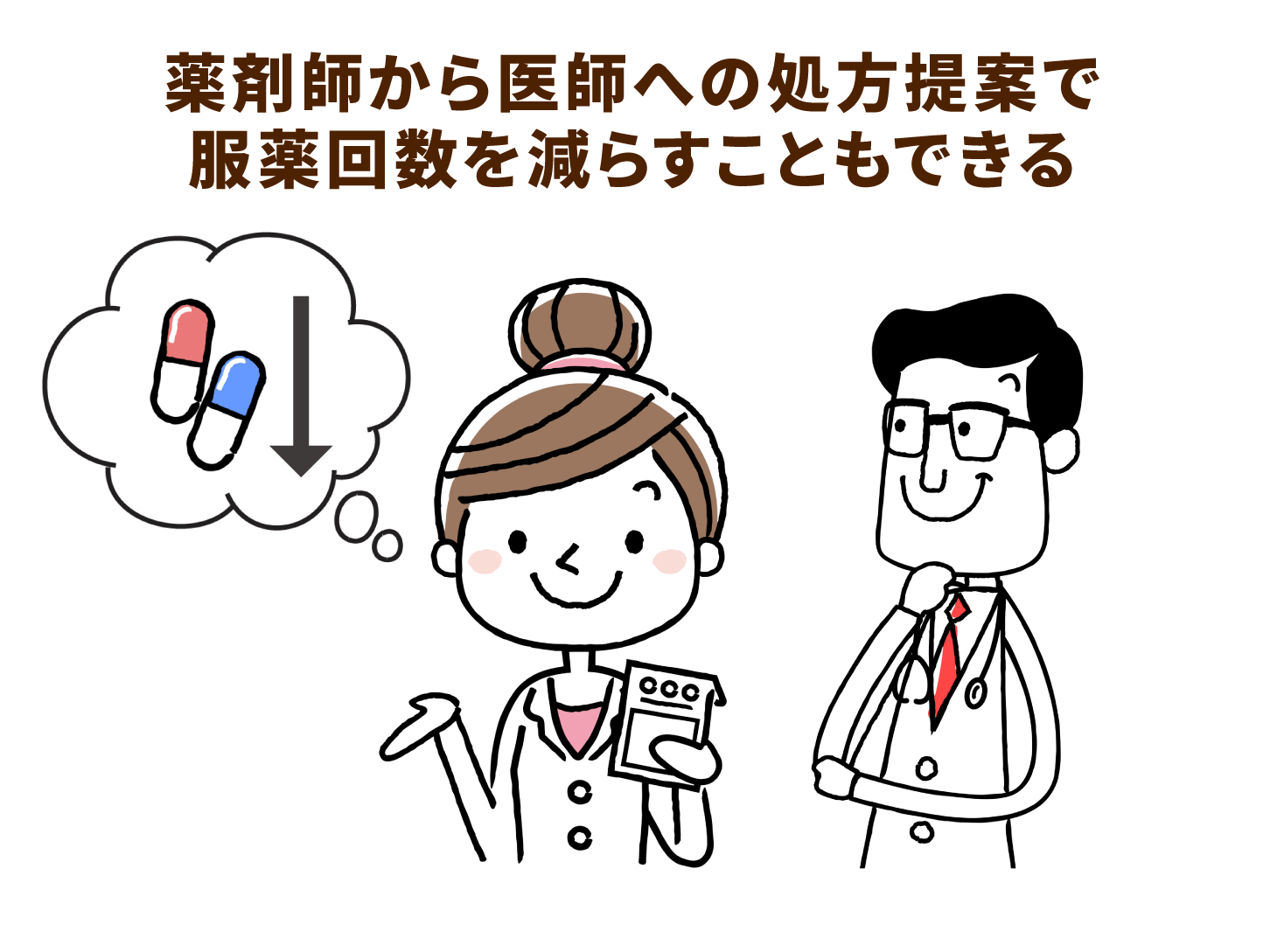
この末期がんの方は無事在宅環境を整えることができ、希望通り自宅に戻って最期まで看取ることができました。
このように、病院を退院して在宅医療に移行する際、もし帰宅後も薬物治療を継続するような場合には、薬剤師が退院時(退院前)カンファレンスに同席することで、適切かつ確実な申し送りを行うことができます。
特に薬剤師による在宅訪問を希望しているときは、事前に訪問してもらう薬局の薬剤師に声をかけておき、カンファレンスに同席してもらうと良いでしょう。困ったときは病院の地域医療連携室やケアマネージャー、薬剤師に相談してみてください。