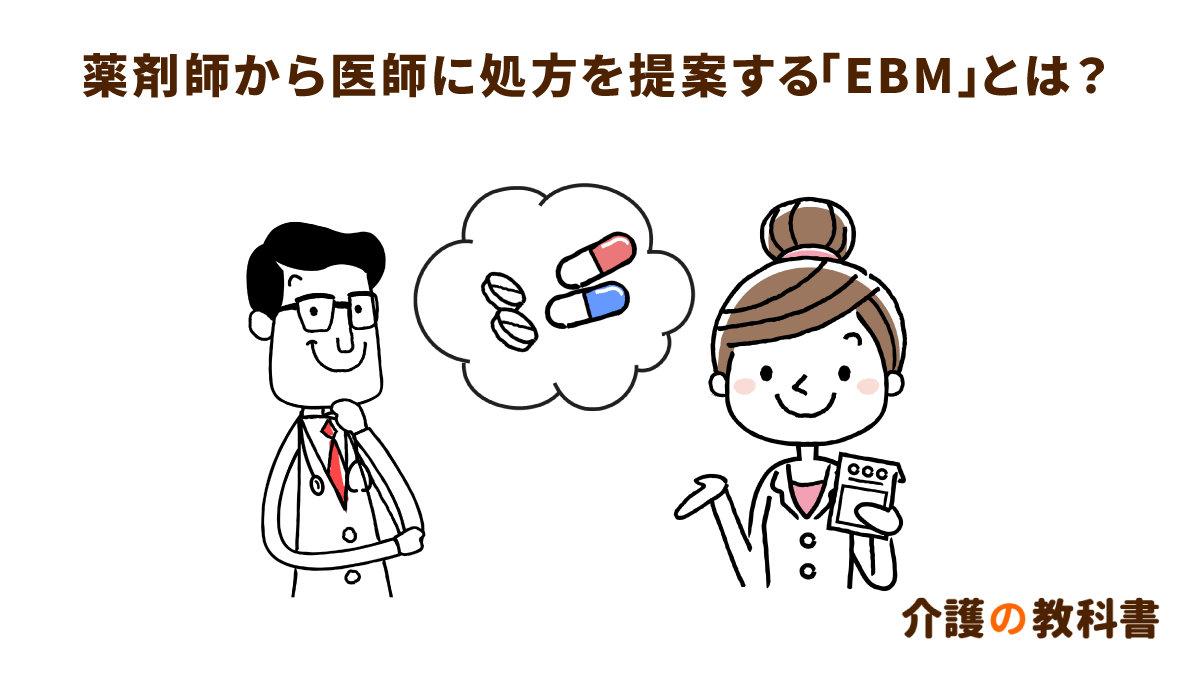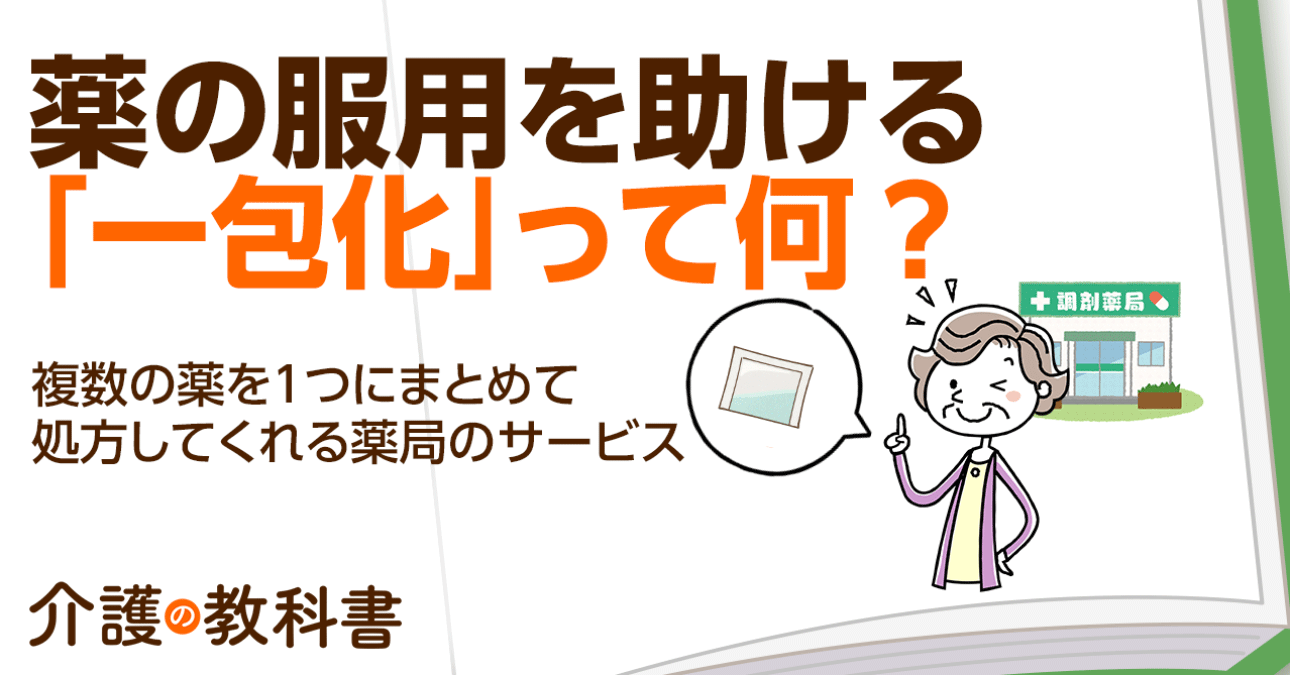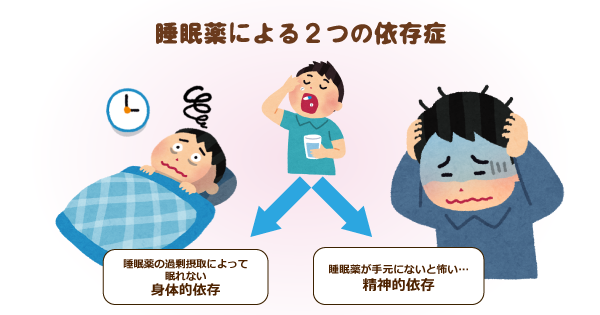病院で薬剤師業務をするかたわら、医学論文の紹介やその読み方、論文の活用に関する記事を執筆しているメディカルライターの青島周一です。身近な医療・健康に関するテーマを得意としていますので、今後ともよろしくお願いいたします。
医療現場で薬を処方するのは医師の仕事です。しかし、患者さんにとって最も有効性が期待できる薬を、最も適した用法用量で処方できるよう、薬剤師が医師に提案をすることも少なくありません。
とはいえ、薬の有効性や安全性をどのように評価すれば良いのかについて、客観的な基準や決まりがあるわけではありません。治療の効果や副作用の影響が、どれほどの確率で発生し得るかについては、患者さんの年齢や健康状態によって大きく変わります。もしかしたら明日の天気を予想するよりも難しいことかもしれません。
現在の処方提案の課題
薬剤師は、薬学という専門知識を活かして薬の化学的な特性や生物学的な影響、あるいは体内における薬の動きなどを分析します。服用した薬が体の中にどれほど吸収され、吸収された成分が体にどのような影響をもたらし、そしてどのように体外に排泄されていくかを考えるのです。しかし、これだけでは「薬の有効性がどれほど期待できるのか」「副作用のリスクがどれくらいの確率で生じるのか」について、客観的な情報を得ることはできません。
例えば、血圧を下げることで脳卒中の発症リスクを低下させるような薬があったとしましょう。この薬の生物学的、あるいは化学的な特徴を把握したとしても、脳卒中の発生確率について語れることは少ないはずです。薬がどのように血圧を下げるのかという理屈を知っていたとしても、薬を飲んだ患者さんの将来的な脳卒中リスクについてはわからないからです。
医師に処方提案をする際には、薬の生物学的、あるいは化学的な特徴に基づく分析だけでなく、患者さんの生活にどれほどの影響を与えうるのかという「実際的な薬の効果」を丁寧に評価する必要があります。この実際的な効果をどのように見積もるかが、質の高い処方提案を行ううえでの課題となります。
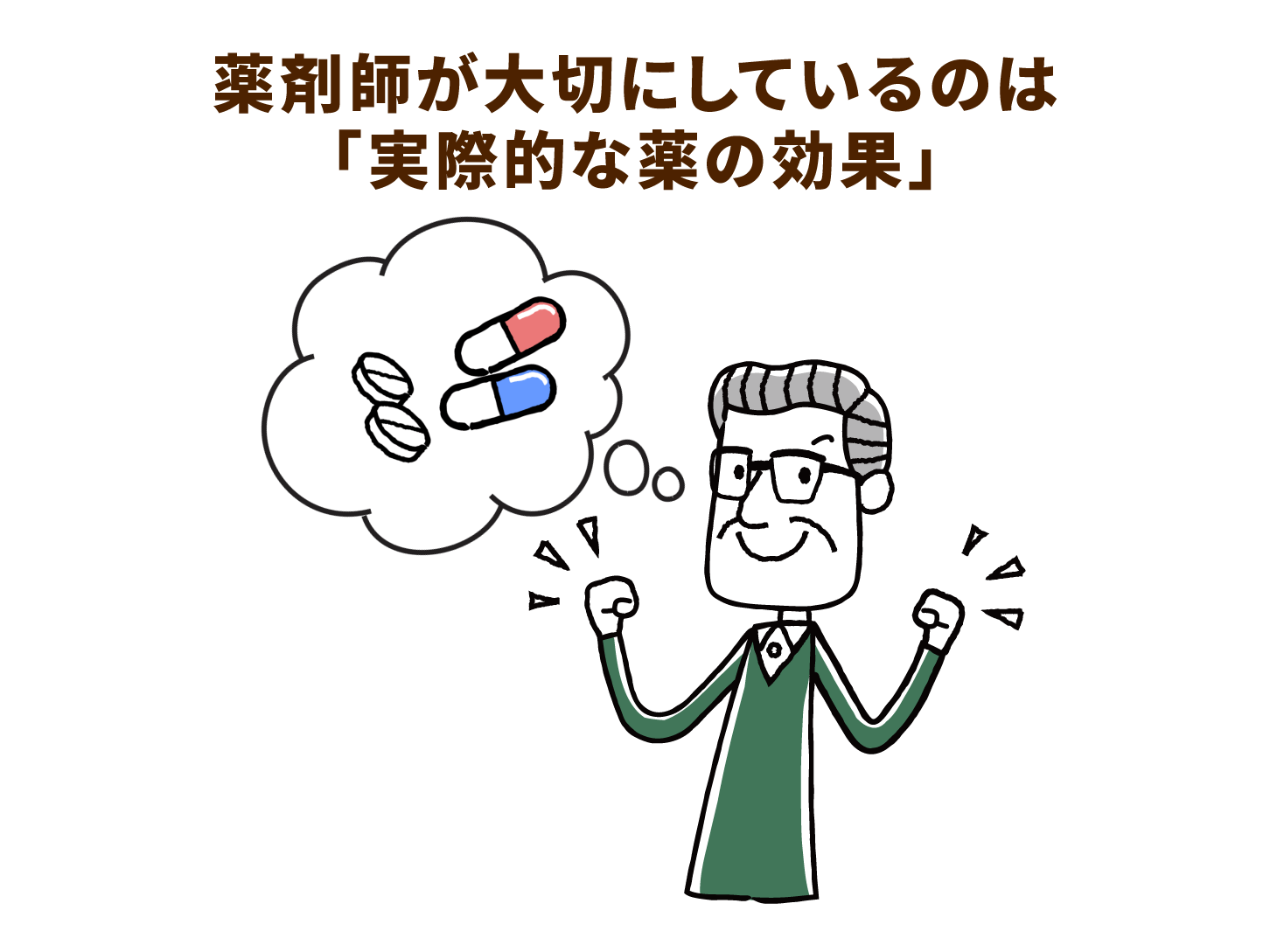
EBMという考え方
EBMとは「Evidence based Medicine(エビデンス・ベースド・メディシン)」の頭文字をとったものです。日本語では「科学的根拠に基づく医療」と訳されます。科学的根拠のことを単にエビデンスということもありますが、エビデンスという言葉は情報技術、あるいは金融業界など、さまざまな文脈で用いられています。保健医療の分野においてエビデンスと言った場合は、人を対象とした臨床研究の結果を指すことが一般的です。この「人を対象とした臨床研究の結果」こそが薬の実際的な効果の把握に必要不可欠なのです。
人の健康状態と、健康状態がもたらす生活への影響は、僕らが想像するよりもはるかに複雑です。薬の吸収量や速度、作用メカニズム、排泄経路などの知識だけでは、薬を飲んだ後の患者さんの生活が、どう変化していくのかを予測することは困難です。
また、動物を対象とした実験結果についても同様の指摘が可能です。例えば、うつ病モデルマウスの実験結果が、うつ病を患う人に対しても適用できるのかと問えば、動物実験の結果が仮説であることに気づくはずです。マウスのうつ病と人間のうつ病では、日常生活に与える影響の度合いが大きく異なりますし、そもそもマウスと人の生活状況を同列に比較することはできないでしょう。
もちろん、動物実験の結果が無意味というわけではありません。動物実験を始めとする基礎医学研究の結果は、科学の発展に必要不可欠な仮説を提供してくれます。しかし、医療現場で医療従事者が意思決定する際に必要とされる情報の多くは、重要な仮説そのものではなく、その仮説を実際の人で検証した臨床試験の結果=エビデンスなのです。このことは傘を持って家を出るかどうかを気象メカニズムによってではなく、その日の降水確率によって判断していることに似ています。
EBMは利用可能な最も信頼できるエビデンスを踏まえたうえで、最善の臨床判断を模索する医療者の行動指針です。具体的には、医療現場で遭遇した疑問を一定のフォーマットで整理し、その疑問の解決に参考となりそうなエビデンスの検索を行います。検索されたエビデンスは批判的に考察し、その考察を踏まえたうえで意思決定を行います。もちろん、最終的な判断をしたのちも、一連の作業に関する再評価を行い、継続して患者さんをフォローし続けることまでがEBMのプロセスです。
また、EBMの実践において、最終的な意志決定はエビデンスだけでなく、患者さんの価値観や生活環境、そして医療者の経験も考慮することが求められています。エビデンスだけで治療方針を決定してはいけないこと強調しているEBMの考え方は、人の生活が科学のような合理的なものだけでは構築されていないという前提に基づいています。
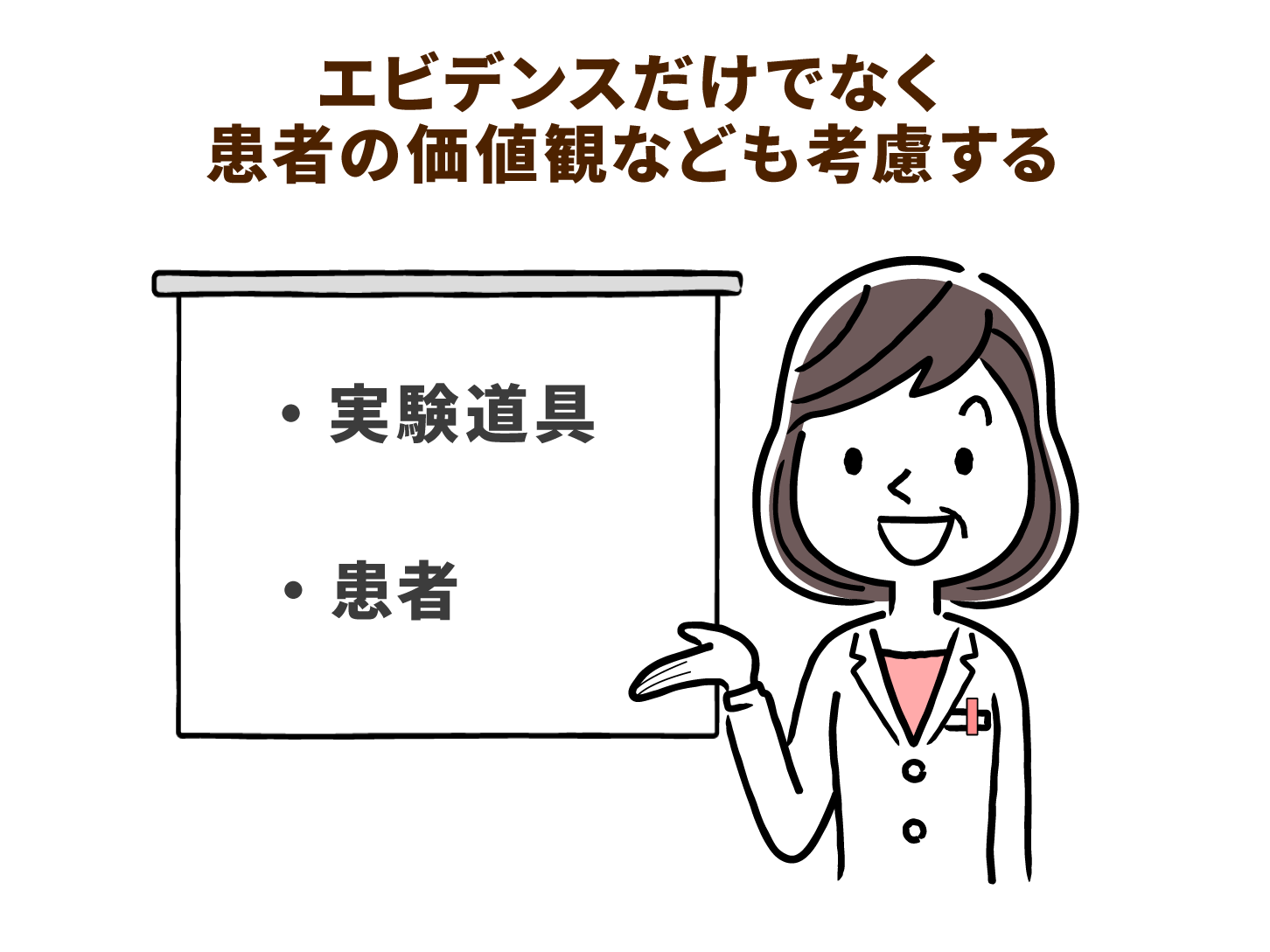
僕たちが生きている日常は、科学的ではないもの、非合理的なものであふれています。不安や心配を和らげるため、何かに祈りをささげたり、健康に良くないと知りつつも飲酒や喫煙をすることもあるでしょう。エビデンスがあるからといって、人の生活すべてがエビデンスに従っているわけではないのです。
エビデンスは医療者が治療方針を決断する際の判断材料の一つであり、患者さんの価値観や患者さんの生活環境などと同じように扱うことがEBMの基本的な考え方です。
EBMスタイル診療支援を実践するメリット
エビデンスに基づく情報を「処方提案書」として文章にまとめ、医師の診療を支援する業務を、僕は「EBMスタイル診療支援」と呼んできました。一般的な薬剤師の処方提案業務と異なるのは、薬剤師主導で情報発信を行っていくことはもちろん、エビデンスに基づく情報(事実)の提示と、それを踏まえた薬剤師の推奨(意見)を明確に分けて提供することにあります。エビデンスを医師と共有するだけでなく、そのエビデンスを提示した背景にある文脈や、エビデンスに基づき薬剤師が何を考え、現在においてどんな治療が推奨できるのかを具体的に提示するのです。
EBMスタイル診療支援は、薬剤師の主観だけではなく、また仮説や推論だけでなく、患者さんの生活レベルにどのような影響が起こりうるのかを、エビデンスに示された統計データを駆使して確率的に提示していきます。このような情報を、血液検査の結果やレントゲン画像と同じように、医師が治療方針を決定する際の判断材料にしてもらうことが目的です。
EBMは料理のレシピをまとめたクッキングブックのような、一律で普遍的な行動指針ではなく、患者個別の問題を取り扱うための多様性に満ちた行動スタイルです。また最終的な意思決定においては、エビデンスだけでなく、患者さんの想いや医師の治療方針、あるいは薬剤師としての経験も考慮することが強く求められます。
治療の方針についてエビデンスは重要な示唆を与えてくれますが、エビデンスだけに従って生きることは、決して豊かな生活とは言えないでしょう。
また、EBMにおけるエビデンスの取り扱いは「適用」であって「押しつけ」ではないことに注意しなければいけません。薬剤師による処方提案は、医師という相手が存在してこそ、効果的に機能する多職種連携の一つです。薬剤師の意見を押しつけるのではなく、臨床検査の結果やレントゲン画像と同じように処方提案を医師の判断材料の一つにしてもらうことで、より質の高い薬物療法を患者さんに提供できると考えています。