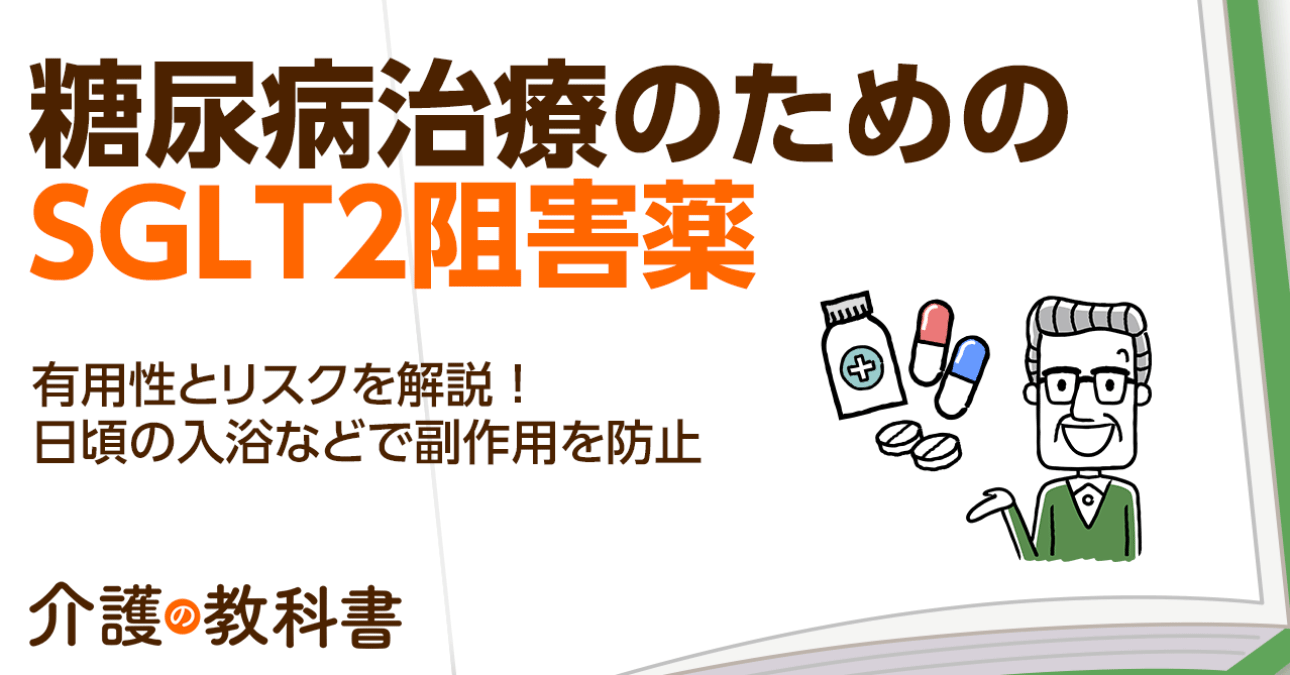今回は糖尿病の治療薬についてご紹介いたします。
第53回で糖尿病の概要を取り上げていますので、あわせてご覧いただけるとより理解が深まると思います。
糖尿病の薬物療法の特徴
糖尿病の治療において、血糖値を下げる「インスリン」の投与が適応でない場合には、まず食事療法や運動療法を試みます。これだけで改善する人もいますが、それだけでは血糖コントロールが難しい人もいます。そのような場合には、糖尿病治療薬が処方されます。
糖尿病の合併症である網膜症、神経障がいの発症や急激な悪化を防ぐためにも、急速な血糖値の降下や低血糖を起こさないように注意しながら薬物療法を開始します。
そのため、通常は1剤から飲み始めます。少量から始め、適宜増量して数ヵ月以内に反応が見られるかを判断します。
もし血糖値が思うように下がらなければ、さらに1剤上乗せします。こちらも少量から始め、適宜増量して数ヵ月以内の反応を見ます。これでもコントロールができなければ、さらに上乗せを行います。このように、血糖値の変動を見ながら、量や種類を少しずつ調整しながら治療を行います。
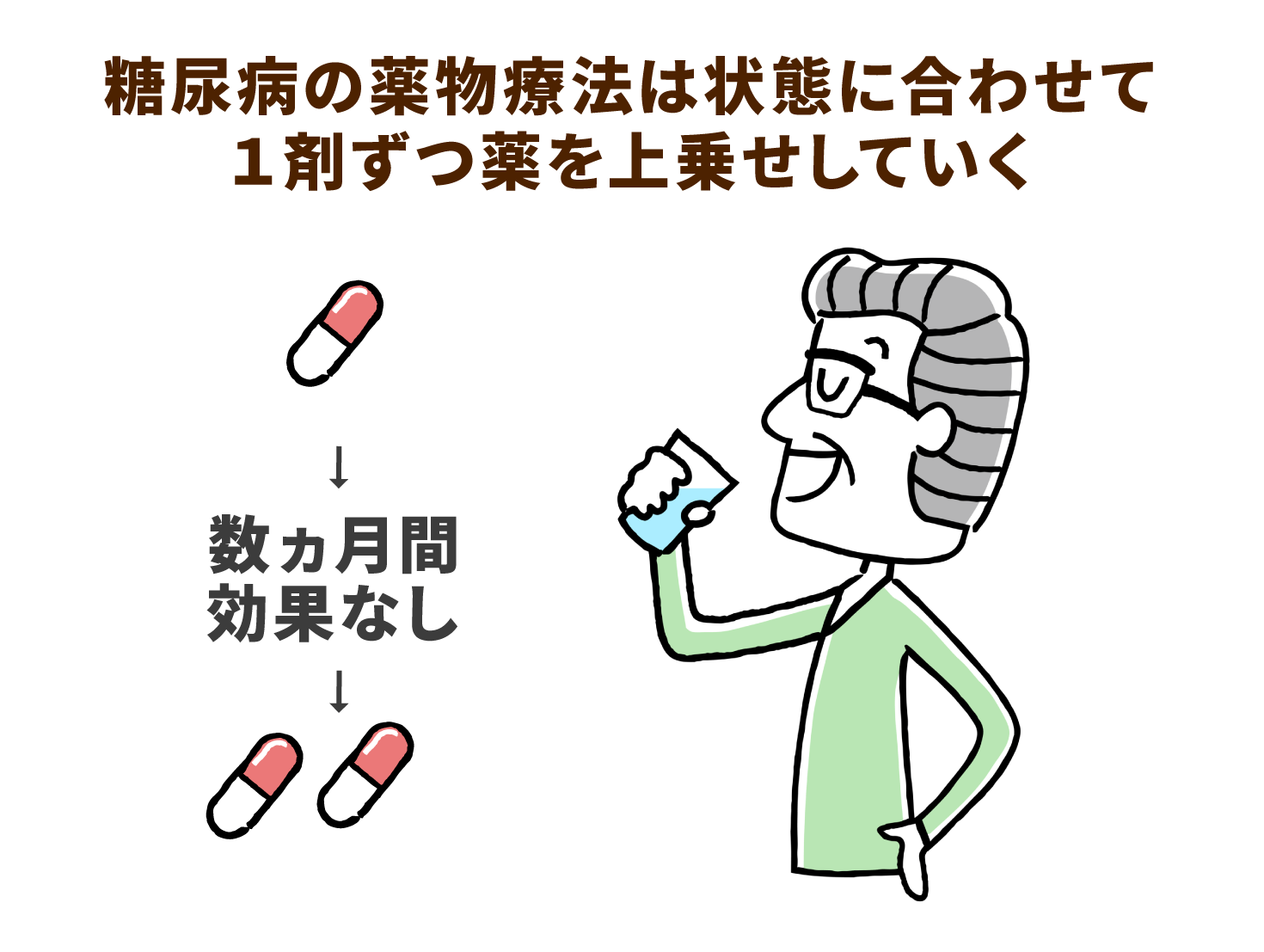
糖尿病治療薬(飲み薬)の種類
糖尿病の飲み薬には、大きく分けて「インスリンの効きを良くするもの」「インスリンの分泌を良くするもの」「食事で摂った糖分の分解や吸収を遅らせるもの」「糖の排泄を促すもの」の4種類があります。
1.インスリンの効きを良くする薬
ビグアナイド薬、チアゾリジン薬
インスリンが十分に分泌されているにもかかわらず、インスリンの効き目が悪くなっている状態(インスリン抵抗性)だと、血糖値が下がりにくいことがあります。このインスリン抵抗性を改善するビグアナイド薬は、治療の最初に使われることが多い薬です。
主な副作用として、下痢や悪心・嘔吐などの消化器系副作用があります。また、重篤な副作用として血液中の乳酸値が上昇する「乳酸アシドーシス」が報告されています。筋肉痛や倦怠感などの初期症状がみられた場合には、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。
2.インスリンの分泌を良くする薬
SU薬(スルホニルウレア薬)、速効型インスリン分泌促進薬(グリニド薬)、DPP-4阻害薬
インスリンの分泌をつかさどる膵臓に働きかけ、インスリンを分泌させて血糖値を下げる薬です。
SU薬は血糖値の降下作用が強い一方で、低血糖の副作用報告も多いので、服用には注意が必要です。
グリニド薬は、主に食後の高血糖を下げる目的で服用します。効果の発現が早いため、食事の直前(食直前)に服用するのが特徴的です。目安として、食事でお箸を持つ前に服用するようにしましょう。食前30分での服用だと、食事開始前に低血糖を起こすこともあるので注意が必要です。
DPP-4阻害薬は、食前でも食後でも飲める薬です。食事が摂れなかったときに薬だけ飲んでも低血糖を起こしにくいという特徴があります。ただし、絶対に低血糖にならないというわけではありません。
3.食事で摂った糖分の分解や吸収を遅らせる薬
αグルコシダーゼ阻害薬
食後、著しい高血糖がみられる場合に効果が期待できる薬です。
食事で摂った糖の吸収を遅らせるため、必ず食直前に服用する必要があります。食後に飲むと効果が激減してしまうので、飲み忘れに注意しましょう。副作用として、お腹にガスが溜まり、おならが出やすくなることがあります。
4.糖の排泄を促す薬
SGLT2阻害薬
余分な糖を尿と一緒に体外に出すことで、血糖値を下げる薬です。尿中に糖分を排出するので、尿路感染症の副作用が知られています。また、尿量が増えるため脱水にも注意が必要です。服用中は適度な水分補給を心がけましょう。高齢者は脱水に気づきにくいこともあるため、比較的若い世代に使われやすい薬です。
服用中は意図的に尿中に糖を出しているので尿検査は陽性になります。しかし、これをもって糖尿病の状態が悪くなっているわけではありません。
糖尿病治療薬(注射薬)の種類
糖尿病の注射薬は、主にインスリンとインスリン分泌促進薬(GLP-1受容体作動薬)に分かれます。
1.インスリン
膵臓からインスリンの分泌が不足しているときや、インスリンの働きが低下したときに使われます。
効果が早く現れる「超速効型」「速効型」や、ゆっくり現れて長く続く「持効型」、「速効型と持効型の間の中間型」など、作用時間によって細分化されており、糖尿病の状態によって使い分けられています。
急な低血糖にも迅速に対応できるようにブドウ糖を常に携帯しておくなど、低血糖時の対応についてあらかじめ準備しておきましょう。
2.インスリン分泌促進薬(GLP-1受容体作動薬)
膵臓に働きかけ、インスリンの分泌を促進する薬です。1週間に1回の注射で治療できるものもあり、薬の飲み忘れが多い人などにも適しています。
膵臓にインスリンを分泌する力が残っていることが前提の薬なので、適応は2型糖尿病のみになります。また、この薬はインスリンの代替薬にはならないので注意しましょう。
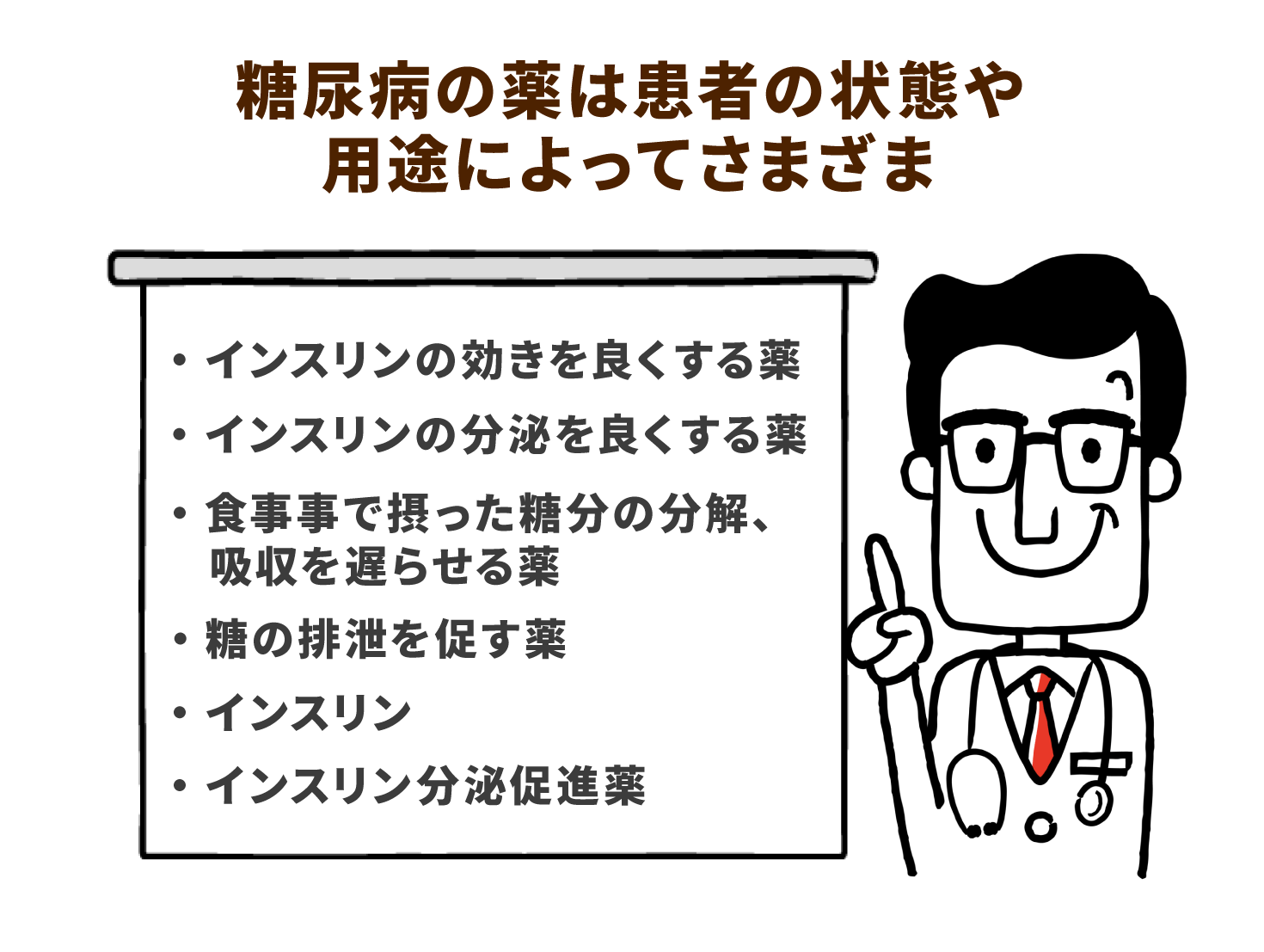
以上、今回は糖尿病治療薬についてご紹介しました。
糖尿病は自覚症状が少ないこともあり、自己判断で治療を止めてしまう人が多い疾患の一つです。
認知症の人や仕事が多忙で薬の管理が難しい人など、治療の継続が難しいときには医師か薬剤師に相談してください。生活スタイルにあった薬を見つけて、無理のない治療を継続していきましょう。