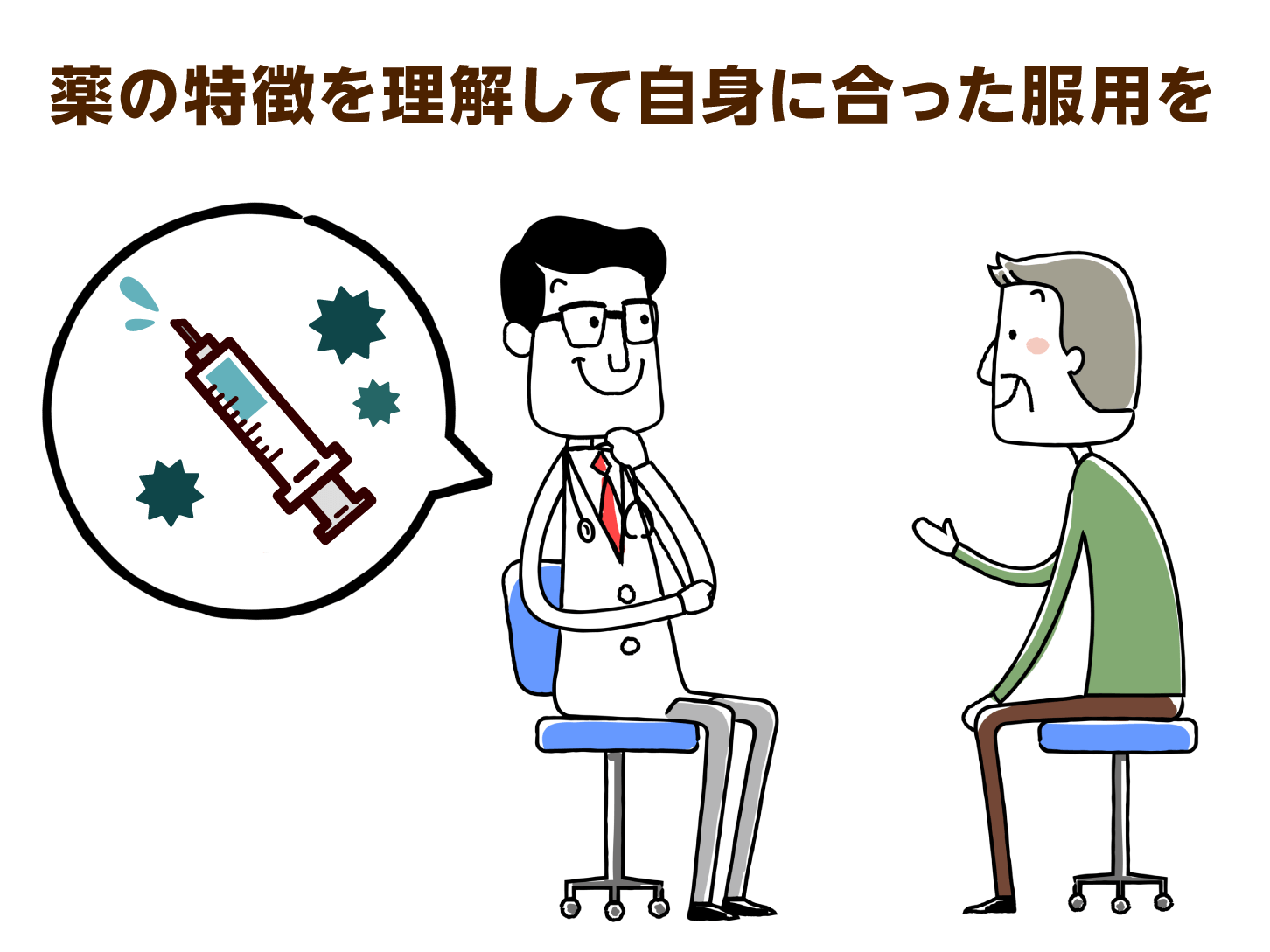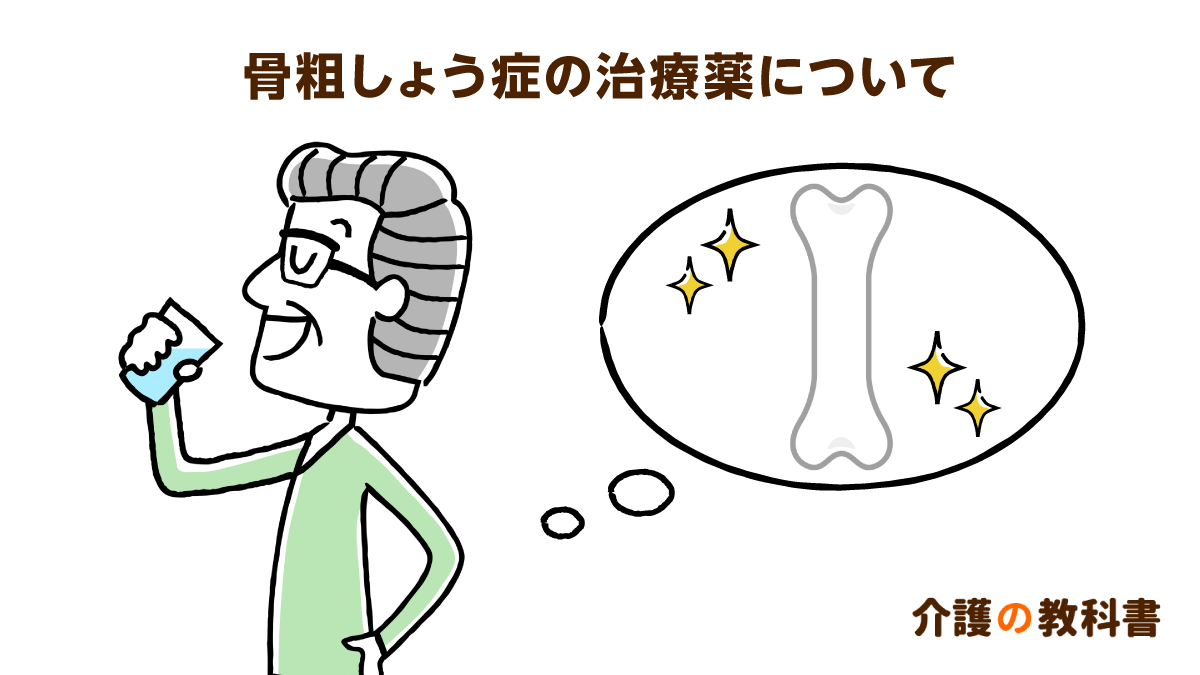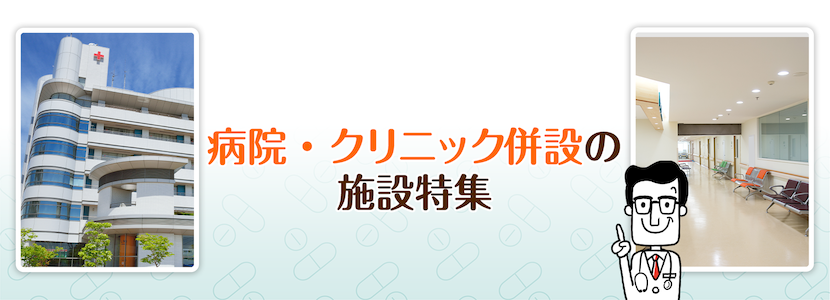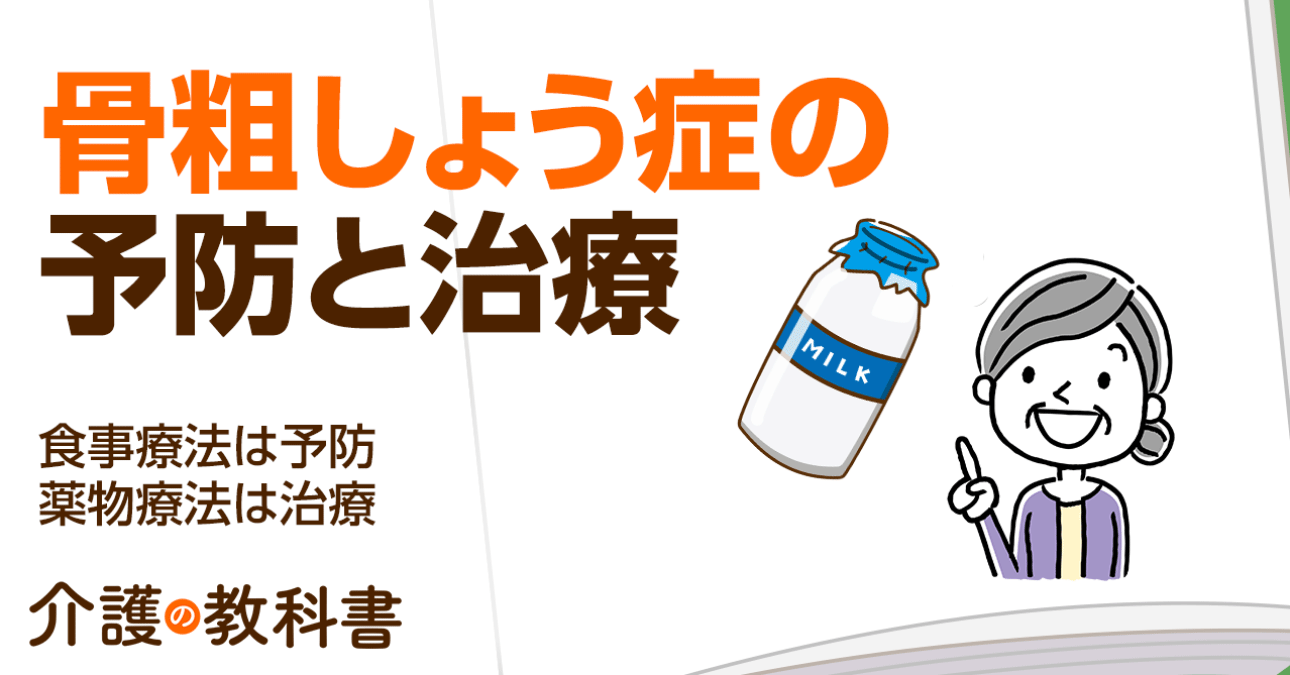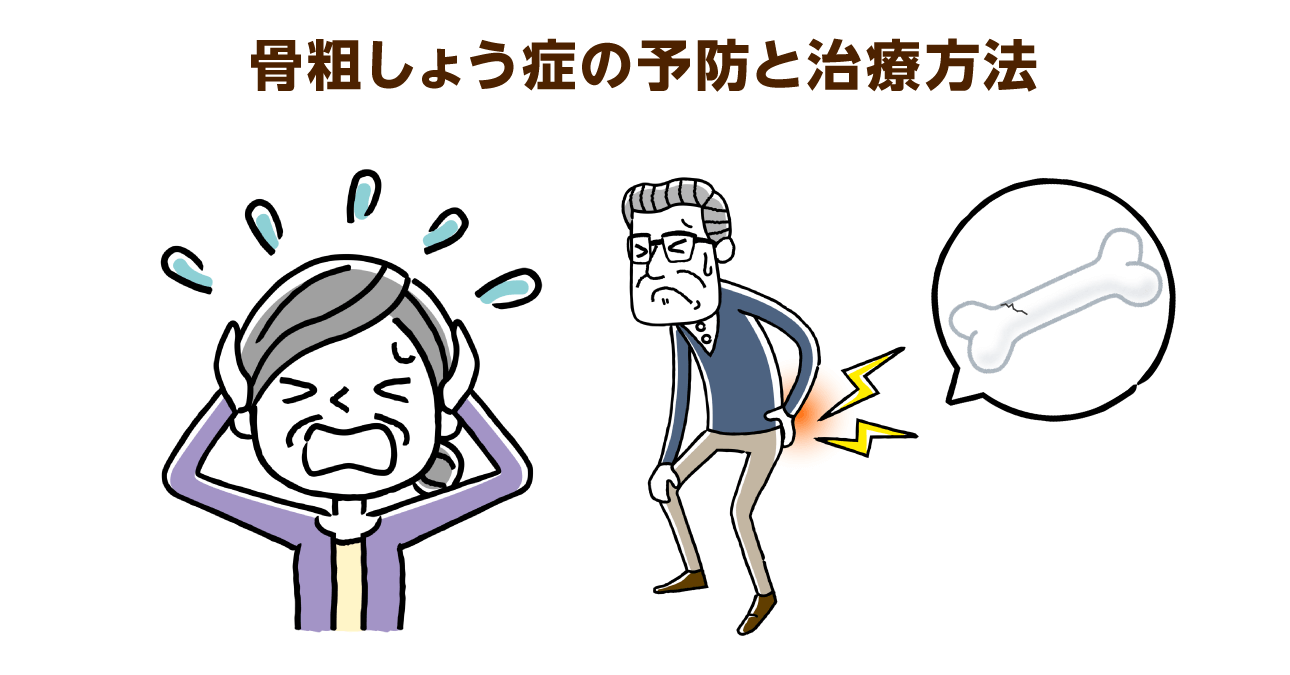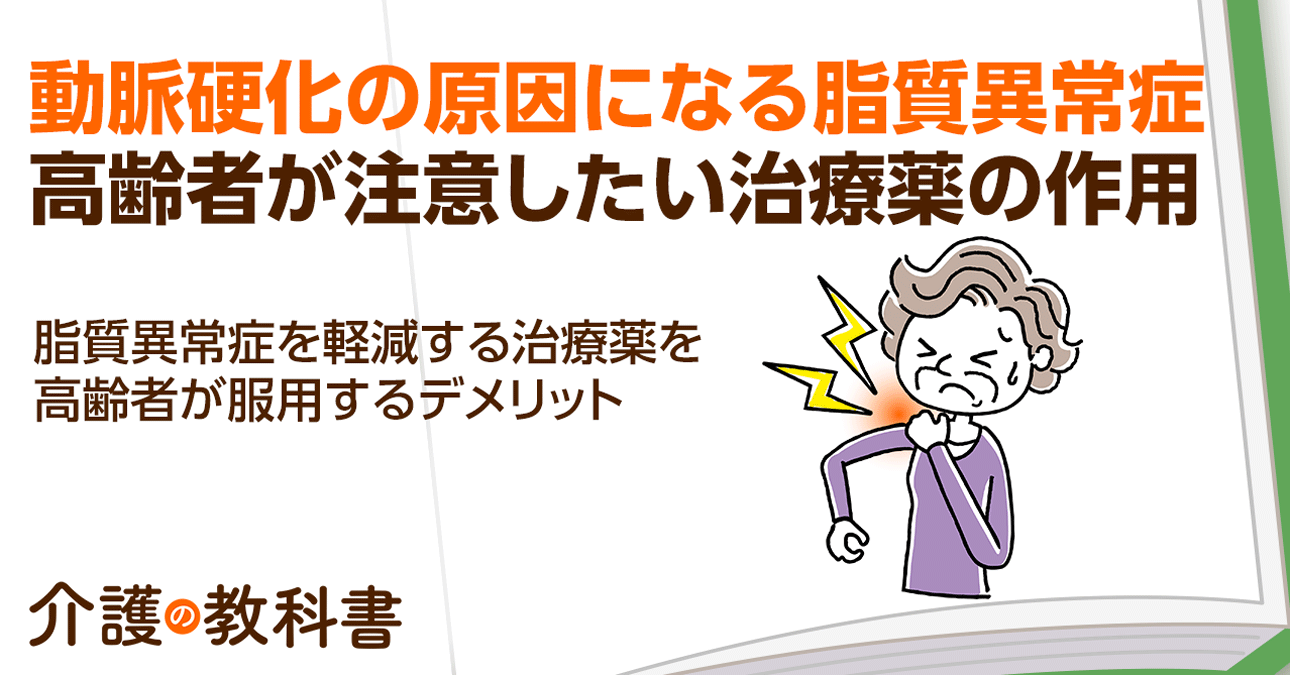こんにちは。薬剤師の雜賀匡史です。
今回のテーマは「骨粗しょう症の治療薬」についてです。
第44回では骨粗しょう症の概略について取り上げたので、今回は具体的な治療薬の種類や、使用する際の注意点などをご紹介させていただきます。
4つの治療法で骨密度の低下を防ぐ
骨粗しょう症は骨がスカスカになり、骨折しやすくなる病気です。放っておけば骨折を繰り返すなどの危険性がありますので、それを防ぐために骨密度の低下を抑えることが必要となります。
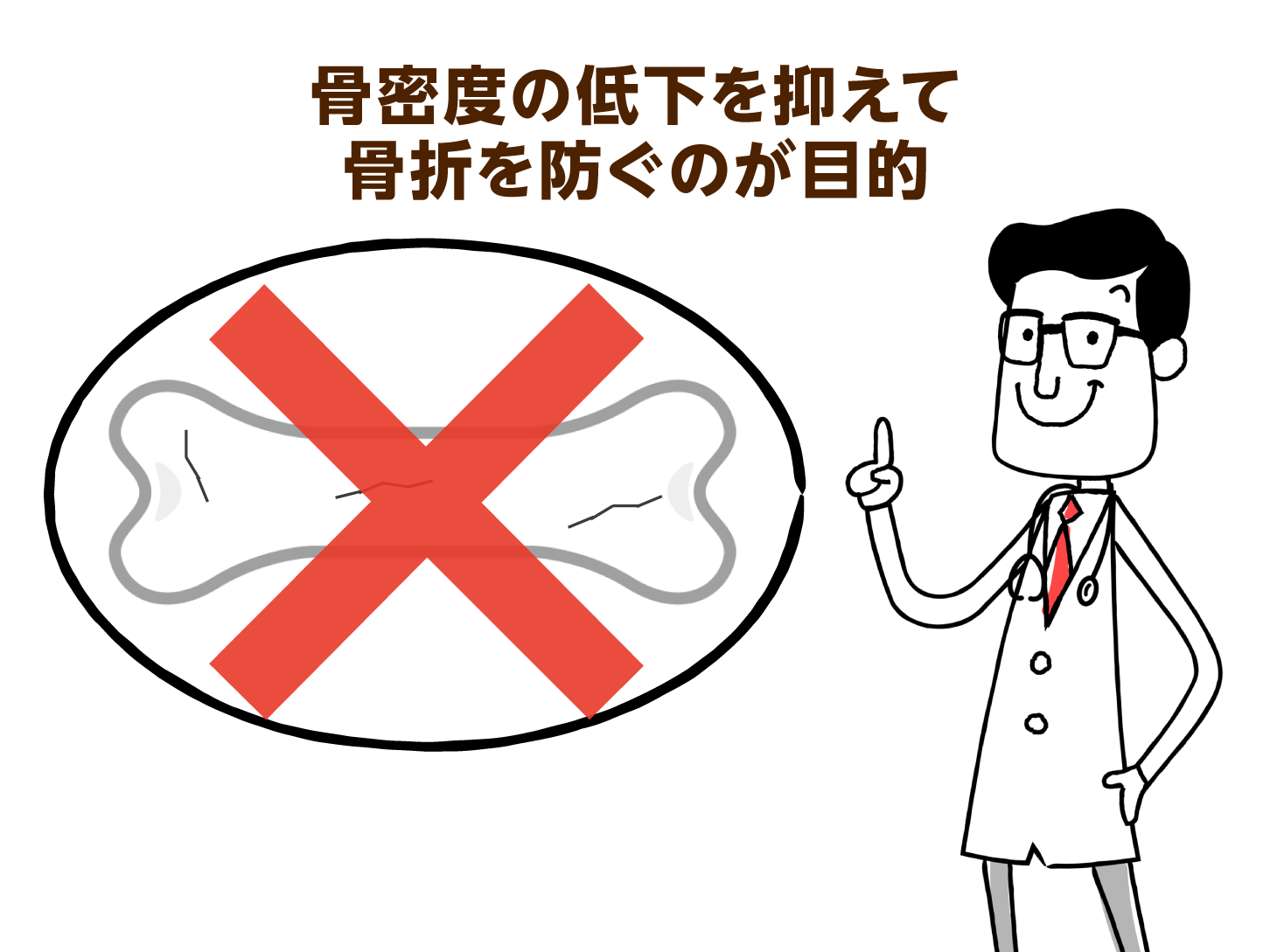
治療方法としては代表的なものとしては下記の4つを組み合わせ、一人ひとりにあった治療を行っていきます。
- 薬物療法
- 食事療法
- 運動療法
- 理学療法
主流は骨代謝の原理を利用した治療薬
骨は常に古い骨を壊す「骨吸収」を行い、代わりに新しい骨をつくる「骨形成」という作業を繰り返し行いながら強度を保っています。つまり、骨粗しょう症の方に対しては、骨吸収を抑制し骨形成を促進することで、骨の強度を保つことが可能です。現在は、この骨代謝の原理を利用した治療薬が主流となって使われています。
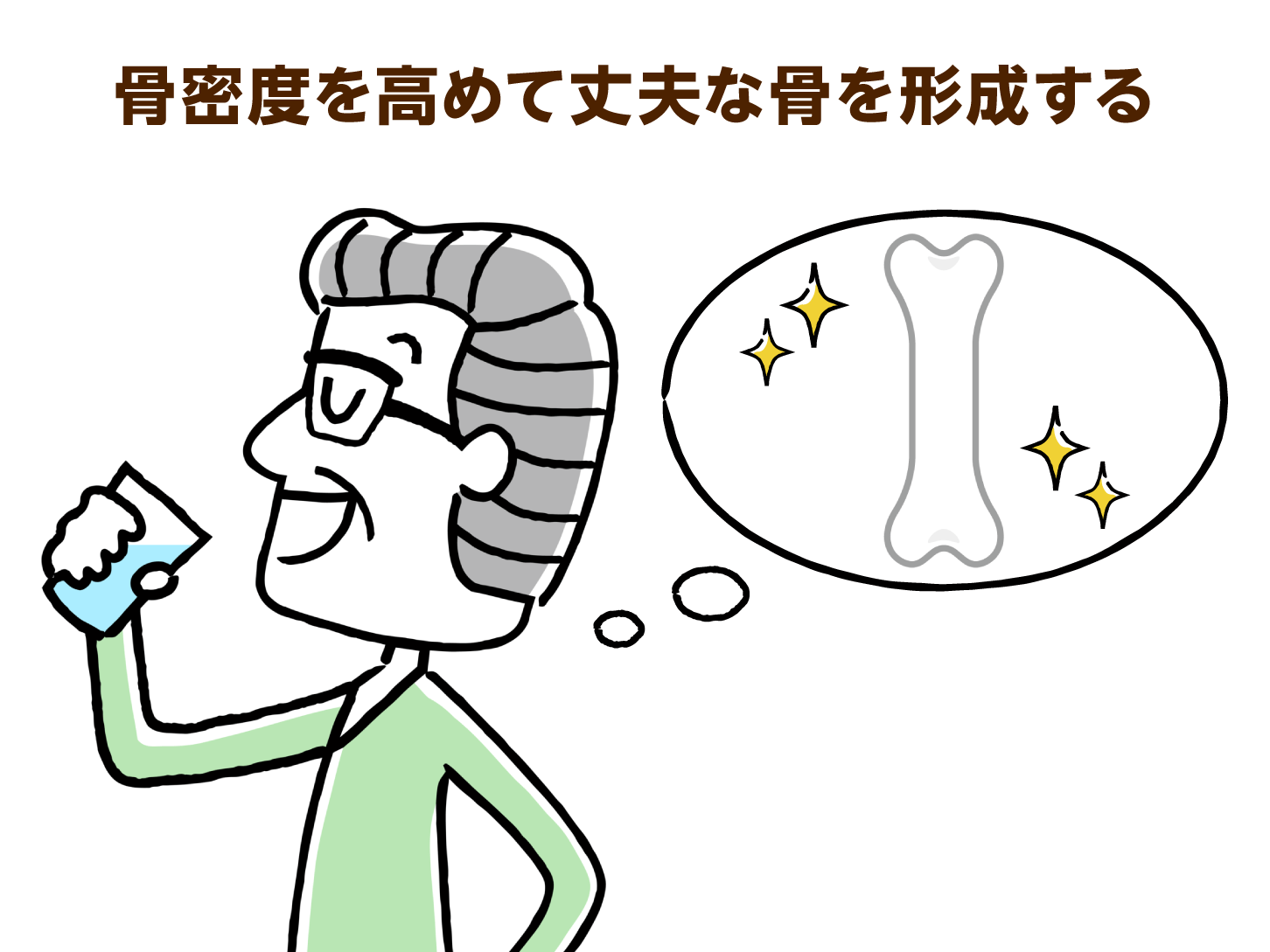
骨粗しょう症における治療薬のタイプは大きくわけて「骨吸収を抑制する薬」「骨形成を促進する薬」「骨代謝を改善する薬」の3つです。これらについて、深く掘り下げていきます。
骨吸収を抑制する薬
- 骨吸収の速度を緩やかにすることで骨形成が追いつき、古い骨が新しい骨へと変わっていきます。これにより骨密度が高まり、丈夫な骨が形成されるというわけです。骨吸収を抑制する薬は以下の通りとなります。
- ビスホスホネート製剤
- 骨粗しょう症治療薬の第一選択薬として使われることの多い薬です。毎日服用するタイプの薬から、週1や月1の服用で良い飲み薬タイプ、注射薬のタイプまで幅広くあり、多くの方に使われています。
- 服用の注意点として、食事やカルシウム、マグネシウムなどのミネラル分と一緒に服用すると薬の吸収が低下してしまうので、起床時などの空腹時に服用する必要があります。カルシウムやマグネシウムを多く含んだミネラルウォーターでの服用は避けてください。また、粘膜への刺激を避けるため、服用後30分は横にならないようにしましょう。
- 副作用として、頻度はまれですが「顎骨壊死(がっこつえし)」と呼ばれるあごの骨の組織や細胞が局所的に悪くなってしまう例が報告されています。服用中の人が歯科受診する際には、歯科医にこの薬を服用中であることを伝え、日頃から口腔内の衛生を保つようにしましょう。
- SERM(選択的エストロゲン受容体調整薬)
- 閉経によって女性ホルモンの分泌が低下することで起こる骨粗しょう症の方を治療するものなので、基本的に男性には使われません。骨密度が低下している人や、椎体骨折の治療に積極的に用いられている薬です。
- 抗RANKLE抗体
- 骨を壊す細胞の働きを活発にする「ランクル」というたんぱく質の働きを抑える薬で、半年に1回皮下注射で投与します。副作用として低カルシウム血症が報告されており、この注射をするときには必ずカルシウム製剤及びビタミンD製剤を服用する必要があります。
- 女性ホルモン剤
- 骨量の減少を抑える働きがあります。女性ホルモンの分泌量が減る、閉経期の女性が対象です。
骨形成を促進する薬
- 副甲状腺ホルモン剤
- 重症例や他剤で効果が得られにくいときなどに使われることが多い、新しい骨を形成させる薬です。連日あるいは1週間に1回使用する注射薬になります。投与期間は2年間までと限られているので使用期間に注意が必要。代表的な副作用として、悪心や嘔吐、頭痛、倦怠感などがあります。
骨代謝を改善する薬
- ビタミンD3・ビタミンK2・カルシウム製剤
- ビタミンD3とビタミンK2、カルシウム製剤には骨密度を上げる効果があります。これらを使うときは、薬の過剰投与による「高カルシウム血症」に注意しなければなりません。血液をサラサラにする「ワルファリン」という薬を飲んでいる方は、ビタミンK2製剤を飲むことはできませんので注意しましょう。
薬と生活面の両方から健康な骨を維持!
今回は骨粗しょう症の代表的な治療薬についてご紹介しました。これらの薬は単剤で使われることもあれば、状態に応じていくつかの種類を組み合わせて使うこともあります。それぞれの薬の特徴を理解しておくと、副作用が出たときに早い段階で気づくことが可能です。
また、薬以外にも日頃から健康な食事や運動をすることも、骨粗しょう症による骨折を防ぐためには大切。薬と生活の両方から見直し、いつまでも健康な骨を維持できるよう心がけましょう。