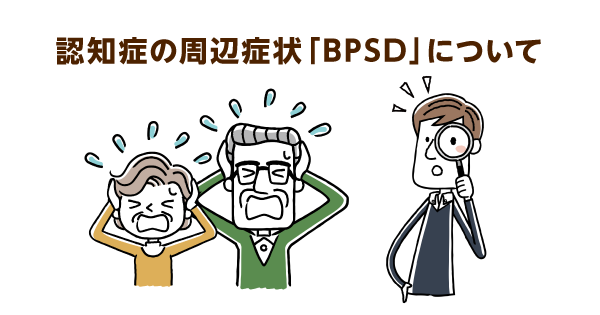こんにちは。メディスンショップ蘇我薬局で管理薬剤師・訪問薬剤師をしている雜賀匡史です。
前回は認知症治療薬の種類や特徴、「身体のなかでどのように作用しているのか」について説明しました。
今回は、「認知機能に悪影響を与える薬の使い方と、悪影響を及ぼす可能性の高い薬」について紹介します。
認知症の薬とケアについて
※中核症状…記憶障害や判断力の障害など
※行動心理症状(BPSD)…暴言、暴力、易刺激性(イライラ)など
認知症に対して薬物療法でできることは1~2割

みなさんは、「BPSD症状」による暴力や興奮症状に、どう対応されているでしょうか?
薬を飲んでもらうことや、ケアを充実させることを考えますか?
10年近く前、私が今の薬局に勤め始めたばかりの頃、認知症の人と接する機会がほとんどなかった私ですが、訪問先の認知症の方(男性)で、介護者に暴力を振るう方がいました。
殴る、噛む、つねるなど、さまざまな興奮症状があったため、家族が精神科の病院を受診させ、そこで鎮静剤が処方されたのです。
鎮静剤というのは、いわゆる「抗精神病薬」。
それを飲むと、確かに暴力行為はなくなりました。
しかし、その人からなくなったのは暴力行為だけではありません。
人間らしさも同時に失われてしまったのです。
興奮症状というのは、一日中現れているわけではありません。
その男性は訪問時に笑顔も見せてくれる素敵な人でしたが、薬によって笑顔どころか、顔から表情がなくなってしまったのです。
認知症の人とかかわる経験が少なかった私は、その状況を初めて目にしたとき愕然として、これが治療なのだろうか?とさえ感じました。
この出来事で、認知症の人と接するには、疾患や薬の知識だけでは不十分だと痛感したのです。
これを機に、薬学部では一度も学んだことのなかった認知症ケアを学び始めました。
そして薬物治療と非薬物治療の2つの視点から、認知症の人とかかわることの大切さを知ったのです。
薬剤師がこんなことを言うとおかしいかもしれませんが、認知症という疾患は薬や処方をどんなに工夫しても、充実したケアには勝てません。
ご家族からBPSD症状に効く薬を聞かれることがあるのですが、私から服薬をすすめるケースはほとんどなく、その多くはケアや環境の改善で解決しています。
認知症に対して薬物療法にできることは1~2割程度で、ケアなどの非薬物療法によって8~9割は状態を改善することができます。
薬を信頼し、薬に頼り過ぎると、思わぬ形で裏切られてしまうのが認知症という疾患なのです。
抗精神病薬の欠点
BPSD症状で抗精神病薬を用いるケースは減少していますが、未だにゼロにはなっていません。
抗精神病薬の服薬で生じうる弊害は、その人らしさを失うことだけではないのです。
2005年にアメリカとカナダで、認知症高齢者に抗精神病薬を使用すると「死亡率が1.7倍高くなる」という報告がありました。(※出典1)
死亡原因の主な原因は、心血管イベントによる突然死と、肺炎です。
海外ではその後も同様の報告が続いており、日本で行われた試験では抗精神病薬を服薬されている方の死亡率が約2.5倍上昇したという報告もありました。
こうした背景もあり、抗精神病薬は必要最低限の使用にとどめるよう注意喚起がなされています。
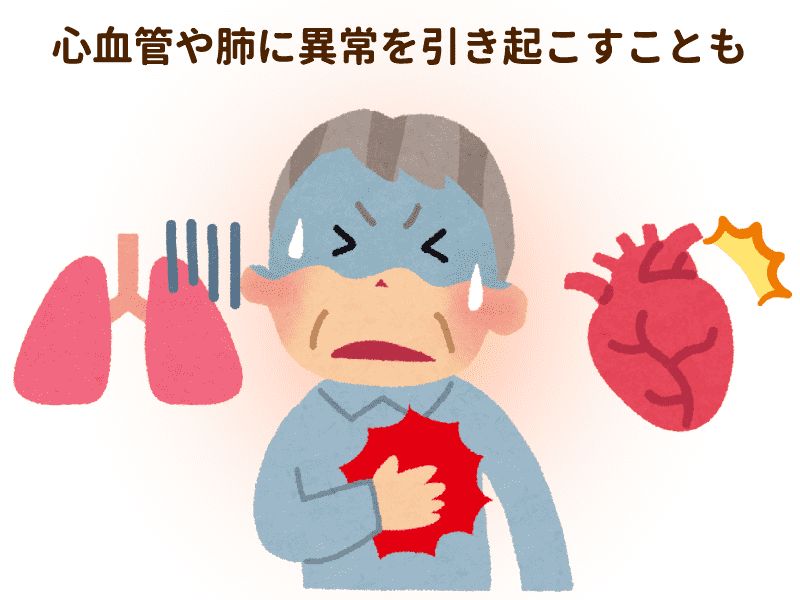
抗精神病薬を漫然投与しないためのポイント
BPSDで抗精神病薬が処方されたとき、最も避けなければならないのは「漫然投与」。
漫然投与とは、以前に処方された薬を継続して長期間服用することです。
どんな人でも日々状態が変化しており、たとえ健康な人でもずっと同じ状態の人はいません。
薬は身体の状態変化とともに用量や種類の調節が必要ですので、介護者の方は日々の状態変化を医師や薬剤師に細かく伝えることが大切になってきます。
状態変化を医療従事者に伝えるときのポイントとしては、悪い症状のみを伝えるのではなく、症状が良くなった改善点についても同時に伝えるということ。
治療や服薬によって症状が改善したことを伝えないと、医療従事者側は症状が継続していると勘違いしてしまうことがあります。
すると、処方も同様に継続されてしまうことがあるのです。

認知機能に影響を及ぼす薬剤
アセチルコリンは全身のさまざまな場所に存在しているため、認知症以外の薬でもアセチルコリンの作用を抑える働きをもった薬があり、それらを総称して抗コリン薬と呼びます。
たとえばパーキンソン病治療薬、泌尿器系薬、かぜ薬、抗アレルギー薬、抗うつ薬などの種類の薬に、多く存在します。
アセチルコリンを抑制する薬を全て避けて、パーキンソン病などのような治療することは現実的に難しいですし、治療上の有益性が上回るから処方されており、認知症だと絶対に飲んではいけないという話ではありません。
ただ、これらの薬が新たに処方追加になったときに、認知機能に明らかな変化が見られたり、言動や行動に異常がみられるような場合には注意が必要です。
このような場合は、追加された薬が原因で起こる「薬剤性認知機能障害」を疑う必要があります。

症状の細かな変化は、介護されている方が一早く気づくことのできるところです。
細かな変化でも、気になるときは早めに医師、薬剤師に相談することで、薬が原因で引き起こされる認知機能障害を防ぐことができます。
最後に一言
今回は、認知機能に悪影響を及ぼす薬を説明しました。
ここまで説明してきたように、薬物療法には限界があります。
認知症に良いと言われているサプリメントについては記述しませんでしたが、薬と同様で、過信し過ぎないようにしましょう。
認知症の人すべてに効能を示す薬やサプリメントは、残念ですがまだ存在しません。
充実したケアが、何よりの薬です。