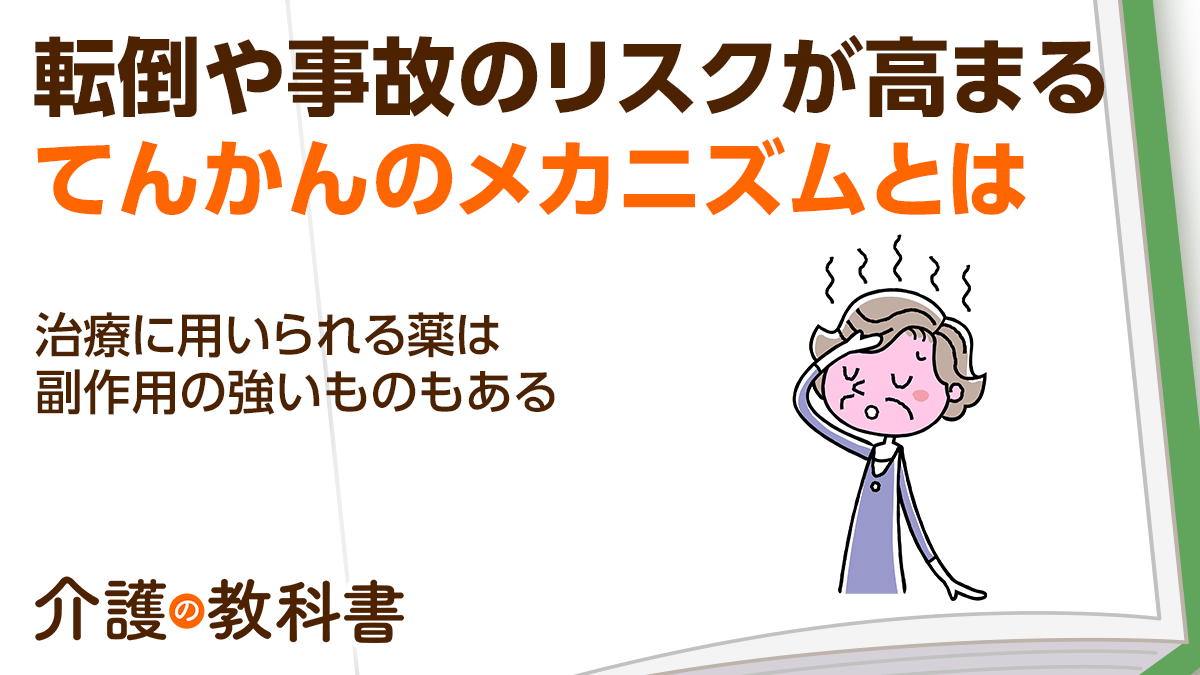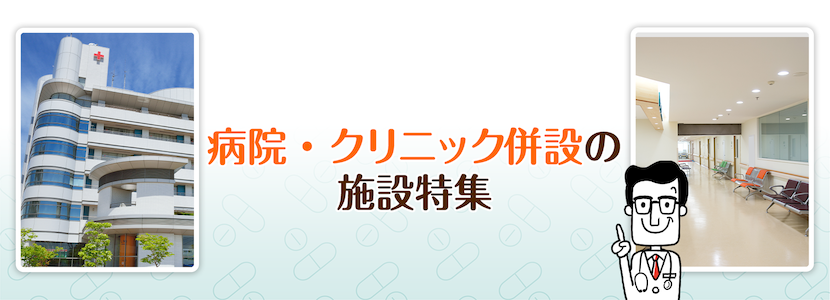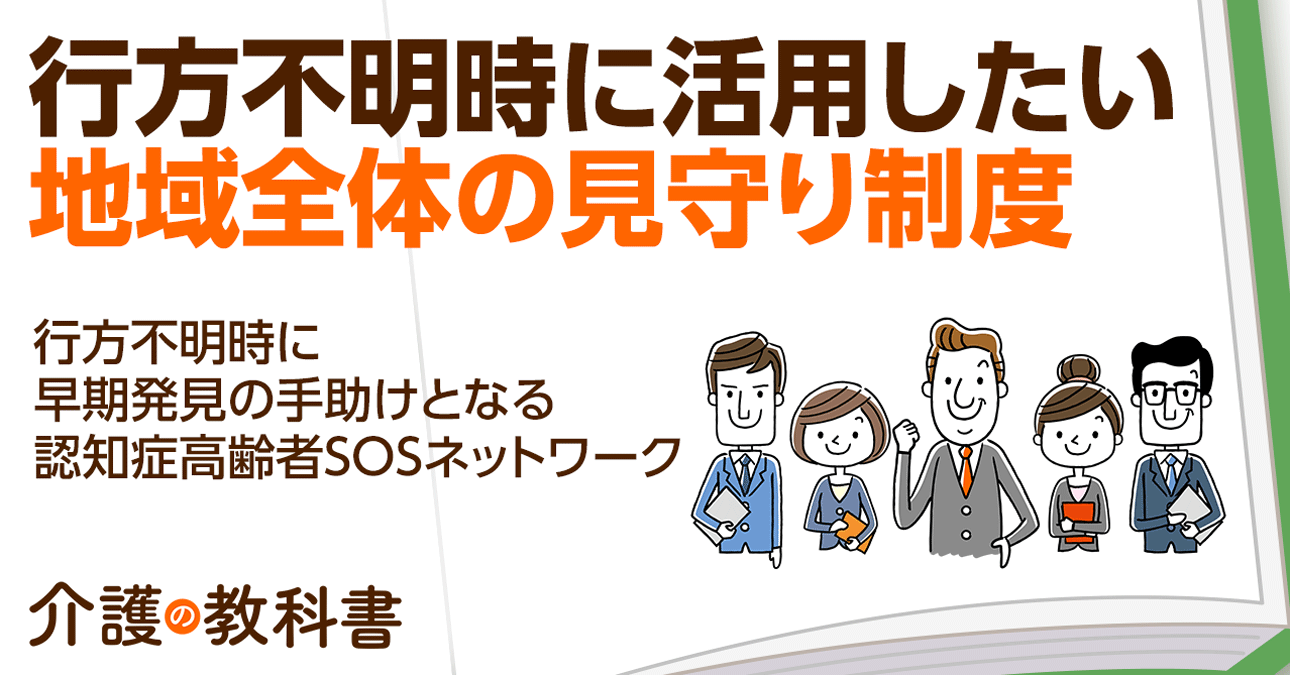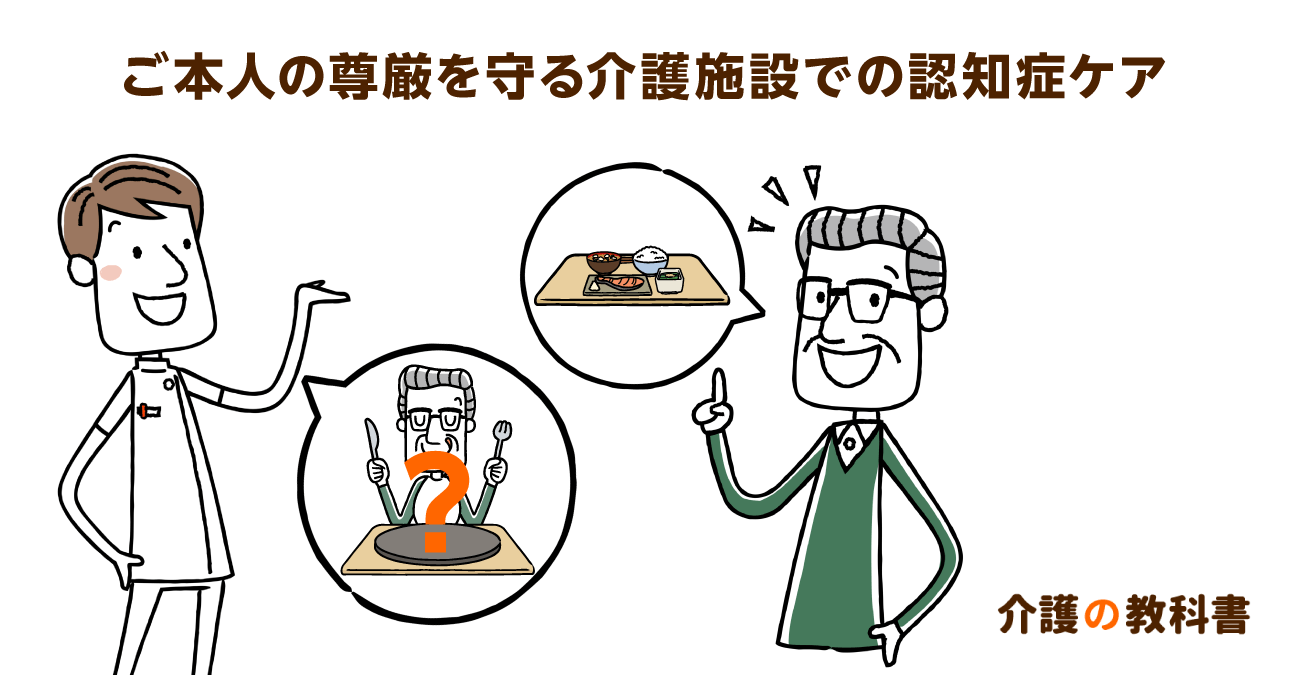脳の神経細胞が過剰に活動することによって、けいれんなどを引き起こす病気をてんかんといいます。
けいれんのみならず、体の一部が動かしにくくなったり言葉が出にくくなったりするなど異常を起こしている脳の場所によって、てんかんの症状も異なります。
てんかんは、小児や高齢者で発症しやすいことが知られており、高齢化が進む現代社会では、てんかんを患う高齢者も増えています。
この記事では、高齢者のてんかんについて、その特徴や原因について解説します。
てんかんの症状と発症しやすい年齢
てんかんの症状は、突如として発作的に表れることが一般的で、てんかん発作と呼ばれます。
発作とは、症状が突発して現れ、短時間で消失する病状のことです。てんかん発作によるけいれんは、全身に現れることもあれば、顔や手足の筋肉だけに現れることもあり、障がいされた脳神経の部位によって症状の程度もさまざまです。
けいれんがひどい場合には意識を失うことがあるほか、手足のしびれや動悸などの症状も現れることもあります。

神経の異常や障がいによって発症する病気は、総じて神経疾患と呼ばれます。てんかんは、高齢者において脳卒中や認知症に次いで多い神経疾患であり、高齢化が進む現代社会では、てんかんを患う人も増加しています。
40歳以上の日本人約3,000人を対象とした調査によれば、てんかんを患っている人の割合は男性で1,000人あたり4.9人、女性で1,000人あたり8.4人と報告されています。この割合は高齢になると増加し、65歳以上では1,000人あたり10.3人と報告されています。
また、米国で行われた調査によれば、てんかんの年間発症率は、45~59歳で10万人あたり10.6件、60~74歳で10万人あたり25.8件、75~89歳で10万人あたり101.1件と、高齢になるほど発症率が増加していました。
てんかんと各病気との関連
脳卒中の関連性
成人が発症するてんかんの、おおよそ半分が原因不明だと言われています。ただし、てんかんの発症には喫煙などの生活習慣、うつ病、脳腫瘍、頭部の怪我など、さまざまな要因が関連していると考えられています。
特に脳卒中は、高齢者のてんかんにおける最も一般的な原因であり、高齢者におけるてんかん発作の30~40%は、脳卒中を発症した経験のある人に発生します。
脳卒中は、脳の血管に障がいが生じることで発症し、主に脳梗塞と脳出血に分けることができます。
- 脳梗塞
- 脳の血管が詰まってしまい、血流が途絶えることで脳細胞が障がいされてしまう病気
- 脳出血
- 脳の血管が破れて出血し、脳内にあふれた血液が脳細胞を圧迫して障がいを引き起こす病気。なお、脳を覆っている膜内に出血が起こってしまう病気は、くも膜下出血と呼ばれます。
脳卒中を発症すると、脳の神経細胞が障がいされ、脳神経の活動に異常が生じやすくなります。脳卒中後にてんかんを発症しやすい理由は、神経細胞に対する直接的なダメージや、脳内における生理的な機能の変化だと考えらえています。
なお、脳卒中後に発症するてんかんは、発症するタイミングによって早期発作と遅延発作に分類することができます。早期発作は脳卒中を発症後、1週間以内に起こるてんかん発作であり、脳梗塞を発症した人に生じやすいことが知られています。一方、脳卒中を発症後、1週間以上たってから起こるてんかん発作が遅延発作です。
認知症の関連性
近年では、てんかんと認知症の関連性に注目が集まっています。認知症はてんかんの原因であるとともに、てんかん発作が認知機能を低下させる可能性が指摘されているからです。
認知症は大きく、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症に分けられますが、高齢者において、最も多い認知症はアルツハイマー型認知症です。
アルツハイマー型認知症とてんかんの関連性を検討した研究は数多く報告されており、てんかんを発症する危険性は、65歳以上のアルツハイマー型認知症患者で、6~10倍高くなることが知られています。また、てんかんを患う高齢者では、認知症を発症しやすいことを報告した研究もあります。
ただし、現状ではアルツハイマー型認知症がてんかんを引き起こす理由や、てんかん発作が認知機能を低下させる理由については、良くわかっていません。
現段階では、認知症によって脳神経が徐々に変性し、神経の生理的な機能にも変化が生じるため、てんかん発作の危険性が高まると考えられています。
また、血管性認知症は脳梗塞や脳出血によって脳が障がいを受けて発症するため、脳神経に対する直接的なダメージがてんかんを引き起こしていると考えられます。
高齢者におけるてんかんで注意すべきこと
てんかん発作は、けいれんや意識の消失など、日常生活に大きな影響を与えます。手足に力が入らなくなったり意識を失うこともあるので、転倒による怪我や骨折の原因になります。
自動車などを運転中にてんかん発作が発生した場合では、重大な交通事故を引き起こす危険性が高まります。
実際、てんかんを患う高齢者では、転倒や骨折の危険性が2~6倍高まることが知られています。

また、18歳以上の成人を対象とした研究では、てんかんを患っている人と、そうでない人に比べて、重大な交通事故の危険性が37%、自転車による事故の危険性が68%高いという結果も報告されています。てんかんの発作は、前触れなく突如として発生するため、不慮の事故の原因となり得るのです。
抗てんかん薬のメリットとデメリット
てんかんの発作を予防する薬は抗てんかん薬と呼ばれます。抗てんかん薬の種類は豊富で、病状によって使い分けられることが一般的です。
フェノバルビタール、フェニトイン、バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピンなど、古くから用いられている抗てんかん薬は、けいれんを抑える効果が強い一方で、副作用も出やすいことが特徴です。
高齢者は腎臓や肝臓の機能が低下していることも多く、薬が体内に残りやすいことから、副作用の危険性と薬の有効性のバランスは必ずしも良いものではありませんでした。
また、抗てんかん薬は、他の薬との飲み合わせが悪い薬も多く、数多くの薬が処方されている方にとっては薬物相互作用の危険性もあります。一方、近年では副作用の危険性が少ない抗てんかん薬も新たに開発され、広く使用されるようになってきています。
以下の表に主な抗てんかん薬のメリットとデメリットをまとめます。なお、抗てんかん薬の使い分けは、障がいを受けている脳の部位や病状によって判断されます。一般的には神経疾患の専門医等によって、患者さんごとに最適な薬の選択と投与量が決定されます。
| 抗てんかん薬 | 主なメリット | 主なデメリット |
|---|---|---|
| フェノバルビタール | けいれんを抑える作用が強い | 他の薬との相互作用が起きやすい 副作用が出やすく、投与量の調節が難しい |
| フェニトイン | ||
| バルプロ酸ナトリウム | ||
| カルバマゼピン | 神経痛などにも効果が期待できる 他の薬との相互作用が起きやすい |
|
| トピラマート | けいれんを抑える作用が強い 他の薬との相互作用が起きにくい |
認知機能の低下などの副作用がある |
| ラモトリギン | けいれんを抑える作用が強い 投与量の調節が容易 |
他の薬との相互作用が起きやすい |
| ガバペンチン | 他の薬との相互作用が起きにくい 投与量の調節が容易 |
けいれんを抑える作用が弱い 眠気の副作用が出やすい |
| レベチラセタム | けいれんを抑える作用が強い 他の薬との相互作用が起きにくい 投与量の調節が容易 |