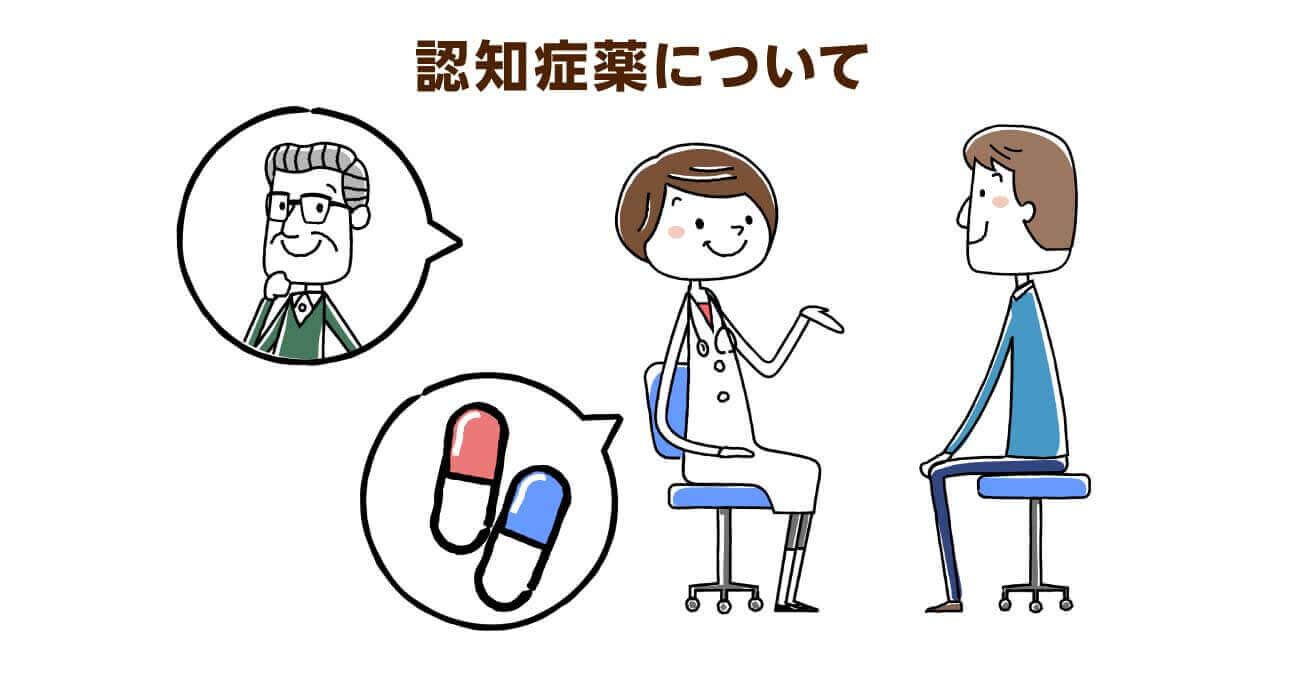こんにちは。株式会社なごみ薬局・代表の渡邊 輝です。今回は、私自身も相談されることが多い、「服薬拒否への対応」についてお話ししていきたいと思います。
介護の現場でも薬局でも、服薬拒否をする要介護者は珍しくありませんが、介護者にとってはそれが大きなストレスになってしまうことも。そこで今回は、服薬指導のポイントをまとめてみました。
飲んでもらえるようにするには次の3つを確認します。
- 飲む意味を介護者側が理解してあげる。
- 飲み方を教えてあげる。
- 飲むインセンティブ(動機付け)をしてあげる。
以上の3つのポイントを念頭に置きながら読み進めてほしいと思います。
まずは、介護をする側が薬についての理解を深めていきましょう!
なぜその薬が処方されたのか?その薬の効果は?副作用は?
介護士や家族が、薬の効果や副作用を知ってはいけない理由はありません。命をつなぐ、その人らしい生活を支援する、要介護者の意思決定を支援するという目的があれば、学ぶことはできるはずです。

私は、「ケアとは人に関心を持つことから始まる」と思っています。その人の健康を思いやることをいろんな観点から捉え、この機会に薬について詳しく知ってみてはいかがでしょうか。
薬の情報は、患者さんに渡すことが法律で義務付けられているので、要介護者に断ったうえで、内容を把握しておきましょう。また、薬の名前、副作用で検索すればより詳しく知ることができますし、難しい医療用語も検索してみれば分かりやすい説明があるかと思います。それでも意味が分からないときは、ぜひ、薬剤師に「これはどういう意味でしょうか?」と、気軽に相談してみてください。
特に、薬剤師や医者よりも寄り添う時間が多い介護士こそ、わずか数種類の副作用を知っておくことでプロアクティブ(先回りの)サービスやリスクマネジメントができ、日々の支援の質が高まると思います。
| 薬の分類 | 種類と対象 | 主な副作用 |
|---|---|---|
| 抗精神病薬 | 認知症患者への抗精神病薬全般 | 手足の震え、神経障害、脳血管障害など |
| 睡眠薬 | ベンゾジアゼピン系睡眠薬・抗不安薬・非ベンゾジアゼピン系睡眠薬 | 認知機能の低下、転倒、骨折、せん妄、運動機能の低下など |
| 抗パーキンソン病薬 | パーキンソン病治療薬(抗コリン薬) | 認知機能の低下、せん妄、不活発、口渇、便秘など |
| インスリン | インスリン製剤 | 低血糖など |
| 抗うつ薬 | 三環系抗うつ薬・消化管出血のある人へのSSRI薬 | 認知機能低下、せん妄、便秘、立ちくらみ、消化管出血の再発など |
薬が飲みやすい環境を整えてあげましょう!動機付け(インセンティブ)も大事です
薬が飲みやすい環境を整えてあげるのも思いやりです。以下の項目を確認して、その人に合った環境を提供してあげてください。
- 飲むタイミング(朝なのか、夜なのか、食後なのか食前なのか)
- 貼り薬、目薬、吸入薬、注射など薬の摂取方法は?
- 医師や薬剤師に相談して、1日1回の服用頻度に変えてもらう
- 空を捨てずに、お薬カレンダーに入れてチェック
- 習慣にするための工夫
ただし、健康に関わることなので、個人の判断で変更するのはおすすめできません。何か変更をする場合は、必ず処方した医師・薬剤師の確認を取ってください。
また動機付け(インセンティブ)という点では、以下の点を上手く伝えて、「薬を飲みたい」と思ってもらえるようにすることが大事です。
- 飲むことで、何が良くなるのか。
- その人が健康になることで何が良いのか。
- ご本人の自己実現の目的に近づくのか。
- 褒める、サプライズ、小さな喜びを作る。
薬学部生の薬局実習で教えていること…

薬局実習で薬学生に教える時には以下のようなポイントを重点的に伝えています。
- 共感する
- 相手の痛みや疾患を共に感じること。完全に相手の痛みを理解することは経験しない限りできませんが、理解しようとすることはできます。 つまり、患者さんから「この介護士は私を理解してくれている」と思ってもらうことはできるはずです。
- 誰かに共感してもらえていること自体が心の支えになり、穏やかになります。
- 傾聴する
- 傾聴はただ聞くのではなく、「聞いているということ」を相手に伝えることも含まれます。体を相手に傾け、寄り添い、聞くことに全力で集中し、その時は聞くこと以外は何も考えないようにしてください。また、丁寧に問いかけることで、その人の本当の苦悩や気持ちを引き出すことができます。
- 名前で呼ぶ
- 名前で呼ぶことで、「あなたは特別です!」という安心感を与えることができます。「あなたの薬は…」ではなく「渡邊さんの薬は…」と話しましょう。会話の中で最低5回は名前を入れるといいかもしれません。公の場でない限り、嫌がる人はほとんどいません。
- 口の中に化学物質を入れるのですから、信用できない人に飲めと言われても、誰だって飲みたくありません。名前で呼ぶことは、あなたに特別な興味・関心を持っていますよ、という意思表示になります。また、渡すべき薬を間違ってしまうリスクを減らせることもメリットです。
人は信頼できる人の話しか聞きません!
信頼関係は「小さな約束の積み重ね」で積み上げることができます。 時間を守る、作業報告をする、名前や好きなことを覚える、挨拶をするなどです。 資格を取ることも、社会的に信頼されている証拠になります。シンボルとして資格を取り、影響力を与える手段として活用しましょう。
目的を共有することが大事!
薬を飲ませることが目的ではなくて、病気が治り、心からの笑顔がみられるように行動変容させることが、服薬指導の本来の目的です。場合によっては服薬指導しないのがベストかもしれませんし、たくさん効果や副作用を説明して信頼関係を築く必要があるかもしれません。
その判断をするためには、本来の目的が何かを共有するところからはじめてはいかがでしょうか。お孫さんと会いたい、外出したいなど、最初は話してくれないかもしれませんが、生きる目的を共有しましょう。
動かそうとする自分自身が自立的に判断し、相手に合わせて話を選択する必要があります。自立してない人が、自立支援をすることはできないのです。
大して難しい話ではなく、相手に関心を持ち、相手に寄り添って、心を込めて、自分ができる限りの支援をすれば良いのです。薬剤師でなくとも、誰にでも薬の勉強はできますし、誰にでも副作用のモニタリングや、気付きをケアマネや医師と共有することができます。
どうしても飲んでくれない時は、意思を尊重してあげても良いと思う!

飲むことを拒んでいる阻害要因を見つけられない時や、信頼関係を築けないときや、どうしても薬を信用することができない患者さんもいらっしゃいます。
その時は、その「飲まない」という意思決定を尊重し、相手を認めることにしています。
※医師は飲んでいる前提で治療方針を決めていきます。ズレが生じないように、服用していないことは必ず医師・薬剤師と共有して下さい。
飲むことを妨げている、人には言えない本当の問題がある可能性があります。
恥ずかしさだったり、約束していたり、宗教上の問題だったり、こだわり、固定観念、吐いてしまったことがある、言葉にできないアレルギーがある、など。
認知症の方など、飲み方を忘れてしまうこともあります。認知証の場合は、私は総力戦と捉え、支援に関わっている全員で考えるようにしています。私は、薬剤師や介護士が家族をしっかりと巻き込んで要介護者に向き合うことが大事だと思います。そして時には、われわれ薬剤師や介護士が家族を支えてあげなければなりません。
決して患者軽視ではなく、生活を支える人を支えることで、薬を飲んでもらえるような信頼関係を構築、サポートしていきます。
人はさまざまな背景や文脈を持って生活していますので、短時間ですべてを知ることは不可能です。しかし、要介護者からすれば、自分のことを知ろうとしてくれる「理解者」にはなることができます。
- 「薬剤師と介護士の方へ」
- 服薬指導をする薬剤師や支援する介護士自身の中に問題がある場合もあります。
-
- 自分がやったらバカにされる
- 間違ったことを言ったらどうしよう
- どうせ無理
- 自分の仕事じゃないから
…と自分で自分のできる範囲を決めつけてしまっていると、いくらやっても信頼関係は築けません。
誰かと競争しているわけではなく、目の前の人を支援・貢献する。それが仕事であり生き方です。