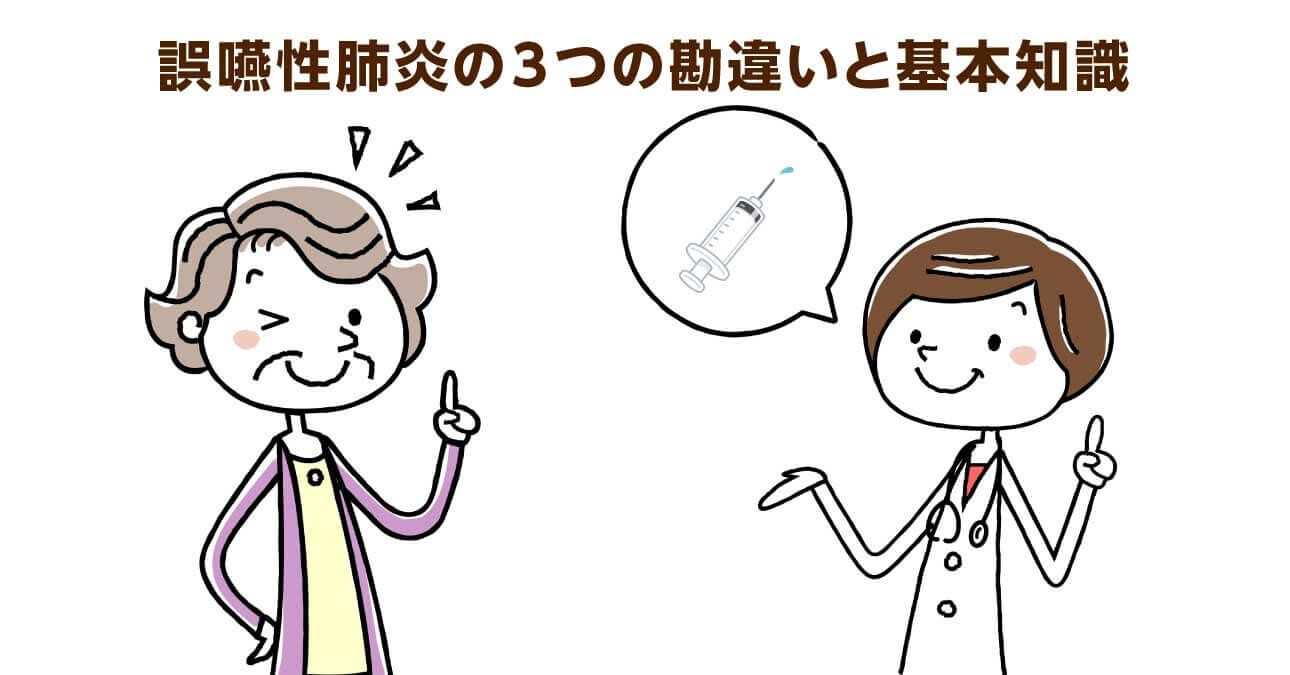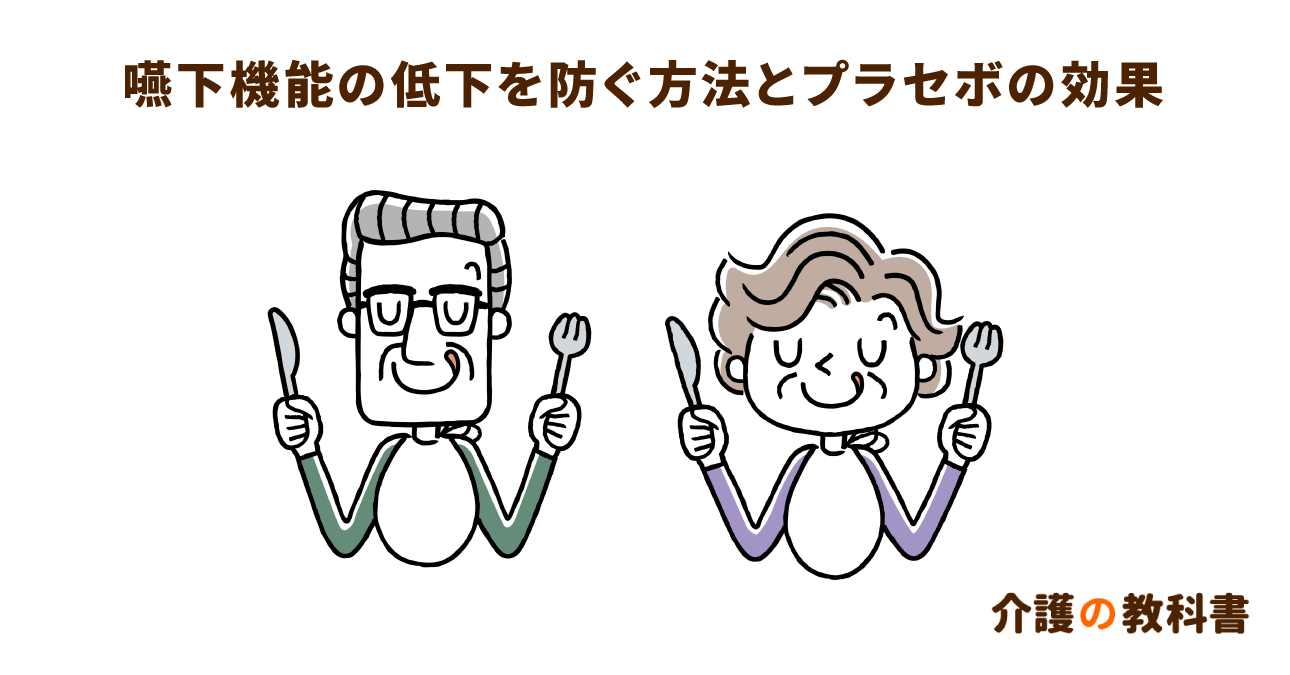食と生を支えるコンサルタントナースの西です。
食べるための機能は加齢の影響を受け、高齢者では低下しやすいことがわかっています。 食べるために必要な機能でもある「摂食嚥下機能」についてや、毎日の口腔ケア時にできる摂食嚥下障がいの予防策をご紹介します。
摂食嚥下障がいのメカニズム
摂食嚥下は、先行期、準備期、口腔期、咽頭期、食道期といった5つのプロセスがあります。
口に食べ物を持ってくるまでを先行期、食べ物を飲み込むのに適した形態に咀嚼する準備期、舌で食物を喉に送り込む口腔期、ごっくんと飲み込む咽頭期、食道のぜん動運動で胃へ運ぶ食道期に分けて考えることができます。
摂食嚥下障がいとは、これらの一連のプロセスに一つ以上の支障がある状態をいいます。
摂食嚥下障がいと聞くと、重く受け取める方もいるかもしれません。確かに、口から食事が食べられなくなる重度の摂食嚥下障がいの方もいます。
しかし、摂食嚥下障がいは軽いレベルであれば、高齢者の多くが無自覚に抱えているものです。例えば、「歯や義歯の問題で、硬いものが噛めなくなり咀嚼が難しいと感じる」「一口で多くの量が飲み込みにくくなった」といった自覚がある方は意外と多いものです。
これは加齢の影響で、歯の喪失、口腔周囲や喉の筋力低下、喉頭の下垂などが食べにくさや飲み込みにくさにつながっているのです。要介護の高齢者など、体の動きが低下している方は、加齢の影響を受けやすくなります。
しかし、日常的に摂食嚥下にかかわる筋肉を動かすことが、摂食嚥下障がいを予防する対策になります。
口の中をしっかり確認しよう
摂食嚥下機能の低下がわかりやすく現れるのは、口腔内の状態です。そのため、食事の前後に口腔内の観察をしっかり行うことが大切です。
食前には口腔内の汚れだけでなく、粘膜が乾燥していないかどうかの観察も行いましょう。
口腔内が湿っていないと舌の動きが不十分になりやすく、乾燥した舌では食事の味も感じにくくなることがあります。
食前に口腔内を観察し、乾燥などがあれば、軽くうがいを行ってもよいでしょう。うがいが難しい場合は、スポンジブラシなどで拭き取るだけでも乾燥を改善する効果があります。
食後には、食べかすが口腔内に残っていないかどうかをしっかり観察しましょう。頬と歯肉の間に食べかすが多く残っている場合は、舌や頬の動きなどが低下していることもあります。
口腔内の観察から、摂食嚥下機能低下を早期に発見し、食事形態や姿勢などを見直すことができれば誤嚥性肺炎の予防にもつながります。
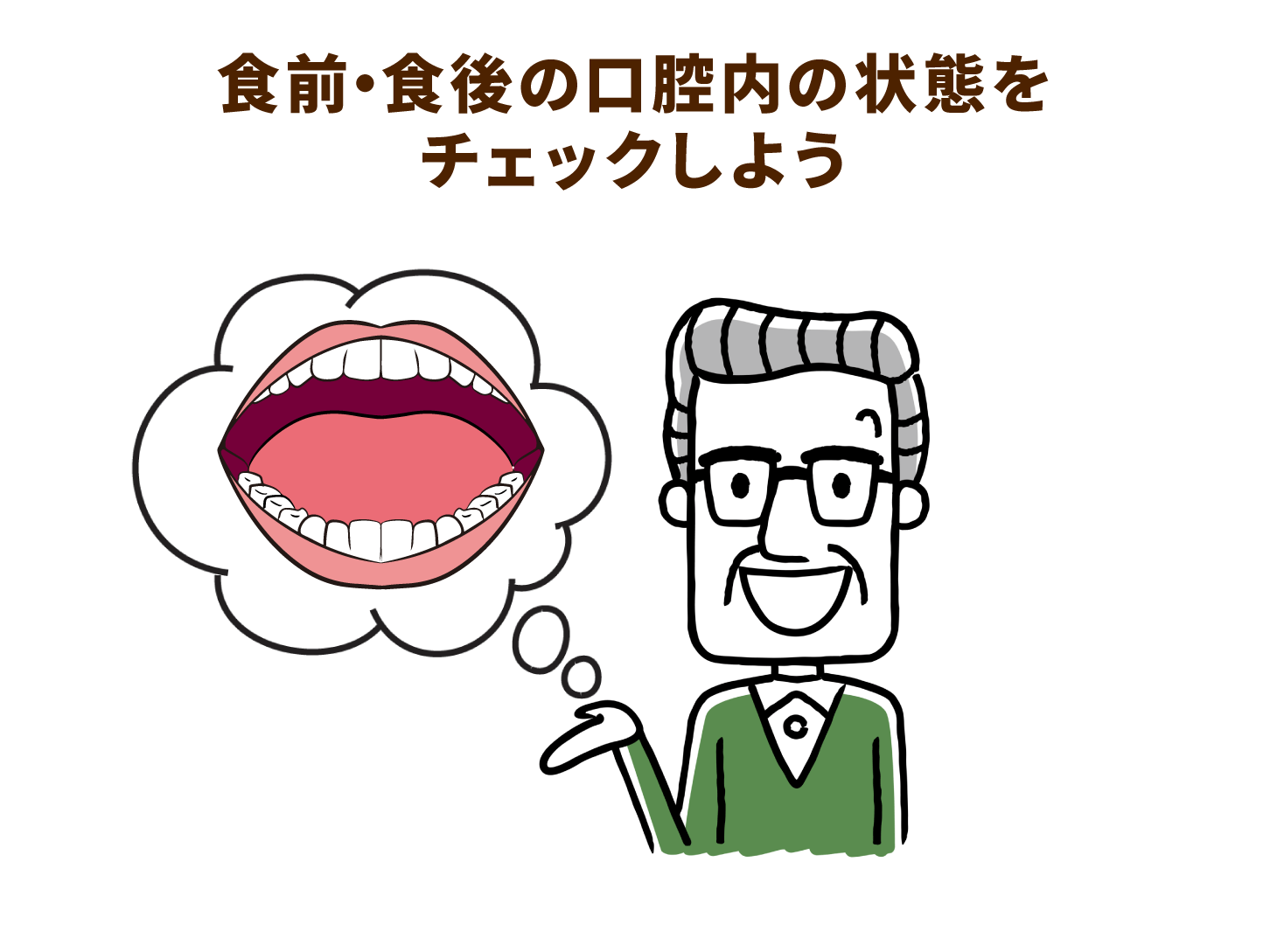
口腔ケア時に工夫を凝らす
日頃から手足を動かさないと筋力が衰えるのと同じように、摂食嚥下にかかわる筋力も日常的に意識して使わないと低下します。
そこで大切なのは、口腔ケア時に工夫を加えることです。口腔ケア時に意識的に舌や頬、また口唇などの口腔周囲の筋力を動かすことが、摂食嚥下障がいの予防にはとても大切です。
口腔ケアを介助する場合
頬を清掃する際にスポンジブラシや口腔ケアティッシュなどで、上から下に頬を伸ばす感じで行うと、良い頬の運動となります。
また、舌の清掃時に、本人に「あっかんべーと舌を出してください」と伝えて、しっかり舌を出してもらうと、自然なかたちで舌の動きが引き出せます。
「舌をしっかり出す」「口の中に引く」「舌で左右の口角を舐める」といった舌の運動を取り入れても良いでしょう。また、舌の動きが低下していないかどうかも合わせて確認しましょう。
舌は大きな筋肉で、摂食嚥下機能の維持にとても大切な役割を果たします。
舌をナイロン毛のついた舌ブラシで清掃し、刺激を与えるのも良いでしょう。ただし、舌をこすりすぎると、味蕾(味覚を感じるセンサーのこと)を傷つけてしまい、痛みが伴いやすくなります。舌ブラシは5回程度、やさしく奥から手前に動かすように使用しましょう。
舌苔が多い場合は口腔内保湿ジェルなどを使用し、取れる分から少しずつ行ってください。一度ですべて取ろうと頑張りすぎないように注意してください。
最後に、口唇をつまんで横に広げる運動を加えると、口唇の運動になります。このとき、口唇が乾燥していないか、口角が切れたりしていないか確認してから行ってください。
口唇に乾燥や傷があると、動かすたび痛みが増すことがあります。乾燥がある場合は口腔内保湿ジェルなどを口唇に塗布し口唇の保護を優先しましょう。
本人で口腔ケアが行える場合
水分での誤嚥の心配がなく、本人でうがいができる方には、口腔ケアの最後にしっかりとブクブクうがいを行ってもらうと良いでしょう。
ブクブクうがいを効果的に行うと、口唇をしっかり閉じることができ、頬も十分に動かせます。「しっかりブクブクと口の中で、水を動かしてください」などと声掛けしながら、本人にブクブクうがいを行ってもらってください。
5回以上は、しっかりとブクブクうがいを行い、意識的に口唇や頬の筋力を鍛えましょう。
ここで、注意したいのは、上を向いてのガラガラうがいです。水が気管に水が入りやすく、うがいの際の誤嚥の危険性が高くなります。要介護の高齢者などの場合は、ガラガラうがいは避けるようにしたほうがよいでしょう。
また、口腔ケアの最後には「舌をしっかり出す」「引っ込める」といった舌の運動を加えても良いでしょう。
頬、舌、口唇を口腔ケア時に意識して使うことが、日常的に摂食嚥下機能を維持することにつながります。
ただし、食事だけで疲れてしまう方の場合は、無理して行わないように気をつけましょう。まず、疲れずに食事ができるかどうか確認しておきましょう。

会話すること自体が摂食嚥下障がいの予防になる
うまく食事ができていない、口腔ケア時の協力が得られない場合は、上記のようなケアを行うことが難しいかもしれません。
そのような場合は「会話をする」「笑う」などを意識的に行うことが、摂食嚥下障がいの予防につながります。会話は脳への良い刺激になるだけでなく、舌の運動にもなります。また、笑うことは口唇や頬の運動になります。少しでも、日常的に口腔周囲の筋肉を動かせるように、楽しい会話を心がけましょう。
もし、食事量が減ってきた、食べれなくなってきた、むせるようになってきたなどを生じた場合は、かかりつけ医に早めに相談することも忘れないでおきましょう。