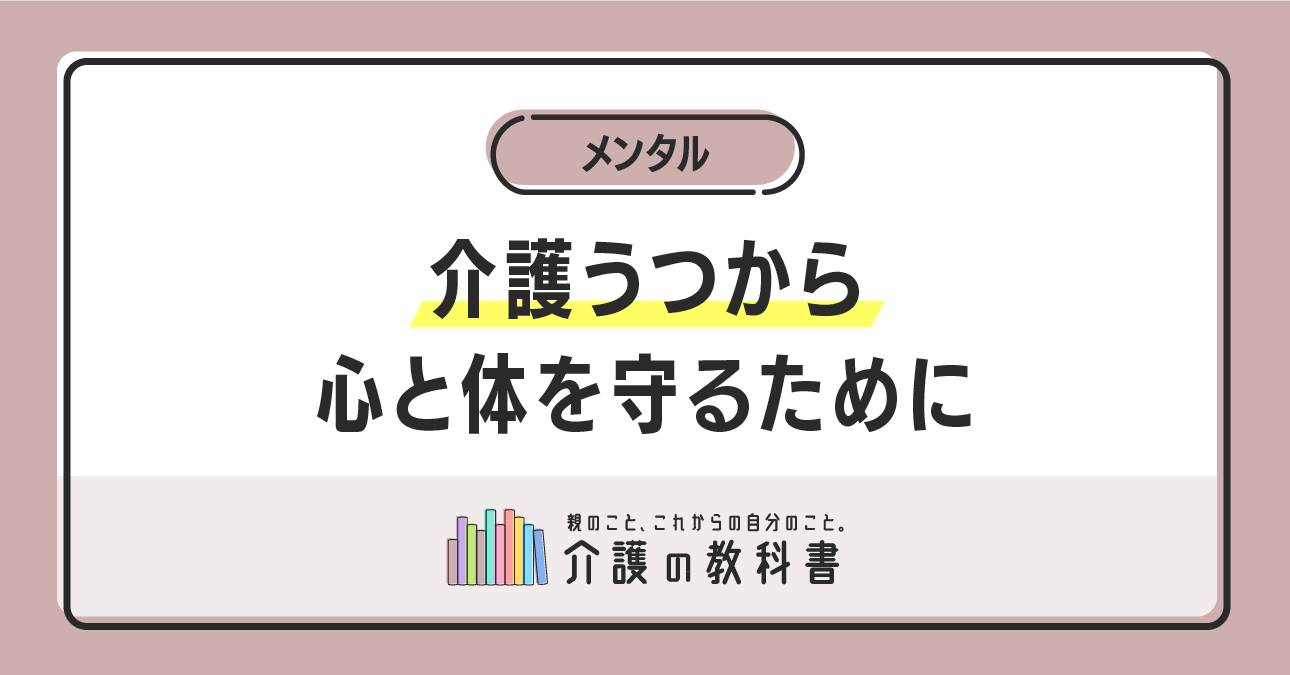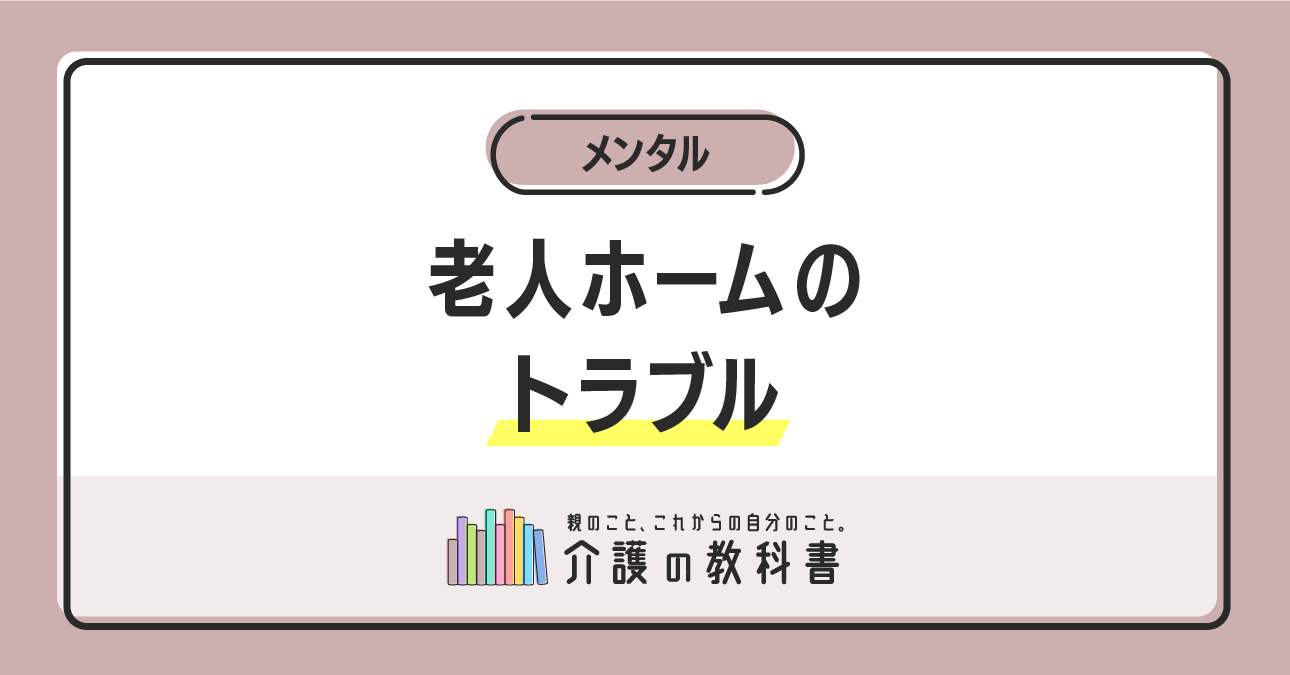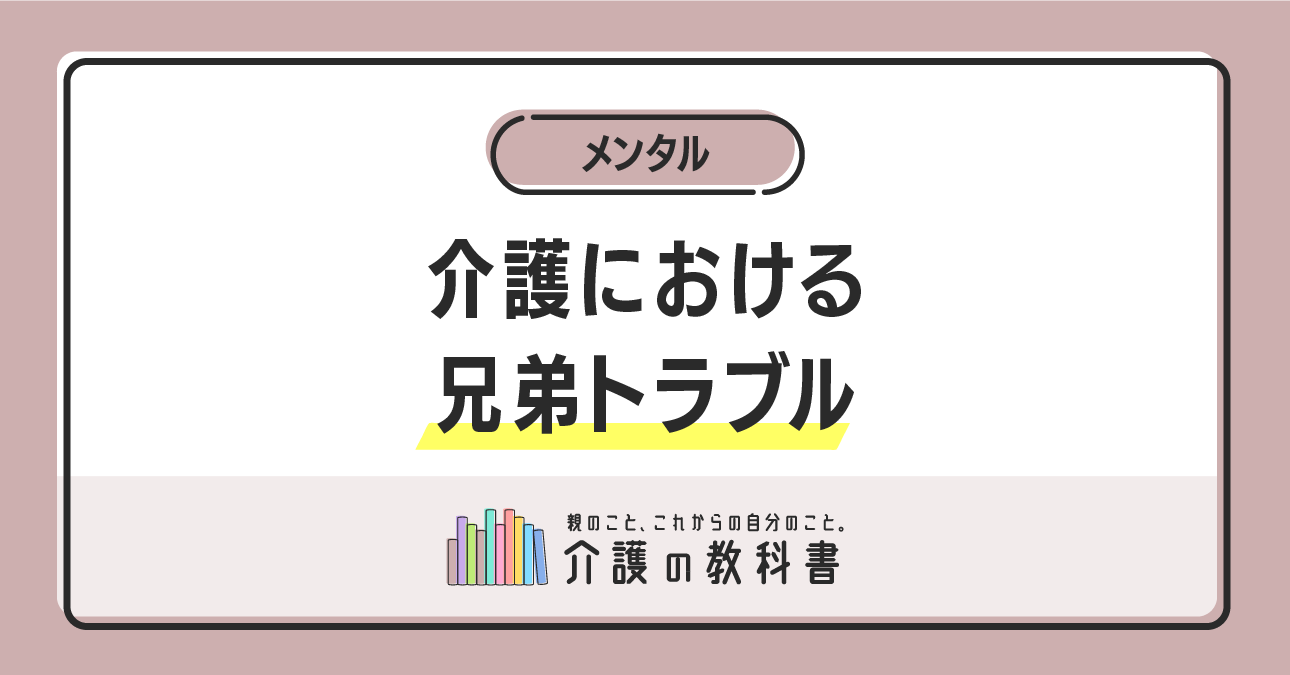介護相談で多いのが「認知症の家族への対応」です。記憶障がいによって何度も同じことを尋ねられるほか、息子を自分のきょうだいや夫と間違えるなど、介護者はそのたびに対応に悩まされます。
今回は、事例をもとに家族の対応を考えていきましょう。
【事例】記憶障がいで母親が自分を認識してくれない
認知症の母親を同居介護しているAさんの事例です。
母親は記憶障がいが進み、最近、自宅にいるのに「B町に帰りますね」と、30年ほど前に住んでいた地域名を頻繁に出すようになりました。
何よりも辛いのは、Aさんが誰なのかがわからなくなってきたことです。
ある日、一緒に買い物に出かけて帰宅すると、母親はAさんに向かって「ありがとうございました」と一礼してスタスタと家の中に入って行きました。
Aさんは「デイサービスの職員さんと間違えているのかも。親族に間違えられるのならまだしも、他人だと思われるのは辛い」と話します。
「お互いに気持ちよく、安心できるかかわりをしたい」と、認知症の本を読んだり、講習会に積極的に参加したりしていますが「娘だとわかってもらえないまま、否定せずに母の話に合わせていると、どんどん辻褄が合わなくなります。私のやり方がよくないのでしょうか」と、Aさんは途方に暮れてしまいました。
このように、認知症の人へ対応方法について勉強し、さまざまなことを試してはうまくいかず、心が折れてしまった経験がある方は多いのではないでしょうか。
記憶障がいに対応するときのポイント3つ
認知症にもさまざまなタイプがあります。認知症で最も多い「アルツハイマー型認知症」は、記憶障がい(もの忘れ)の症状が強く出ます。
何度も同じ質問を繰り返すのは不安が原因なので、否定せずに話を聞く対応が良いという情報が一般的です。
その反面、Aさんのように「話を合わせるだけでは、うまくいかない…」と悩まれている方もたくさんいらっしゃいます。特に、自分が誰であるかを間違われたまま会話を続けるのは難しく、心理的負担も大きいものです。
そこでAさんには、3つのポイントをお伝えしました。
1.関係性を間違って呼びかける場合
無理に話を合わせる必要はありません。
「私は○○よ」と訂正すると、「あ、そうだったそうだった」と名前を思い出してくれることもあれば、キョトンとすることもあったりと、要介護者の体調や状態、気分で毎回違う反応が返ってくるものです。
間違いを訂正するときは、気持ちを込めすぎずにサラリと伝えましょう。
余裕があれば、笑って言えるとパーフェクトですが、間違えられた当人にとってはショックですから、無理に笑うことはありません。
最初からパーフェクトを目指さず、「私、〇〇よ」と笑顔で名乗ることから試してみてください。
ただし「訂正をするときの心の状態」は注意が必要です。
間違われたというショックから、「間違っている!」「忘れちゃったの!?」「思い出してよ!」という心の状態のまま訂正すると、相手に伝わるのは「否定的なエネルギー」です。なんとか思い出してもらおうとする強引さが相手に伝わってしまいます。
「私、だーれだ?」といったクイズ形式にするのもあまりおすすめできません。「私のことを覚えているよね?」「思い出してよ!」という要求が無意識に伝わり、相手へストレスを与えることがあるからです。
想像してみてください。なんだか見覚えがあるけれど思い出せない人から「私は誰でしょう?」と詰め寄られたら、誰だって「怖い!嫌だ!」と思いますよね。クイズ形式は、残念ながら逆効果になることがほとんどです。
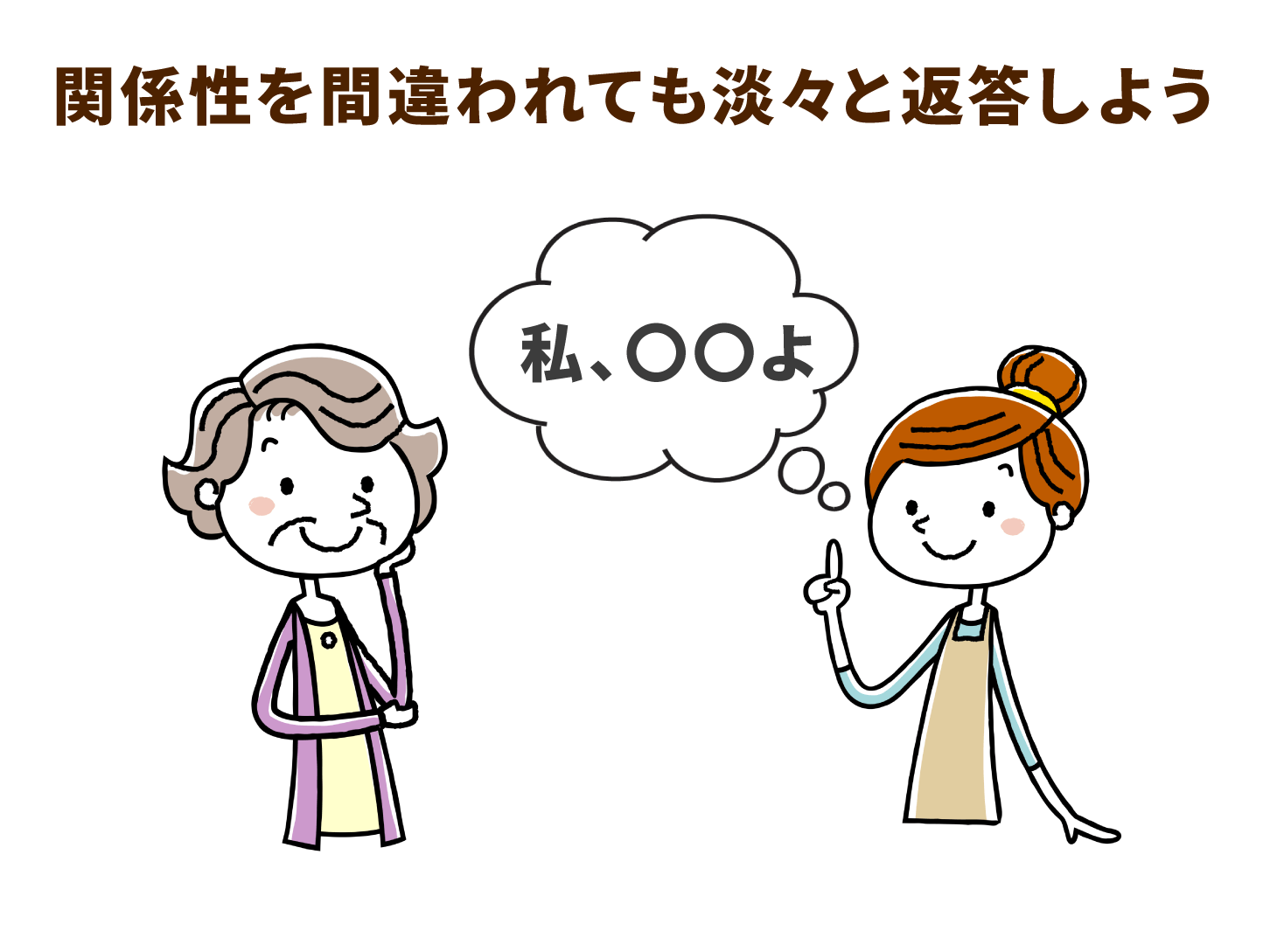
2.関係性を間違ったまま話し続ける場合
認知症が進んだ私の祖母も、私のことを妹だと思い込んでいました。「旦那さんどうしてはるの?」「子どもは?」と、私の実際の状況とかけ離れた質問を繰り返しされるので対応に困ったものです。
架空の話に答える場合は、「お気遣いありがとうございます」「心配してくれてありがとう」など感謝や気持ちを受け取る返答をすると会話がちぐはぐになりません。
また、「何か心配なことがあるの?」「何が気になっているの?」と具体的に何を心配しているのかを聞き返してみるのも良いでしょう。
「ここに来てくれたことで、旦那さんに叱られない?」「仕事を休んだんでしょう?申し訳なくて」など、相手への気遣いや思いやりの気持ちからの発言だということがわかると、うれしくなるものです。
3.何を言っても落ち着かず、興奮しているとき
不安で焦っているように見えるときは、話の内容を正さず、相手の質問をそのまま使って返します。
具体例
- 「明日はデイサービスがあるの?」→「デイサービスがあるかどうかが気になるのね」
- 「心配なのよ」→「心配なのですね」
- 「怒ってるのよ!」→「怒っているんですね」
- 「帰る!」→「帰りたいですね」
こうして淡々と返すだけでも、変化が起きることがあります。返答が難しいときは、「そうかそうか」とうなずくだけでも構いません。
それを繰り返しながら、「心配なのですね」「気になっていることがあるんですね」「それは苦しいですね」と、気持ちを反映させた言葉がけをしてみてください。
少し感情の起伏が治まってきたら、「何が一番心配ですか?」と尋ねてみると、少し状況が変わることもあります。
自分の心の状態が伝わる
家族介護者、介護現場の方のほとんどが経験されているように、思いを込めて説得するよりも、うんうんとうなずくだけの方が落ち着くことはよくあります。
今回は3つのポイントをお伝えしましたが、最も重要なのは対応する人の心の状態です。
「安心してもらおう」「なんとか落ち着いてもらおう」と思えば思うほど、こちらの焦る気持ちが相手に伝わってしまいます。「母のために!」と相手を思う気持ちが強いときほどうまくいかないものです。
「思い出してもらいたい」「自分のことを忘れないでほしい」という気持ちを諦める必要はありませんが、何度も同じやりとりが繰り返されるときには、まず淡々と返して、相手が落ち着くのを優先しましょう。
ショックな気持ちは、誰かに話したり、スマホのメモに書き出したり。SNSでつぶやいたりと、意識して言語化してみてください。この言語化が、自分の心を休める時間になります。
ご相談くださったAさんは「無理に辻褄を合わせようとしなくて良かったんですね!それがわかっただけでもホッとしました」と、安心されていました。
具体的なノウハウは介護者の味方になってくれますが、一番は「今までしてきたことは間違いじゃない。ちゃんとやれている」という自分への自信や労いです。
うまくいくときもあれば、いかないときもありますが、誰も悪くありません。
何がなんでも状況を変えなければという責任感やプレッシャーを下ろし、たまにうまくいったら「よかった!今日はラッキー!」と喜ぶことから始めてみてくださいね。

みなさんが家族間で抱えている悩み、介護で経験されていること、対策をとられていることをぜひ教えてください。お困りのことやご相談には、こちらの「介護の教科書」の記事でお答えできればと考えています。
「介護サービスを嫌がって使ってくれない」といった日々の介護の悩みについては、拙書『がんばらない介護』で解説をしています。ぜひ、手にとって参考にしていただければと思います。