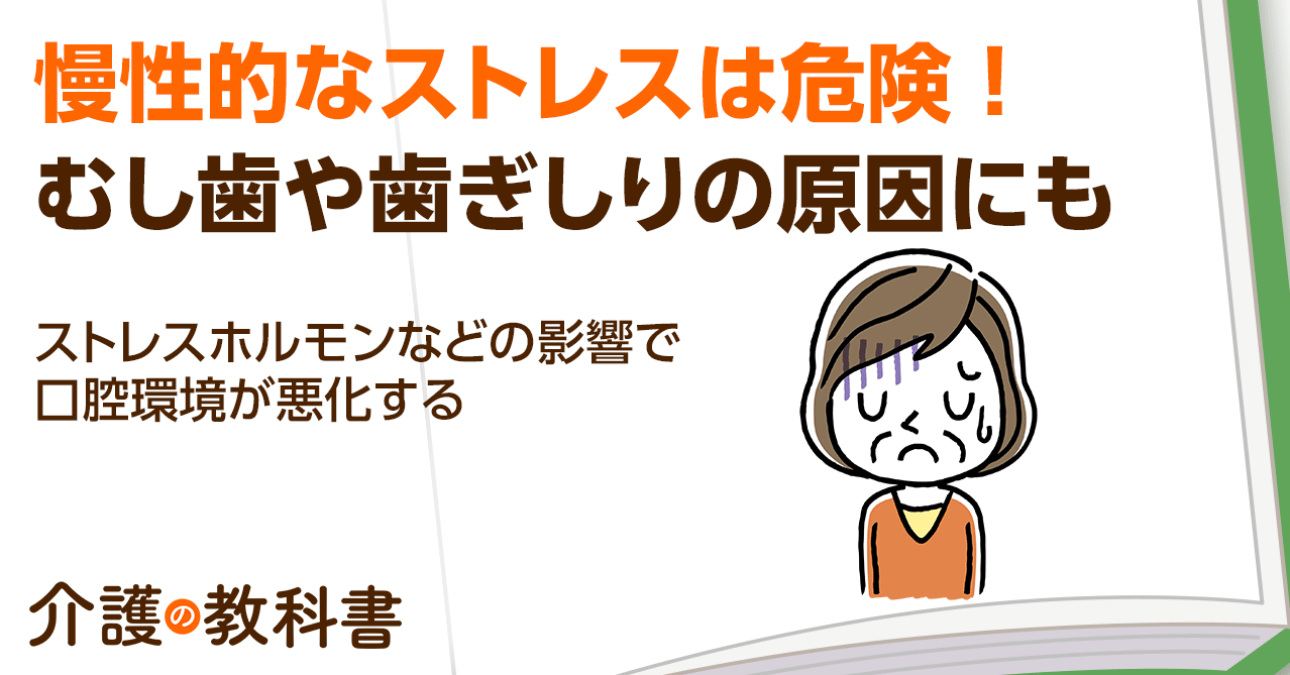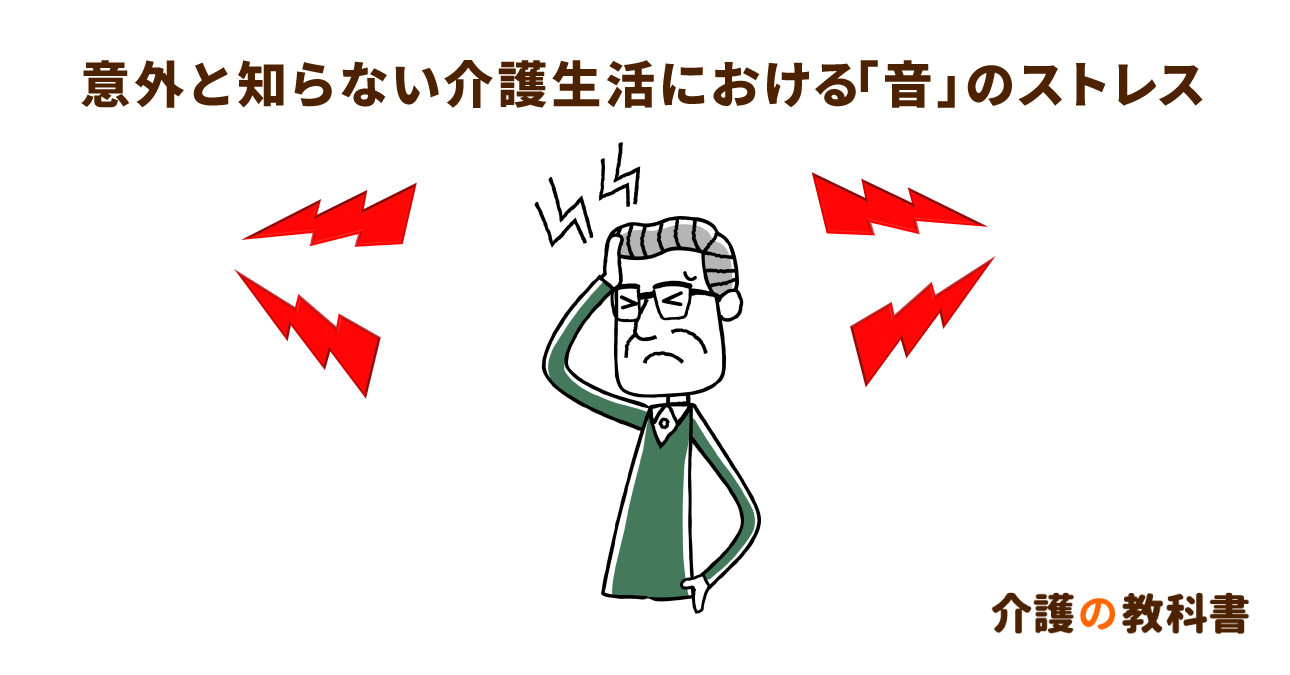皆さんこんにちは。陽だまりのnekoの夢のmaruこと井上百合枝です。
これまでの記事の中で「ケアが必要になった方の心理状態」に焦点を当てて参りましたが、今回は少し視点を変えて、「介護するご家族の心理状態とストレスの対処法」についてお話させていただきます。
ストレスの原因「ストレッサー」の4分類
まず、ご自宅で介護している皆さま、そして、施設などに働かれている介護従事者の皆さまは「いつ施設から電話かかってくるかわからない」と、いつも気を張っておられますよね。中には旅行などを控えている方もおられるでしょう。心身ともに本当にお疲れ様です。
筆者は、「介護」はたとえ介護サービスを利用していたとしても、24時間365日、いつもご家族のそばにあるものだと認識しております。それゆえ、介護者自身の心身のケアをしっかりしていかないと、ご本人との大切な時間を、ともによりよく過ごすことはできなくなってしまうのではないかと考えています。
そもそも、なぜ介護は心身ともに疲れるのでしょうか。ストレスの原因から見ていきましょう。
ハンス・セリエという生理学者は、ストレスの原因となるストレッサ―を以下の通りに分類しました。
- 物理的ストレッサ―:気温・騒音・混雑など
- 化学的ストレッサ―:公害・薬物・酸素欠乏・栄養・酒・タバコなど
- 身体・生理的ストレッサ―:疲労・不眠・病気・けがなど
- 心理的・社会的ストレッサ―:人間関係・仕事上の問題・家族の問題
さらに、ストレッサーは「外的要因」と「内的要因」に分けることができます。
「外的要因」に当てはまるのが物理的ストレッサ―と化学的ストレッサー。一方、「内的要因」には心理的・社会的ストレッサー、身体・生理的ストレッサ―が該当します。
また、ホームズらが示した社会的再適応評価尺度では、ライフイベントの中の1~43位までのストレス尺度のうち、11位「家族の健康上の大きな変化」、15位「仕事の再調整」、16位「経済状態の大きな変化」、19位「配偶者との口論の大きな変化」などが挙げられています。
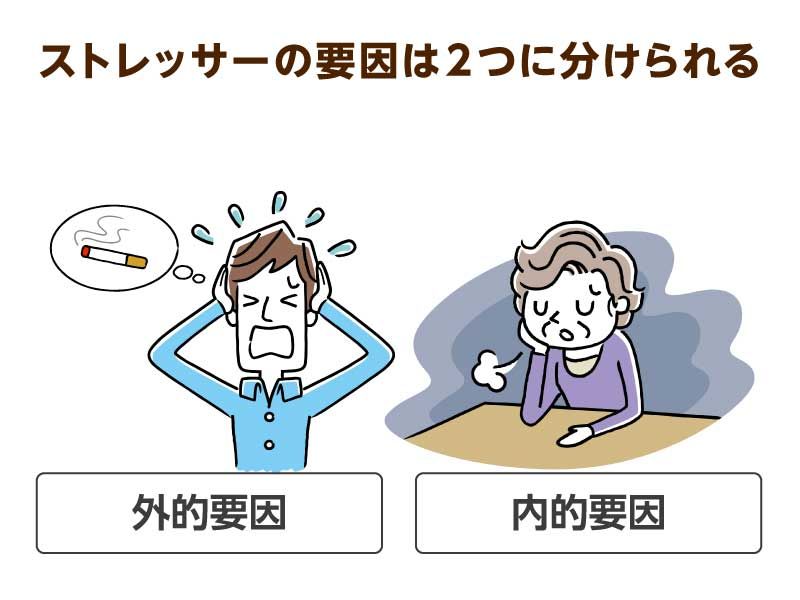
介護をする方にとってのストレスの原因とは
先に述べたことから、介護をする方のストレスはさまざまなストレス要因が交錯しているように感じます。
時間の使い方に制限が生まれる
まず、介護が始まると日常の時間の使い方が大きく変化します。精神的にも物理的にも介護に割かれる時間が増加し、24時間介護のことが頭から離れない方も多いようです。仕事をしている方にとっては、働き方や職場におけるポジションなどを変えざるを得ない状況になることもあります。周りの方から介護に対する理解を得られないこともあるかもしれません。
また、介護が始まることで介護者が友人と過ごす時間や自分の家族との水入らずの時間、自分のための時間が極端に減少することも少なくありません。
経済的な負担や環境の変化が家族内の不和の原因に
介護にかかるお金が発生することで、経済的な変化も生じてきます。ご夫婦やご家族の意見に差異が生じることもあるでしょう。
特にご自宅で介護をする方は、部屋の割り振りや部屋内の配置、室温調整、匂いなどにも変化が出てくることで、家族関係にも変化が生じる可能性もあります。
ご家族の健康状況の変化が最大のストレス
何より、ご家族の心身の健康上の大きな変化が起きることで介護が始まります。その状態が、介護する方にとって大きなストレッサ―であることは間違いありません。

介護ストレスの対処法
このようにして発生する介護のストレスには、どのように対処すればいいのでしょう。
ここでは、介護のストレッサーとして多く発生すると考えられる「内的要因」(心理的・社会的ストレッサー、身体・生理的ストレッサ―)について、筆者からいくつかの対処方法を提案させていただきます。
1:能動的な考えで介護に取り組む
「『~ねばならない』『~と思われたくない』『親の介護はやって当然(あたりまえ)だと思われている』からやる」という受け身的な考えから、「私が介護することを自分で決めた」という能動的な考え方に変えましょう。
介護に限らず、“やらなければならない”ことをやるよりも、“自分でやろうと決めたことをやる”ことの方が楽しいし、気持ちが楽になります。これは、介護を継続していくうえでも同様です。「私は介護をしているのだから、~ねばならない」というのではなく「私は介護していても~ができる」と考えられるように、気持ちや環境を整えていきましょう。
その際、ご本人との楽しかった思い出や、介護をしていて「よかった」と思えたことに着目して介護することをお勧めします。前向きなイメージを持ちながら接することで、介護する側もされる側も心が元気になっていくのです。
2:介護する空間の動線を良くする
介護がスムーズにできて、ストレスが減少するように動線を見直しましょう。物理的動線だけでなく、非物理的動線も確認することも大切です。
確認項目の一例
- 居宅の中や外出における家族の動線や介護動線
- 家族内の報告・連絡・相談の方法や時間
- 医療・介護サービス事業者などとの連絡・相談・調整方法
- 職場内での(特に介護に対する)報告・連絡・相談・調整方法
- 介護におけるリスク想定した報告・連絡・相談方法など
3:協力者をつくる
介護は1人ではできません。物理的な協力者だけでなく、精神的に支えてくれる協力者も必要ですので、周りに相談してみましょう。
家族に話し合いの協力を依頼したり、介護の分担を提案。友人などに相談してみることも効果的でしょう。また、かかわりのある医師・看護師・地域包括支援センター・ケアマネージャー・介護事業者などに相談することも大切です。

4:楽に介護するための知識を得る
介護者の会や研修などに参加したり、本やインターネットなどから情報などから、介護を楽に行うための知識を得てみましょう。
ただし、特にインターネットに関しては事実と異なる内容が見られる場合があります。信頼のある情報源か適宜確認をするようにしてください。
5:リフレッシュする時間をつくる
介護者にも、自分の人生を大切にしたり、リフレッシュしたりする時間が必須です。介護者であるご自身の心や体が喜ぶ時間をつくりましょう。読書や音楽を聴いたり、映画、旅行、友人との交流、睡眠、運動、リラクゼーションや美容室に行くなどが挙げられます。お酒やたばこはストレッサーにもなりうるので、留意が必要です。
ただし、この時間をつくりだすためには、家族や介護サービス事業者などとの相談・調整が必要です。1人で時間の捻出方法に迷うのではなく、思い切ってほかの人に相談してみましょう。
ストレスを1人きりで抱え込まない
いつか終わりがくるのが介護ですが、多くの場合は“いつ”終わるのかわからないものです。介護する方もされる方も、無理や我慢をしてストレスを長期間1人で抱え込まないことが、介護を少しでも楽に続けていくための秘訣だと思います。
ストレスがまったくない生活はありません。介護する皆さまがストレスとうまくつきあいながら、心身への負担が少しでも減って生活も介護も続けていかれるよう願って止みません。